子育てや住宅ローンなど支出が増えやすい既婚世帯では、資産運用の失敗が家計に与える影響も大きくなります。そこで手軽に始められる投資先として「REIT(不動産投資信託)」が注目されていますが、実はメリットばかりではありません。本記事では「REIT デメリット 既婚」という疑問を持つ読者に向け、リスクの中身をひも解きながら、夫婦で安心して取り組むための具体策を紹介します。読み終えるころには、自分たちに合った投資判断が下せるようになるでしょう。
REITとは何かを短くおさらい
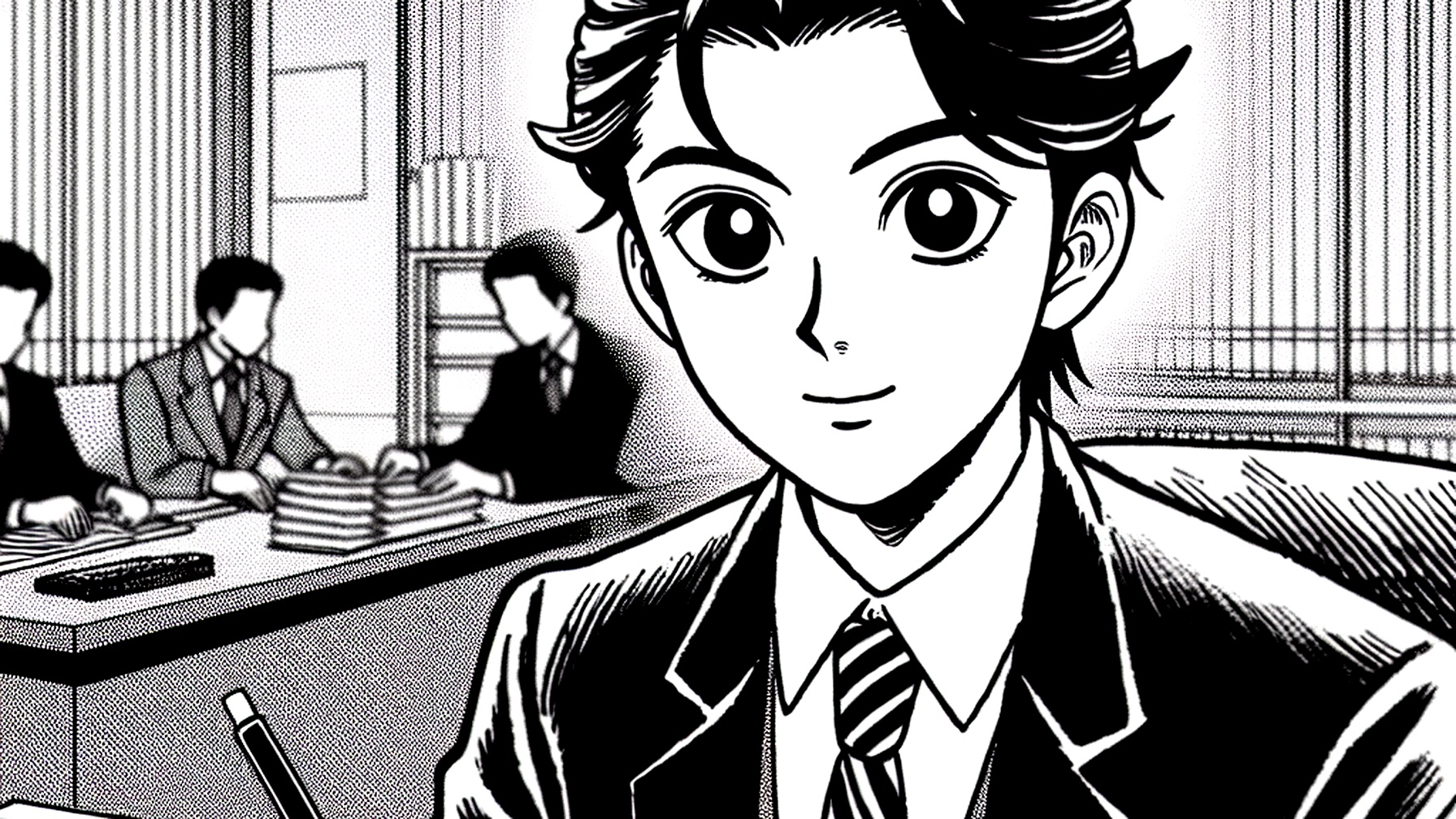
まず押さえておきたいのは、REITが複数の投資家から集めた資金でオフィスビルや住宅を購入し、賃料収入や売却益を分配する仕組みだという点です。株式と同じように証券取引所で売買できるため、数万円から不動産収益にアクセスできる点が人気を集めています。
しかし、REITはあくまでも上場商品の一種であり、価格は日々変動します。東証REIT指数を見ると、2020年3月のコロナショック時には前年末比で約35%下落しました。つまり、物件を直接所有する場合と違い、短期的な値動きリスクが高いと理解することが大切です。また、分配金は保証されておらず、空室率や金利動向によって減配する可能性があります。
加えて、投資対象となる物件は運用会社が決めるため、個人が立地や築年数をコントロールできません。自分で選べないからこそ分散効果が働く一方、投資家は運用の成否を運用会社に委ねる形になります。
既婚者が感じやすいREITの三つのデメリット
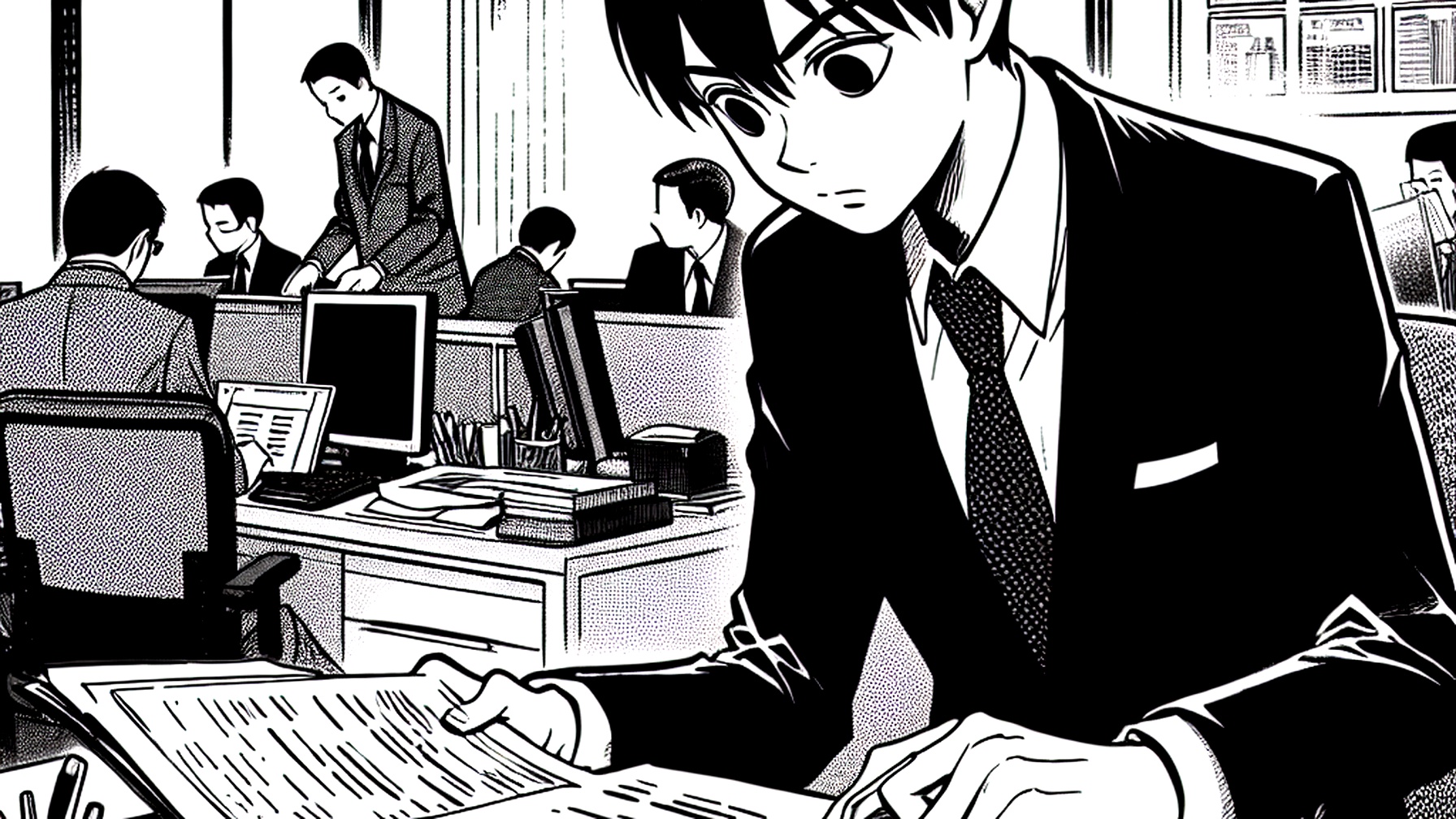
重要なのは、家計を共同で支える既婚者に特有のリスク感度です。ここでは三つの視点からデメリットを整理します。
第一に、分配金の変動リスクが家計収支に直結しやすい点です。総務省「家計調査」では、30代共働き世帯の可処分所得は平均で月約38万円ですが、教育費の増加期には黒字幅が月数万円まで縮小します。そこへ減配が重なると、生活費の補填に資産を切り崩す恐れが高まります。
第二に、REIT価格の下落時に心理的ストレスが夫婦間の不協和を生む可能性がある点です。例えば金融庁の2025年NISA統計では、夫婦共同名義口座の解約理由に「市場変動で意見対立」が15%含まれていました。価格変動を想定したルール作りが欠かせません。
第三に、所得税と住民税の負担増です。REITの分配金は不動産所得ではなく配当所得として扱われ、配偶者控除や住宅ローン控除とは別枠で課税されます。共働きで所得が高い世帯ほど総合課税を選ぶと税率が高くなるため、手取りが想定より減ることがあります。
デメリットへの具体的な対処法
ポイントはリスクを可視化し、事前に対応策を組み込むことです。まず家計への影響を抑えるには、分配金を生活費に組み込まず、全額再投資口座へ自動振替にする方法が有効です。減配時も支出計画が揺らぎません。
次に価格変動への心理的ストレスを減らすため、購入前に「夫婦で許容できる下落率」を数値化しましょう。たとえば「15%下がったら家計会議を開く」と定義すると、感情的な衝突を避けられます。日々の価格ではなく半年ごとの評価額で確認すると、過度な売買を防げます。
税負担については、特定口座とNISAを併用するのが基本戦略です。2024年から恒久化された新NISAは、年間360万円の投資枠と最大1800万円の非課税限度額があります。REIT分配金も非課税対象になるため、高所得世帯ほどNISA枠を優先的に使うと効果が大きいといえます。
最後に、ポートフォリオ全体でREITが占める割合を20%以内に抑えると、株式や債券との値動きの違いを活かしながら家計の変動を平準化できます。国土交通省の不動産価格指数を確認しつつ定期的にリバランスすれば、長期でのリスク管理がしやすくなります。
それでもREITを活用する価値
実は、デメリットを理解したうえで使えば、REITは既婚者の資産形成に大きなメリットをもたらします。まず、現物不動産と比べて流動性が高く、必要に応じて一部だけ売却して教育費や住宅修繕資金に充当できます。これはライフイベントの多い既婚世帯に適した特徴です。
また、東証REIT指数の分配利回りは2025年9月時点で平均3.8%でした。長期国債利回りがおおむね1.1%程度であることを考えると、相対的に高いインカムゲインが期待できます。分配金を再投資すれば複利効果が働き、老後資金の積み上げを加速できます。
さらに、J-REIT市場は物件タイプや地域で多様化が進んでいます。物流施設特化型や住宅特化型などテーマを選べるため、夫婦が興味を持ちやすく学習コストを抑えられます。共通の趣味として運用を話題にできる点も見逃せません。
夫婦で資産形成を進めるときのポイント
まず、家計の全体像を共有し、投資と生活費の境界線を明確にすることが出発点です。家計簿アプリを連携して双方が同じ数字を見られるようにすると、臨時出費が発生しても迅速に対応できます。
次に、毎月の積立額を「共通口座から拠出する部分」と「それぞれの小遣いから拠出する部分」に分けると、責任の所在がはっきりします。どちらか一方に負担感が偏ると、長続きしません。
加えて、保険や住宅ローンの金利タイプも含めた総合的なリスク管理が必要です。金利上昇局面ではREITの借入コストも増えやすいため、変動金利の住宅ローンを抱える場合は、固定金利への借り換えを検討することで家計全体のリスクを抑えられます。
結論として、夫婦で同じゴールを描き、分散とルール設定を徹底すれば、REITの持つ流動性と利回りを活かしつつデメリットを最小限にできます。
まとめ
本記事では「REIT デメリット 既婚」という切り口から、分配金の変動、価格下落時の心理負担、税負担増という三つのリスクを解説しました。そのうえで、非課税口座の活用や投資割合の上限設定など、具体的な対処策を提案しました。夫婦で情報を共有し、下落時の行動ルールを決めておけば、REITは教育資金や老後資金を効率よく育てる有力な選択肢になります。今日紹介したポイントを参考に、まずは少額から試し、家計に合うかどうかを確かめてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp/
- 金融庁 NISA統計(2025年版) – https://www.fsa.go.jp/
- 東証REIT指数 月次レポート – https://www.jpx.co.jp/
- 総務省 家計調査 年報 – https://www.stat.go.jp/
- 内閣府 家計の金融行動に関する世論調査 – https://www5.cao.go.jp/

