投資の選択肢が増えるなか、「資金は少ないけれど不動産に興味がある」という悩みを抱える人は多いものです。REIT(リート)は少額から参加でき、物件管理の手間も不要なため初心者に人気ですが、「銘柄が多すぎて選べない」「株式とどう違うのか分からない」と戸惑う声もよく聞きます。この記事では、まったくの未経験者が安心してスタートできるよう、REITの基礎から比較ポイント、最新の税制までを丁寧に解説します。読み終えるころには、自分に合ったREITを選ぶ具体的な手順がイメージできるはずです。
REITが提供する魅力と株式投資との違い
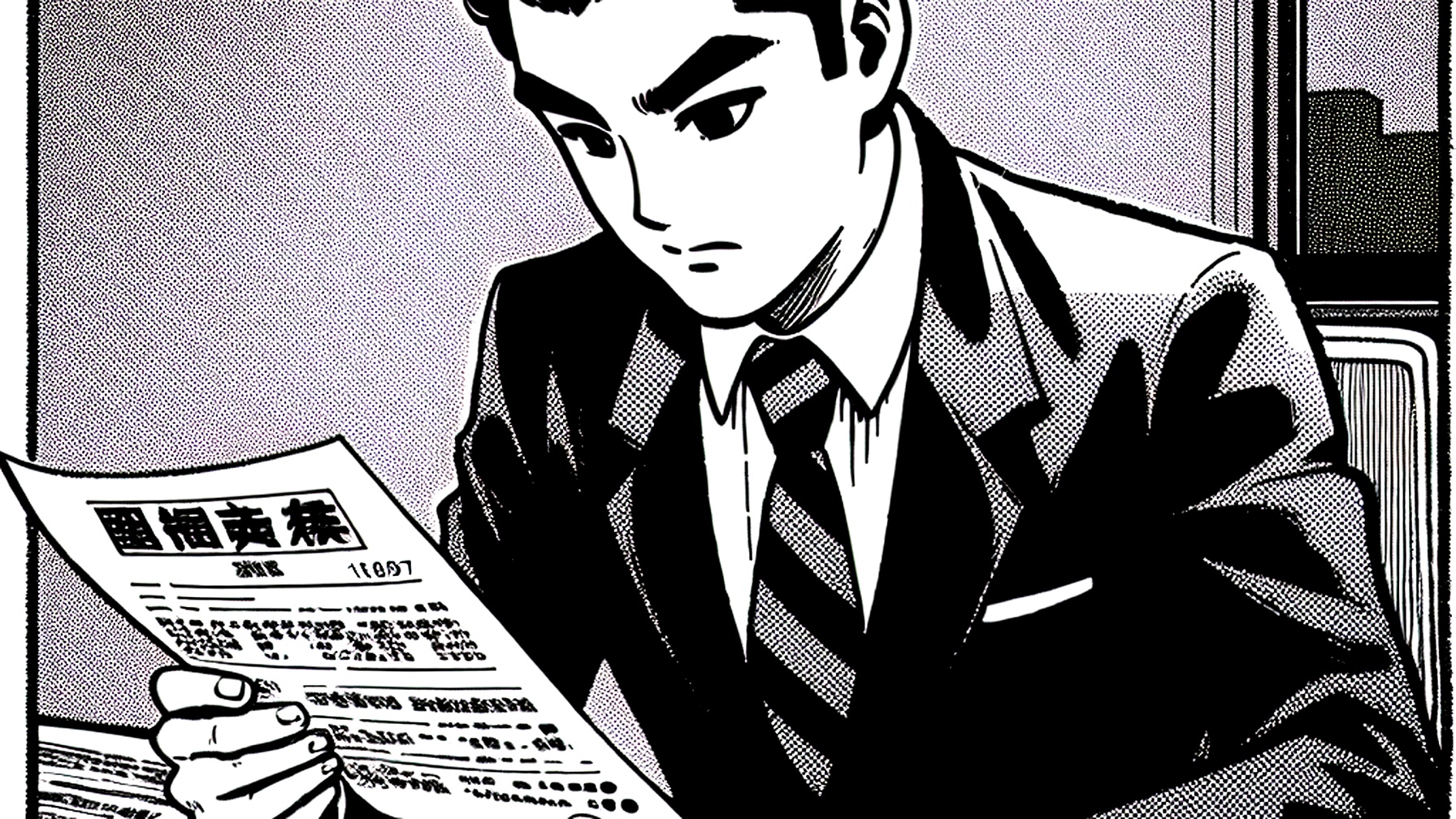
まず押さえておきたいのは、REITの仕組みと株式投資との相違点です。REITは不動産投資法人が保有するオフィスビルや商業施設の賃料収入を源泉に分配金を支払う仕組みで、東証に上場しているため売買の手続きは株式とほとんど変わりません。
一方で、株式は企業の事業活動全体から生まれる利益を配当として受け取りますが、REITは賃料という安定収入がベースになるため、景気の波を受けにくい特徴があります。また、法律上「利益の90%超を分配すれば法人税が免除される」ため、配当性向が高い点も魅力です。
日本取引所グループの2025年8月データによると、東証REIT指数は過去10年間の年平均リターンが約6%で推移し、TOPIXの約5%をわずかに上回りました。ただし価格変動は株式より小さいとはいえ、「オフィス市況悪化」など特有のリスク要因も存在します。つまり、株式とは異なる値動きの源泉を持つ資産として、ポートフォリオ分散に役立つことが最大のメリットと言えるでしょう。
さらに重要なのは、投資口価格が1口10万円前後の銘柄が多く、手数料込みでも数万円から購入できる点です。未経験者が「まずは少額で体験したい」と考える場合に、REITは低いハードルで不動産収益を取り込める優れた入り口になります。
未経験者が比較するときの基本視点
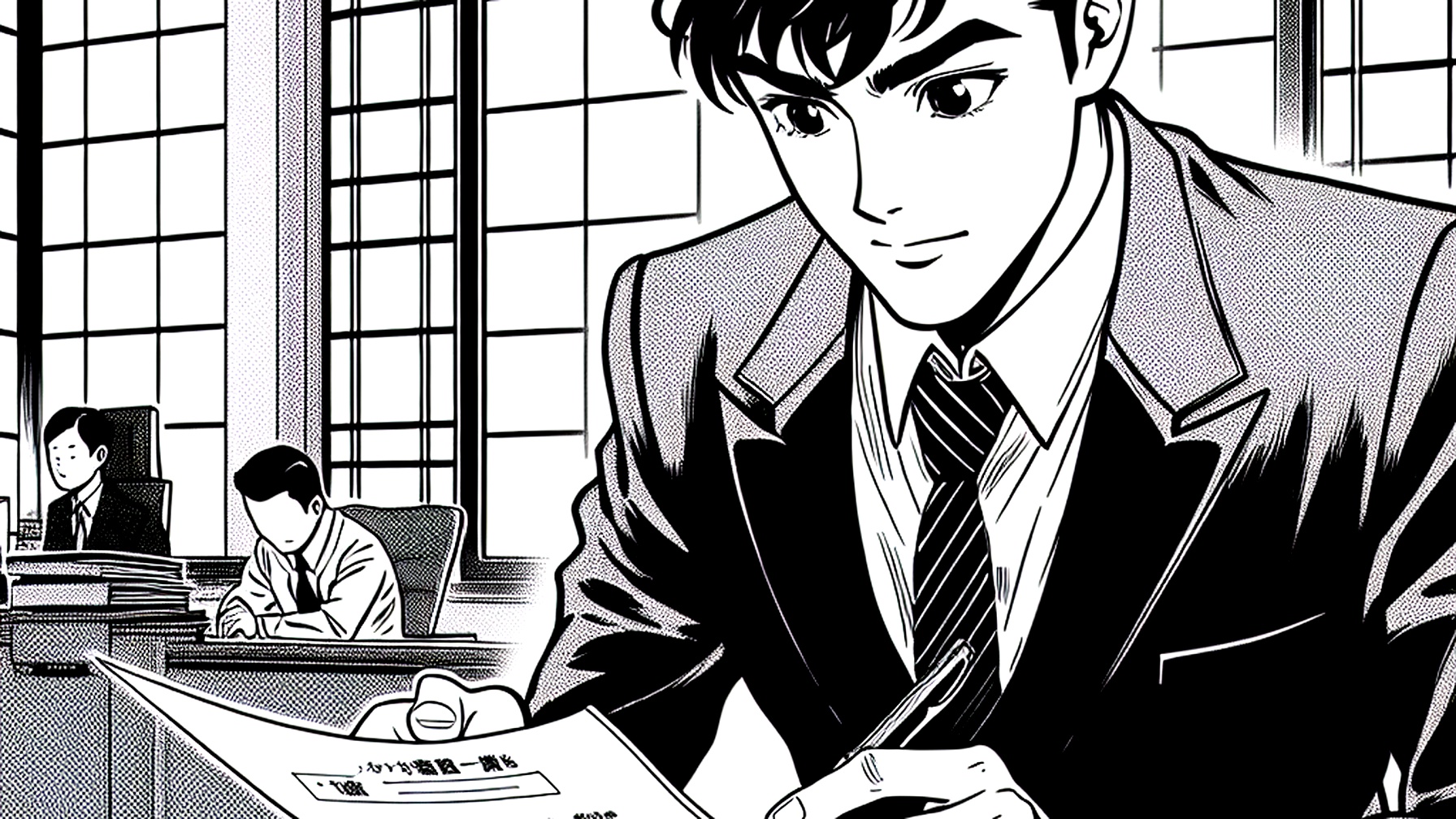
ポイントは「分配金利回り」「資産規模」「物件用途」の三つを軸に銘柄を比較することです。利回りだけで判断すると、高い分配金の裏に空室リスクや築年数の古さが潜む場合があるため注意が必要です。
まず分配金利回りは、J-REIT協会の平均が2025年9月時点で3.9%ですが、個別銘柄では2%台から6%超までばらつきます。利回りが高いほどリスクも高まりやすいので、物件の所在地やテナント構成を併せて確認しましょう。
次に資産規模ですが、総資産が3,000億円を超える大型REITは物件数が多く、テナントの入れ替わりによる影響を吸収しやすい傾向があります。一方、総資産1,000億円未満の小型REITは成長余地が大きい反面、単一テナント依存度が高いケースもあるため、財務指標(LTV=負債比率)が50%以下かどうかをチェックすると安心です。
物件用途では、DX化で需要が伸びるデータセンターや物流施設が注目されていますが、オフィス中心のREITでも優良立地なら安定性があります。用途の分散が進んでいる総合型REITなら、一つのセクターの不調が直撃しづらい点が強みです。
「REIT 比較 未経験」の検索で情報を集めている方は、これら三つの指標を並べて見るだけで、表面的な利回りに惑わされずに済みます。まずは上場している全銘柄を一覧できる証券会社のスクリーニング機能を活用し、気になる銘柄をピックアップしましょう。
分配金利回りと価格変動リスクのバランス
実は、分配金利回りが高い銘柄ほど市場価格の変動も大きい傾向があります。東証のボラティリティ指標によれば、2023〜2025年の3年間で利回り上位10銘柄は年率変動幅が平均23%となり、全銘柄平均の18%を上回りました。
そこで重要なのは、利回りと価格変動を合わせた「総リターン」で比較することです。たとえば、分配金利回りが4%で年間値上がりが2%なら総リターンは6%ですが、値下がりが3%なら実質リターンは1%に過ぎません。初心者は「分配金=利益」と誤解しやすいので注意が必要です。
また、REITの分配金は投資口数に比例して増減します。追加投資で利回りを強化する場合、購入タイミングも無視できません。東証REIT指数が急落した局面で買い増すと、平均取得単価が下がり、将来のリターンが安定しやすくなります。
逆に、過度な集中投資は避けるべきです。日本銀行の統計によれば、個人投資家の保有REIT数は平均2.3銘柄にとどまりますが、経験者ほど5銘柄以上に分散する傾向があります。未経験者でも、業種や資産規模の異なる3銘柄程度に分けるだけで、価格変動リスクを大幅に抑えられます。
2025年度の税制とコストを押さえる
まず押さえておきたいのは、2024年から刷新された新NISAが2025年度も有効で、売買益・分配金が非課税になる点です。年間360万円までの成長投資枠でREITを購入すれば、通常20.315%かかる税金がゼロになります。非課税期間は恒久化されたため、長期保有を前提に活用すると効果が高まります。
ただし、新NISA口座で買い付けたREITを売却すると、その年の非課税枠は復活しない点に注意が必要です。短期売買を繰り返すより、毎月分配金を受け取りながら値上がりを待つ戦略が向いています。
一方でコスト面も見逃せません。証券会社の売買手数料は多くが無料化されましたが、信託報酬にあたる「資産運用報酬」が年0.3〜0.8%かかります。2025年10月時点で国内REITの平均は0.45%です。分配金利回りが同じでも報酬が高いほど実質リターンは目減りするため、目論見書で確認しましょう。
また、上場REITには「物件取得時の消費税還付」など特有の税制メリットがありますが、個人投資家が直接享受できるわけではありません。物件取得が増え分配余力が高まる時期には利回り改善が期待できるものの、必ずしも短期で反映されない点を理解しておくことが大切です。
自分に合ったREITを選ぶ具体的ステップ
基本的に、未経験者は「①目的の明確化→②情報収集→③比較→④購入→⑤モニタリング」という流れで進めると迷いが少なくなります。まず目的を「安定分配重視」「値上がり期待」「インフレヘッジ」のどれに置くか決めましょう。
次に情報収集では、証券会社の銘柄一覧やREIT協会の月次レポートを活用します。ここで分配金利回りと資産規模、用途別構成をスプレッドシートに整理すると、視覚的に強弱がつかめます。
比較段階では、先に述べた三つの指標に加え、スポンサー企業の信用力も確認すると安心です。たとえば大手デベロッパーや金融機関がスポンサーのREITは資金調達力が高く、追加物件の取得がスムーズに進む傾向があります。
購入後は四半期ごとに運用報告書をチェックし、分配金の推移やLTVの変化を把握しましょう。著しい空室率の上昇や借入金利の上昇が見られた場合は、売却して別銘柄に乗り換える判断も検討します。こうした定期的なモニタリングが、長期で安定収益を得る鍵となります。
最後に、2025年10月現在、東証上場REITは65銘柄に拡大しており、物流・ホテル・住宅といった新セクターも充実しています。選択肢が増えたことで比較の手間はかかりますが、その分、自分のリスク許容度やライフプランに合った銘柄を見つけやすくなっています。
まとめ
REITは少額で始められ、物件管理の手間も不要な点が大きな魅力です。しかし、銘柄ごとのリスクとリターンの差は意外と大きく、分配金利回りだけに注目すると失敗することがあります。本記事で紹介した「分配金利回り・資産規模・物件用途」の三つの軸で比較し、新NISAなど2025年度の税制メリットを活用すれば、未経験者でも安定的な不動産収益を得られる可能性が高まります。まずは少額から試し、定期的なモニタリングを習慣にして、自分だけのポートフォリオを育てていきましょう。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp
- 一般社団法人投資信託協会 – https://www.toushin.or.jp
- 一般社団法人日本リート協会 – https://www.j-reit.jp
- 国土交通省 不動産市場動向資料 – https://www.mlit.go.jp
- 財務省 税制改正資料(2025年度) – https://www.mof.go.jp

