資産形成を始めたいけれど、「株よりは安定してほしい」「物件を持つのはハードルが高い」と感じる人は多いはずです。実際、私の相談窓口でも「少額で不動産収益を得る方法はないか」という声が年々増えています。そこで注目を集めているのが不動産投資信託、いわゆるREITです。本記事では、REITの仕組みから投資メリット、そして「初心者は何を選べばよいのか」までを、2025年10月時点の制度や市場データを踏まえて丁寧に解説します。読み終えるころには、自分に合ったREITの選び方が具体的にイメージできるようになるでしょう。
REITとはそもそも何か
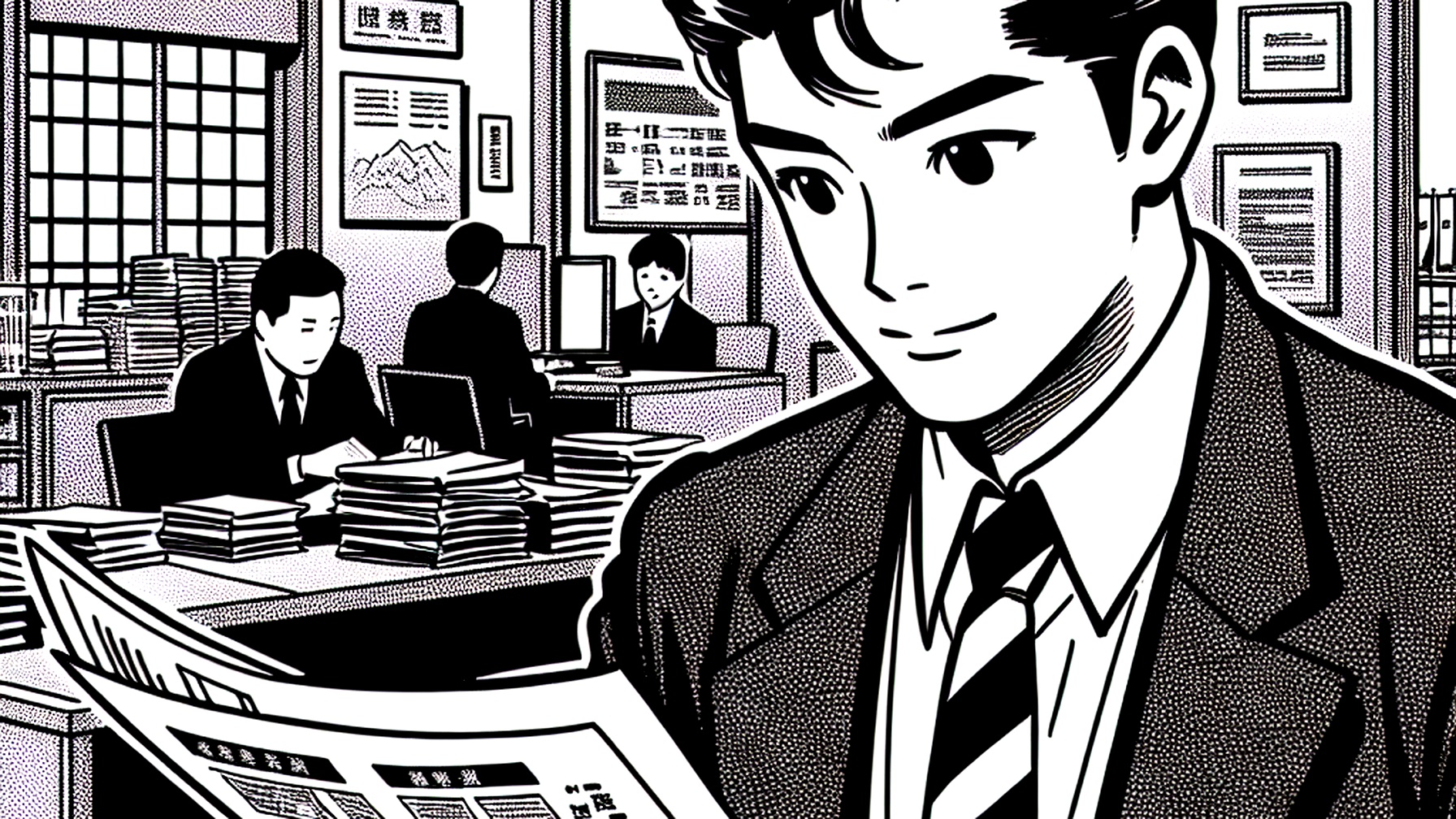
まず押さえておきたいのは、REITが「Real Estate Investment Trust」の略であり、多数の投資家から集めた資金でオフィスや住宅、物流施設などの不動産を購入し、その賃料や売却益を分配する仕組みだという点です。株式と同じように証券取引所で売買できるため、現物不動産よりも流動性が高いことが特徴となります。
投資家が得る収益は、賃料収入がベースの「インカムゲイン」と、物件売却益や株価上昇による「キャピタルゲイン」の二本立てです。実はこの構造こそが、安定収入と成長性を同時にねらえる理由と言えます。さらに、REITは税制上の優遇を受けるため、利益の90%以上を分配するかぎり法人税が実質的に免除されます。つまり多くの利益が投資家に還元されやすい仕組みになっているわけです。
東証のデータによれば、2025年8月時点で上場REIT(J-REIT)は66銘柄、時価総額は約18兆円にまで拡大しています。これは、新規物件の取得が活発だった2010年代前半と比べても約1.5倍に相当します。市場規模の拡大にともない、投資対象もオフィス主体から住居、物流、ホテル、さらにはデータセンターへと多様化しました。初心者にとっては、ライフスタイルに合わせて複数のセクターを組み合わせられる選択肢が増えたと言えるでしょう。
REIT投資の4つのメリット
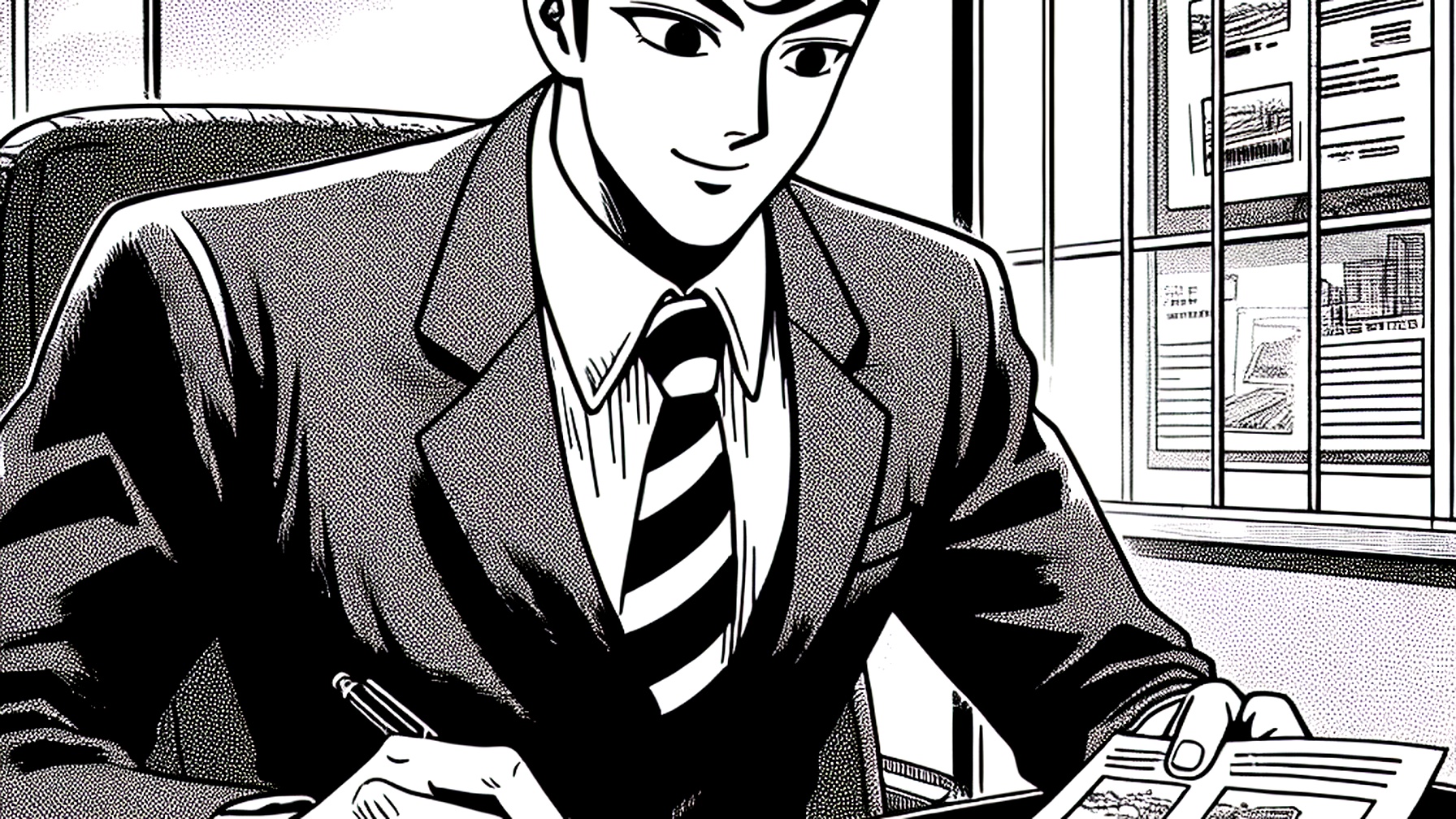
重要なのは、REITがもたらす具体的なメリットを体系的に理解することです。ここでは代表的な利点を四つ取り上げ、数字を交えて解説します。
第一に、分配利回りの高さです。東証REIT指数の平均分配利回りは2025年9月末時点で3.6%前後となっており、長期国債利回り(約1.3%)や主要銀行の定期預金金利(0.02%程度)を大きく上回ります。配当性向が高い理由は前述の税制優遇にあります。
第二に、小口投資が可能な点が挙げられます。多くの銘柄は1口10万円前後から購入でき、住宅1室を買う場合の初期費用と比べると圧倒的に低コストです。これにより、ポートフォリオを段階的に拡大する戦略が取りやすくなります。
第三に、流動性の高さが魅力になります。株式と同様に平日の日中であればリアルタイムで売買ができるため、急な資金需要にも対応しやすいのが実情です。
第四に、運用の手間がほとんどかからないことです。物件管理は専門の資産運用会社が行うため、オーナーとして入居者対応や修繕手配をする必要がありません。つまり時間的コストを抑えながら不動産収益を得られる点が、忙しいビジネスパーソンにも支持される理由と言えるでしょう。
リスクとデメリットを冷静に知る
とはいえ、メリットだけで判断するのは危険です。REITにも固有のリスクが存在します。また、価格が株価同様に変動する以上、元本保証ではありません。
まず、金利上昇リスクが挙げられます。REITの多くは借入金でレバレッジをかけて物件を取得しているため、金利が上がると支払い利息が増え、分配金が低下するおそれがあります。日本銀行は2024年にマイナス金利を解除し、2025年上期の平均短期金利は0.55%程度まで上昇しました。今後も段階的に金利が上がれば利回りが圧縮される可能性は意識しておくべきです。
次に、物件セクターごとの需給変動です。たとえばコロナ禍明けの2023年以降、都心オフィスの空室率はやや高止まりしています。一方でEC需要拡大に伴う物流施設の賃料は堅調に推移しています。つまり、REITごとに保有物件の用途や立地が大きく異なるため、銘柄選定を怠ると想定外の収益変動にさらされることになります。
さらに、自然災害リスクも軽視できません。2024年の能登半島地震では、一部の地方商業施設を保有するREITが修繕費を計上し、分配金が一時的に減少しました。保険加入で一定程度はカバーされるものの、地域分散が不十分な銘柄は影響が大きくなる点に注意が必要です。
初心者は何を基準に銘柄を選ぶか
実は初心者が最も悩むのが「具体的にどのREITを買えばよいのか」という点です。そこでポイントは三つの視点に集約されます。
一つ目は、セクター分散です。住居系は景気変動の影響を受けにくく安定していますが、成長性は限定的です。物流系は賃料上昇が期待できる一方で開発競争が激しく、供給過多のリスクを抱えます。つまり、複数セクターを組み合わせることで全体のボラティリティを抑えることが重要です。
二つ目は、LTV(Loan to Value=負債比率)の水準です。日本取引所グループの統計によると、2025年6月末の平均LTVは44%でした。過度な借入は分配金変動を増幅させるため、50%以下を目安に選ぶと安定度が高まります。
三つ目は、NAV倍率(純資産価値倍率)です。株価が資産価値に対して割安かどうかを示す指標で、1倍を下回れば割安とされます。ただし、低すぎる場合は物件の質や将来性が疑問視されている可能性があるため、賃料の増加率や稼働率をチェックして総合的に判断しましょう。
個別銘柄の分析に時間をかけられない人は、東証REIT指数に連動するETFを活用する方法もあります。最低投資額はおよそ2万円台からとさらに小口化されるうえ、セクター分散も自動的に行われるため、入り口としては有効です。
2025年度の制度を活用した投資アプローチ
まず押さえておきたいのは、2024年に刷新された新しいNISA制度が2025年度も継続している点です。年間投資上限360万円、非課税保有限度額1,800万円のうち、成長投資枠を利用すればREITやREIT ETFも投資対象になります。分配金と売却益が最長無期限で非課税になるため、長期保有を前提とするなら積極的に活用したいところです。
また、企業型確定拠出年金(DC)を導入する企業では、2024年からREIT ETFが組み入れ可能な商品が増えました。DC口座で運用益が非課税となるメリットは大きく、老後資金を形成しながら不動産収益を得られるという二重の効果があります。
他方、補助金やポイント制度のような直接的なインセンティブは、2025年度の時点でREIT投資には設けられていません。したがって、税制優遇を最大限に利用しながら、手数料の低いネット証券を活用するなど、コストコントロールが実質的なリターンを左右します。言い換えると、制度そのものよりも「どの口座で、どの銘柄を、いかなるタイミングで買うか」が成果を決めるのです。
結論として、NISAやDCを活用しつつ、分散投資とコスト削減を徹底することが2025年以降のREIT運用のカギになります。
まとめ
REITは少額から始められ、比較的高い分配利回りを期待できる一方で、金利や物件需給など不動産固有のリスクも背負います。本記事で示した「セクター分散」「LTV確認」「NAV倍率の見極め」という三つの視点を押さえ、NISAや企業型DCといった2025年度の税制優遇を活用すれば、初心者でもリスクを抑えながら安定収益をめざせます。まずはETFなどで市場全体の動きを体験し、自分なりの投資スタイルを固めてから個別銘柄にステップアップしてみてください。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp
- 東証REIT指数月次レポート 2025年9月版 – https://www.jpx.co.jp/markets/indices/j-reit-index
- 国土交通省 不動産市場動向レポート 2025年夏季 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 統計データ「資金循環統計」2025年6月 – https://www.boj.or.jp

