不動産投資を始めたばかりの方にとって、「手元のマンションを建て替えるべきか、それともREITで分散投資するほうが賢明か」という悩みは切実です。実は両者は対立する選択肢ではなく、税金面を理解したうえで組み合わせれば、安定したキャッシュフローと長期的な資産形成を同時に狙えます。本記事では2025年10月時点の制度と市場データを踏まえ、マンション建て替えの判断軸、REITの活用法、そして税金対策の基礎を丁寧に解説します。読み終える頃には、自分に合った投資ルートを見極めるための具体的な視点が手に入るでしょう。
REITの仕組みとマンション投資の違いを押さえる
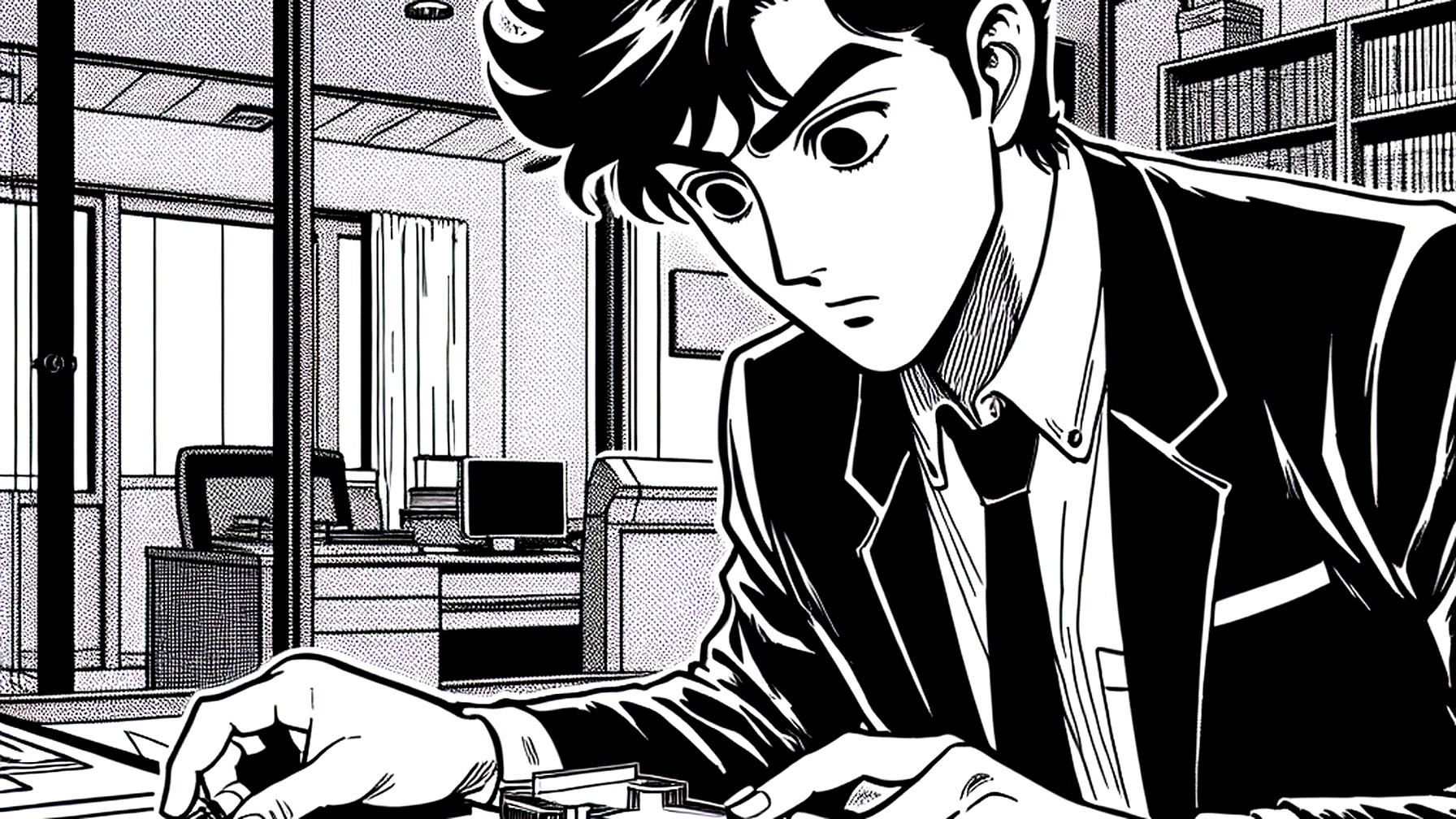
まず押さえておきたいのは、REIT(不動産投資信託)は複数の物件に小口で投資できるファンド型商品である点です。個別マンションを所有する場合と比べ、流動性の高さや初期費用の低さが際立ちます。一方で分配金は市場動向に左右され、物件を直接運営するわけではないため自分の裁量余地は限られます。
東京証券取引所のデータによると、2025年9月末時点の東証REIT指数分配金利回りは4.1%です。これは都心ワンルームマンションの実質利回り平均3.5%をやや上回りますが、借り入れレバレッジを効かせにくい点を考慮する必要があります。また、REITの値動きは金利上昇局面で下振れしやすく、株式市場の影響も受けるため、ボラティリティは決して低くありません。
つまり、自己資金が限られる初心者にとってREITは手軽な入口ですが、安定収益を重視するなら現物マンションとのハイブリッド戦略が有効です。次章では、その判断を左右する税金の基本を確認します。
税金が左右する投資効率のポイント
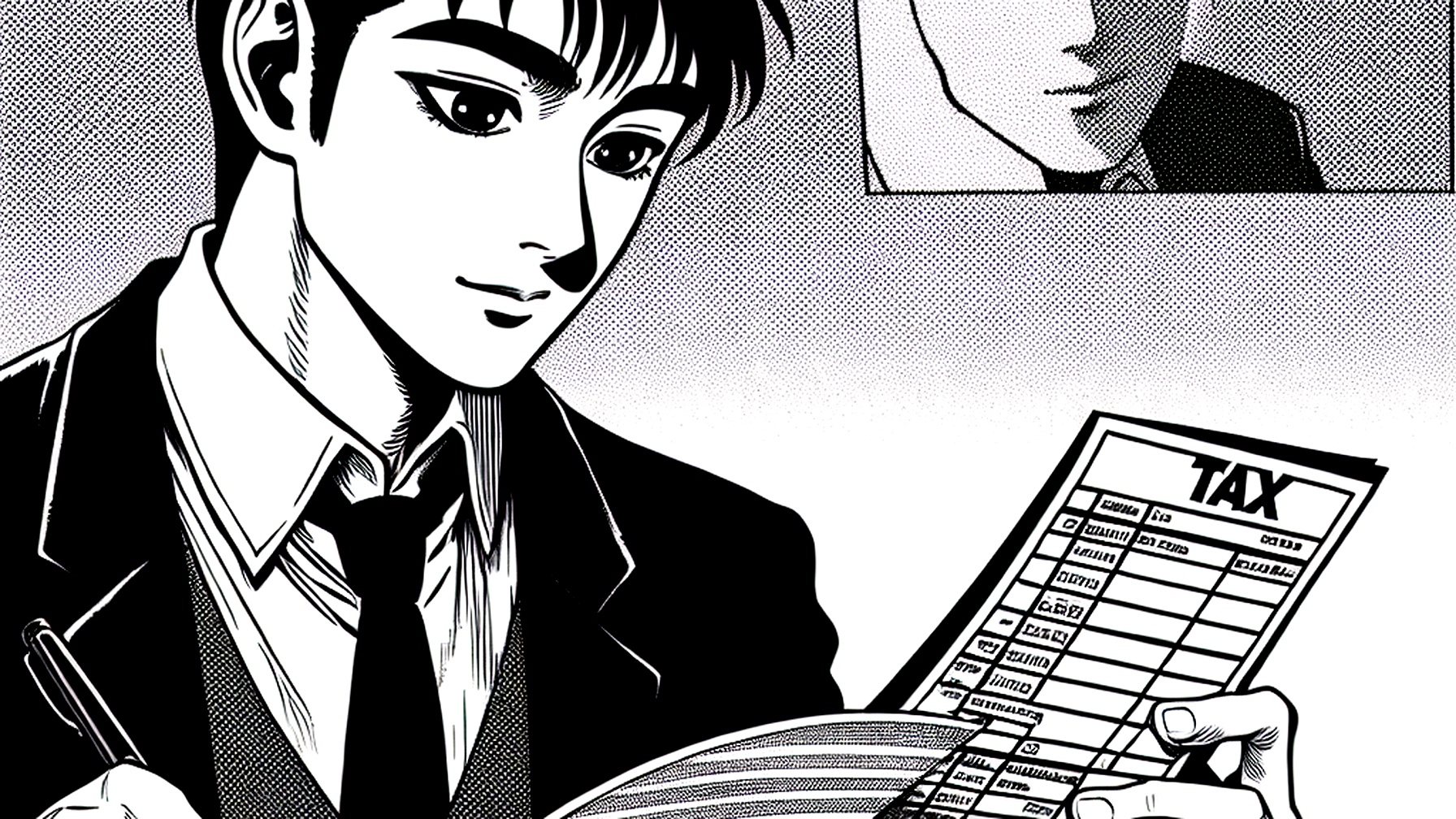
重要なのは、同じ不動産でも課税方式が大きく異なる点です。REITの分配金は金融所得として20.315%の源泉分離課税で完結します。一方、マンション経営の所得は総合課税となり、他の給与所得と合算されるため、税率が段階的に上がる仕組みです。
個人がワンルームマンションを所有すると、減価償却費や修繕費を経費計上できるため、課税所得を圧縮する効果があります。例えば建物価格1,800万円、耐用年数47年の場合、年間約38万円を経費にでき、実効税率30%のオーナーなら約11万円の節税効果になります。しかし耐用年数を過ぎた後は償却メリットが消え、キャッシュフローの伸びが鈍化します。
一方REITでは経費計上の裁量がない代わりに、確定申告が不要で手間が小さいという利点があります。つまり、所得税率が高い高年収層ほど現物マンションで節税し、税率が低い層や確定申告を避けたい層はREITを厚めにするなど、税負担を基準にポートフォリオを調整する考え方が合理的です。
マンション建て替えを判断する三つの軸
ポイントは、建て替え費用、入居需要、そして税金の三つを同時に検討することです。2025年度の「マンション建替え円滑化法」改正により、所有者の5分の4以上の賛成があれば、従来よりスムーズに建て替え計画を進められます。ただし費用負担が大きい点は変わらず、戸当たり2,500万〜3,500万円が現実的な水準です。
建て替え後の新築マンションは耐震性や省エネ性能が向上し、家賃の上昇が見込めます。東京都23区の新築分譲価格は平均7,580万円(不動産経済研究所、2025年9月)と高騰が続き、賃貸市場にもプラスの影響を及ぼしています。しかし建築費の高止まりで利回りは圧縮されやすく、資金調達コスト次第では期待収益が伸び悩むリスクがあります。
税金面では、固定資産税が建物評価額の上昇に伴い増える一方で、2025年度も適用される「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」が3年間続くため、当初は圧迫感が和らぎます。また建て替え時の譲渡所得税を繰り延べられる「居住用財産の買換え特例」(2027年12月まで予定)も検討材料になります。これらの制度を活用できるかどうかで、実質利回りに1%以上の差がつくケースも珍しくありません。
REITと建て替えを組み合わせる資産形成術
実は、REITと自主管理マンションを併用するとキャッシュフローを平準化しやすくなります。建て替え期間中は家賃収入が途絶えるため、REITの分配金で生活費を補う形が機能します。また金融機関は分散投資を評価する傾向があり、保有REITの時価が自己資本としてみなされる場合もあるため、追加融資を引きやすくなる効果も期待できます。
例えば総資産5,000万円の投資家が、2,000万円をREIT、残り3,000万円を築25年のマンションに配分したとします。マンションを建て替える際に自己資金1,000万円と借入2,000万円が必要になっても、REIT部分を担保に入れずに済むケースがあり、ポートフォリオ全体の安全余裕度が向上します。
さらに税金面では、REITの損益通算ができない点を逆手に取り、マンション側で赤字を出さないよう修繕タイミングを調整しつつ、分配金を再投資すると複利効果が高まります。このように、二つの手法は補完関係にあると理解すると、投資計画に柔軟性が生まれます。
シミュレーションで見る10年後の差
まず、築30年マンションを建て替えずに保有し続け、家賃下落率1%/年、空室率10%で計算すると、10年累計キャッシュフローは約1,800万円です。次に建て替えを実施し、家賃を25%アップ、空室率5%と想定し、建て替え費用3,000万円を20年ローン金利1.6%で組むケースでは、減価償却と税制優遇を織り込んだ10年累計キャッシュフローは約2,100万円になります。
一方、建て替えを見送り、3,000万円をREITに投じた場合、分配金4.1%で10年間複利運用すると税引後累計は約1,600万円です。表面上は建て替えが最も高い結果ですが、空室率や金利上昇に弱い点を踏まえると、REITと組み合わせてリスクを分散する案が総合的に安定しやすいといえます。
この比較からわかるのは、資金の時間価値とリスク耐性をどう設定するかで最適解が変わるということです。早い段階で複数シナリオを作り、税引後キャッシュフローで評価する習慣を身につけることが成功への近道になります。
まとめ
本記事では、REITの手軽さとマンション建て替えの成長余地を税金の視点から整理しました。建て替えは高コストながら節税制度と家賃上昇が見込める一方、REITは少額から流動的に運用できる特徴があります。大切なのは両者を二者択一と考えず、収入の波をならす補完関係として設計することです。まずは自己資金、税率、ライフプランを具体的に書き出し、10年後のキャッシュフローを比較してみましょう。その一歩が、将来の資産形成を大きく左右します。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 東京証券取引所(REIT指数データ) – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省「マンション建替え円滑化法」 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局「住宅・土地統計調査」 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁「所得税法令集」 – https://www.nta.go.jp

