多くの人が「会社員収入だけでは将来が不安」と感じ、安定した不労所得を求めています。しかし、REITを買うべきか実物不動産、とくにシェアハウスに挑戦すべきかで迷う声は少なくありません。本記事では、両者の仕組みとリスク、2025年度の税金対策までを体系的に解説します。読み終えるころには、自分に合った投資スタイルと具体的な次の一歩が明確になるはずです。
不労所得の基本とリスクを正しく知る
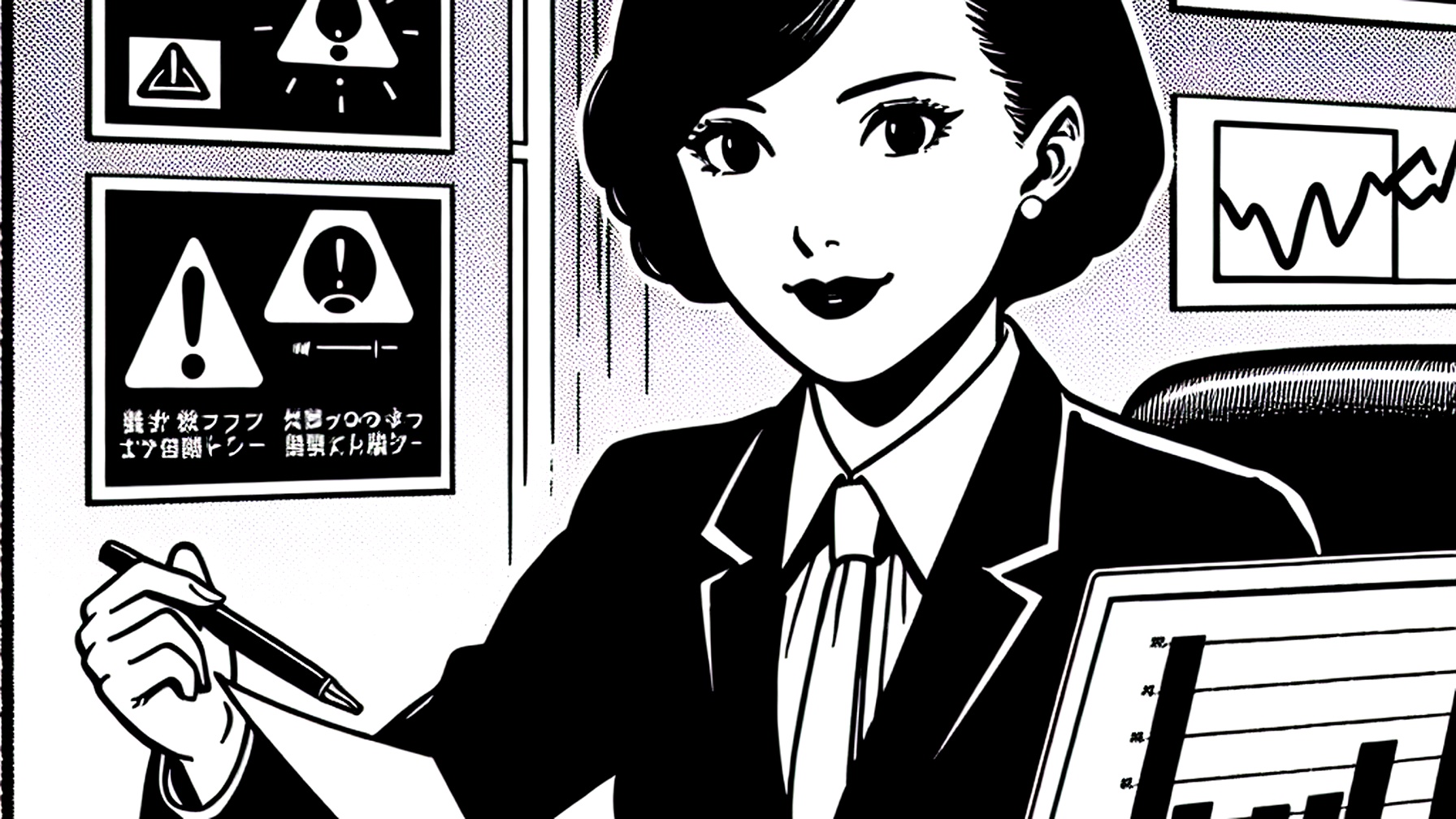
まず押さえておきたいのは、「不労所得=まったく働かない収入」ではない点です。多くの場合、最初の調査や資金計画、定期的な管理確認といった“手間”を先にかけることで、後に時間的ゆとりを生み出します。つまり初期努力を資産に埋め込み、継続的なキャッシュフローを得る仕組みが重要になります。
一方、リスクを過小評価すると目標に届きません。総務省「家計調査」(2025年版)によると、家賃収入を得ている世帯の年間空室率は平均9.2%です。株式配当の変動幅と比べれば小さく見えますが、ローンを抱えたまま収入が止まる可能性は精神的負担が大きいといえます。
加えて、資産価値の減少や修繕費の突発的な発生は避けられません。これらを緩和する方法として、複数の収益源を組み合わせる分散投資が有効です。次の章から、候補となるREITとシェアハウスを詳しく見ていきます。
株式市場で買えるREITの仕組みと魅力
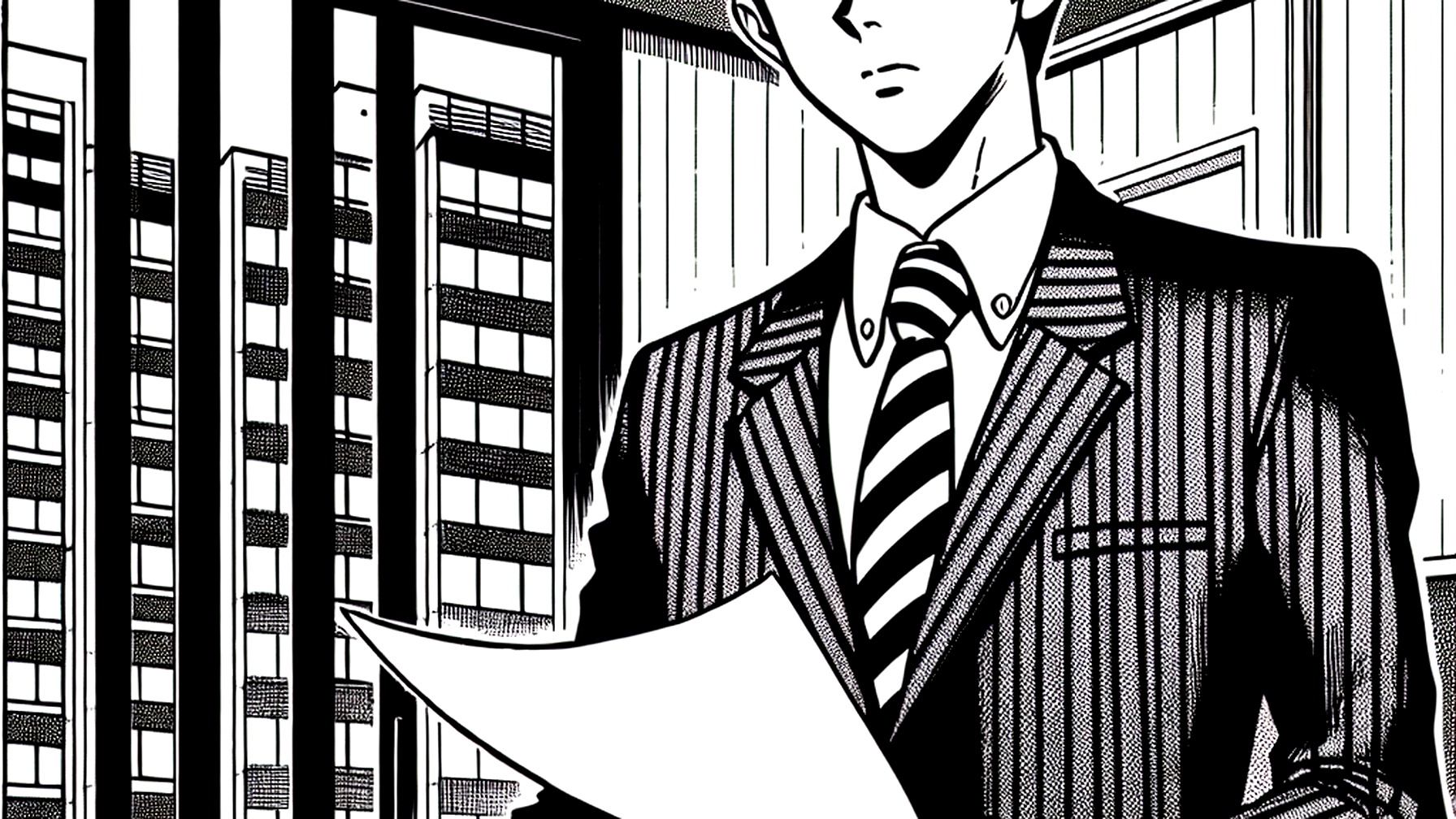
ポイントは、REITが少額から購入でき、運用と管理をプロに任せられる点です。東京証券取引所のREIT指数は2025年10月時点で1,990ポイント前後を推移し、配当利回りは平均4.1%と公表されています。銀行預金金利が0.02%程度にとどまる現状を踏まえると、インカムゲインを狙いやすい資産といえます。
REITは「不動産投資信託」の略称で、投資家から集めた資金でオフィスビルや物流倉庫、住居などを購入し、賃料収入を投資家に分配する仕組みです。法律上、利益の九割超を配当に回すため、分配金が安定する特徴があります。また、株式と同様に証券口座で売買できるため、物件購入時の印紙税や登記費用がかかりません。
気を付けるべきは価格の変動リスクです。東証データでは、コロナ禍直後の2020年3月から2023年末にかけて、月間最大下落幅が約30%に達しました。分配金は減りにくい一方、価格が下がれば含み損が生じます。よって、配当利回りだけでなく、保有期間中の価格変動に耐えられる資金計画が欠かせません。
税金面では、分配金が「配当所得」に区分され、上場株式と同じく20.315%の源泉徴収が行われます。特定口座を利用すれば確定申告が不要ですが、他の株式損失と損益通算する場合や、所得が900万円を超えてふるさと納税の控除上限を上げたい場合などは申告した方が有利です。
シェアハウス投資の最新トレンドと注意点
実は、シェアハウス市場にはここ数年で大きな変化がありました。国土交通省「賃貸住宅市場調査2025」によると、全国のシェアハウス戸数は約7.6万室で前年より4.3%増えています。外国人留学生や短期転勤者の需要が戻りつつあることが背景です。
シェアハウスの魅力は、1戸当たりの賃料は低くても、複数入居者の合計家賃で高い利回りを確保しやすい点にあります。例えば都内23区の木造2階建て物件をリノベーションし、6室で運営したケースでは、表面利回り10%前後が珍しくありません。一般的なワンルーム投資の6%程度と比較すると、キャッシュフローに余裕が生まれます。
しかし、運営コストがかさむ点を軽視すると失敗します。共有部の光熱費や清掃費、人間関係のトラブル対応など、通常の賃貸より管理が複雑です。また、2018年のシェアハウス融資問題を受け、金融機関は自己資金3割以上を求める傾向が続いています。資金繰りに無理がないかを常に点検し、運営会社との契約内容を精査する必要があります。
2025年度はシェアハウス関連の特別補助金や新しい減税制度は公表されていません。ただし、省エネ改修を行う場合に利用できる「住宅省エネ2025キャンペーン」の補助対象になり得るケースがあります。公式ガイドラインでは、共有部分の断熱改修費用が補助率上限以内なら申請可能と明記されています。適用可否は施工内容で変わるため、事前に専門業者へ相談しましょう。
税金を味方につける2025年度の節税ポイント
重要なのは、税制を正しく理解し、合法的に手取りを増やすことです。不動産所得は総合課税で累進税率が適用されるため、所得が高いほど節税の効果が大きくなります。2025年度の所得税法では、青色申告特別控除(65万円または55万円)が継続しており、電子帳簿保存と期限内申告が条件です。
不動産所得と給与所得の損益通算は引き続き認められています。ただし、国税庁は赤字が長期化するケースを“租税回避のおそれ”として注視すると公表しています。減価償却の計算や修繕費の計上タイミングを適切に行い、実態を伴う経費だけを計上する姿勢が求められます。
また、個人で複数物件を所有し規模が大きくなった場合、家族経営の合同会社へ移行する選択肢があります。法人化すると実効税率が23.2%前後に一定化し、給与所得控除を活用した所得分散も可能です。ただし、法人設立費用や社会保険加入義務が発生するため、シミュレーションは必須です。
REITに関しては、NISA(少額投資非課税制度)の新制度が2024年から恒久化され、年間投資枠を活用すれば分配金と譲渡益が最長で無期限非課税となります。一般NISAの成長投資枠を用いてREITを買い付け、シェアハウスからの不動産所得と合算することで、課税所得の分散が図れます。
ポートフォリオで考える安定収益の組み立て方
まず、短期的な流動性と長期的な利回りを組み合わせる視点が欠かせません。REITは売買が容易で、キャッシュポジションを調整しやすい一方、価格変動リスクがあります。これに対し、シェアハウスは現金化に時間がかかる反面、賃料が数年単位で読める安定要素があります。
言い換えると、両者を組み合わせればメリットの補完が期待できます。例えば、手元資金1,000万円のうち300万円をNISAでREITへ、700万円を頭金としてシェアハウスを取得し、残りはローンを活用するプランが考えられます。東証REIT配当利回り4.1%とシェアハウス実質利回り8%を想定すると、平均利回りは約6.7%となり、単一投資よりブレが小さくなる計算です。
さらに、ライフイベントに備えた資金計画が必要です。家族構成の変化や退職時期を踏まえ、売却出口を複数設定すると安心感が増します。REITは証券口座で即日換金できますが、シェアハウスは最低でも3〜6か月の売却準備期間を見込み、ローン残高と市場価格の乖離を定期確認することが大切です。
最後に、情報収集の質が成果を左右します。国交省の統計や金融庁の開示資料をチェックし、セミナーやSNSの体験談は裏付けデータと照合しましょう。正確な数字と自分の投資目的を結びつけることで、ブレないポートフォリオが完成します。
まとめ
結論として、REITとシェアハウスは性質が異なるものの、組み合わせることで安定した不労所得の柱を築けます。REITは少額・高流動性、シェアハウスは高利回り・低流動性という強みを持ち、税金面ではNISAや青色申告を活用することで手取りを最大化できます。この記事を参考に、自身のリスク許容度と資金計画を見直し、まずは少額のREIT購入や物件見学から一歩踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 賃貸住宅市場調査2025 https://www.mlit.go.jp/
- 総務省 家計調査年報2025 https://www.stat.go.jp/
- 東京証券取引所 REIT指数統計データ https://www.jpx.co.jp/
- 金融庁 NISA制度の概要 https://www.fsa.go.jp/
- 国税庁 令和7年度(2025年度)所得税法等の改正のあらまし https://www.nta.go.jp/

