マンション投資に興味はあるものの、「本当に儲かるのか」「損をしない方法はあるのか」と不安を抱く人は少なくありません。特にネット上には成功談と同時に「マンション投資 危険」というキーワードもあふれ、情報が錯綜しています。この記事では、2025年10月時点で明らかになっているリスクとその見極め方を具体的に解説します。読み終えるころには、ご自身の判断軸を持ち、無理なく安全に投資を検討するための基礎知識が身につくはずです。
なぜ価格上昇だけを信じると危ういのか
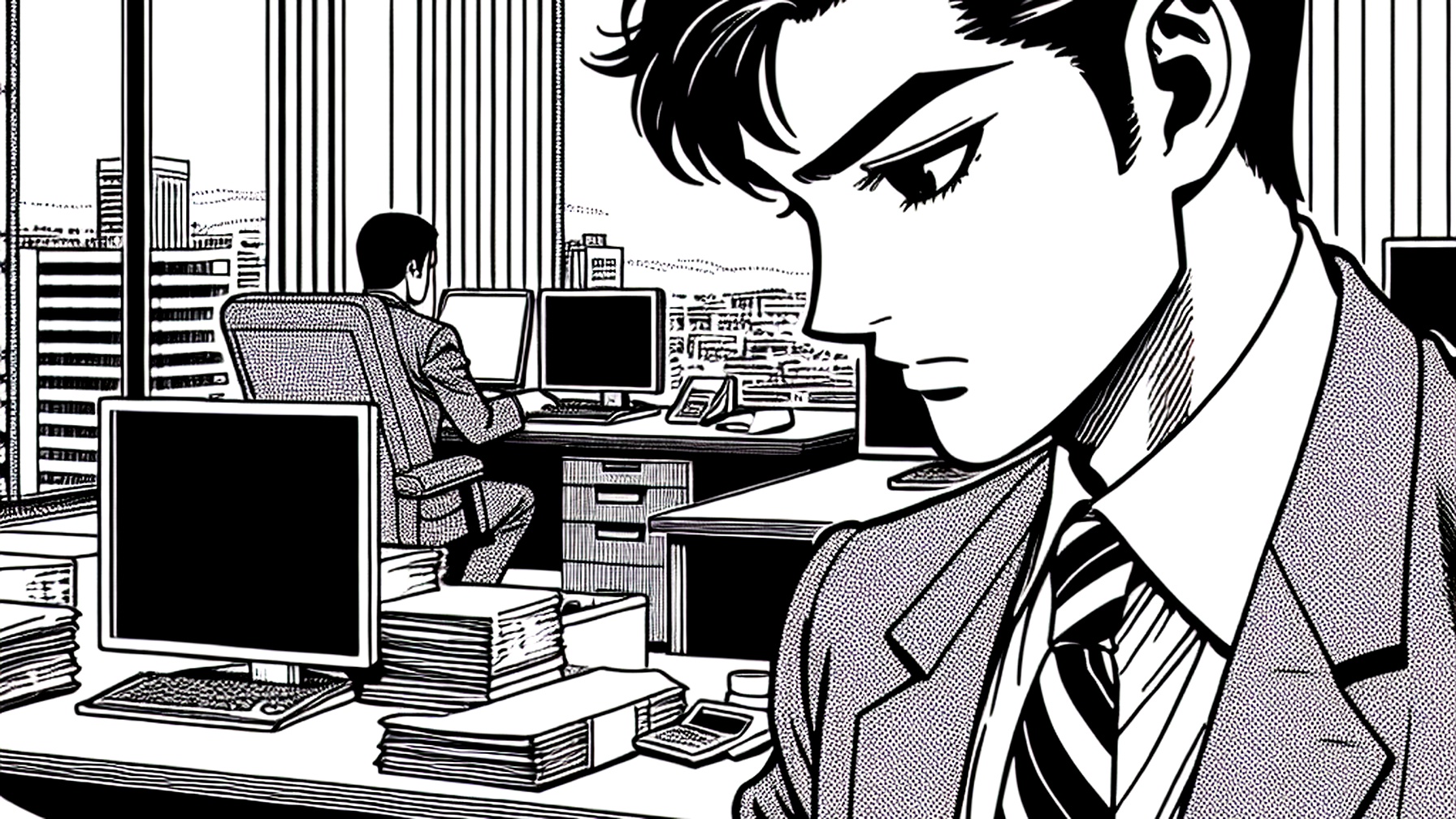
重要なのは、直近の価格トレンドだけで投資判断をしないことです。価格が上がり続けるという思い込みは、最初の落とし穴になります。
まず、東京23区の新築マンション平均価格は2025年10月時点で7,580万円と過去最高を更新しました。しかし、不動産経済研究所のデータでは、同じ23区内でも立地や駅距離によって成約速度に大きな差があると示されています。つまり「都心だから安心」という単純な図式は成り立たないのです。
さらに、国土交通省の住宅着工統計を見ると、首都圏の供給戸数は2023年から緩やかに増加しています。供給が増える一方で人口が横ばい、あるいは緩やかに減少するエリアでは、販売価格が下がるタイミングが訪れやすくなります。価格は永遠に右肩上がりではなく、市場環境によって調整局面が必ず来ることを意識すべきでしょう。
実は、不動産価格は金利や景気と連動する側面もあります。景気後退期に入ると高額物件ほど値下がり幅が大きい傾向があり、短期の差益狙いで購入すると想定外の損失を抱えるケースが少なくありません。したがって、価格上昇のみを根拠に投資を決めることこそ大きなリスクと言えます。
空室リスクと人口動態をどう読むか
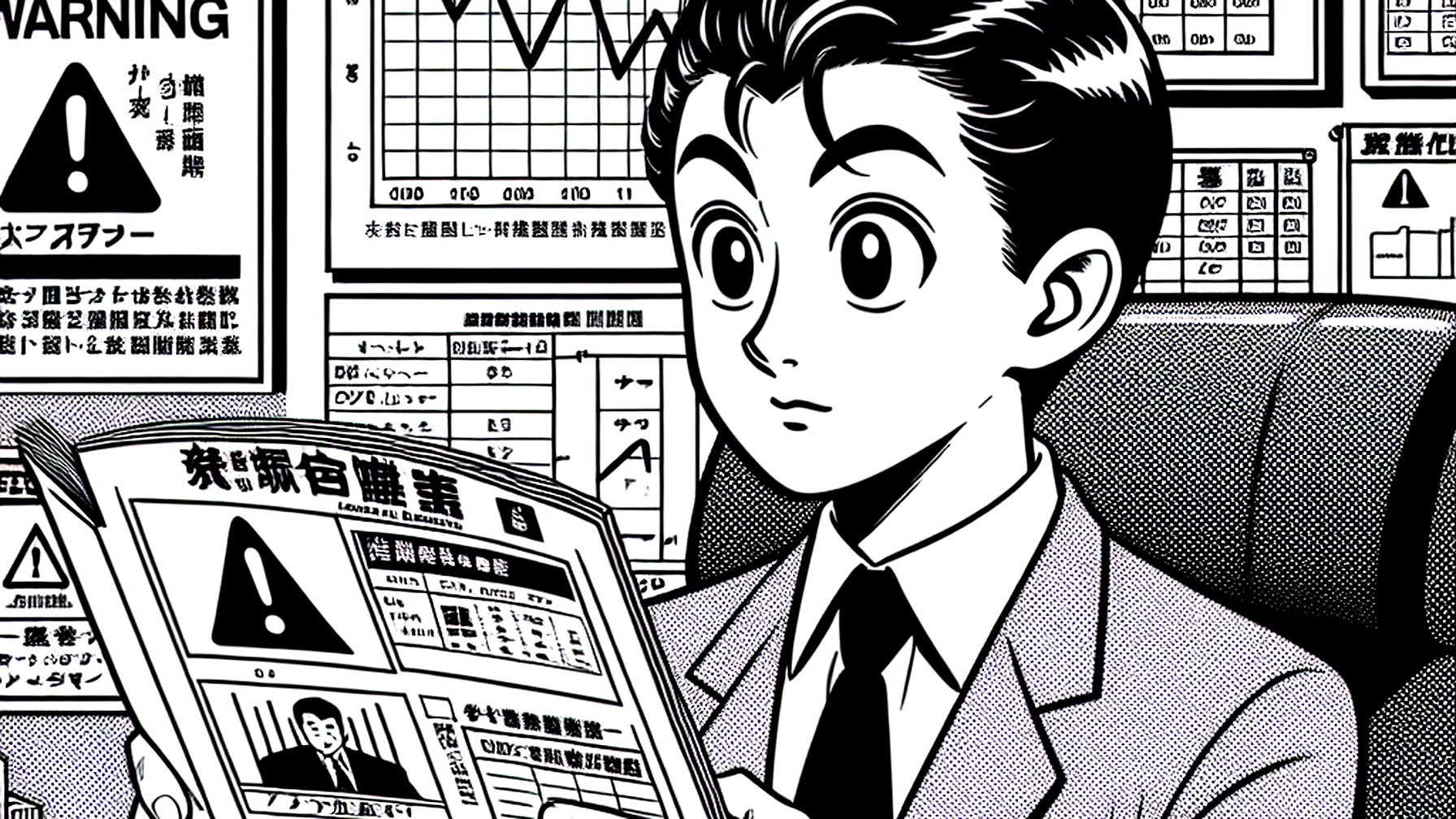
ポイントは、エリアごとの人口動態を具体的な数字で確認することです。空室リスクは物件固有の問題だけではなく、街全体の将来像と深く結びついています。
総務省の住宅・土地統計調査によると、全国の集合住宅空室率は2023年時点で13.6%でしたが、地方都市では20%を超える地域もあります。郊外の築浅マンションであっても、若年人口の流出が続けば将来の空室率は高まります。つまり、築年数や設備だけでなく、地域の人口推移を読み取る力が欠かせません。
一方で、都心部でも安心はできません。単身者向けワンルームが過剰供給気味なエリアでは、競合物件が多く賃料下落が起こりやすくなります。例として、山手線沿線の一部地域では、2024年以降新築ワンルームの供給が年間5,000戸を上回り、築古物件が値下げ合戦に巻き込まれました。賃料が下がれば利回りは急速に低下します。
また、空室期間が長引くほど広告費やリフォーム費がかさみ、キャッシュフローを圧迫します。人口動態データに加え、周辺の供給計画や再開発の進捗状況まで把握することで、空室リスクを数値的にシミュレーションできるようになります。
キャッシュフローを削る“隠れコスト”の存在
実は、購入後に出てくる支出を見落とすと、表面利回りが高くても手残りはほとんど残りません。ここで鍵になるのが修繕積立金と管理費の将来的な上昇です。
新築時の修繕積立金は抑えられて設定されることが多く、築10年を過ぎると2倍以上になる例も珍しくありません。財務省のマンション総合調査でも、築15年超の物件では月額平均1.8万円まで上昇しています。購入時に月々の収支が黒字でも、積立金改定で赤字に転落するケースが後を絶たないのです。
さらに、入居者の退去に伴う現状回復費用や、給排水管の更新など突発的な修繕が必要になることもあります。これらは長期保有を前提とするほど無視できない金額になります。つまり、購入前に長期のキャッシュフロー表を作成し、収益と支出を少なくとも20年間はシミュレートする作業が重要です。
加えて、副業として運営する場合は、確定申告に時間と手間がかかります。簿記ソフトの導入費や税理士報酬も“隠れコスト”になりやすいので、最初から計算に入れておくと収支のブレを小さくできます。
金融機関選びと金利変動が利益を左右する
まず押さえておきたいのは、同じ物件でも融資条件が変われば利回りが大きく変動するという事実です。マンション投資では自己資金よりも金利のインパクトのほうが大きい場合が多々あります。
2025年度の住宅ローン金利は長期固定で1.7%前後、変動で0.5%台が一般的ですが、投資用ローンは1.9〜3.5%と幅があります。日本銀行の統計でも、1%の金利差は3,000万円を30年で借りた場合、総支払額に約500万円の開きが出ると試算されています。したがって、金融機関ごとの融資姿勢や審査基準を比較する労力は惜しむべきではありません。
また、変動金利を選んだ場合は将来の金利上昇リスクを見逃せません。日銀が金融緩和を段階的に縮小すると、金利は徐々に上向く可能性があります。固定金利であれば安心という声もありますが、固定にすると当初金利が高くなるため、短期的なキャッシュフローは圧迫されやすい点に注意が必要です。
金融機関選びと併せて、繰上返済や借り換えの余地を残しておくとリスクヘッジになります。借入条件を定期的に見直し、自分の収入や金利環境に最適化する姿勢が、長期的な収益安定につながります。
法制度と管理トラブルを軽視しない
ポイントは、マンション管理に関わる法制度が年々強化されていることを理解することです。遵守を怠ると、思わぬトラブルで収益が削られる可能性があります。
2025年4月に全面施行された改正マンション管理適正化法では、長期修繕計画の作成と定期見直しが義務化されました。計画がない、または不足がある場合、管理組合が行政指導を受ける恐れがあり、その費用をオーナーが負担するケースも想定されます。購入前に管理組合の運営状況と修繕計画書を確認することが欠かせません。
さらに、民泊解禁エリアが拡大する一方で、住民間のトラブルも報告されています。民泊が横行すると賃貸マンションの居住環境が悪化し、長期入居者が退去する事例が増えています。管理規約で民泊禁止の条項を設けても、監視体制が不十分だと違反を止めるのは困難です。法的手続きや管理会社との連携体制を事前に確認し、トラブル発生時の対応フローを把握しておくと安心です。
最後に、2025年度の固定資産税評価替えは地価上昇エリアで負担増が見込まれます。税負担は賃料に転嫁しにくい費用であり、収支シミュレーション時に反映しておかないと利回りが目減りします。法制度の動向と税負担を一体で考えることが、安定経営の近道になります。
まとめ
本記事では、価格上昇への過信、人口減少による空室リスク、修繕費などの隠れコスト、金利変動、そして法制度面の注意点という五つの視点からマンション投資の危険性を整理しました。結論として、リスクは正しく把握し適切に対策を打てば大幅に軽減できます。具体的には、公的データで人口と供給を確認し、長期キャッシュフローを作り、複数金融機関を比較し、管理組合の健全性を見極めることが欠かせません。これらを丁寧に実行することで、マンション投資は危険ではなく、安定した資産形成の手段に変わります。今日得た知識をもとに、まずは気になるエリアの人口動態と管理状況を調べる一歩から始めてみてください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudosan-keizai.co.jp
- 国土交通省 住宅着工統計 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 統計データベース 長期金利推移 – https://www.boj.or.jp
- 東京都都市整備局 空家実態調査 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

