不動産投資に興味はあるものの「多額の自己資金や専門知識が必要そう」と二の足を踏む人は多いはずです。実は上場不動産投資信託(REIT)なら、小口の資金で本格的な不動産運用に参加でき、日々の管理業務も不要です。本記事では、2025年10月時点での最新データを交えながら、REITを使った副業を“簡単”に始める方法とメリットを詳しく解説します。読み終えた頃には、具体的な購入ステップやリスク対策までイメージできるようになるでしょう。
REITとは何かと基本構造
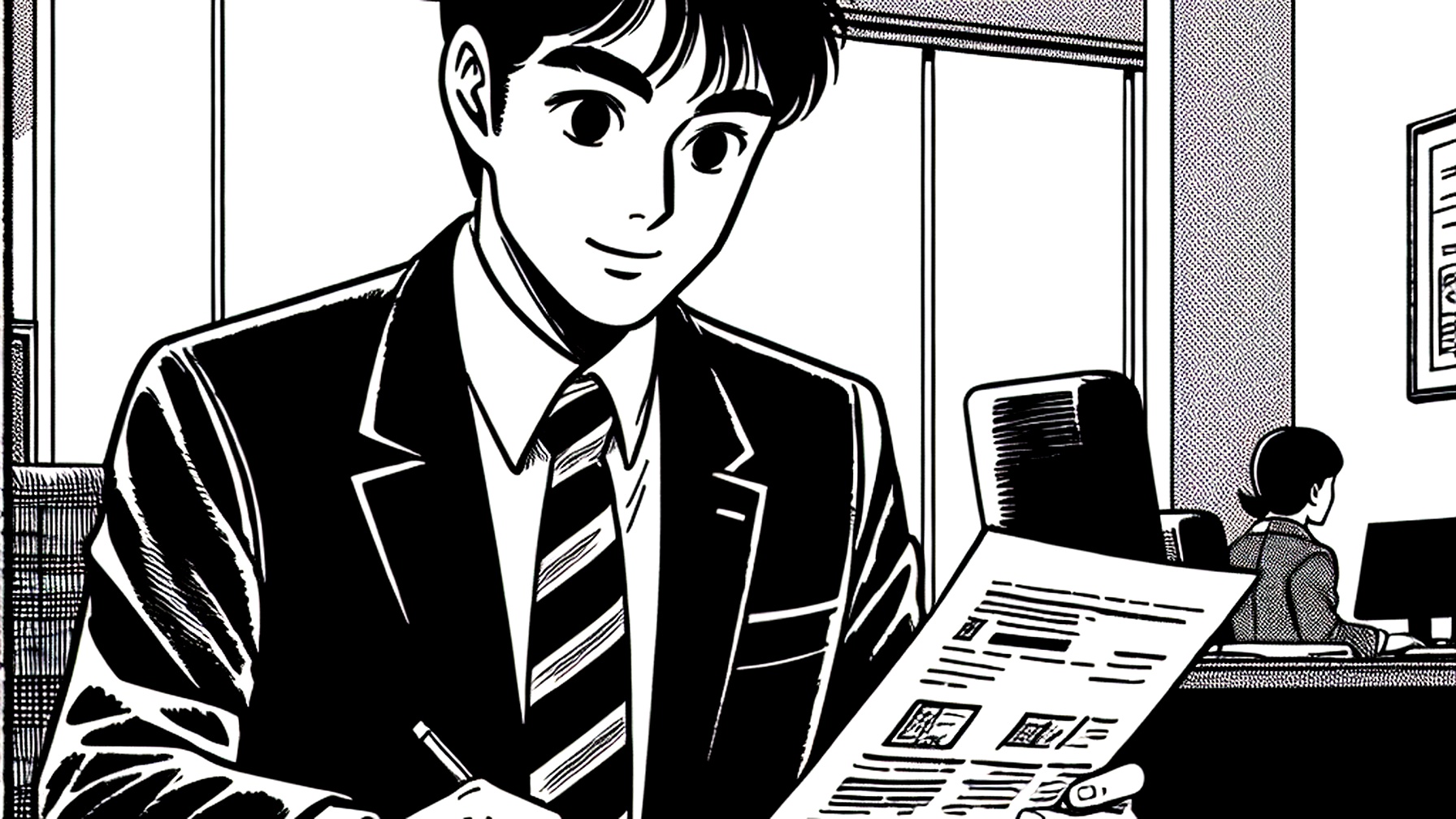
まず押さえておきたいのは、REITが「投資家から集めた資金で複数の不動産を取得し、その賃料や売却益を分配する仕組み」だという点です。投資信託の一種で、株式と同様に証券取引所に上場しているため、売買は証券口座からワンクリックで完結します。
REITを運用するのは「資産運用会社」と呼ばれる専門集団です。物件選定からテナント募集、修繕計画までを一括して行うので、投資家は管理業務に関わりません。つまり、区分マンション投資のように家賃滞納や設備故障に頭を悩ませる必要がないのです。
また、REITは法律上、不動産収益の90%超を投資家に配当することで法人税が実質的に免除されます。国土交通省の2025年「不動産証券化統計」によれば、東証REIT指数の平均分配利回りは3.8%前後で推移しており、長期国債利回り(約1.1%)を大きく上回っています。利回りの高さと税制メリットが相まって、安定配当を狙う副業先として注目を集めています。
さらに、複数物件を一つのポートフォリオで保有するため、空室リスクが個人保有より分散されやすい点も特徴です。たとえば商業施設特化型のREITでも、都市ごとにテナント構成を分けることで、地域景気の偏りを緩和しています。小口でありながら分散効果を享受できる点は、初心者にとって大きな魅力でしょう。
副業にREITを選ぶメリット
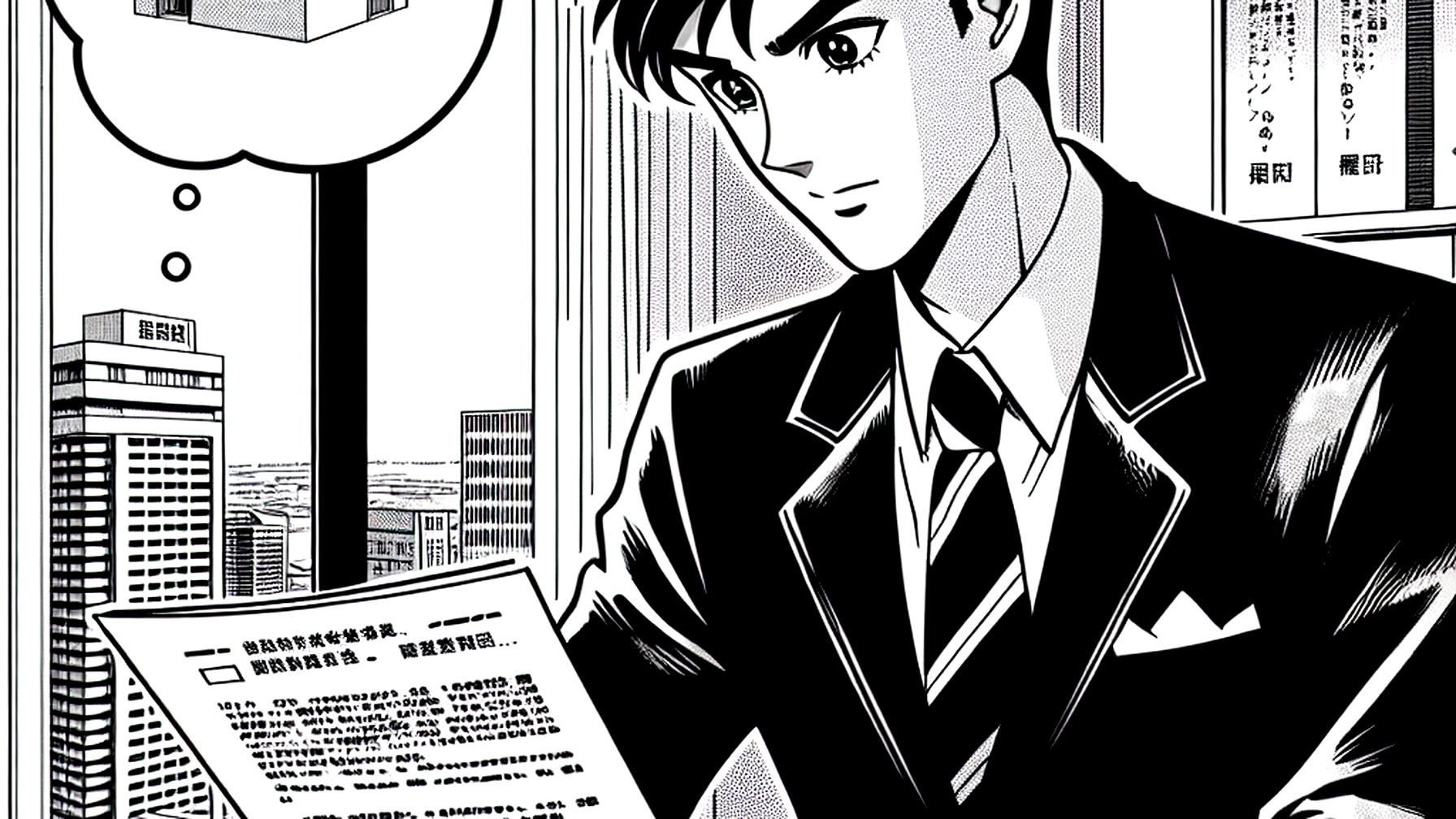
重要なのは、副業として取り組む場合にREITが他の投資より時間と手間を節約できることです。平日日中に働く会社員でも、スマホアプリで価格を確認し、注文を出すだけで参加できます。
第1のメリットは「流動性」です。一般の不動産は売却まで数か月を要しますが、REITは株式同様に1営業日で現金化できます。このため急な資金需要が発生しても、処分を慌てずに済みます。
第2に「情報開示の透明性」が挙げられます。上場規則により四半期ごとに財務データや運用レポートが公表されるため、家賃収入や入居率の変化を定量的に把握できます。日本取引所グループの2025年版ファクトブックによると、平均入居率の月次開示率は95%を超えており、個別不動産より格段に情報が豊富です。
そして第3が「少額投資のしやすさ」です。2025年10月時点で最も価格が低い銘柄は1口5万円前後から購入可能で、一般NISA口座を利用すれば年間240万円までの分配金が非課税となります。副業収入の税負担を抑えたい人にとって、制度面の利点は見逃せません。
仕組みが簡単な理由と購入方法
ポイントは、REITが「証券投資の形をとる不動産」であるため、手続きや管理が簡素化されていることです。ここでは、実際に購入するまでの流れを順を追って確認します。
最初に必要なのは証券会社の口座開設です。すでに株式取引をしている人であれば、そのままREITも購入できます。口座を作る際は、手数料水準と取扱銘柄の多さを比較しましょう。ネット証券各社の2025年手数料は約定代金100万円まで無料化が進んでおり、取引コストをほぼゼロにできます。
次に銘柄を選定します。利回りだけを見ると高配当銘柄に目が行きがちですが、運用方針や含み益の状況も必ず確認します。投資法人が公表する「資産運用報告書」には、鑑定評価額と取得価格の差額が開示されており、含み益が大きいほうが資産価値の下支えになります。
購入自体は株式と同じ注文画面で行います。最低売買単位は1口なので、例えば100万円の予算でも2〜3銘柄に分散できるでしょう。分配金は年2回支払われる銘柄が多く、配当金自動受取サービスを設定すれば、手間なく副業収入を得られます。
最後に、保有後の管理は「運用報告書の確認」と「適宜のリバランス」に集約されます。報告書はPDFで配信されるため、通勤中にスマホで確認するだけで十分です。リバランスは半年に1度、銘柄の比率を見直す程度で、実働時間は月1時間もかかりません。
リスクと上手なコントロール術
実は、REITにも価格変動や金利上昇といったリスクが存在します。しかし適切なコントロール策を講じれば、大きなダメージを避けやすくなります。
まず価格変動リスクへの対策として「分散投資」を徹底します。オフィス主体型、物流施設型、住宅型など、用途の異なる銘柄を組み合わせることで景気変動の影響を均等化できます。金融庁の2025年資産運用白書では、用途分散を行ったポートフォリオの年間価格変動率が単一用途より約25%低下したと報告されています。
次に金利上昇リスクです。REITは借入金を利用してレバレッジをかけるため、金利が上がると分配金が減少する可能性があります。確認すべき指標は「LTV(負債比率)」と「平均借入金利」です。LTVが50%以下、平均借入金利が1%台の銘柄は、急激な金利上昇局面でも耐性が高いと評価されています。
さらに自然災害リスクにも注意が必要です。耐震補強や立地分散に積極的な銘柄を選び、保険加入状況もチェックしましょう。2025年度からは、REIT向け地震保険料率が一部引き下げられ、保険加入率は過去最高の92%に達しています。保険加入状況をIR資料で確認すれば、災害損失を織り込んだリスク管理体制の有無が見えてきます。
2025年時点の市場動向と今後の見通し
まず、足元の市場環境を押さえると、2025年10月の東証REIT指数は2,050ポイント前後で推移し、前年同月比で約6%上昇しています。オフィス空室率の改善とインバウンド需要の回復が背景にあります。
一方で米国の利上げペースが鈍化したことで、国内長期金利の上昇も限定的となり、REITの分配利回りの優位性が保たれています。日本銀行が2025年9月に示した指し値オペの柔軟化方針でも、住宅ローン金利の急騰は避けられるとの見方が多く、金融環境は穏やかです。
今後の注目点は、脱炭素ニーズを取り込む「グリーンREIT」の拡大でしょう。環境性能の高いビルや太陽光発電施設を組み込む銘柄が増え、ESG投資マネーの流入が加速しています。2025年時点で総資産1兆円超の大手REITでは、太陽光由来電力比率を30%以上に引き上げる計画を公表しました。環境配慮型物件はテナント需要も根強く、長期的な賃料上昇を後押しする可能性があります。
結論として、副業目的の個人投資家にとって、REIT市場は流動性と配当利回りの両面で魅力的な環境が整っています。今後も金利動向とESGトレンドを注視しつつ、用途分散と財務健全性に優れた銘柄を選ぶことで、安定収益を期待できるでしょう。
まとめ
ここまで述べてきたように、REITは小口資金で始められ、管理の手間がほとんどかからない点で「副業に最適な簡単投資」と言えます。流動性の高さ、情報開示の透明性、税制メリットがそろい、2025年の市場環境も追い風です。まずは証券口座を用意し、複数銘柄に分散して少額から試してみることをおすすめします。行動を起こすことで、配当収入が家計の新たな柱となり、資産形成のスピードが一段と高まるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産証券化統計2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 日本取引所グループ 東証REITファクトブック2025 – https://www.jpx.co.jp
- 金融庁 資産運用白書2025 – https://www.fsa.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料2025年9月 – https://www.boj.or.jp
- 一般社団法人投資信託協会 REIT年報2025 – https://www.toushin.or.jp

