副業として不動産投資に興味はあるものの、物件価格の高騰や情報の多さに圧倒され、最初の一歩が踏み出せない方は少なくありません。特に「築古物件なら手が届きそうだけれど、本当に大丈夫だろうか」と不安を感じる声をよく耳にします。この記事では、副業で収益物件を探す初心者が築古物件を活用する際のメリットと注意点を網羅的に解説します。読むことで、物件選びから資金計画、2025年度の制度まで、実践的な知識を得られるはずです。
副業としての不動産投資を始める前に知るべきこと
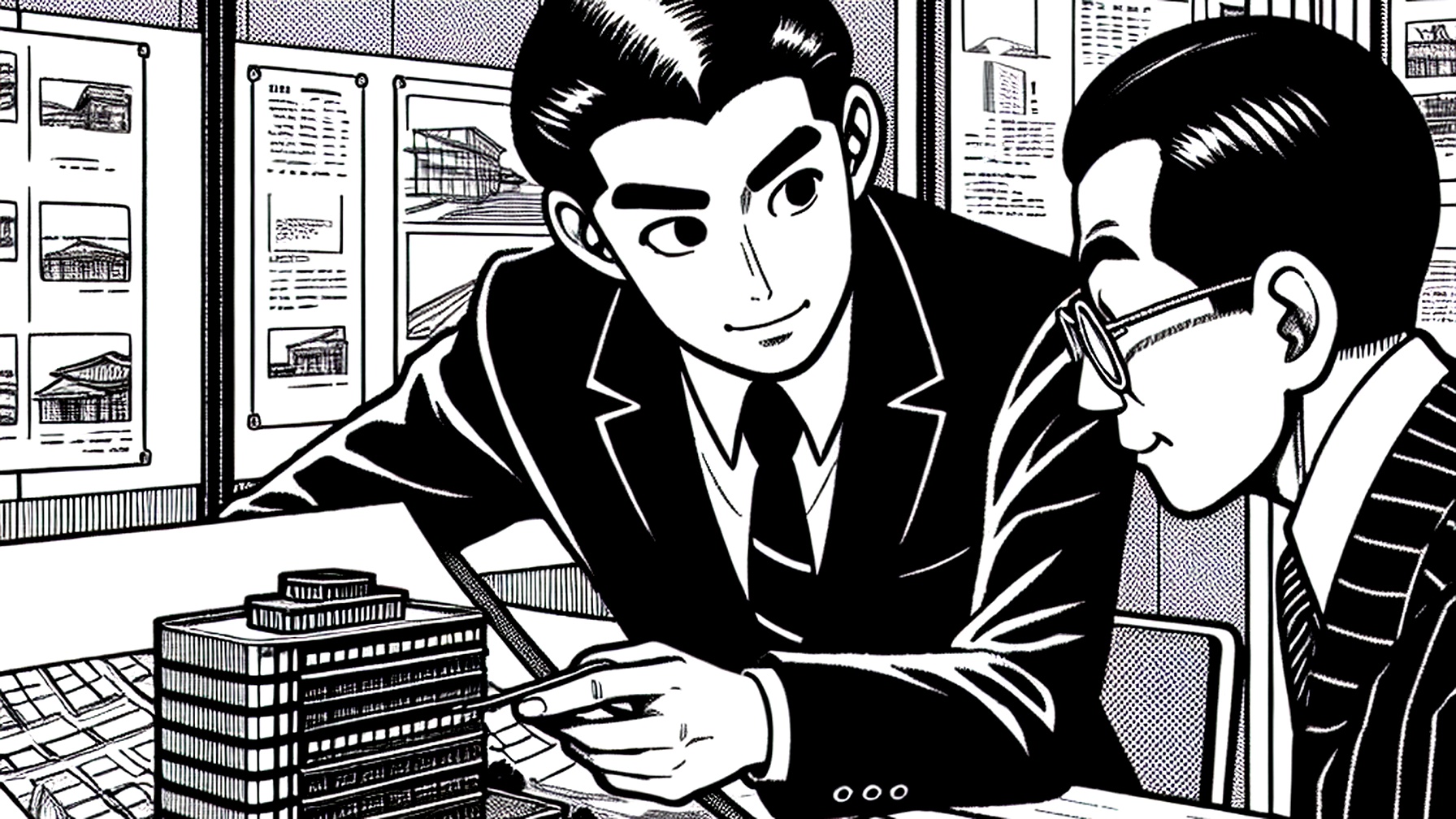
まず押さえておきたいのは、副業で不動産投資を行う目的を明確にすることです。会社員の給与とは別に安定収入を得たいのか、将来の年金代わりに長期保有したいのかで戦略は変わります。目的が定まれば、利回り重視か資産価値重視かなど、物件選定の基準も自ずと絞られます。
一方で、副業として不動産投資を行う場合は、時間と労力のバランスにも注意が必要です。管理を外部に任せるのか、自主管理に挑戦するのかで想定する手間が大きく異なります。副業時間を圧迫しない範囲で収益を最大化するには、自身のライフスタイルを客観的に分析し、管理方針を早めに決めておくことが肝心です。
2024年から2025年にかけて、都心部の新築価格は高止まりしています。そのため少額から参入しやすい築古物件への注目度が高まっています。ただし、築年数が古いほど修繕リスクは増えるので、表面利回りだけで判断すると想定外の出費を招きかねません。次の章では、築古物件が副業向きとされる理由と、そのリスクをどう抑えるかを詳しく見ていきます。
築古物件が副業向きといわれる理由
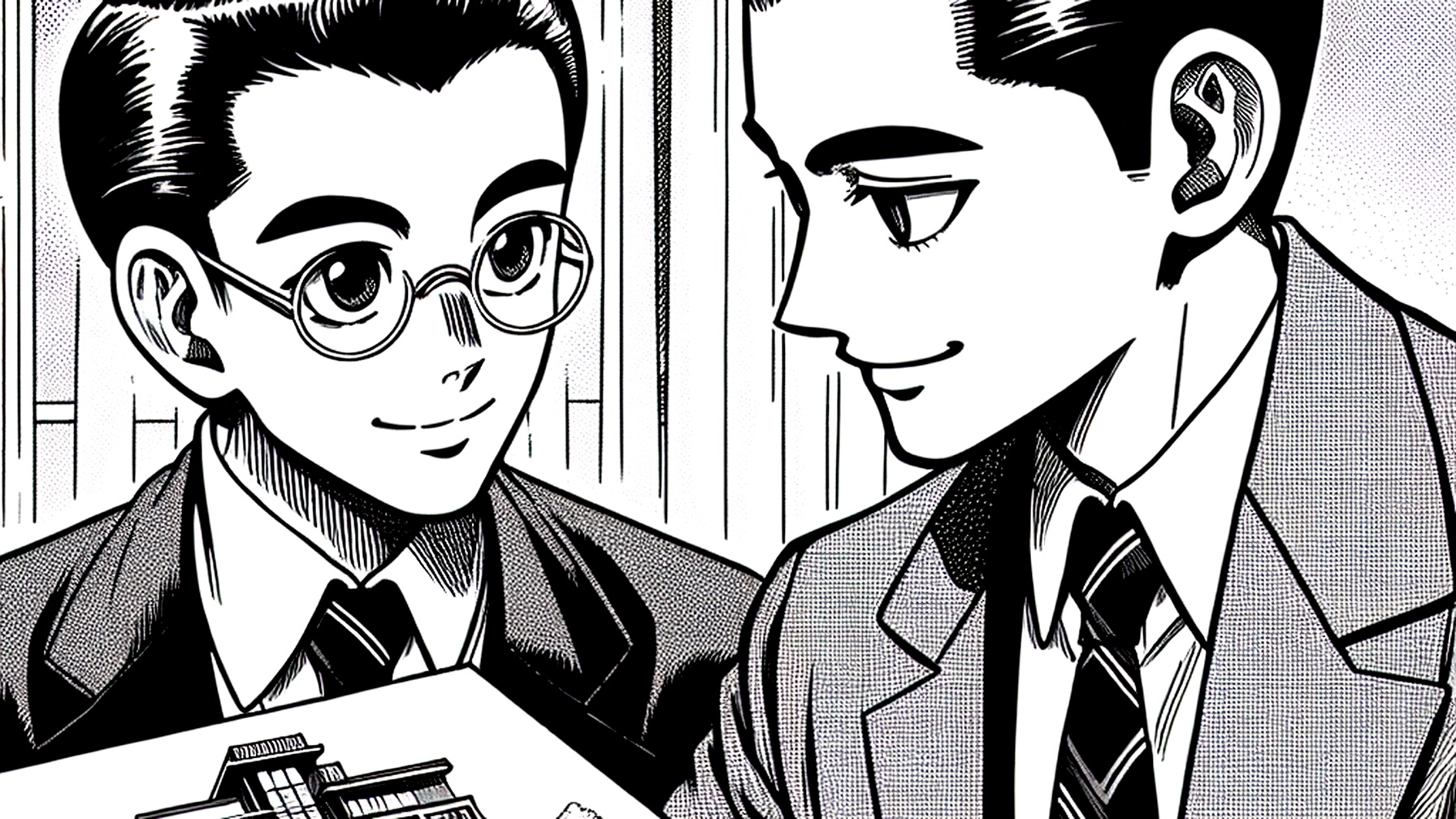
ポイントは、購入価格が抑えられるためレバレッジ効果を効かせやすいことです。築古の区分マンションなら、都心でも500万円前後から探せるケースがあり、自己資金100万円程度で始められる場合もあります。また、建物価格の割合が高いので、減価償却費を経費計上しやすく、所得税の圧縮効果が期待できます。
実は、築古物件は賃料下落が緩やかな傾向があります。国土交通省の賃貸住宅市場データによると、築30年を超える物件の平均賃料は築20年以降からゆるやかな下降線を描き、急落はしません。つまり、最初から賃料が低めに設定されているため、下落幅が限定的でキャッシュフローが読みやすい利点があります。
しかし、重要なのは修繕計画の立て方です。築年が古いほど屋上防水や給排水管など高額修繕が発生しやすくなります。購入前に長期修繕計画を確認し、直近で大規模修繕を終えているかを見極める必要があります。さらに、現地内覧で共用部の清掃状態や入居者層を観察すると、管理体制の良し悪しを定性的に判断できます。
また、副業投資家にとって時間は限られた資源です。築古物件の中でも、すでに管理組合が機能している区分マンションや、信頼できる管理会社が付いている一棟アパートを選ぶことで、運営負担を抑えられます。次章では、具体的な収益物件のチェックポイントを体系的に整理します。
収益物件を選ぶ際のチェックポイント
まず押さえておきたいのは立地です。築古であっても最寄り駅から徒歩10分圏内、人口集中地区(DID)内であれば、退去後のリーシングが比較的スムーズに進みます。総務省の国勢調査によると、DID内の人口は2025年も微増傾向で、地方都市でも中心部は堅調です。一方、郊外のバス便エリアは空室率が高く、改装コストが回収しづらいリスクがあります。
次に、利回り計算は実質ベースで行いましょう。管理費、修繕積立金、固定資産税、空室損を差し引いたネット利回りが5%以上であれば、ローン金利2%前後でもキャッシュフローが黒字化しやすいです。ローン返済比率は家賃収入の50%以下を目安にすると、突発的な修繕にも対応しやすくなります。
物件の構造も見逃せません。鉄筋コンクリート造(RC)は耐久性が高い一方、修繕費が大きくなりやすい特徴があります。木造は修繕費は抑えられるものの、法定耐用年数が22年と短く、ローン期間が制限される場合があります。金融機関によっては、築年数+融資期間が木造で30年以内、RCで47年以内といった基準を設けているため、返済期間とキャッシュフローのバランスを確認しましょう。
最後に、出口戦略を描くことで安心感が増します。将来的に物件を売却してキャピタルゲイン(売却益)を狙うのか、完済後も家賃収入を得続けるのかで、運営中の意思決定も変わります。特に副業投資家は本業のキャリアプランとも絡め、何年後に売却するのかをシミュレーションしておくと判断に迷いません。
2025年度の制度と融資動向を押さえる
実は、2025年度は築古物件を取得する際に活用できる制度がいくつか継続されています。代表的なのが「住宅ローン控除(賃貸併用部分は対象外)」と「固定資産税の新築軽減」。ただし、どちらも築古物件のみを投資用に取得する場合は直接の対象外です。投資家に関係が深いのは、登録免許税の軽減措置と不動産取得税の特例で、一定の要件を満たすと税率が1%下がります。2025年3月31日取得分までの期限付きなので、スケジュールを逆算して契約する必要があります。
金融機関の融資姿勢にも変化があります。日本銀行の「貸出動向調査」では、2024年後半から不動産向け融資の態度が「やや積極的」に転じました。特に地域金融機関は、築古でも家賃実績が安定している物件に積極的です。融資審査では、借上げ保証よりも実際の入居率を重視されるため、売主から過去2年分の家賃表を入手し、稼働実績を提示するとスムーズです。
保証料や団体信用生命保険(団信)の内容もチェックしましょう。2025年4月から、一部のノンバンクで団信を付帯しないプランが選択可能になりました。保険料を抑えつつ金利が0.3%ほど高くなるため、キャッシュフローとの兼ね合いで選択肢が広がっています。副業投資家は融資枠を有効に使うために、複数行を比較し、物件によって最適な組み合わせを検討すると良いでしょう。
リスク管理と出口戦略の立て方
重要なのは、想定外を想定内に変えておく姿勢です。築古の収益物件では、突発的な設備故障や入居者トラブルが起こり得ます。あらかじめ年間家賃収入の10%を修繕予備費として積み立てておけば、急な出費でも資金繰りに困りません。また、家賃保証会社を利用すると、滞納リスクを一定程度抑えられます。
空室対策としては、ターゲット入居者を明確にし、内装リフォームを差別化する方法が有効です。例えば、築30年のワンルームでも、インターネット無料や家具家電付きプランを導入すると、単身赴任層の需要を取り込めます。国土交通省の調査では、ネット無料を導入した物件の平均空室日数が30%短縮したというデータもあり、初期投資以上の効果が期待できます。
出口戦略では、売却時期の目安を「大規模修繕の前後」で設定すると合理的です。修繕前に売るなら、改装費を買主に織り込んだ価格交渉が必要ですし、修繕後に売るなら販売価格を上乗せできるメリットがあります。築古物件の場合、耐用年数の残りを意識する買主も多いため、早めに不動産仲介会社に相談し、市場動向を把握することが大切です。
加えて、本業の収入や家族構成の変化も出口戦略に影響します。転勤や独立などでライフプランが変わった際は、物件保有の意義を再確認し、売却か追加購入かを判断すると良いでしょう。柔軟に計画を見直す姿勢こそ、長期的な副業成功の鍵になります。
まとめ
今回の記事では、副業 収益物件 築古物件というキーワードを軸に、物件選びから制度活用、リスク管理までを解説しました。築古物件は手頃な価格と税務メリットが魅力ですが、修繕リスクを軽視すると収益が圧迫されます。ネット利回りで5%以上を確保し、修繕予備費を積み立てることで、安定したキャッシュフローが得られるでしょう。これから物件を探す方は、2025年度の税制特例期限を意識しつつ、複数の金融機関を比較して最適な融資を組むことをおすすめします。行動を先延ばしにせず、学んだポイントを具体的な物件調査に活かしてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 国勢調査 2025年速報値 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 貸出動向調査 2025年7月 – https://www.boj.or.jp
- 不動産流通推進センター 賃貸市場データブック2025 – https://www.retpc.jp
- 東京都住宅政策本部 賃貸住宅実態調査 2024 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

