築年数が30年を超えるアパートを購入しようとすると、「本当に採算が合うのか」「空室ばかりではないか」と不安になる方が多いものです。実は、築古物件には新築にはないメリットがある一方で、見落としやすい固有のリスクも潜んでいます。本記事では、長年アパート経営を支援してきた立場から、築古アパートの代表的なリスクと具体的な対策を丁寧に解説します。読み終えたときには、数字の裏付けをもとに物件を見極め、収益を安定させるための視点が身につくはずです。
築古アパートに潜む三大リスク
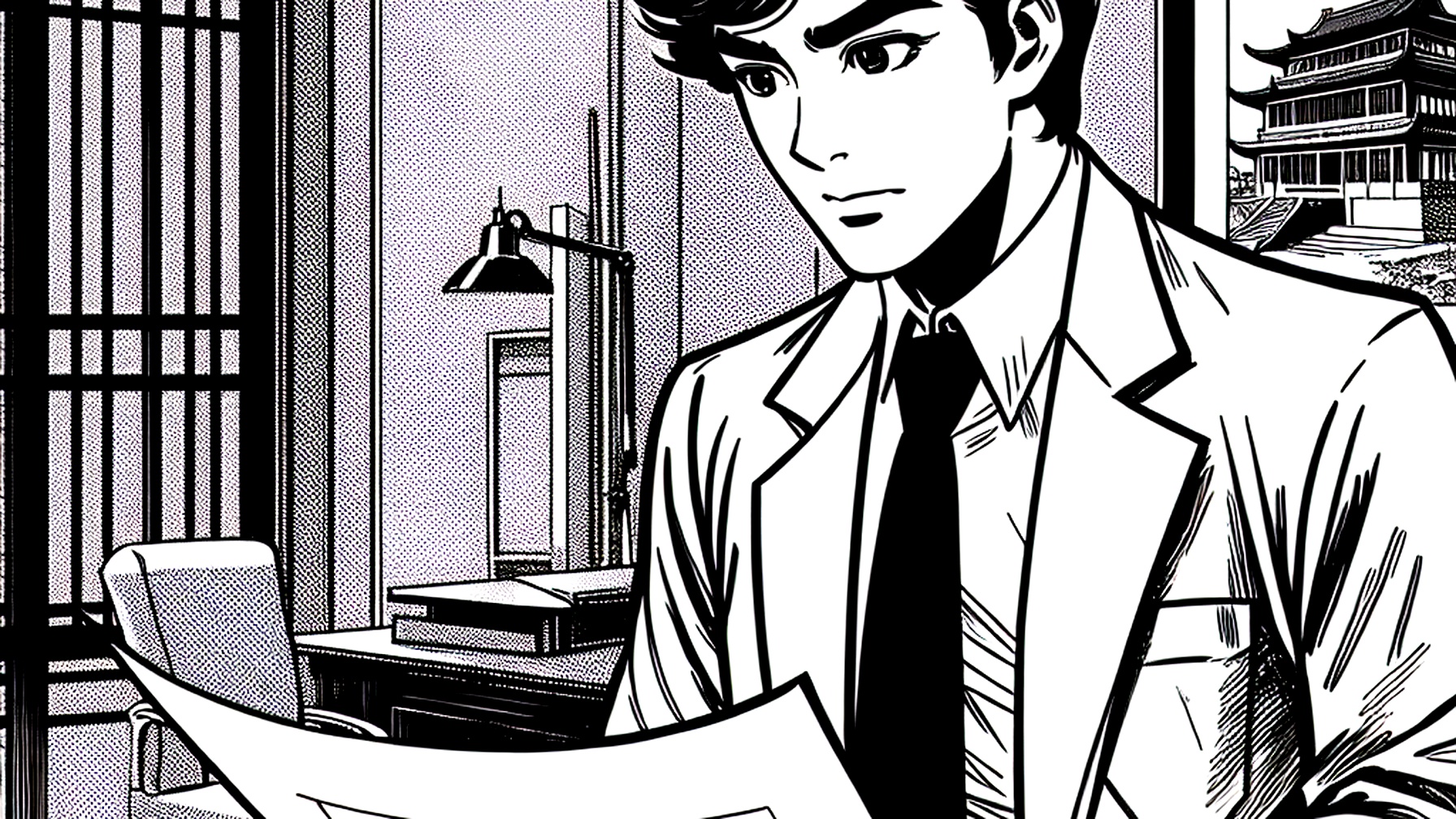
重要なのは、築古特有のリスクを「家賃」「設備」「法規制」の三つに整理して把握することです。これらは互いに絡み合い、表面的な利回り計算では見えないコストを生み出します。
まず家賃水準は周辺の新築や築浅に比べ下がりやすく、募集期間も長期化しがちです。国土交通省住宅統計によると、2025年8月時点の全国アパート空室率は21.2%で、前年より0.3ポイント改善したものの依然として高水準にあります。築古ほど競争力を失いやすい点を無視できません。
次に設備面です。給排水管や屋根防水の寿命は30年前後とされ、突発的な漏水や雨漏りが長期休業に直結します。修繕履歴が曖昧なまま購入すると、想定利回りが一気に崩れる恐れがあります。
最後に法規制リスクです。1981年以前の旧耐震基準で建てられた物件は、地方自治体の指導で耐震診断や補強を求められる場合があります。費用が高額になって初めて収支が赤字化するケースもあるため、購入前の専門家による調査が不可欠です。
空室率と賃料下落を見抜く方法
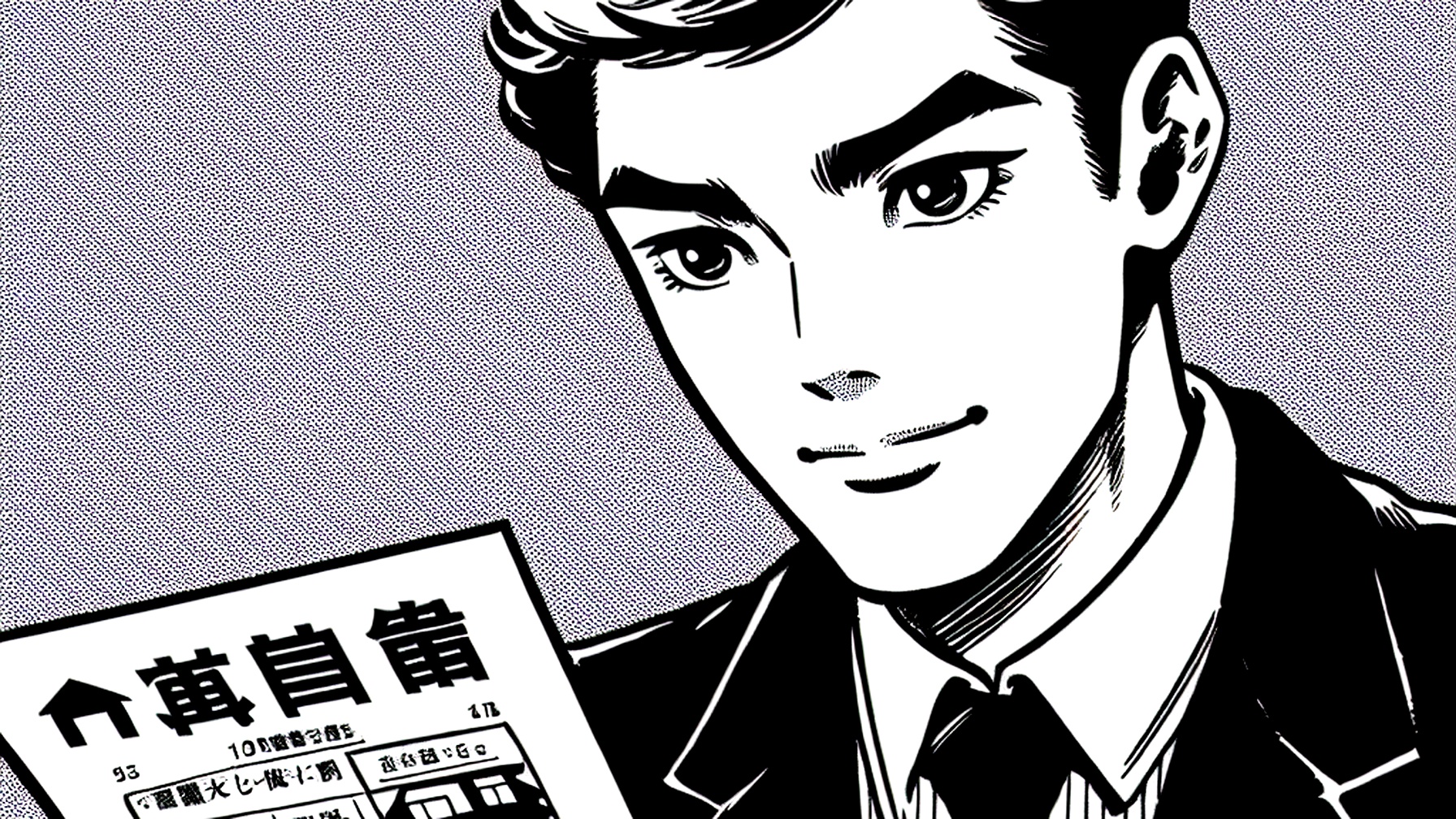
ポイントは、市場データを基に「現在の家賃が維持できるか」を判断することです。
最初に、同一エリア・同タイプの成約家賃を過去3年分調べると、家賃の下降トレンドや募集期間の傾向が分かります。価格の下落幅が年2%を超える地域では、入居者入替えのたびに賃料改定が必要となり、長期の収益計画が揺らぎやすくなります。
次に、人口動態を確認します。総務省の住民基本台帳人口移動報告では、地方圏の20代人口が2024年から2025年にかけて1.5%減少しました。学生や若年単身者向けの築古アパートは、この数値以上に影響を受けやすく、空室率が平均を上回る傾向があります。
さらに、現地調査で「競合物件の外観」「管理状態」「入居者層」を観察しましょう。外壁にひびが入り共用部が暗い物件が多いエリアでは、リフォーム投資が埋没しやすく、回収期間が伸びがちです。言い換えると、周辺が同じく築古ばかりであれば、適切なリノベーションが差別化となる余地があります。
修繕費・法規制コストの正体
まず押さえておきたいのは、築古アパートの修繕費は「計画的支出」と「突発的支出」に分けられる点です。計画的支出の代表は外壁塗装と屋根防水で、目安は10〜15年ごとに150万〜250万円です。突発的支出としては給水管破裂やシロアリ被害などが挙げられ、10万円単位の出費が突然重なることがあります。
また、2025年度の建築基準法改正により、延べ床面積200㎡超の木造賃貸住宅は省エネ基準適合が義務化されました。築古アパートでも増築や大規模改修を行うときは断熱材追加やサッシ交換が必要となるケースがあり、追加コストが数十万円単位で発生します。ここを見落とすと、当初計画より利回りが1〜2ポイント低下することも珍しくありません。
加えて、固定資産税評価額が下がることで税負担が軽くなると考えがちですが、耐用年数を大きく超えた物件は建物比率が小さくなり、減価償却の節税効果も限定的です。税務面のメリットだけに期待して購入するのは危険と言えるでしょう。
融資とキャッシュフローの落とし穴
実は、築古アパートの収支を圧迫する最大要因は、金利よりも「融資期間の短さ」にあります。金融機関は法定耐用年数(木造22年)を基準に融資期間を設定するため、築30年の物件では10年前後に短縮される事例が一般的です。返済期間が半分になれば月々の元金返済額は倍近くに跳ね上がり、表面利回りが高くても手残りが極端に減ることがあります。
日本政策金融公庫の2025年4月調査では、築25年以上の木造アパートに対する平均融資期間は13.5年、平均金利は2.15%でした。同じ利回り8%でも20年返済と13年返済では、年間キャッシュフローに50万〜70万円の差が出る計算です。
このギャップを埋めるには、自己資金を物件価格の30%程度投入し、融資額を抑える方法が有効です。さらに、返済比率(年間返済額÷年間家賃収入)を50%以下に維持すれば、空室が出ても家計を圧迫しにくくなります。
リスクを抑える物件選びと運営戦略
ポイントは、「目に見える利回り」よりも「長期の収支安定」を軸に判断することです。
まず、築年にとらわれず構造とメンテナンス歴を把握します。築40年でも躯体が頑丈で、10年以内に屋根・外壁を更新していれば、修繕積立を平準化しやすくなります。管理会社にヒアリングして入居者属性やクレーム内容を確認すると、不安要素が可視化され、賃料下落の可能性を早期に察知できます。
次に、リノベーションはターゲットを絞って実施しましょう。単身学生向けなら高速インターネット、共働き世帯向けなら宅配ボックスといったように、費用対効果が大きい設備に集中すると回収期間が短縮されます。国交省の住宅市場動向調査では、通信環境の整備が入居決定要因になる割合は2023年の29%から2025年は34%へ上昇しています。
最後に、出口戦略も並行して考えます。将来売却する場合、土地の活用価値や再建築可否が価格に直結するため、接道状況や用途地域を必ず確認してください。将来の売却益を視野に入れることで、目先のキャッシュフローだけに依存しない安定経営が可能になります。
まとめ
結論として、築古アパートのリスクは「家賃下落・修繕費・融資期間」の三つに集約できます。これらを事前に数値で把握し、計画的に対策を講じれば、高利回りというメリットを最大限に活かすことができます。空室率や法改正など不確実性はあるものの、適切なデータ分析と専門家の協力でコントロールは可能です。まずは本記事で紹介したチェック項目をもとに、自身の投資条件を整理し、シミュレーションを作成するところから始めてみてください。確かな準備こそが、築古アパート投資を成功に導く最短ルートになります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 2025年 – https://www.soumu.go.jp
- 日本政策金融公庫「中小企業の資金使途調査」2025年4月 – https://www.jfc.go.jp
- 東京都都市整備局「耐震化促進に関するガイドライン」2025年度版 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- e-Stat 政府統計ポータルサイト – https://www.e-stat.go.jp

