将来の資産形成を考えたとき、REITにするか、それとも現金一括で物件を買うかで迷う人は少なくありません。検索画面には「REIT メリット 現金一括 本当に」という言葉が並びますが、断片的な情報だけでは判断が難しいものです。本記事では2025年10月時点の公的データと実務経験を踏まえ、両者の違いを体系的に整理します。読み終えたとき、自分の資金計画やリスク許容度に合った投資スタイルが見えてくるはずです。
REITが注目される背景と仕組み
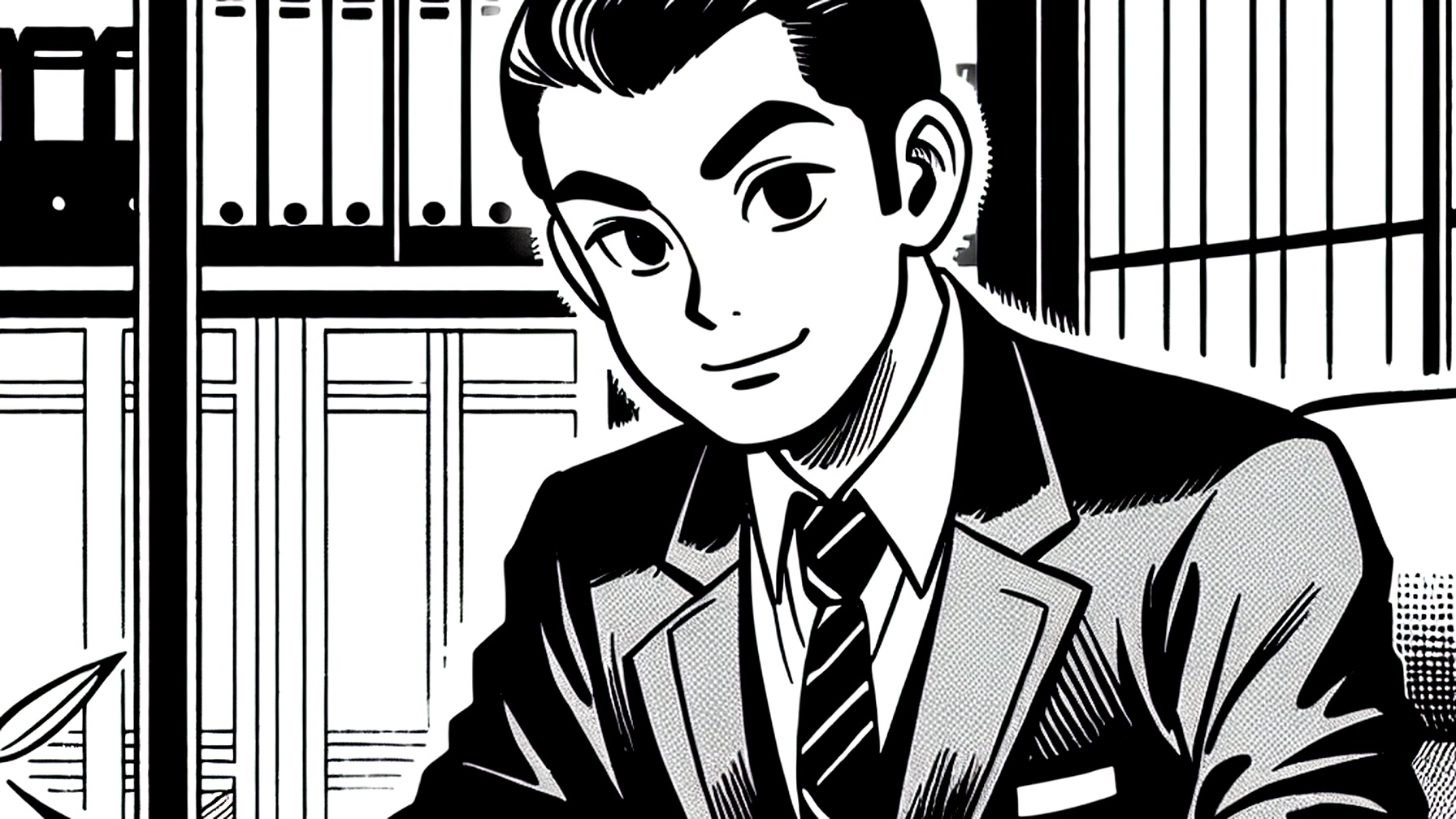
まず押さえておきたいのは、REITがなぜ個人投資家に広がったのかという点です。REIT(不動産投資信託)は複数の物件をファンド化し、投資家が少額から参加できる仕組みです。東京証券取引所の上場REIT指数は、国土交通省の不動産価格指数とほぼ連動しながらも流動性が高い点が特徴です。
一方で、個別物件の購入にはまとまった資金と長期の管理責任が伴います。REITは資産運用会社が運営し、収益は配当として四半期ごとに分配されるため、日々の管理を気にせずに不動産収益を得られるのが魅力です。日本取引所グループによると、2025年9月末時点で上場REITの平均分配利回りは3.8%前後で推移しています。定期預金の平均金利が0.25%にとどまる現状を考えると、利回り面でも選択肢となりやすいのです。
ただし、REIT価格は株式市場の影響を受けやすく、短期的には値動きが大きくなります。価格が下落しても保有物件の賃料が即座に減るわけではありませんが、評価額の変動が心理的ストレスになる点は無視できません。つまり、価格変動を許容できるかどうかがREIT投資の第一関門になります。
REITのメリットを改めて整理
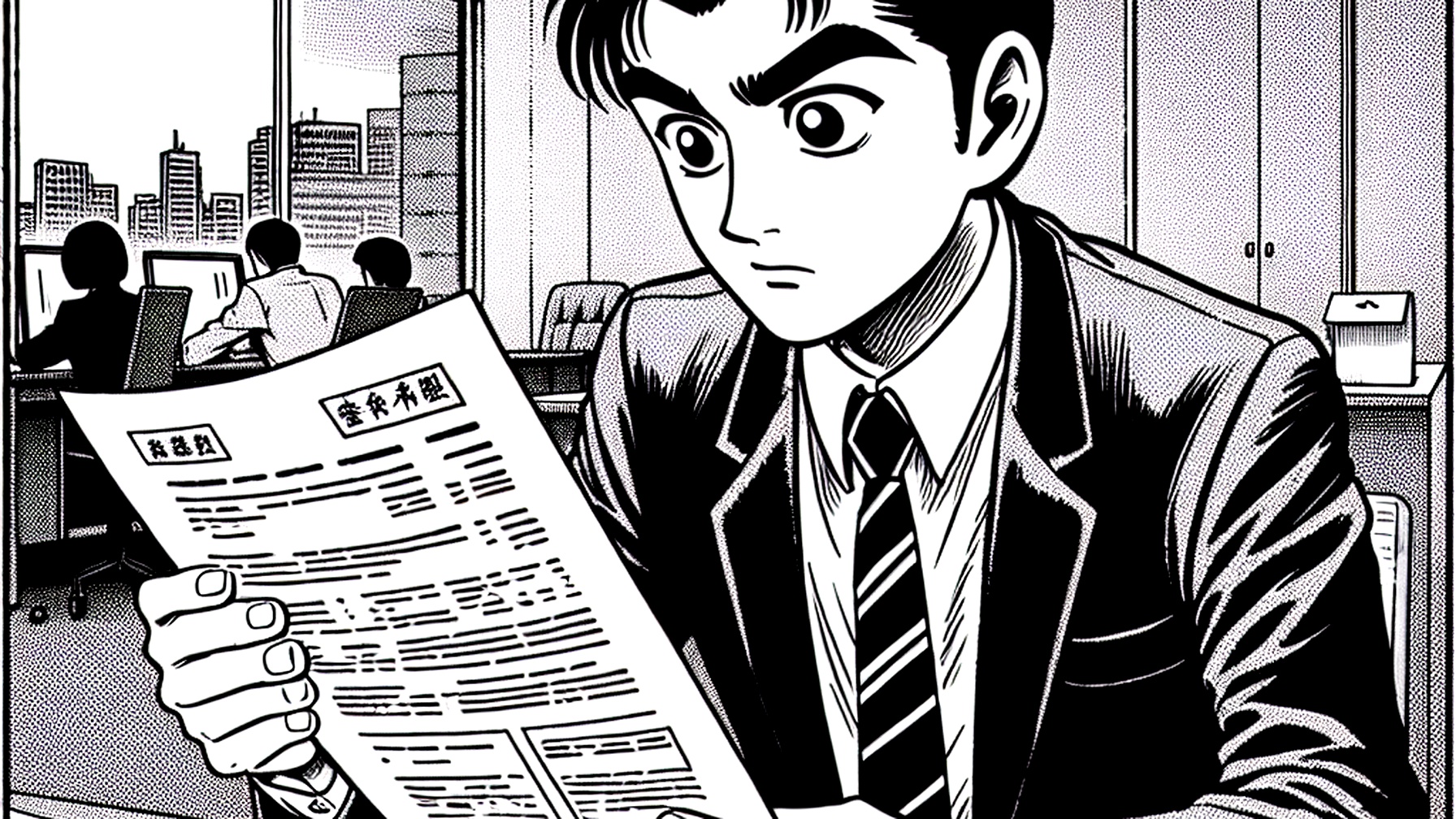
ポイントは、REITが提供する「分散」「流動性」「専門性」という三つの価値です。分散とは複数の物件やテナントに投資することで空室リスクを低減することを指します。例えば首都圏オフィス特化型のREITでも、ビル一棟を買うよりはテナント構成が広がるため、単一企業の退去が直撃する可能性は小さくなります。
流動性の高さは売買手数料と速度に直結します。現物不動産では引き渡しまでに平均2〜3か月かかりますが、REITなら市場取引なので即日売却が可能です。公的データによれば、2025年上半期のREIT一日当たり平均売買代金は約600億円で、十分な出来高が確保されています。
専門性については、運用会社がプロの視点で物件選定やテナント交渉を担います。個人投資家が現地調査や管理会社選定にかける手間を省けるため、本業を持ちながらでも不動産投資に参加できます。実は、この「時間コストの削減」が初心者にとって最大のメリットになるケースが多いのです。
加えて2025年度の税制では、NISA(非課税制度)の恒久化により年間360万円までの投資枠が用意されています。REITの分配金にかかる20.315%の税金を非課税にできるため、配当利回りをそのまま受け取れる点は魅力です。
現金一括で物件を買う場合の実像
重要なのは、現金一括購入が「借金なし=リスクなし」ではないということです。確かにローン返済が不要な分、毎月のキャッシュフローはプラスになりやすいです。家賃10万円のワンルームを2000万円で買い、月々の管理費や固定資産税を差し引くと年間70万円前後の手取りになる試算も珍しくありません。
しかし、一括購入でも突発的な修繕費は避けられません。国土交通省「マンション大規模修繕実態調査」によると、築20年超の区分所有で一戸あたり平均120万円の修繕負担が発生しています。また、空室期間が長引けば家賃収入はゼロになり、保険料や税金だけが出ていく状況になる点も頭に入れておく必要があります。
現金を一つの物件に集中させると、地域や物件タイプの分散が難しくなります。人口減少が続く地方都市では、賃貸需要の減少が長期的な懸念材料です。つまり、たとえローンがなかったとしても、資産脱却のスピードと分散効果の観点でリスクは残るのです。
また、日本政策金融公庫の家計金融行動調査(2025年版)によれば、現金と投資信託を組み合わせた世帯の方が、老後資金準備に対する安心度が高いという結果が出ています。現金一括購入は心理的な安心感を与えますが、流動性を失いすぎるといざというときに対応が遅れる点が弱点になります。
REITと現金一括投資を比較するときの視点
まず押さえておきたいのは、収益性だけでなく「資金拘束期間」と「管理負担」の二軸で評価することです。REITは配当利回りが3〜4%で価格変動がある一方、売却は数秒で完了します。現金一括購入は利回りが5〜7%を狙える半面、売却までに数か月を要し、価格交渉の手間も避けられません。
結論として、想定できる運用期間が5年以内なら流動性の高いREITが有利になりやすいです。逆に10年以上かけてゆっくり資産を育てる意思があり、かつ物件の管理を楽しめる人なら現金一括購入が選択肢となります。どちらも完璧ではなく、自己資金の三分の一をREIT、残りを現金一括やローン併用で物件購入するなど、組み合わせ戦略が現実的です。
一方で、ポートフォリオ全体で見ると株式や債券との相関も重要です。REITは株式市場と中程度の相関があるため、株式比率が高い人は現金一括の現物不動産を組み込むとリスク分散効果が高まります。言い換えると、自分の総資産に対する位置づけを明確にしないと、いずれか一方だけではリスクが偏るというわけです。
2025年度の制度活用と投資戦略のヒント
実は、税金面での優遇策を活用すると両者の差が縮まる場合があります。2025年度のNISA拡充で、REIT投資は年間360万円まで非課税で運用できます。ゆえに配当利回り3.8%をそのまま享受でき、課税口座と比べて税引き後利回りが約0.8ポイント向上します。
一方で、現金一括購入には減価償却という利点があります。木造アパートを取得した場合、耐用年数22年のうち残存期間で償却できるため、所得が高い人ほど損益通算による節税効果が期待できます。ただし、改正電子帳簿保存法により2025年以降はデジタル保存が義務化され、領収書管理の手間が増える点を忘れてはいけません。
さらに、2025年度の住宅エネルギー性能向上計画に沿って、省エネ改修を行うと固定資産税の減額措置(最大3年間2分の1)が受けられます。物件購入後にリフォームを想定している場合、この制度の利用可否は投資収支に影響するため事前に確認が必要です。
ポイントは、制度そのものより「自分のキャッシュフローと税率に照らして最適化する」という視点です。制度を意識しすぎて本質的なリスク管理をおろそかにすると、想定外の出費に耐えられなくなります。つまり、制度はあくまで補助的なツールとして使いこなすことが成功の鍵となります。
まとめ
ここまで、REITと現金一括購入の特徴を資金拘束期間、管理負担、税制面から整理しました。REITは分散と流動性に優れ、NISA非課税枠を生かせば安定的なインカムゲインが期待できます。一方、現金一括購入はローンリスクがない反面、集中投資ゆえの地域リスクと修繕リスクが残ります。大切なのは「どちらが良いか」ではなく「自分の資金量、目的、期間に合う組み合わせは何か」を考えることです。まずは手元資金のうち生活防衛費を除いた範囲で少額から試し、経験を積みながら投資配分を調整していきましょう。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 マンション大規模修繕実態調査 – https://www.mlit.go.jp
- 内閣府 家計金融行動調査(2025年版) – https://www5.cao.go.jp
- 財務省 税制改正資料(2025年度) – https://www.mof.go.jp

