不動産投資を始めたいけれど、都心の新築は高すぎるし、築年数の古い物件はリスクが大きいのではと悩む人は少なくありません。実は築古物件でも、適切なリノベーションや将来の建て替えを視野に入れた長期投資を行えば、安定したキャッシュフローと資産価値の向上を同時に狙えます。本記事では、築古物件を収益物件として育てるメリットや注意点、建て替えのタイミング、さらに2025年度に利用できる税制優遇まで、初心者にも分かりやすく解説します。最後まで読めば、物件の老朽化を味方に付ける具体的な戦略が見えてくるはずです。
築古物件が狙い目になる理由

ポイントは、取得コストの低さとリノベーション余地が大きいことにあります。築年数が30年以上の物件は価格が下がりやすく、うまく仕入れれば表面利回りが高くなる傾向があります。
まず、国土交通省の2024年住宅市場動向調査によると、築30年以上の中古マンションは築10年未満に比べ平均単価が約4割低くなっています。その一方で、賃料は築年数による下落幅が小さいため、購入価格に対する賃料の比率、つまり利回りが上がりやすいのです。また、初期費用を抑えられる分、余剰資金を内装や設備の改善に回せる点も魅力です。
次に、立地の優位性です。昭和期に建てられた住宅は駅近の好立地に多く残っています。郊外の新築よりも交通利便性が高いケースが多く、入居者募集の競争力を高められます。つまり、築古でも場所次第で空室リスクを十分コントロールできます。
さらに、減価償却費の恩恵も見逃せません。木造なら耐用年数22年を過ぎた時点で4年、鉄骨造やRC造でも7〜12年で償却できるため、経費計上額が大きくなります。結果として課税所得を圧縮し、手取りキャッシュフローを高める効果が期待できます。
ただし、建物の構造やインフラの老朽化は慎重に見極める必要があります。耐震補強が困難な場合や給排水管の劣化がひどい場合は、後述する建て替えまでの期間や総コストをしっかり計算しておきましょう。
長期投資でキャッシュフローを安定させる視点
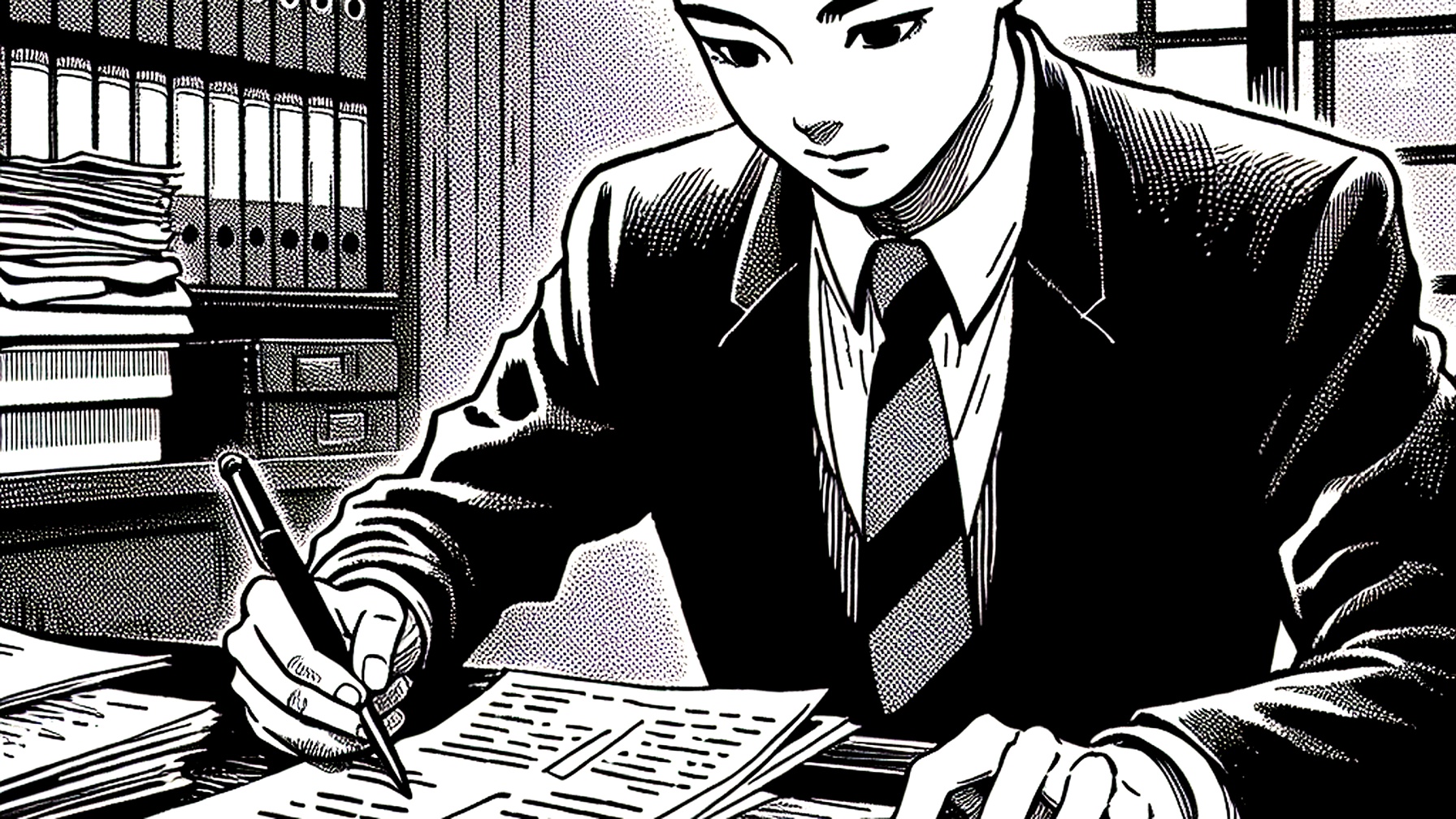
実は築古物件の収益力を最大化する鍵は、短期転売ではなく長期保有にあります。時間を味方に付ければ、融資残高を着実に減らしつつ、家賃収入を積み重ねられます。
まず押さえておきたいのは、リフォーム計画の段階的実行です。一度にフルリノベーションを行うとキャッシュフローが一時的に悪化します。そこで共用部の照明LED化、室内のクロス張り替え、設備交換など、費用対効果の高い項目から順に進めると、家賃アップと稼働率向上を早期に実現できます。
また、長期保有を前提にすると、金利タイプの選択も重要です。日本銀行が2025年4月に公表した金融システムリポートでは、長期金利が緩やかに上昇傾向にあるものの、実質金利は依然低水準にとどまると示されています。固定金利で資金を確保し、家賃収入がインフレとともに微増するシナリオに備えると、実質負債負担を軽減できます。
さらに、空室対策をルーティン化することが欠かせません。具体的には、入居後3年を目安に室内メンテナンスを提案し、退去を未然に防ぎます。レントロールの定期チェックや管理会社との月次面談を継続すれば、問題点を早期に発見し、長期的な稼働率90%超を維持しやすくなります。
このように、キャッシュフローの安定と物件価値の維持を同時に図ることで、融資返済完了後には実質家賃が年金のような役割を果たし、次の建て替え資金を自己資本で確保する道も開けます。
建て替え判断のタイミングとコスト感覚
重要なのは、修繕の延長線で対応できる段階と建て替えに踏み切る段階を見極めることです。建物の寿命と金融機関の評価が交差するポイントが、投資家の決断期になります。
まず、耐震基準をチェックしましょう。1981年の新耐震基準以前の物件は、現行基準を満たさない可能性があります。耐震改修費が建て替え費の30%を超える場合、金融機関は追加融資より建て替え融資に前向きです。つまり改修と建て替えの費用差が小さいときがスイッチの合図です。
次に、建て替えコストの概算を把握します。2025年の建設物価調査会データでは、首都圏RC造マンションの建築単価は坪90万円前後です。解体費、設計費、各種手数料を加えると、30戸規模で総額2.5億〜3億円が相場です。この金額を自己資金2割、金融機関融資8割で組む場合、返済比率を家賃収入の50%以内に収められるかが可否の目安になります。
さらに、テナント退去や近隣調整にかかる期間も計画に含めます。実務的には、退去交渉から解体着工まで平均18カ月程度を見込むと、資金計画に余裕が生まれます。この間の機会損失を最小限に抑えるには、賃貸管理会社との連携が不可欠です。
最後に、建て替え後の出口戦略を描きます。建築確認申請時点で、ファミリー向けか単身向けか、ターゲットを明確に設計し、完成後の売却利回りまたは保有利回りを試算します。この工程を怠らなければ、築古物件の価値を次世代にリレーできるでしょう。
2025年度の税制優遇を活用した資金計画
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続が決定している「住宅ローン控除」の仕組みです。個人が自宅併用の賃貸住宅を建て替える場合、床面積要件をクリアすれば、借入残高の0.7%を最大13年間所得控除できます。賃貸専用でも、法人化を選択することで、減価償却費や金利を損金処理でき、実効税率を抑えられます。
一方で、建て替え後に適用される固定資産税の軽減措置も見逃せません。総務省の通知によると、2027年度課税分まで新築住宅の固定資産税は3年間、税額が2分の1に減額されます。三階建て以上の耐火構造なら5年間に延長されるため、中長期のキャッシュフロー計画が立てやすくなります。
さらに、中小企業経営強化税制を活用すると、法人が新築アパートに導入した高性能設備に対し、即時償却または税額控除10%を選択できます。2025年度の適用期限は2027年3月末までとされていますので、建築スケジュールにゆとりを持たせると確実です。
資金調達面では、政策金融公庫の不動産賃貸業向け融資が活発です。2025年4月時点の金利は0.9%台から1%台前半で、長期固定20年を組めるケースもあります。これを民間金融機関のプロパー融資とブリッジさせれば、自己資金割合を抑えつつ資金繰りの安全性を高められます。
このように、税制と公的融資を組み合わせることで、建て替えによる初期負担を大幅に軽減できます。制度の詳細や申請期限は毎年更新されるため、着工前に必ず最新情報を確認し、専門家のサポートを受けましょう。
まとめ
築古物件は取得価格の低さ、立地の良さ、減価償却の大きさが魅力です。段階的なリフォームでキャッシュフローを確保し、耐震性や設備更新費用が建て替え費に迫った時点で、新築への切り替えを検討します。さらに、2025年度も利用できる住宅ローン控除や固定資産税軽減を活用すれば、長期投資の収益力は一段と高まります。まずは物件調査と資金計画から着手し、老朽化を恐れずチャンスに変えていきましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2024 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 金融システムリポート2025年4月 – https://www.boj.or.jp
- 建設物価調査会 建築費指数2025 – https://www.kensetu-bukka.or.jp
- 総務省 固定資産税減額制度ガイド2025 – https://www.soumu.go.jp
- 中小企業庁 経営強化税制の概要2025年度版 – https://www.chusho.meti.go.jp

