不動産投資を始めたいものの、「区分より一棟のほうが良いと聞くけれど本当だろうか」と迷う人は少なくありません。実際に私の相談者でも、価格の大きさや融資期間の長さに尻込みしてチャンスを逃すケースが多々あります。本記事では、一棟マンション投資の具体的なメリットと注意点を分かりやすく整理しました。読めば、区分所有との違いや資金計画のポイントが明確になり、自分に合った投資スタイルを判断できるようになります。
一棟マンション投資とは何か
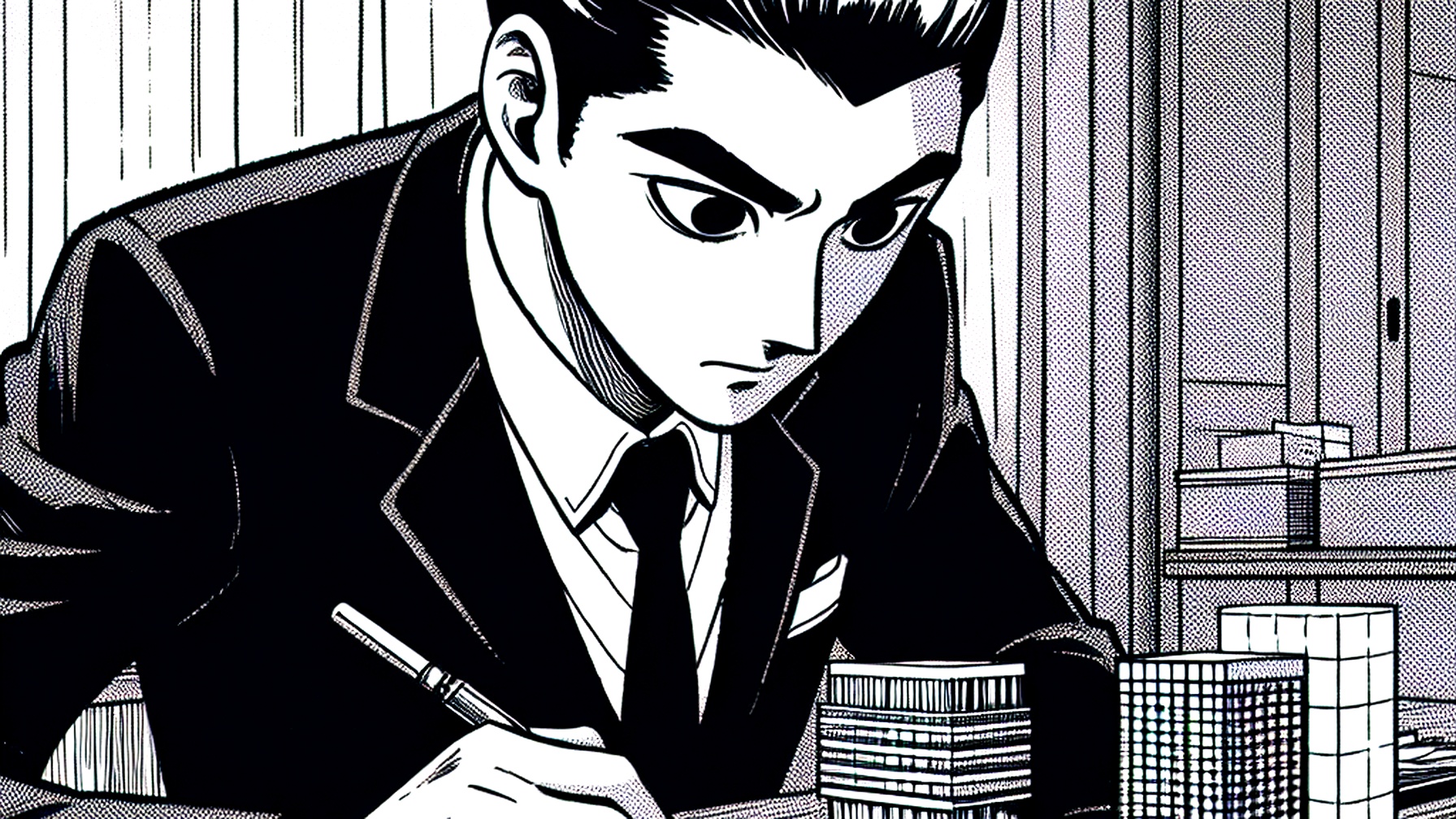
まず押さえておきたいのは、一棟マンション投資の定義です。一棟投資とは、建物と土地をまとめて購入し、全戸を自分で運用する手法を指します。これに対し、区分投資は建物の一部屋だけを所有する方法です。つまり所有権の範囲が広くなる分、賃料収入も管理責任も大きくなるのが特徴です。
一棟マンション メリットとして代表的なのが、収益源が複数戸に分散される点です。仮に一室が空室でも他の部屋から賃料が入るため、キャッシュフローが安定しやすい傾向にあります。また建物全体を自由にリノベーションできるため、賃料アップを狙う施策を自分の裁量で実行可能です。さらに、土地と建物を一括で担保に取れるため金融機関の評価が高く、長期融資を受けやすいことも投資家にとって大きな魅力となります。
一方で、初期投資額が大きい、空室が続くとダメージが大きいなどのリスクも存在します。そのため、立地選定や収支計画を丁寧に行うことが前提となります。このセクションではメリットに焦点を当てつつ、リスクと表裏一体であることを念頭に置いて読み進めてください。
キャッシュフローが安定しやすい理由
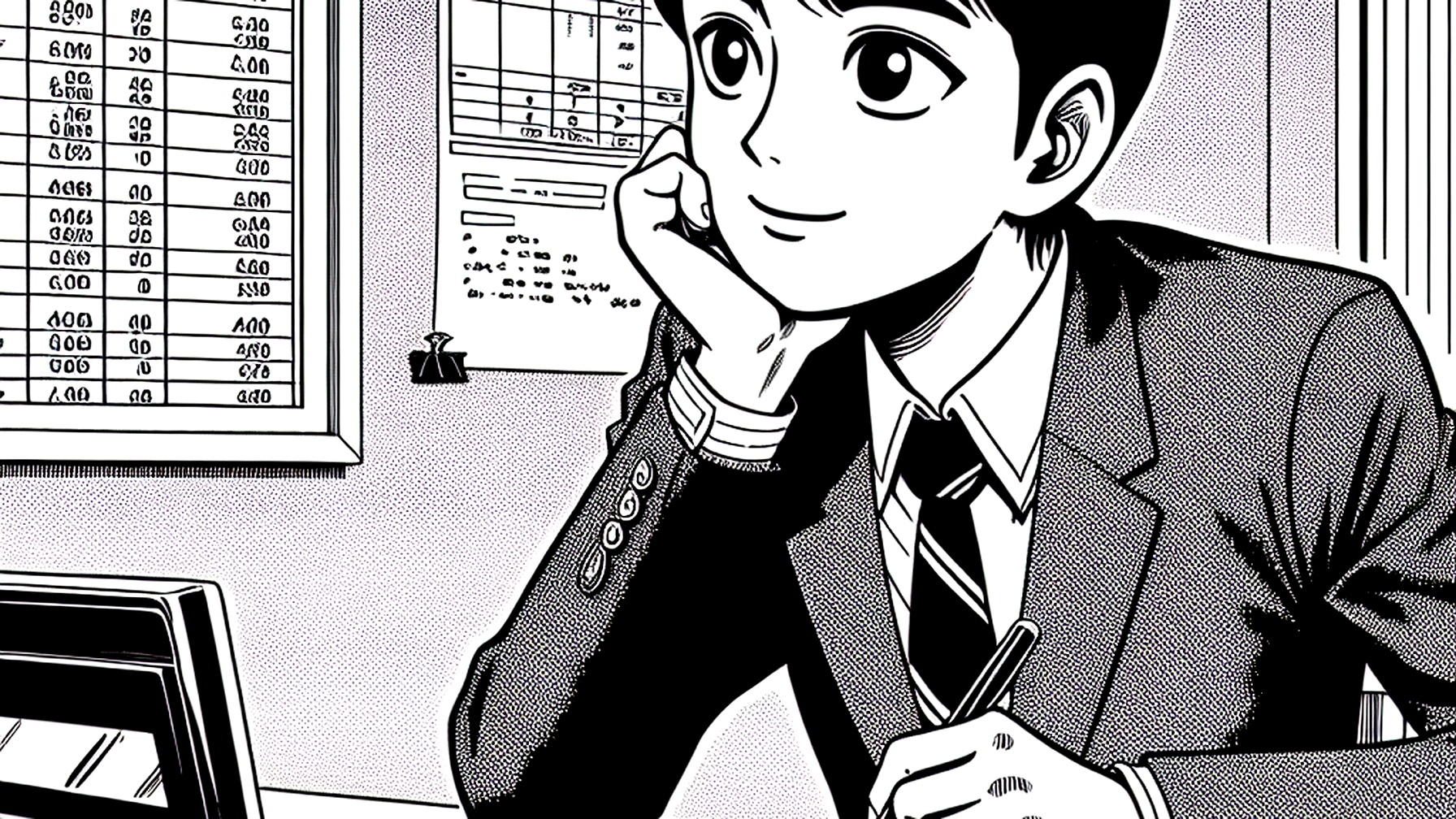
重要なのは、戸数が増えるほど賃料収入が平均化されるという構造です。例えば10戸のマンションを想定し、毎月の平均家賃を8万円とすると満室時の月収は80万円になります。仮に2戸が空室になっても64万円が確保でき、ローン返済や運営費に充当できる余裕が残ります。区分物件が空室になった場合の収入ゼロと比べると、精神的な負担も小さく済むでしょう。
また、日本銀行の2025年7月時点の「金融システムレポート」によれば、全国の住宅ローン金利は平均1.1%台を維持しています。低金利が続くうちに長期固定で融資を組めば、返済額を一定に保ちながら家賃をインフレヘッジに活用できます。家賃収入がじわじわ上がっても返済額は変わらないため、実質的なキャッシュフローの向上が期待できるわけです。
さらに、家賃設定を自分で決められる点も一棟マンション メリットの一つです。例えば共用部にワークラウンジを設け、インターネット無料サービスを提供するなど、入居者満足度を高める施策を組み合わせると、平均家賃を3〜5%上げても入居率を維持できるケースが多く見られます。区分所有では管理組合の合意が必要となり、スピーディーな改善が難しいため、このフットワークの軽さは大きな差別化要因になります。
規模の経済と税制メリット
実は、一棟投資は「規模の経済」を享受しやすい仕組みです。管理会社との交渉では、戸数が多いほど管理委託費を低く抑えられます。例えば首都圏の管理委託費は平均で賃料の5%前後ですが、一棟20戸以上になると3%台まで下がる事例もあります。ランニングコストを抑えた分、表面利回りが同じでも実質利回りは高くなるわけです。
同時に、税制面でも大規模投資の恩恵があります。不動産所得は減価償却費を経費計上でき、築年数の古いRC造(鉄筋コンクリート)の一棟マンションなら耐用年数47年を超えた部分を4年で償却する「定額法」を活用できます。これにより前半数年間は所得税と住民税の負担を軽減でき、手元キャッシュフローを厚くすることが可能です。2025年度の税制改正でも、この減価償却の基本枠は維持されており、個人・法人いずれの投資家にも引き続き有効な手法とされています。
さらに、一棟物件は土地価格の比率が高いため、相続税対策としても注目されています。国税庁「財産評価基準」に基づき、賃貸用不動産は自用地に比べて評価額が約2〜3割減額されるケースが一般的です。将来の相続を見据えて、早めにキャッシュフローを生む資産に組み替えておくことは、長期的な家族の財務戦略にもつながります。
管理の自由度と長期価値
ポイントは、オーナーの裁量で建物全体の価値向上策を打てることです。共用部のデザイン刷新、IoT設備の導入、外壁塗装のタイミングなどを自分で決定できるため、長期的な資産価値を維持しやすくなります。区分所有だと管理組合の合意形成に半年〜1年以上かかることが普通で、機会損失が発生しやすいのと対照的です。
東京23区の新築マンション平均価格は2025年10月時点で7,580万円(不動産経済研究所)と過去最高を更新しています。価格が高止まりする局面では中古の一棟マンションに割安感が生じ、適切にリノベーションすれば新築に近い賃料を得られる余地があります。築25年程度のRC造物件を外観・設備ともに刷新した結果、家賃が平均15%上がった例も珍しくありません。
さらに長期的な視点で見ると、持続的な賃料アップは売却価格にも直結します。一般に収益還元法では、年間家賃収入を資本還元率(利回り)で割り戻して価格を算定します。家賃を月1万円上げるだけでも、表面利回り6%のマーケットなら物件価値が約200万円上昇する計算です。小さな改善を積み重ねることで出口戦略の選択肢を広げられるのは、一棟投資ならではの醍醐味と言えるでしょう。
リスクと向き合うためのチェックポイント
まず押さえておきたいのは、一棟マンション メリットを最大化するにはリスク管理が前提だということです。最大のリスクは空室率の上昇であり、人口動態や周辺の新築供給量を丁寧に調べる必要があります。総務省「住民基本台帳人口移動報告」によれば、2025年時点でも東京都区部への転入超過は約8万人と高水準ですが、地方都市では転出超過が続く地域もあります。立地選定を誤ると空室リスクは一気に高まります。
資金計画でも、自己資金を物件価格の20〜30%確保しておくとローンの返済比率が安定します。日本政策金融公庫の統計では、自己資金比率が1割未満の投資家は5年以内の返済遅延率が2倍に高まる傾向が報告されています。つまり、余裕を持った自己資金が長期運用への安心材料になるわけです。
最後に、修繕計画を事前に立てることも欠かせません。国土交通省「長期修繕計画ガイドライン」では、RC造マンションの大規模修繕は12年周期が推奨されています。屋上防水や外壁タイルの補修を適切に行えば、修繕コストの急増を防げます。長期修繕計画を信頼できる建築士に依頼し、積立金を毎月家賃収入から確実に引き当てておく仕組みを作りましょう。
まとめ
結論として、一棟マンション メリットは安定キャッシュフロー、規模の経済、税制優遇、管理自由度、そして資産価値向上の余地という五つの柱に集約されます。これらを活かすためには、立地調査と資金計画を丁寧に行い、長期修繕と入居者満足を常に意識する姿勢が重要です。今日からできる行動として、候補エリアの人口動態を調べ、金融機関へ仮審査を申し込むだけでも一歩前進します。自分に合った投資戦略を描き、安定した不動産収益を手に入れましょう。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudosankeizai.co.jp
- 日本銀行「金融システムレポート」 – https://www.boj.or.jp
- 国税庁「財産評価基準書」 – https://www.nta.go.jp
- 総務省「住民基本台帳人口移動報告」 – https://www.soumu.go.jp
- 国土交通省「長期修繕計画ガイドライン」 – https://www.mlit.go.jp

