不動産投資に興味はあるものの、「区分マンションは手軽と聞くけれど、本当に安全なのか」と不安を抱える人は多いはずです。実際、少額で始められる一方で、空室や修繕など見落としがちなリスクが潜んでいます。本記事では15年以上の実務経験をもとに、初心者がつまずきやすいポイントを整理し、2025年10月現在の最新データを交えてわかりやすく解説します。読み終えたころには、区分マンション投資で避けるべき落とし穴と、リスクを抑える具体策が明確になるでしょう。
区分マンション投資の基本と注目点
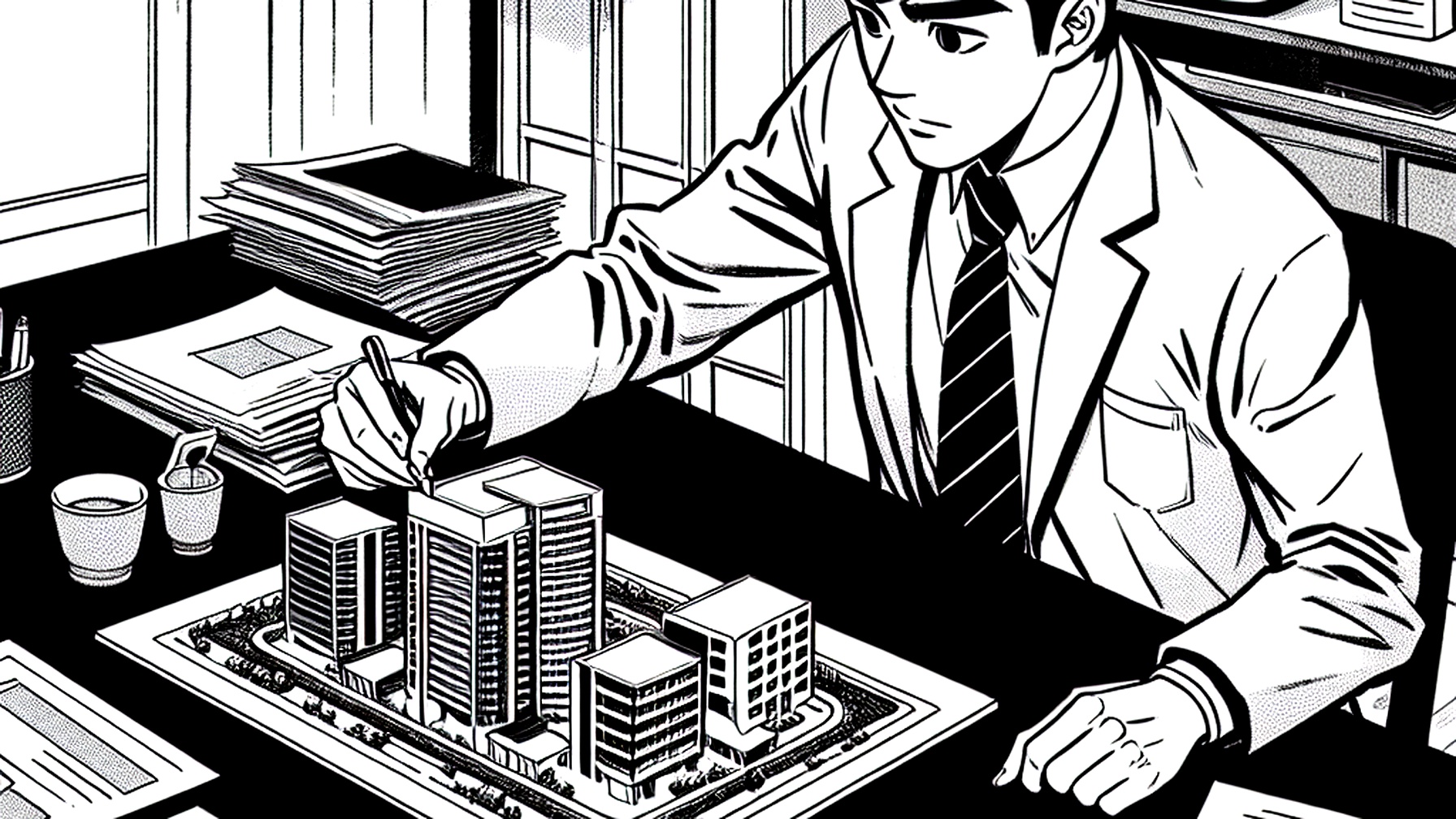
まず押さえておきたいのは、区分マンション投資の仕組みとメリットです。ワンルームやファミリータイプの一室を購入し、賃貸に出すことで家賃収入を得るモデルは、自己資金が限られていても参入しやすい点で人気があります。
一方で、2025年時点の新築マンション平均価格は東京23区で7,580万円と高騰が続いており、不動産経済研究所のデータでも前年比3.2%の上昇が確認されています。中古を含めた区分マンションなら2,000万〜4,000万円台もありますが、価格が落ち着く地方では賃料水準や人口動態の読みにくさが増します。つまり、手軽さの裏にはエリアごとの需給バランスを見極める難しさが潜んでいるのです。
家賃保証付きのサブリース契約など、魅力的に映る販売手法も増えています。しかし、利回り表記が実質コストを反映していないケースも珍しくありません。重要なのは表面利回りだけに目を奪われず、実質利回りや将来的な維持費を加味したキャッシュフローを試算することです。
空室リスクと賃料下落への備え
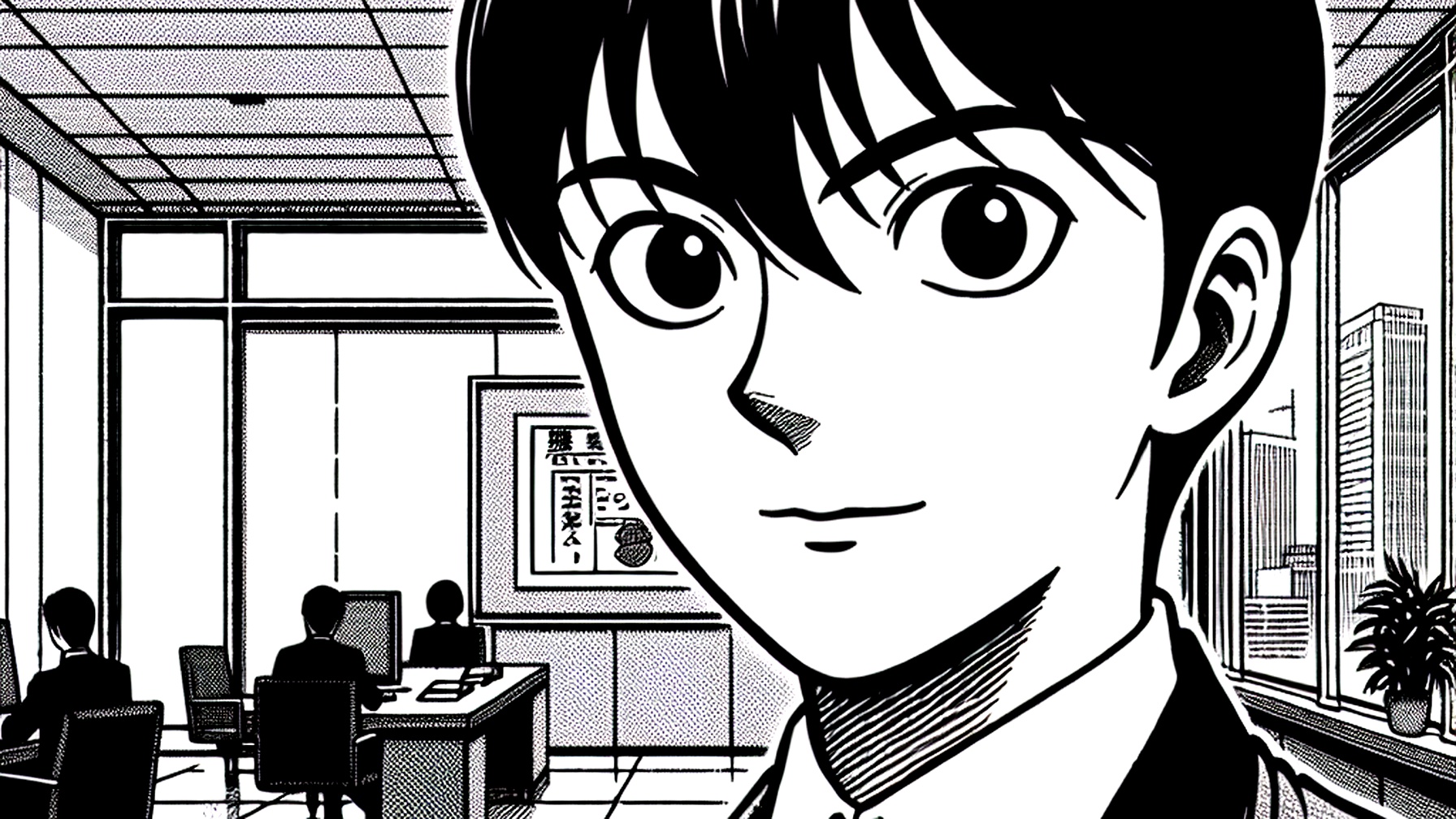
ポイントは、空室期間と賃料下落が収益に与えるインパクトを具体的に把握することです。空室率が5%か20%かで年間手取りは大きく変わり、楽観的なシミュレーションではすぐに資金繰りが苦しくなります。
総務省の住民基本台帳人口移動報告によると、2024年度は東京都の転入超過が前年より縮小しました。オンライン勤務の定着で郊外や地方移住が進み、賃貸需要の読み方が難しくなっています。この傾向はワンルーム需要の中心だった単身世帯にも影響し、賃料相場が横ばいから微減へ転じるエリアが散見されます。
空室リスクを抑えるには、駅徒歩10分以内や築15年以内など、需要が底堅い物件を選ぶことが第一歩です。また、入居者募集を仲介会社任せにせず、写真のクオリティやオンライン内見への対応など細部をブラッシュアップする姿勢も欠かせません。賃料設定は周辺相場より500〜1,000円ほど低めにスタートし、早期入居を優先するほうが長期的な総収入を守りやすいです。
修繕積立金・管理費の上昇リスク
実は、購入後にじわじわ効いてくるのが修繕積立金と管理費の負担です。国土交通省の長期修繕計画ガイドラインでは、築30年時点で当初の約2倍の積立水準が推奨されています。総会で値上げ決議がなされると、保有コストは想定以上に膨らみます。
築20年超の区分を購入する場合、直近5年の会計報告を確認し、積立金残高と大規模修繕予定をチェックすることが不可欠です。積立不足が続くマンションでは次回工事費用を一括徴収する恐れがあり、数十万円単位の追加負担が発生しかねません。
また、管理会社の変更でサービス水準が低下すると、清掃や設備点検の質が落ち、結果として物件価値が毀損します。区分所有者として議決権を行使し、理事会や総会に積極的に参加する姿勢が安定経営への鍵です。
物件価値と流動性リスクを読み解く
重要なのは、出口戦略まで見据えた購入判断です。人口減少が進む地域では「売りたくても買い手がつかない」状態が現実になりつつあります。逆に、都心でも供給過剰エリアでは築古ワンルームの価格が頭打ちです。
不動産価格指数(国土交通省)によれば、2025年前半の東京中古マンション指数は前年比+1.1%にとどまり、上昇幅が鈍化しています。もし金融緩和が転換し金利上昇に向かえば、投資家需要が冷え、価格下落の圧力が強まる可能性があります。
流動性リスクを抑えるには、賃貸だけでなく売却ニーズも高いファミリータイプや、再開発計画が進む駅前エリアを選ぶことが有効です。さらに、周辺で新築供給が増えるタイミングでは競合の影響を受けやすいため、将来の開発計画を役所の公開資料で確認しておくと安心です。
法制度と税務リスクの最新動向
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続する住宅ローン減税の適用条件です。区分マンションを自己居住目的で取得し、その後賃貸に回す場合、入居開始から原則10年間は取得時の減税額を維持できますが、賃貸化の時期によっては返還義務が生じるケースがあります。制度を活用する際は税理士への事前相談が必須です。
また、インボイス制度が導入されたことで、課税事業者として登録すると家賃が非課税である一方、管理費や修繕費にかかる消費税を控除できない点が混乱を招いています。課税売上と非課税売上が混在する投資家は、簡易課税を選択するか免税事業者を維持するかで実質負担が変わるため、シミュレーションが欠かせません。
さらに、2025年度税制改正では相続時精算課税制度の拡充が予定されており、親世代からの資金援助を受けて区分マンションを購入する手法が注目されています。適用上限や申告手続きが複雑なため、金融機関と税務署の両方で最新情報を確認しながら進めるとリスクを抑えられます。
まとめ
区分マンション投資は少額で始められ、融資も付きやすい反面、空室・修繕・流動性・制度変更といった多面的なリスクを抱えています。本文で解説したように、需要が安定する立地と適切な価格で購入し、将来の修繕計画や法制度まで視野に入れておくことが成功への近道です。行動に移す際は、物件情報だけでなく管理組合議事録や地域の人口データにも目を通し、保守的なキャッシュフロー試算を作成してください。リスクを正しく把握したうえで一歩踏み出せば、区分マンションは長期的な資産形成の強い味方になってくれるでしょう。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁 令和6年度税制改正の解説 – https://www.nta.go.jp
- 東京都都市整備局 住宅市場動向調査2025 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

