家賃収入で将来の不安を減らしたいと考える人は多いものの、「不動産投資はリスクが大きいのでは」と心配する声も絶えません。実際、空室や金利上昇で苦労した事例はニュースでも取り上げられます。とはいえ、仕組みを正しく理解し、数字で計画を立てれば、安定して稼げる資産になるのも事実です。本記事では、初心者がつまずきやすいポイントに焦点を当て、リスクを抑えながら収益を伸ばす具体策を解説します。読後には、自分に合った投資戦略を描けるようになるはずです。
不動産投資で「稼げる」の本質
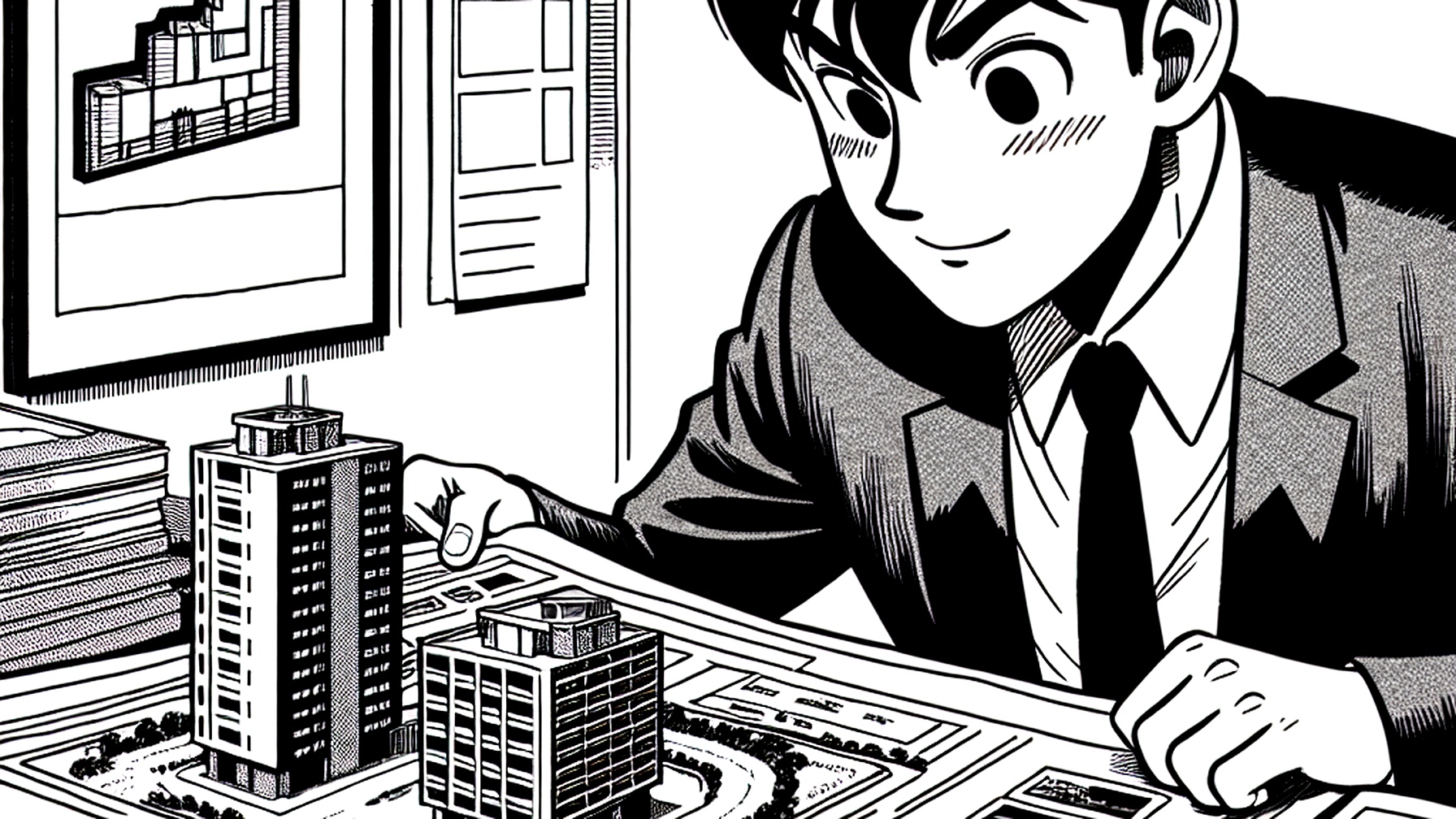
まず押さえておきたいのは、「稼げる」とは単に家賃が入る状態を指すのではなく、手元に残るキャッシュがプラスで推移することです。国土交通省の不動産価格指数(2025年7月公表)によると、全国の住宅価格は前年同月比で3.2%上昇しましたが、同時に管理費や固定資産税も増加傾向にあります。
一方で、総務省の家計調査を参照すると、賃貸住宅に住む世帯は依然として全体の34%を占めています。つまり賃貸需要は底堅いものの、費用増を加味しなければ純利益は縮小します。収入と支出のバランスを把握しないまま購入すれば、「家賃は入るのにお金が残らない」という矛盾に直面しかねません。
実は、年間収支が数十万円単位で変動する要因の多くが運営コストです。保険料や修繕費は控えめに見積もると後で痛手を受けます。稼げる投資家は、初期段階から実質利回り(家賃収入−年間経費)を重視し、ローン返済後にいくら残るかを冷静に計算しています。
見落としがちなリスクの正体
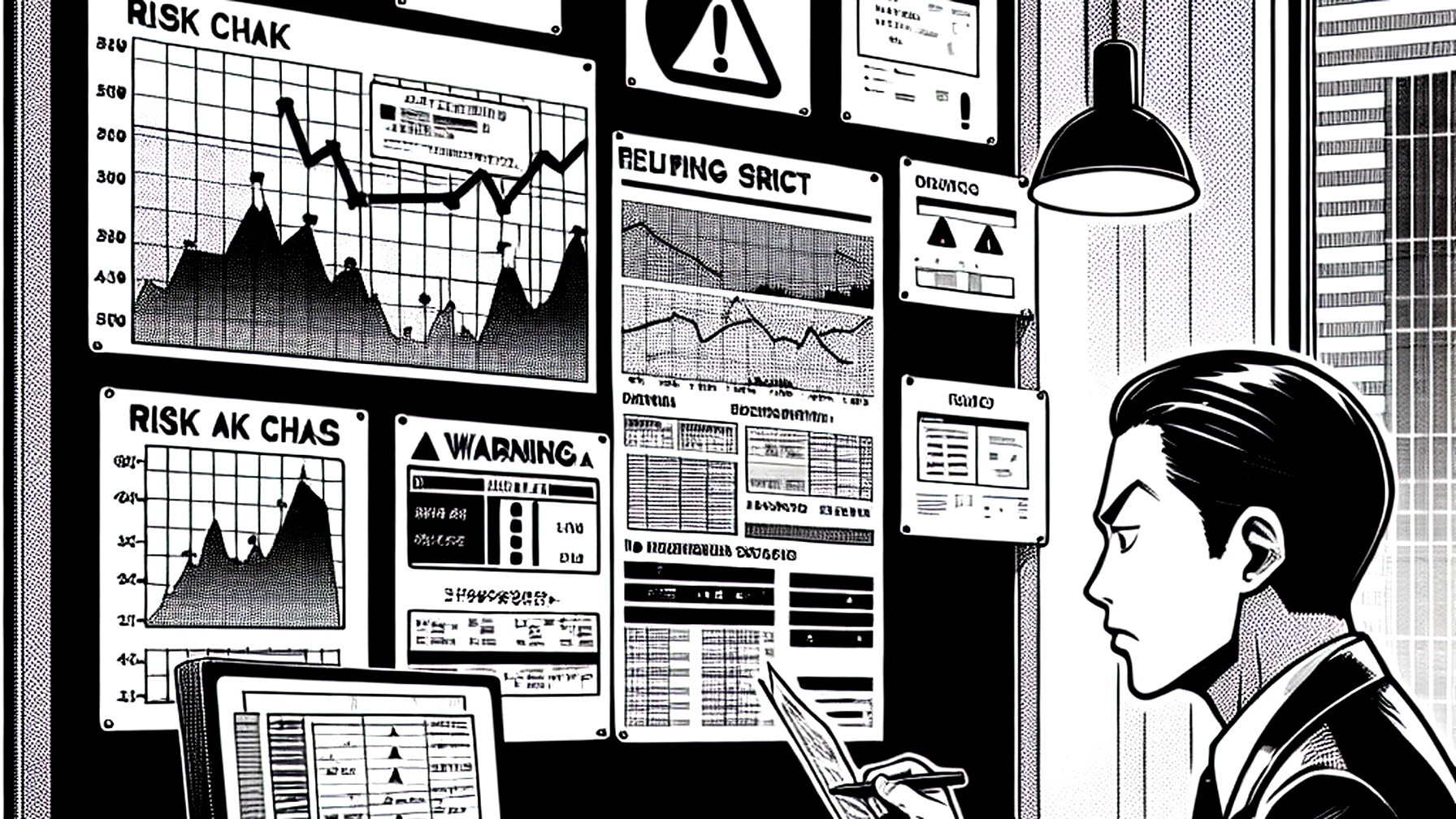
ポイントは、リスクを「発生確率」と「影響度」に分解することです。空室率は立地で大きく変わり、東京23区の平均5%に対し、人口減少が進む地方都市では15%を超える地域もあります(総務省 2025年地域別推計)。
さらに、金利リスクは長期保有になるほど無視できません。日本銀行の貸出平均金利は2025年4月時点で1.1%ですが、2022年の0.8%から着実に上昇しています。変動金利での借入が多い個人投資家は、今後1%の上昇でも月々の返済が数万円膨らむ可能性があります。
また、法的リスクも軽視できません。2021年にスタートした賃貸住宅管理業法により、管理委託契約の透明化が義務づけられました。2025年度も同法は有効で、対応していない管理会社と契約すると行政指導の対象になり、結果として運営コストが跳ね上がる恐れがあります。リスクを洗い出し、数字でシミュレーションする習慣が欠かせません。
キャッシュフローと資金計画の作り方
重要なのは、購入前に三つの数字を決めることです。第一に自己資金の割合、第二に目標利回り、第三に耐えられる空室率です。自己資金は価格の20〜30%を用意すると、融資条件が有利になるうえ、返済比率も抑えられます。
次に、目標利回りは表面ではなく実質で見る必要があります。たとえば年間家賃360万円、諸経費80万円、ローン返済180万円なら、実質利回りは(360−80−180)÷物件価格となります。ここで5%以上を確保できれば、税引き後でも黒字を維持しやすいでしょう。
最後に、空室率と金利上昇のストレスシナリオを設定します。空室20%、金利+1.5%でも赤字にならなければ、長期保有中の不測の事態に耐えられます。つまり、キャッシュフロー計算書を作り、最悪ケースでも月次キャッシュがプラスかゼロに収まるよう設計することが安全への近道です。
リスクを抑えて稼ぐ物件選定術
まず押さえておきたいのは、立地と物件タイプの組み合わせです。都心ワンルームは購入価格が高い分、学生と単身社会人の二つの層を狙えるため、継続入居率が高い傾向にあります。一方で郊外ファミリータイプは賃料は安定しますが、世帯主の転勤や子どもの進学で退去すると空室期間が長期化しやすい特徴があります。
つまり、投資目的とキャッシュフロー戦略に応じた立地選びが稼ぐための核心です。たとえば年金代わりに安定収入を得たい人は、人口流入が続く政令指定都市の中心部を選び、短期売却益を狙う人は再開発が進むエリアの築浅マンションを検討するなど、出口戦略まで視野に入れます。
さらに、物件の管理状態を確認する現地調査が欠かせません。共用部の清掃状況、ポストのチラシ散乱、掲示板の古い貼り紙などは住民属性を示すサインです。実際、国土交通省の賃貸住宅市場調査(2024年度版)では、共用部の美観が良い物件は空室期間が平均で1.8カ月短いという結果が出ています。稼げる物件ほど管理の質に投資している点を見逃さないようにしましょう。
2025年度に使える支援策と税制のポイント
実は、2025年度も個人投資家が活用できる制度は少なくありません。代表例は「不動産所得と給与所得の損益通算」です。不動産収入が赤字の場合、給与所得と合算して所得税を軽減できる仕組みは2025年度も継続されますが、過度な節税目的と判断されると税務調査の対象になるため、収支の実態を伴わせることが大前提です。
また、建物の減価償却費は依然として強力な節税ツールです。築25年の木造アパートを購入した場合、法定耐用年数が残り少ないため、最短4年で償却できます。この早期償却はキャッシュは出て行かずに経費計上できるため、実質的な手残りを厚くします。ただし短期で大きな経費計上を行うと、5年超の長期保有を前提にしないと売却益に対する税負担が重くなる点に注意しましょう。
さらに、国土交通省が管轄する「賃貸住宅リフォーム支援事業」は2025年度も継続予定で、省エネ性能向上やバリアフリー化に対する補助率は上限で工事費の1/3です。補助申請には事前審査と完了報告が必要となるため、着工前にスケジュールを確認してください。ローンの金利優遇策は大半が自宅用ですが、地方銀行では投資用物件に対しても期間限定で固定金利を引き下げるキャンペーンを実施する場合があります。情報収集を怠らず、条件を比較することがコスト削減につながります。
まとめ
リスクを恐れて何もしなければ、家賃収入という選択肢は生まれません。一方で、数字と制度を把握せずに物件を買えば、ローン返済や空室に苦しむ可能性が高まります。今回紹介したキャッシュフロー計算、立地選定、そして2025年度も利用可能な税制や補助金を組み合わせれば、リスクを抑えながら「稼げる」不動産投資を実現できます。まずは自己資金の割合と耐えられる空室率を明確にし、小さく始めて経験値を積むことからスタートしてみましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 貸出・預金動向 – https://www.boj.or.jp
- 国土交通省 賃貸住宅市場調査2024 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 タックスアンサー 不動産所得 – https://www.nta.go.jp

