不動産投資に興味はあるものの、高額な自己資金や銀行融資のハードルがネック――そんな悩みを抱える方は少なくありません。実は、1口1万円程度から参加できる「不動産クラウドファンディング」が急速に広まり、2025年現在は店舗物件を対象とした案件も増えています。本記事では、初心者が安心して挑戦できる仕組みと選び方を解説し、リスクを抑えつつ収益を得るための具体的な手順を紹介します。読み終える頃には、ご自身に合ったサービスの見極め方が分かり、一歩踏み出す自信が持てるはずです。
不動産クラウドファンディングとは何か
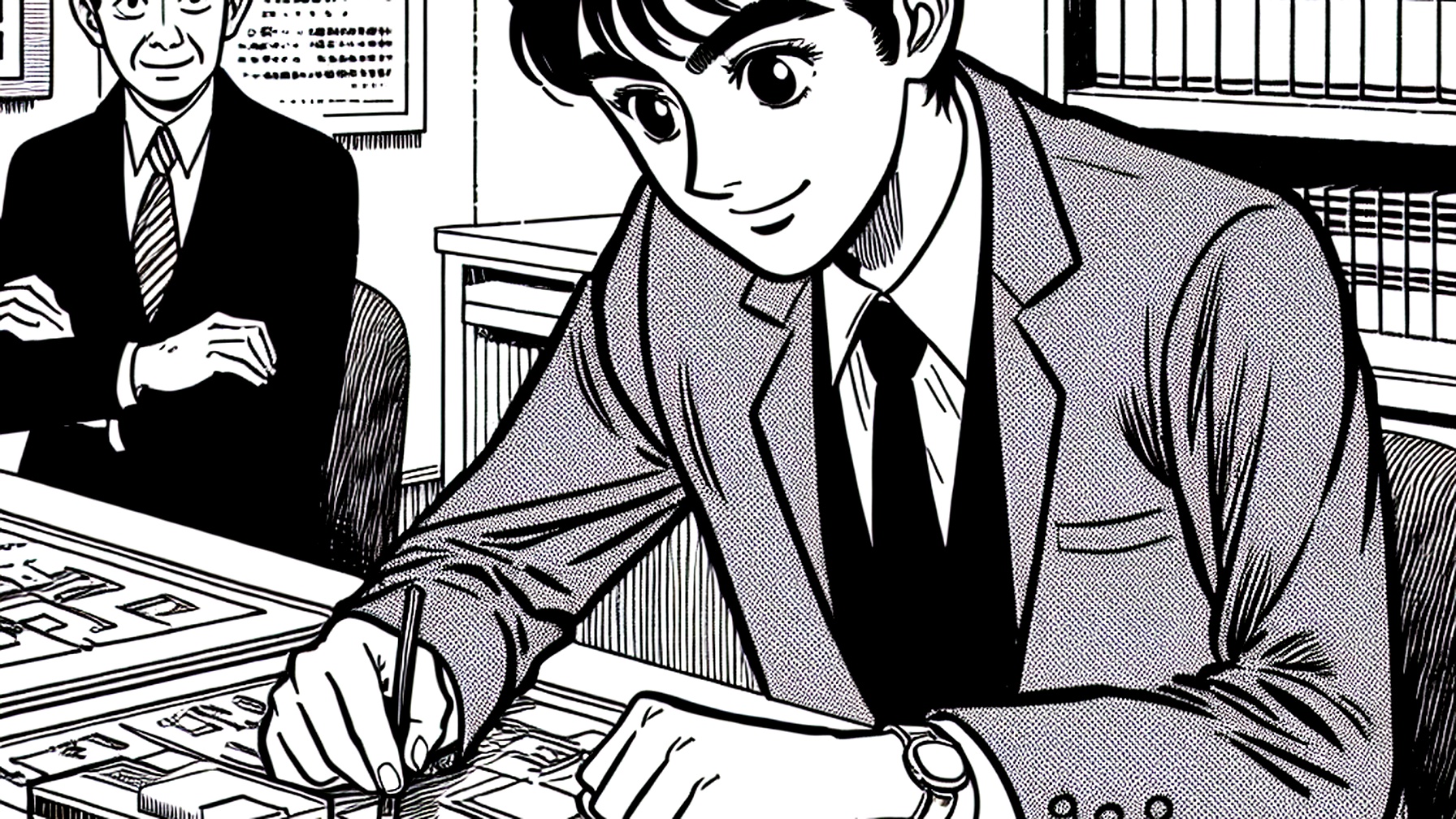
まず押さえておきたいのは、不動産クラウドファンディングが「小口化された不動産投資」である点です。複数の投資家がオンライン上で資金を出し合い、運営会社が物件を取得・運営して配当を分配します。不動産特定共同事業法に基づき、運営会社は宅建業免許に加えて金融商品取引法上の登録も必要なため、一定の監督体制が整っています。
仕組みとしては、投資家は運営会社が設定した匿名組合契約を結び、配当は運用期間に応じて分配されます。通常、元本が優先劣後構造で守られる案件が多く、劣後出資部分を運営会社が負担することで損失発生時のクッションになります。つまり、元本割れのリスクはゼロではないものの、従来の直接保有型よりもリスクが限定されやすい点が魅力です。
一方で、途中解約が原則できない、上場株式のように自由に売買できないといった流動性の低さはデメリットです。そのため、運用期間と生活資金のバランスを見極めて参加することが重要になります。
店舗特化型案件の魅力とリスク
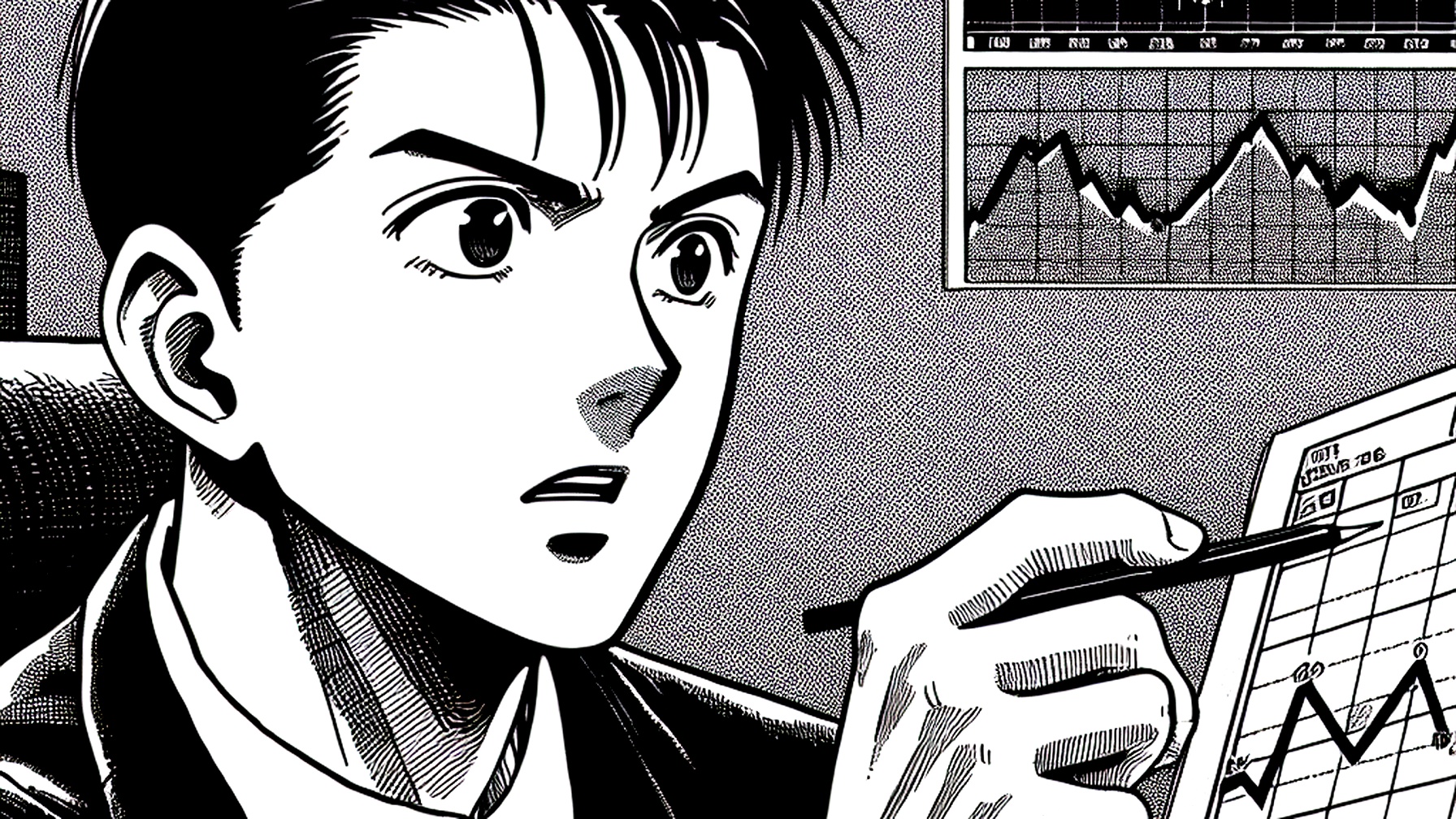
ポイントは、店舗物件が「家賃以外にも売上連動賃料で上振れを狙える」ことです。飲食店や物販店は売上高に応じた歩合賃料を採用するケースが多く、景気やトレンドに乗れば分配金が想定以上になる可能性があります。また、オフィスや住居より契約期間が短めでも、賃料単価が高いためキャッシュフローが厚いのが特徴です。
しかし、店舗は立地依存度が極めて高く、周辺競合や消費マインドの影響を受けやすい点がリスクです。日本政策投資銀行の2024年調査では、コロナ禍からの回復が進んだものの、地方中心部では空室率が依然15%前後で推移しています。つまり、物件の選定基準とテナント審査が甘い案件には注意が必要です。
さらに、原状回復費用や設備投資負担の範囲がテナント契約により異なるため、運営会社の説明資料を細部まで確認する姿勢が欠かせません。劣後割合が総投資額の20%以上で設定される案件は、初心者にとって比較的安全といえます。
初心者が見るべき四つの評価ポイント
重要なのは、①立地、②テナント属性、③運営会社の実績、④契約条件の4点を総合的に見ることです。
まず立地は、最寄り駅からの徒歩分数だけでなく、周辺の商業動線や再開発計画も合わせてチェックします。例えば、2025年秋に開業予定の広島駅新商業ゾーンのように、人流増加が確実視されるエリアは収益面で優位です。
次にテナント属性ですが、大手フランチャイズや上場企業が入居していれば、与信管理が容易で賃料回収リスクが低くなります。逆に創業間もない個人店の場合は、分配利回りが高めに提示されていても慎重な検討が欠かせません。
三つ目は運営会社の実績です。累計調達額や過去の償還遅延率をサイト上で開示しているかが判断材料になります。金融庁の「クラウドファンディングモニタリング結果」によると、開示が詳しい事業者ほど行政処分を受ける割合が低い傾向があります。
最後に契約条件として、優先劣後比率だけでなく、マスターリース契約の有無や賃料保証期間を確認しましょう。マスターリースとは、運営会社が物件を一括借り上げする形式で、一定期間空室リスクを吸収してくれます。特に初めての投資では、保証期間が運用期間と一致している案件が安心材料になります。
2025年度に利用できる主なサービスと比較
まず代表的なのが「CRE Funding」です。同サービスは物流施設で知名度を上げましたが、2024年末から都市型店舗案件も扱い始め、2025年度の平均予定利回りは年5.2%です。劣後比率は30%と高く、償還実績も延滞ゼロが続いています。
次に「OwnersBook」は、不動産会社ロードスターキャピタルが運営し、国内屈指の貸付型案件数を誇ります。店舗物件は少数ながら、投資対象の評価書を第三者鑑定付きで公開している点が特色です。予定利回りは年4%前後と控えめですが、担保評価が厳格なので堅実派に適しています。
「みんなで店舗ファンド」は、名称通り路面店に特化したプラットフォームで、1口5万円から参加可能です。2025年度の平均利回りは年6%と高めですが、入居テナントが個人経営の場合も多いため、前述の評価ポイントを念入りに確認しましょう。
最後に「ガイアファンディング日本版」は、米国店舗物件の日本人向け募集を行っています。為替ヘッジなしの案件もあるため、円安局面では上振れ、円高局面では下振れリスクが生じることを理解しておきましょう。
安全性を高めるための実践ステップ
まず、生活防衛資金とは別に「投資余力」の範囲で少額から試すことが基本です。1案件に集中せず、運用期間と立地の異なる3~5案件に分散するだけで損失リスクは大きく下がります。
次に、運用レポートを必ず読み、賃料入金状況やテナントの営業成績を追跡します。万一、延滞や退去の兆候が見えたら、同じ運営会社の新規案件への投資は控えるなど柔軟に行動しましょう。
また、2025年4月に改正された電子取引記録保存法により、投資家は電子交付された契約書を5年間保存する義務があります。クラウドストレージやPDF管理アプリを活用して、確定申告時に慌てないよう備えてください。
結論として、店舗特化型の不動産クラウドファンディングは高利回りを狙える一方、景気変動や立地リスクも内包しています。評価ポイントを押さえ、複数案件に分散し、定期的に情報を追う姿勢こそ初心者が長期的に勝ち残るコツです。
まとめ
この記事では、不動産クラウドファンディングの基本構造から店舗物件の特性、初心者が確認すべき四つの評価ポイント、2025年度に利用できる主要サービスまで解説しました。要するに、少額から始められる手軽さに飛びつく前に、立地とテナント情報、運営会社の実績、契約条件を丁寧に調べる必要があります。まずは1万円からでも投資体験を積み、分散投資と情報収集を習慣化していきましょう。そうすれば、店舗物件ならではの歩合賃料アップを享受しつつ、リスクを抑えた安定収益を目指せます。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産特定共同事業ポータル – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei/ftkj/
- 金融庁 クラウドファンディングモニタリング結果 – https://www.fsa.go.jp/
- 日本政策投資銀行 地域商業施設動向調査2024 – https://www.dbj.jp/
- 総務省 電子取引記録保存法ガイドライン2025 – https://www.soumu.go.jp/
- 日本クラウドファンディング協会 年次報告2025 – https://www.jcfa.jp/

