初心者の方は「REIT(リート)って株と何が違うのだろう」「購入して本当に配当がもらえるのか」と疑問だらけではないでしょうか。手元に大きな資金がなくても不動産収益を得られる仕組みとして人気が高いものの、実際に買うとなると銘柄が多く、どれを選べばよいか迷います。この記事では、今から レビュー REIT 比較 をキーワードに、2025年10月時点で有効な制度や最新データを踏まえつつ、選び方のポイントと具体的な注意点を整理します。読み終える頃には、自分に合ったREITを選ぶ基準がはっきり見え、次の一歩を自信を持って踏み出せるはずです。
REITとは何か、そして今投資を検討すべき理由
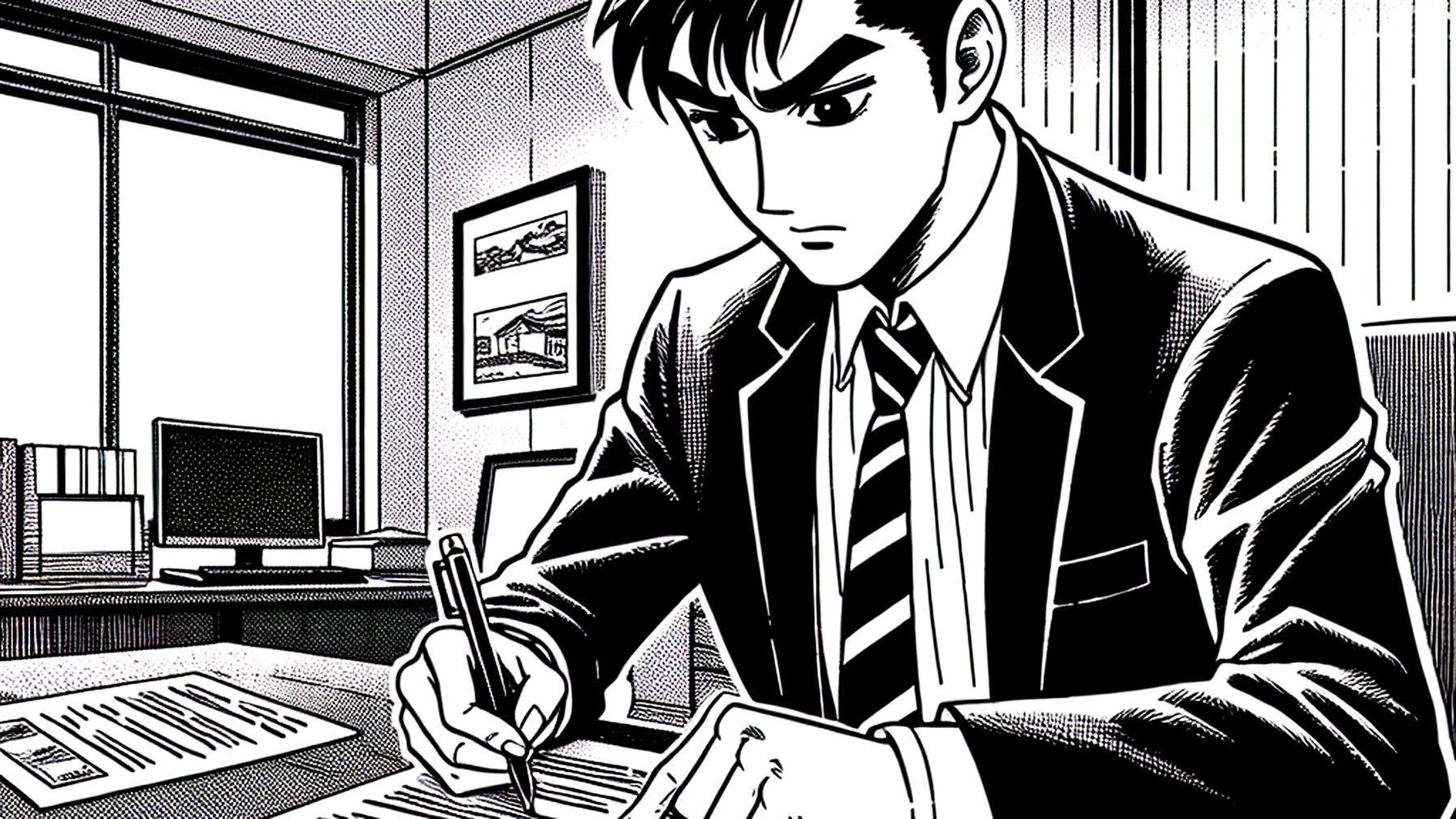
まず押さえておきたいのは、REITが「不動産投資信託」の英語略であり、オフィスビルや物流施設など複数の不動産から得られる賃料を投資家に分配する仕組みだという事実です。株式と似た感覚で売買できる一方、内部で不動産の専門家が運用してくれるため、自分で物件を管理する必要がありません。
日本銀行が公表する資金循環統計によると、2025年6月時点の国内REIT市場規模は約19兆円で、過去5年間でおよそ1.3倍に拡大しています。この背景には、低金利環境の長期化で利回り商品としての魅力が高まったことに加え、2024年に始まった新NISA対応で少額から買いやすくなった点が挙げられます。さらに、上場インフラファンドや海外REIT ETFの選択肢が増え、市場はより多様化しました。
重要なのは、2025年10月現在でも平均分配利回りが3.6%前後と、東証プライム主要株の平均配当利回り(約2.1%)を上回っていることです。つまり、インカムゲインを重視する投資家にとって依然として魅力的な選択肢だと言えます。また、物価上昇局面では賃料改定が期待でき、家賃と連動して配当が増える可能性もあります。
注目すべき指標と数字の見方
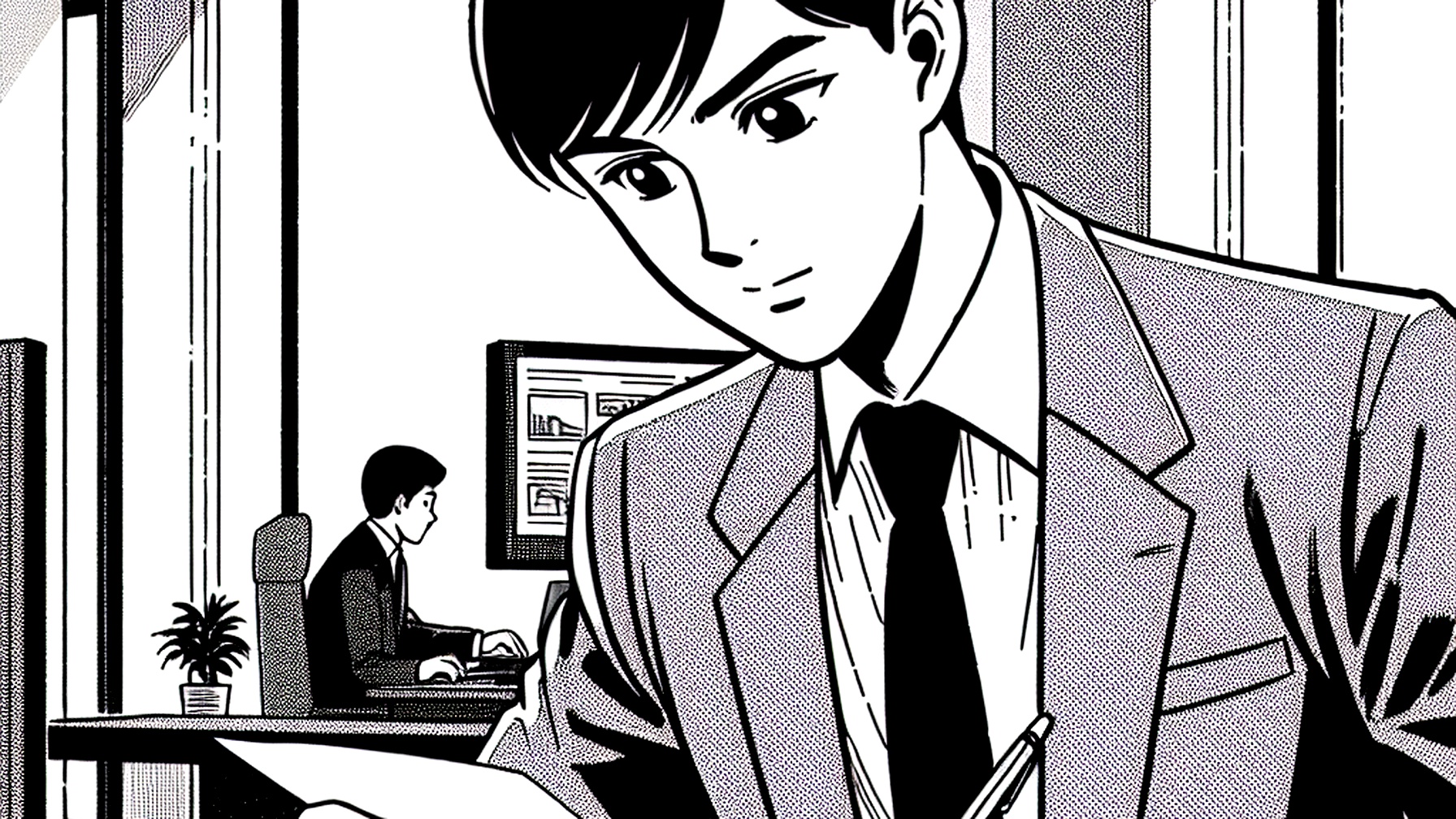
ポイントは、利回りだけでなく「NAV倍率」「LTV」「分配金性向」の三つを同時に確認することです。NAV倍率は保有不動産の純資産価値に対する株価の割安度を示し、1倍未満なら市場価格の方が低いと判断できます。
一方でLTV(Loan to Value)は借入金比率を表し、50%を超えている銘柄は金利上昇時の負担増に注意が必要です。2025年春に日銀がマイナス金利を解除して以降、長期金利は1.3%前後で推移していますが、今後もじわじわ上昇する可能性があります。そのため、安全圏とされる40%台前半を維持しているか確認しましょう。
最後に分配金性向ですが、REITは税制上、利益の90%以上を分配すれば法人税が課されない仕組みです。したがって性向が90〜100%に近いのは当然ですが、100%超が連続する場合は内部留保が枯渇し、修繕資金を追加借入で賄うリスクが高まります。
日本REITと海外REITの違いを知る
実は、同じREITでも日本と海外では値動きの要因が異なります。日本REIT(J-REIT)は賃料の変動幅が小さく安定している反面、人口減少による中長期の需給バランスが懸念されます。
一方で米国REITは住宅、データセンター、ヘルスケアなど用途が多岐にわたり、人口増加とテクノロジー需要に支えられて成長余地が大きい点が魅力です。ただし、FRBの政策金利が5%台と高水準で推移しているため、配当利回りが相対的に割安に見えても金利上昇局面では価格が変動しやすいリスクがあります。
言い換えると、為替と金利の影響を強く受ける海外REITは、分散効果とボラティリティという両刃の剣を持っています。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスによると、2020〜2024年の米国REIT年間リターンは平均7.4%でしたが、最も悪い年(2022年)はマイナス24%と大きく下落しました。国内REITの同期間最悪リターンはマイナス12%だったため、値動きの大きさを理解したうえで組み込む必要があります。
2025年版・注目REITをタイプ別にレビュー
まずオフィス特化型では、日本ビルファンド投資法人が依然として時価総額トップで、空室率は4.2%に改善しています。東京都心部の大型ビルで更新賃料が上昇し、直近期の分配金予想は1口あたり5,200円です。一方でテレワーク定着の影響を受けやすく、中長期では賃料頭打ちの懸念があります。
次に物流型では、GLP投資法人の稼働率が99%と高水準を維持しています。EC市場の拡大が追い風で、2025年度も新規開発物件を複数組み入れる計画です。ただ、開発資金調達でLTVが48%まで上昇しており、追加利上げ時の影響を注視する必要があります。
住宅型では、アドバンス・レジデンス投資法人が分散効果の高い全国型ポートフォリオを構築し、実質利回りは3.4%程度です。家賃改定余地は小さいものの、人口流入が続く政令指定都市に物件を集中させており、空室率は1%台と安定しています。
最後に総合型ですが、イオンリート投資法人が商業施設と物流施設の比率を6:4に調整し、景気変動耐性を高めています。コロナ禍収束後の来店客数が回復したことで分配金は増加基調にありますが、今後の消費動向に注意が必要です。
REIT投資を成功させる資金計画と制度活用
重要なのは、購入価格の10〜20%程度を現金で準備し、急な下落時のナンピン余力を確保することです。SBI証券のシミュレーションでは、毎月5万円を分散投資した場合、平均取得単価を抑えつつ分配金を再投資することで、年3%の複利成長が期待できるという試算があります。
2025年度の新NISA成長投資枠を活用すれば、年間240万円までの投資分配当が非課税となります。非上場不動産クラウドファンディングと異なり、上場REITはNISA対象で、配当も売却益も20年にわたって非課税です。期限は現行制度下で2042年まで設定されているため、長期的な税制メリットを意識して購入時期を分散させると効果的です。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)ではREIT指数連動型の投資信託を選べば掛金が全額所得控除となり、60歳まで運用益非課税が続きます。ただし途中換金ができないため、流動性を確保する目的でNISAと併用する策が現実的でしょう。
結論として、キャッシュポジションを保った上で税制優遇枠を最大限活用し、国内と海外を組み合わせたポートフォリオを作ることが、景気サイクルに左右されにくいREIT投資のカギになります。
まとめ
ここまで、REITの基礎から指標の見方、国内外の特徴、2025年版注目銘柄のレビュー、そして制度を活用した資金計画まで網羅的に整理しました。利回りだけで選ぶと金利上昇や空室率のリスクを見落としがちですが、NAV倍率やLTVに目を向ければ銘柄の健全性を客観的に判断できます。さらに新NISAやiDeCoと組み合わせることで、税引後リターンを大きく押し上げることが可能です。まずは少額から複数銘柄を買い、分配金を再投資しながら自分のリスク許容度を確かめることが、長期的に安定収益を得る最短ルートと言えます。
参考文献・出典
- 日本銀行 資金循環統計 – https://www.boj.or.jp/statistics/
- 金融庁 新NISA制度説明資料(2025年度版) – https://www.fsa.go.jp/
- 東証REIT指数 月次レポート – https://www.jpx.co.jp/
- S&P Dow Jones Indices Annual U.S. REIT Performance – https://www.spglobal.com/
- SBI証券 シミュレーションツール公開データ – https://www.sbisec.co.jp/

