不動産クラウドファンディングに興味はあるものの「本当に儲かるのか」「元本割れしないのか」と不安を抱く人は少なくありません。特に専業で投資を考える場合、生活が収益に直結するため、リスクの正確な把握は欠かせません。本記事では、15年以上プロとして不動産投資に携わってきた視点から、最新(2025年10月時点)の制度や実例を踏まえつつ、初心者でも理解できる形で「不動産クラウドファンディング 実際の リスク 専業」というテーマを深掘りします。読み終えたときには、リスクを見極めながら専業でも活用できる判断軸が得られるはずです。
不動産クラウドファンディングの仕組みと市場の現状
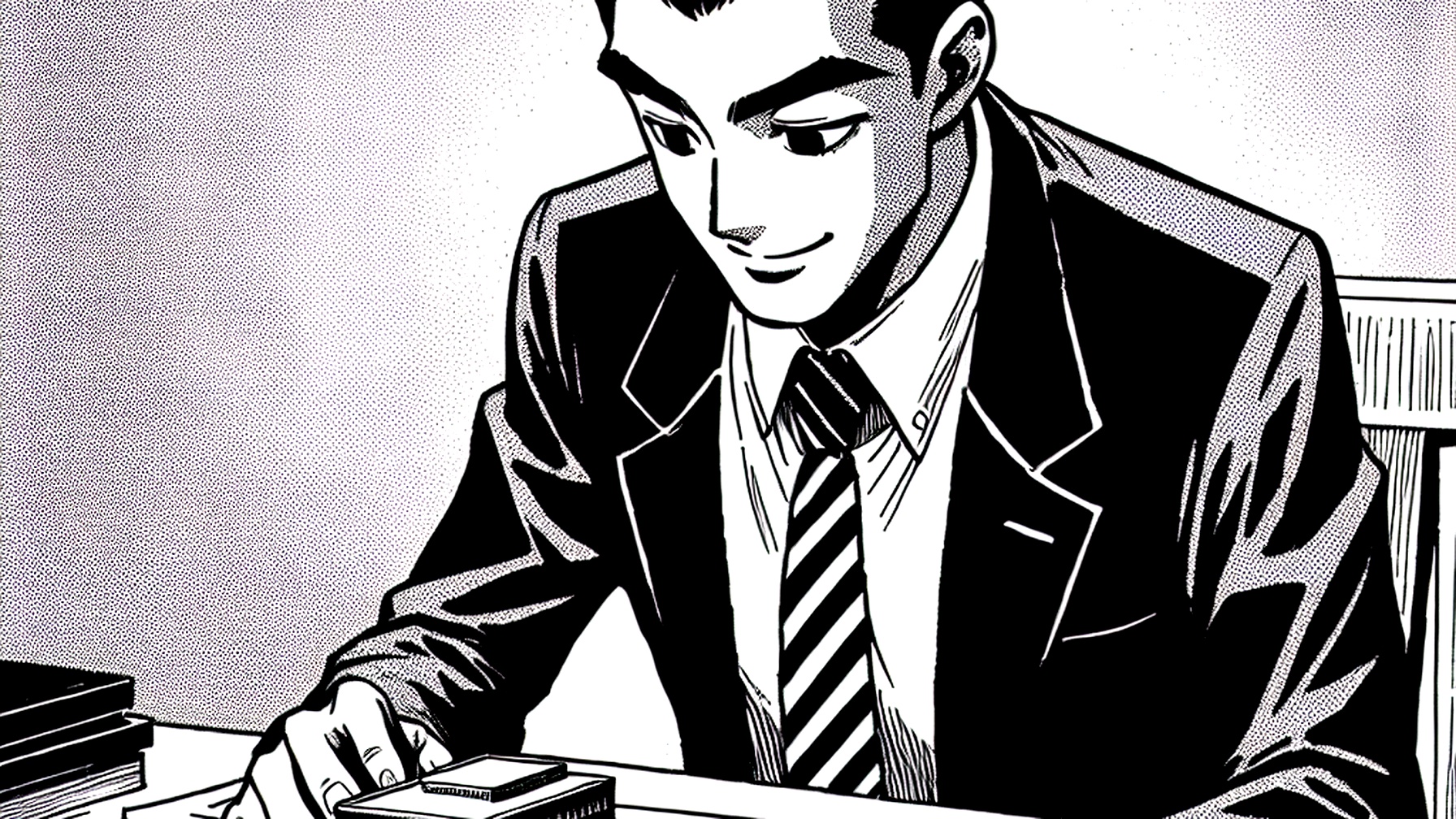
まず押さえておきたいのは、仕組みの理解です。不動産クラウドファンディングとは、不動産特定共同事業法に基づき、複数の投資家が少額ずつ資金を出し合い、不動産を共同で保有・運用するスキームをオンラインで完結させたものを指します。2020年の電子取引業務解禁以降、参入事業者が急増し、金融庁の2024年度調査では市場規模が約1,800億円に達しました。
実は、投資家の8割以上が副業目的で参加している一方、専業で取り組む投資家も年々増えています。利回りは年3〜7%が中心で、J-REITより高く、直接保有より手軽という魅力が背景にあります。しかし、公開情報が限られるため、表面利回りだけで判断すると痛い目を見る可能性があります。
また、2023年以降は「任意組合型」から「匿名組合型」に資金が流れています。これは課税と損益通算の扱いが違うため、専業投資家にとってキャッシュフロー計算が複雑になる点に注意が必要です。つまり、制度の細部を理解しないと、期待とは異なる税負担を負う恐れがあります。
想定外のリスクと実際に起きた事例
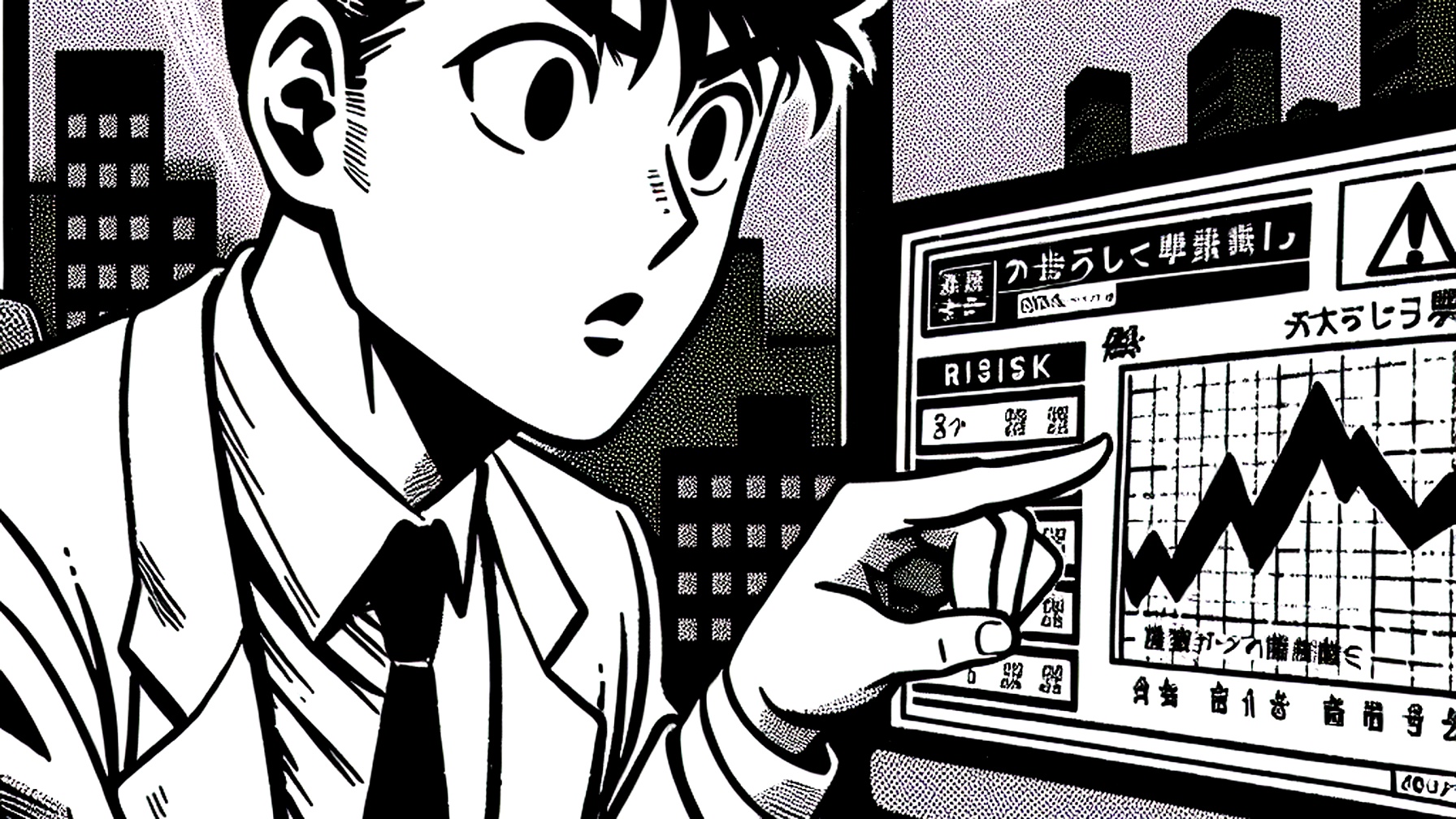
ポイントは、リスクが「元本割れ」だけではないことです。2022年には都内区分マンション再生案件で工期が半年遅延し、分配が1年延期された例がありました。このとき元本は戻りましたが、投資家のIRR(内部収益率)は計画より2%下がりました。資金拘束リスクが現実化した典型です。
一方で、北海道のホテル開発を扱った案件では、運営会社の資金繰り悪化が表面化し、2024年末に元本の10%が減額返済となりました。理由は、ホテル稼働率が想定を下回り、追加資金調達に失敗したためです。公募段階では想定稼働率70%と提示されていましたが、日本政府観光局の実績値は55%に留まっていたことが後から分かりました。つまり、スポンサーの事業計画を第三者データで検証しないと、数字上の甘さに気づけません。
さらに、オフラインでの不動産取引と違い、プラットフォームが倒産するプラットフォームリスクも存在します。2023年に倒産した小規模事業者では、未組成案件の募集資金が保全口座に分別管理されていなかったため、返金まで10カ月を要しました。専業投資家は流動性を確保するため、事業者選びで信託分離の有無を必ず確認すべきです。
専業投資家が確認する三つのポイント
重要なのは、案件を見る前に「事業者」「物件」「契約形態」の三つを体系的に評価することです。まず事業者については、金融庁公開の「クラウドファンディング事業者一覧」で免許区分と行政処分歴を調べ、最低でも直近2期の財務諸表に目を通します。純資産が案件総額の5%未満しかない会社は、トラブル時に救済余力が乏しいため要警戒です。
次に物件の評価では、現物同様に立地分析が要です。国土交通省の地価LOOKレポートや市区町村の人口動態データを用い、賃料下落余地を数値化します。たとえば、人口が5年間で3%以上減少しているエリアは賃料成長率がプラスに転じにくい傾向があります。専業であれば、利回りが高くても賃料成長がマイナスなら期待収益を低めに見積もるのが無難です。
最後に契約形態です。匿名組合型は損益通算ができず、赤字でも他の所得と相殺できません。任意組合型は通算可能ですが、持分が直接保有扱いになるため、固定資産税の負担が生じる場合があります。専業投資家は税理士と相談し、年間キャッシュフローへの影響を試算してから申し込むと、想定外の納税資金不足を防げます。
リスクを抑えるための2025年度制度活用
まず知っておきたいのは、2025年度に完全施行された金融商品取引法の改正です。投資型クラウドファンディングの広告には、リスク要因の表示が義務化され、事業者は第三者による物件価値評価書を開示する必要があります。これにより、過去より透明性は向上しましたが、評価機関の見方が甘い場合もあるため、自身で裏取りする姿勢は依然として重要です。
また、2025年度の中小企業庁「不動産特定共同事業者向けDX促進補助金」は、信託分離システム導入費の2/3を補助する制度で、来年3月まで交付申請が可能です。補助を受けた事業者は分別管理体制が強化されるため、投資家保護の観点で安心材料になります。とはいえ、補助採択後も実装状況を確認しないと、形だけで終わるリスクが残る点に注意しましょう。
さらに、国税庁が2024年から公表を始めた「クラウドファンディング課税FAQ」は、配当所得と雑所得の区分を明確化しています。専業で複数案件を保有する場合、この区分に沿って損益を整理することで、税務調査リスクを低減できます。
ポートフォリオに組み入れる際の戦略
基本的に、専業投資家が不動産クラウドファンディングにフルベットするのは得策ではありません。理由はレバレッジを掛けにくく、複利効果が限定的だからです。自己資金1,000万円を例に取ると、直接保有で銀行融資を活用すれば、年7%の利回りを5倍のレバレッジで回せる可能性があります。しかし、クラウドファンディングではレバレッジが効かず、年5%のリターンが上限に近い案件が多いのが現実です。
一方で、空室リスクや管理負担を外部化できるメリットは大きく、ポートフォリオの安定装置として機能します。私は総投資額の20%をクラウドファンディングに充て、残りを直接保有とREITで分散しています。こうすることで、キャッシュフローのブレが抑えられ、銀行融資の返済原資を安定的に確保できます。
つまり、専業であってもクラウドファンディングは「守りの資産」と位置づけ、短期運用案件を中心に回転率を高めると効果的です。平均運用期間が6カ月の案件を選べば、金利上昇局面でも迅速に資金を引き上げ、直接保有物件の頭金に充当するといった柔軟な戦略が可能になります。
まとめ
ここまで、不動産クラウドファンディングの仕組みから実際のリスク、2025年度の制度活用まで解説してきました。重要なのは、利回りに目を奪われず「事業者の体力」「物件の将来性」「契約形態」の三つを精査し、税務と流動性を総合的に判断することです。専業投資家であれば、資金拘束リスクを最小化する運用期間と分散投資比率を設定し、守りの資産として位置づけることで、全体のキャッシュフローが安定します。最後に、制度改正や補助金情報は常に更新されるため、公式データを定期的にチェックし、自ら裏取りする姿勢を忘れないようにしましょう。
参考文献・出典
- 金融庁「クラウドファンディング事業者に関する情報」 – https://www.fsa.go.jp/
- 国土交通省「地価LOOKレポート2025年7月期」 – https://www.mlit.go.jp/
- 日本政府観光局(JNTO)「宿泊旅行統計調査2024年版」 – https://www.jnto.go.jp/
- 中小企業庁「2025年度 不動産特定共同事業者向けDX促進補助金概要」 – https://www.chusho.meti.go.jp/
- 国税庁「投資型クラウドファンディング課税FAQ(2024年版)」 – https://www.nta.go.jp/

