あなたも「不動産投資 本当に儲かるのか」と疑問を持ったことはありませんか。銀行預金の金利が低い今、家賃収入や売却益で資産を増やしたいと考える人は増えています。しかし、物件価格の高騰や空室リスクなど、心配の種も尽きません。本記事では利益の仕組みから最新データ、2025年度の税制優遇までを網羅し、初心者でも収支のイメージが描けるように解説します。読み終えた頃には、自分に合った投資判断を下すための基礎が身につくはずです。
不動産投資で利益が生まれる仕組み
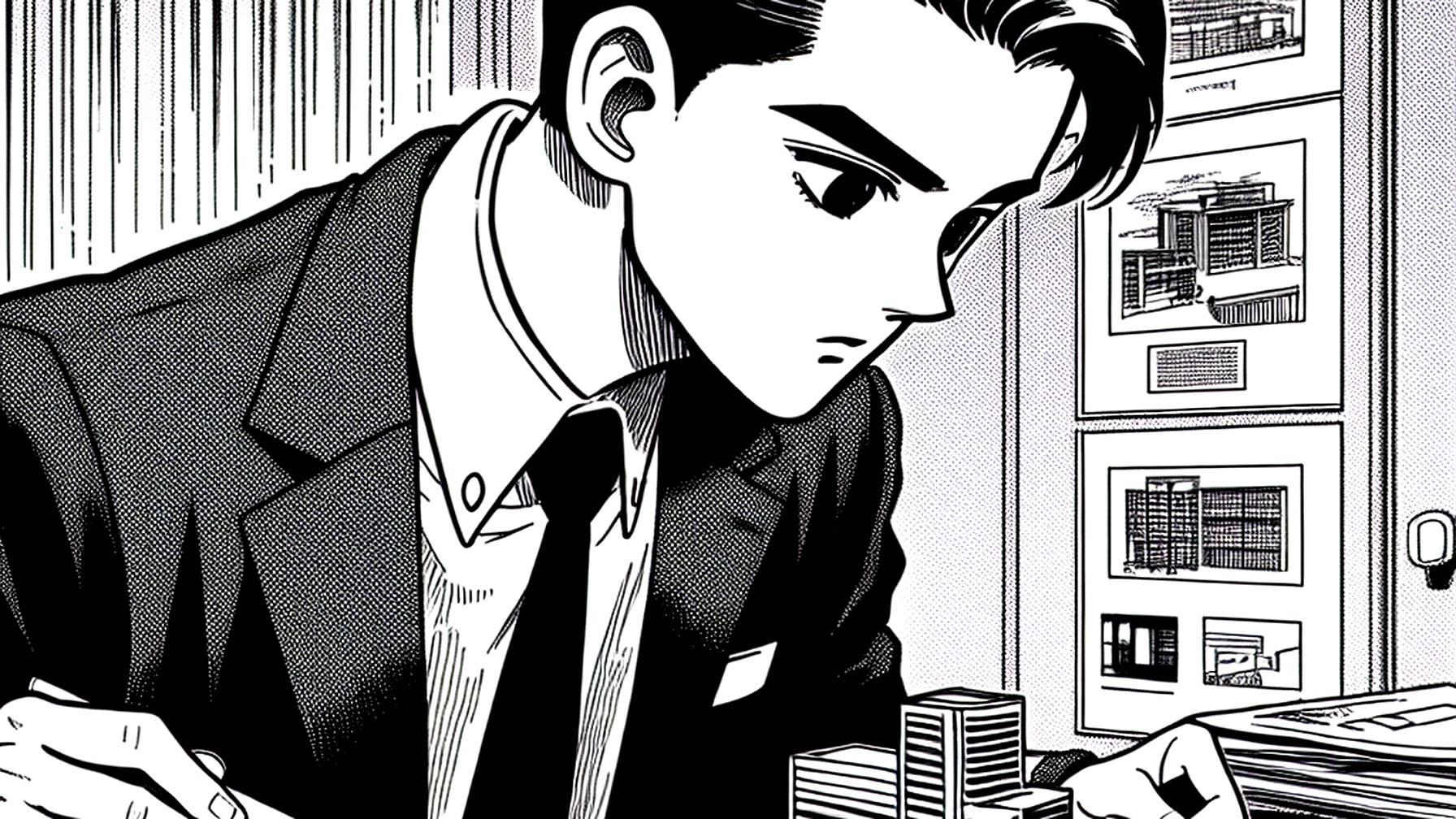
重要なのは、利益が「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」の二本立てで構成される点です。インカムゲインは家賃収入、キャピタルゲインは売却益を指します。両者のバランスを理解することで、長期か短期かという投資スタイルも見えてきます。
まず家賃収入について考えます。入居率九五%を維持できれば、想定家賃十万円のワンルームでも年間百十四万円程度の売上が見込めます。ここから管理費や修繕費を差し引いても、金融機関への返済額を下回らなければ毎月のキャッシュフローは黒字となります。つまり、空室期間を短く保つ工夫が利益の源泉です。
一方、売却益は市場価格の動向に大きく左右されます。国土交通省の不動産価格指数(二〇二五年七月速報)では、東京区部の住宅価格が前年同期比四・二%上昇しています。短期で値上がり益を狙う場合、市場サイクルの見極めが欠かせません。しかし、値上がりが鈍化しても家賃が安定していれば投資は継続可能です。
結局のところ、インカムとキャピタルの両輪をどう組み合わせるかが長期的なリターンを決めます。特に初めての投資では、家賃収入を主軸に据えて生活費に影響しない返済計画を組むことが安全策と言えるでしょう。
収支を左右する五つのコスト
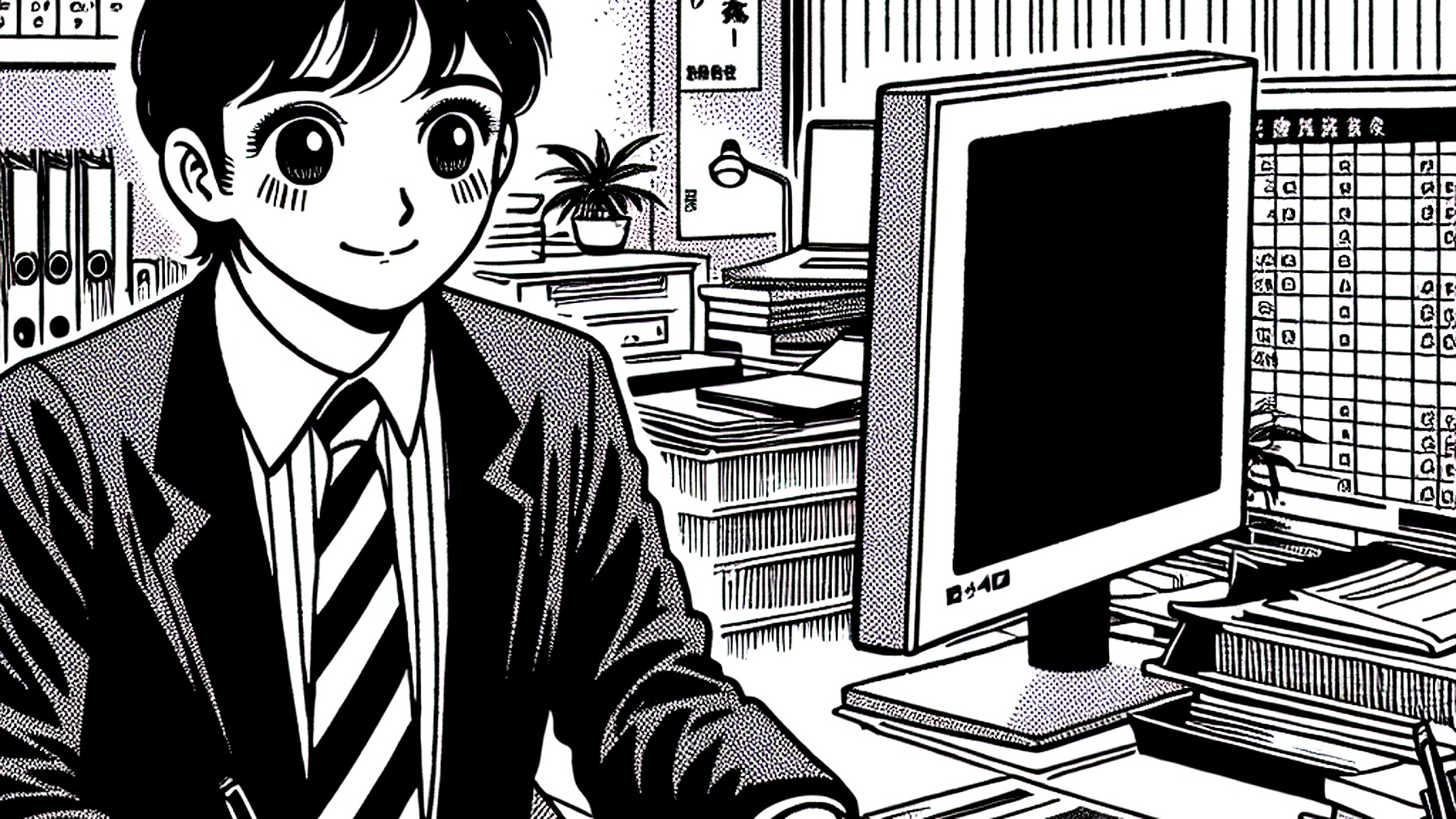
ポイントは、物件価格だけで判断しないことです。購入後に発生する五つのコストを把握しないと、想定外の出費でキャッシュフローが赤字に傾きます。
第一は管理費・修繕積立金です。分譲マンションの場合、月額一万円から二万円が一般的ですが、大規模修繕の時期には増額もあり得ます。第二は固定資産税で、総務省の統計によると、都心部のワンルームで年間八万円前後が目安です。
第三は空室期間にかかる広告費です。仲介会社への成功報酬として家賃一か月分を支払うケースが多く、退去が多い物件ほど負担は増えます。第四は火災・地震保険料で、築浅の鉄筋コンクリート造なら年間一万円台に抑えられますが、木造アパートでは二倍近くになることもあります。
最後に大きな影響を与えるのが金利です。日本銀行が二〇二四年にマイナス金利政策を解除し、変動金利が〇・五%ほど上昇しました。仮に三千万円を三十五年返済で借りている場合、月々の返済額は約七千円増える計算です。金利上昇に備え、自己資金を二割程度入れて借入額を抑えると、収支は安定します。
これら五つのコストを合算し、家賃収入から差し引いたうえで利回りを算出することが、投資判断の出発点となります。
データで読む現在の市場環境
実は、二〇二五年の不動産市場は地域ごとに温度差が広がっています。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、二〇三〇年に向けて全国人口は緩やかに減少する一方、首都圏一都三県はわずかながら増加が続く見込みです。
東京都の空室率は不動産情報サービス企業のデータで三・三%と、全国平均の四・八%より低水準です。これに対し、地方中核都市は五%台に達しており、家賃下落圧力が強まっています。つまり、立地選定を誤ると想定利回りが達成できないリスクが高まります。
賃料の推移を見ると、レインズの月次報告で新築ワンルームの平均募集賃料が前年同月比一・二%上昇と、堅調に推移しています。一方中古マンションの取引価格は、住宅ローン金利の上昇を受け伸びが鈍化しました。家賃は比較的安定しているため、長期保有を前提とするならば高値掴みを避けることが肝心です。
こうしたデータを踏まえると、二〇二五年時点でも都心部は低空室率で安定収益を見込める一方、地方では人口動向と再開発計画を精査する必要があります。数字の裏にある地域特性を読み解く力が投資成功の鍵となります。
初心者が押さえたいリスク管理
まず押さえておきたいのは、リスクを「避ける」のではなく「コントロール」する視点です。空室、家賃下落、金利上昇、災害の四大リスクを想定し、事前に対策を講じれば損失は限定できます。
空室対策では、募集開始を退去の一か月前に前倒しし、室内クリーニングを迅速に済ませるだけでも平均空室期間を半減できます。また、周辺相場より家賃を五%高く設定し、フリーレント一か月を付ける方法も有効です。見た目の賃料を保ちつつ実質的な割引となるため、将来の賃料改定がしやすいからです。
家賃下落への備えとして、間取り変更や設備更新が挙げられます。国土交通省の「賃貸住宅市場の実態調査」では、宅配ボックスや高速インターネットの導入で平均入居期間が一年延びたとの結果があります。初期投資が二十万円程度でも、長期的には空室損失の削減につながります。
さらに、変動金利で融資を受ける場合は、三%まで上昇しても返済できるシミュレーションを作成しましょう。耐震補強や火災保険の見直しも忘れずに行い、物件の資産価値を維持することがリスク低減につながります。
2025年度の税制優遇と資金調達
基本的に、投資用物件は住宅ローン控除の対象外ですが、減価償却費を経費計上できる点が節税の柱です。木造なら耐用年数二十二年、鉄筋コンクリート造なら四十七年が基準で、築年数に応じた計算が必要になります。また、青色申告特別控除六十五万円を活用すれば、所得税をさらに圧縮できます。
二〇二五年度も引き続き「投資用不動産の登録免許税軽減措置」が継続され、個人が中古物件を取得する場合、所有権移転登記の税率が二・〇%から一・五%に減額されます。期限は二〇二六年三月三十一日までと告示されていますので、購入タイミングを計画すると費用を抑えられます。
資金調達では、地銀や信用金庫が地方活性化を目的にアパートローンの金利を一・五%前後で提供しています。ただし、融資審査では自己資金一割以上と、家賃収入による返済比率(返済額 ÷ 家賃収入)が五〇%以下であることが求められるケースが増えました。事前に試算し、自己資金を厚めに準備すると交渉がスムーズです。
さらに、サステナブル投資の流れを受け、断熱性能の高い物件に対しては金利を〇・二%優遇する「グリーンアパートローン」を新設した金融機関も登場しました。省エネルギー性能が高いほど空室期間も短くなる傾向があり、融資条件と収益性の両面でメリットがあります。
まとめ
不動産投資が本当に儲かるかどうかは、インカムとキャピタルのバランス、五つのコスト管理、地域データの読み解き、そして制度活用にかかっています。特に二〇二五年は金利上昇と人口動態の二つの波が投資リターンを左右します。データを基に保守的なシミュレーションを行い、自己資金を厚めに準備することで、長期にわたり安定した収益を得る道が開けます。今後は断熱性能や環境性能といった新しい評価軸にも目を向け、時代に合った物件選びを心がけましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数速報 – https://www.mlit.go.jp/statistics/details/t-kokusaishisu.html
- 総務省 固定資産税に関する統計 – https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/
- 国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口 – https://www.ipss.go.jp/
- REINS マーケット情報 – https://www.reins.or.jp/
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp/

