多くの方が「不動産投資で相続税は本当に下がるのか」と疑問を抱えています。預貯金だけでは税負担が重くなるという話を耳にしても、何がどう違うのか分かりにくいものです。本記事では、不動産投資が相続税対策として機能する仕組みを基礎から分かりやすく解説し、2025年10月時点で利用できる制度や注意点を整理します。読むことで、対策のメリットと限界を理解し、次の一歩を具体的に描けるようになります。
相続税の基本と2025年度の課税環境
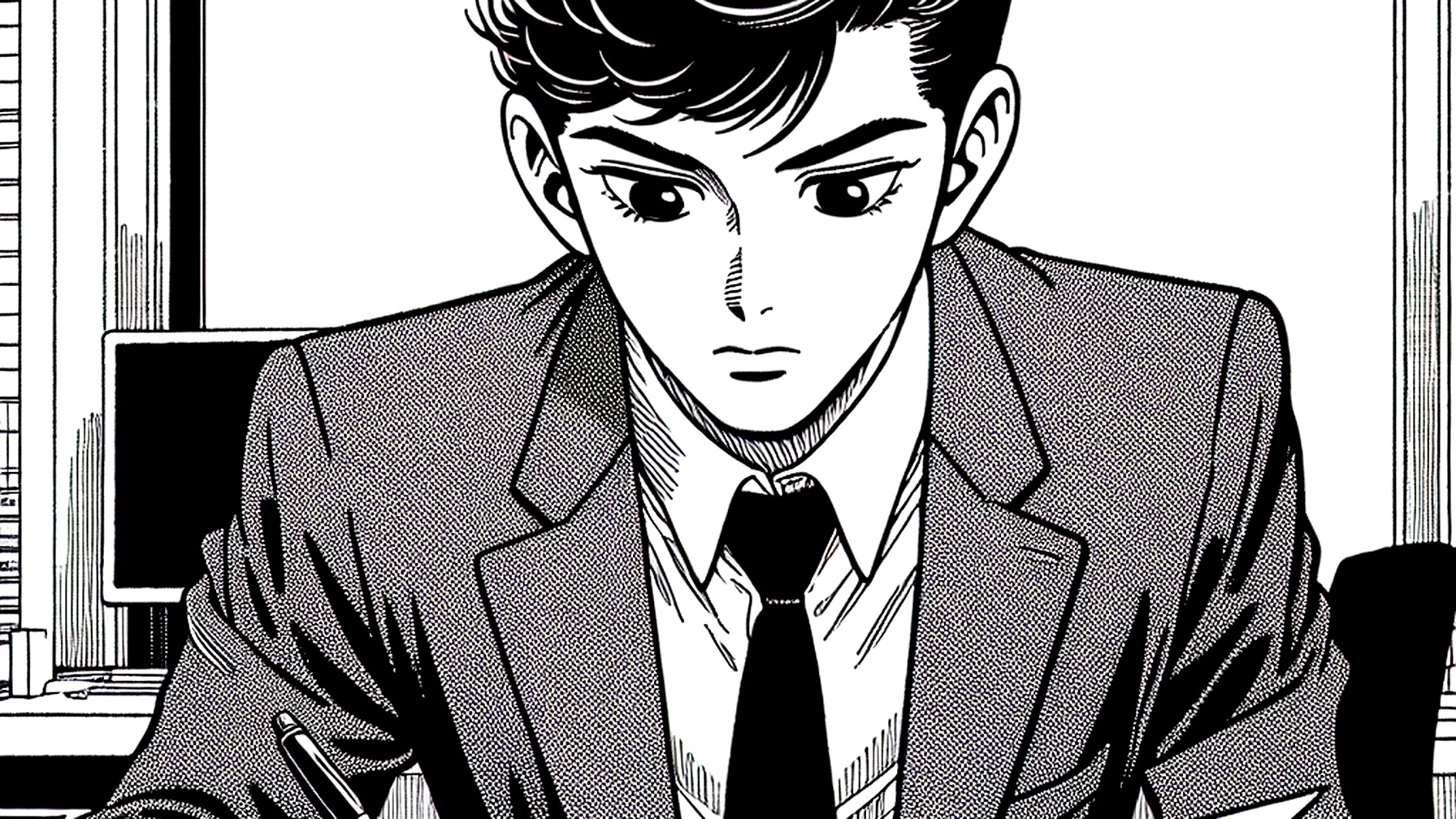
まず押さえておきたいのは、相続税の計算が「評価額×税率」で決まるというシンプルな構造です。国税庁の統計によると、課税対象となる遺産総額は年々増え、2024年には約20兆円に達しました。背景には地価の回復と金融資産の膨張があり、2025年度も基礎控除の見直しは予定されていません。そのため、都市部に自宅を持つだけで課税ラインを超える例が増えています。
一方で、相続税率そのものは2015年改正以降変わっていませんが、税務調査の件数は増加傾向にあります。国税庁は2023事務年度で申告件数の約20%を調査対象とし、そのうち80%で追徴課税が発生しました。つまり、形式だけの節税策は見抜かれる時代です。不動産投資を使うなら、評価方法から運用実態まで正しく理解することが欠かせません。
不動産投資が相続税を抑える仕組み
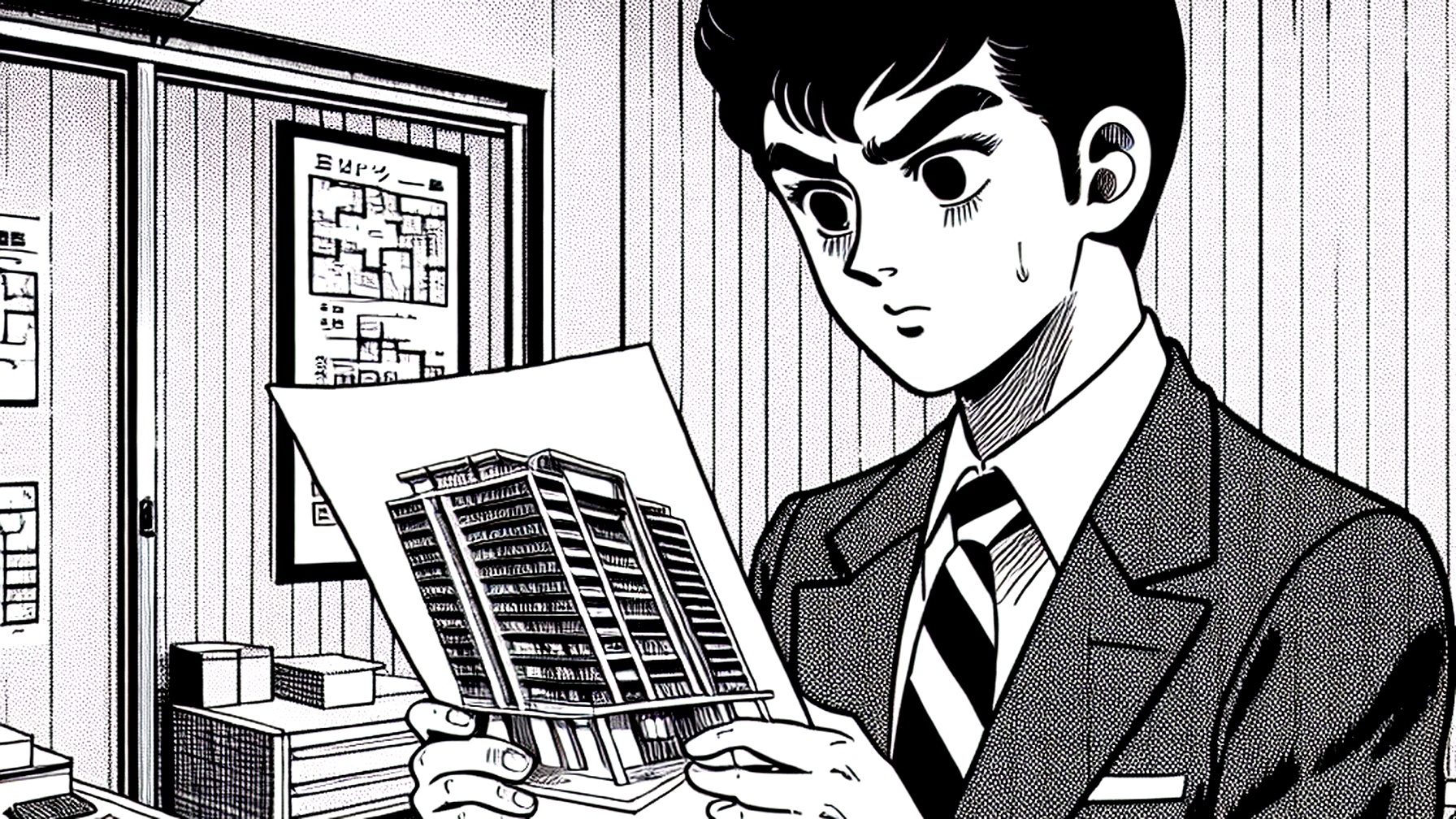
ポイントは、相続税における「評価額」と市場価格が一致しない点にあります。土地は路線価方式、建物は固定資産税評価額で計算されるため、市場価格のおおむね70%前後に圧縮されるのが一般的です。さらに、賃貸中の建物や土地には「貸家建付地(かしやたてつけち)」の評価減が適用され、総額が2〜3割下がるケースも珍しくありません。
たとえば、時価1億円の賃貸アパートを保有している場合でも、評価額は6,000万円前後になることがあります。この差額分がそのまま課税ベースを縮小するため、現金で1億円を残すより税負担が軽くなるのです。ただし、空室が多い物件や実勢家賃が路線価を下回る地域では、減額効果が薄れる点に注意が必要です。
また、2025年度も継続する「小規模宅地等の特例」を組み合わせると、自宅や事業用地の評価が最大80%減額されます。賃貸経営を事業として位置付けることで、この特例の適用範囲を広げられる可能性があるものの、適用要件は細かく、税理士との綿密な確認が必須となります。
節税になる物件選びと運用のコツ
重要なのは、評価減だけに目を奪われず「収益性」とのバランスを取ることです。都心のワンルームは空室リスクが低い反面、路線価が高いため評価減のインパクトが限定的です。一方、郊外の築古アパートは評価額を大きく下げられますが、将来的に賃料が下落すればキャッシュフローが赤字になる恐れがあります。つまり、立地・築年数・間取りなど複数の視点で総合判断を行うことが、成功への近道と言えます。
実は、融資条件も相続税対策の成否を左右します。金融機関からの借入は負債として相続財産から控除できるため、借入が多いほど評価額は下がります。ただし、返済原資が不足すれば家族に負担が残るため、想定空室率20%、金利上昇2%という厳しめのシナリオでシミュレーションすることが望ましいです。
さらに、2025年4月から適用された省エネ基準義務化により、新築アパートは断熱性能の説明責任が明確化しました。高性能物件は建築コストが上がるものの、長期でみれば修繕費が抑えられ、入居者募集でも有利に働く可能性があります。環境性能は評価額には直接反映されませんが、実質利回りを維持するうえで無視できない要素です。
2025年度の制度を活用した具体策
基本的に、節税効果を最大化するには「制度とタイミング」の両方を把握する必要があります。2025年度は、「相続時精算課税制度」の年110万円非課税枠が新設され、暦年贈与との選択肢が広がりました。賃貸用不動産を早期に子へ贈与する場合、この枠を使えば贈与税負担を抑えながら次世代の資産形成を前倒しできます。
また、国土交通省の「サステナブル建築物等先導事業(賃貸住宅版)」は2025年度も継続予定で、環境性能を高めた賃貸住宅には最大200万円の補助が出ます。補助金自体は相続税に直接影響しませんが、建築コストを下げつつ付加価値を高められるため、長期的な収益性を確保しやすくなります。
さらに、法人化による節税を検討する人も増えています。法人保有の場合、役員退職慰労金や所得分散の余地がありますが、株式自体は相続財産に含まれるため、評価方法が変わるだけで課税が消えるわけではありません。株価は決算書の純資産と類似業種比準価額で算定されるため、内部留保が膨らみ過ぎると評価額が上がる点には注意が必要です。
リスクと誤解、そして正しい相談先
実は、「不動産を買えば相続税がゼロになる」という誤解が根強く残っています。国税庁の通達では、取得から短期間で相続が発生した場合や市場相場とかけ離れた賃料設定は否認対象となる可能性が明示されています。2023事務年度の否認率は10%弱ですが、一度否認されると追徴税額に加え加算税と延滞税が課され、節税効果が吹き飛ぶ恐れがあります。
また、空室リスクや自然災害への備えを怠ると、家族が物件の維持管理に苦労します。2024年の能登半島地震では、損壊アパートの解体費用が保険で賄えず、相続放棄を選択した例も報告されました。火災保険に加え地震保険や家賃保証の適用範囲を確認し、引き継ぐ側の負担を具体的にイメージすることが重要です。
最後に、税理士・不動産鑑定士・司法書士といった専門家チームでの連携が成功の鍵を握ります。金融機関の紹介だけに頼らず、複数の専門家からセカンドオピニオンを得ることで、計画の抜け漏れやリスクを最小化できます。家族会議を早めに開き、資産と負債の全体像を共有することが、円満な相続への第一歩になります。
まとめ
不動産投資による相続税対策は、評価額圧縮と借入控除の組み合わせで大きな効果を生む一方、物件選びや運用を誤れば家族に負担を残します。2025年度は相続時精算課税の非課税枠拡充や省エネ補助金など、有利な制度がそろう年ですが、適用要件を満たさなければ逆効果です。まずは収益性と評価減のバランスを見極め、厳しめのシミュレーションを行ったうえで専門家に相談しましょう。準備を早めに始めれば、納税資金の確保と資産承継の両立が現実的な目標になります。
参考文献・出典
- 国税庁「相続税申告事績の概要」https://www.nta.go.jp
- 国土交通省「土地総合情報システム」https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省「サステナブル建築物等先導事業」https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai
- 財務省「租税特別措置法等の概要(2025年度)」https://www.mof.go.jp
- 日本銀行「金融システムレポート2025年4月」https://www.boj.or.jp

