戸建て賃貸の利回りが思ったより伸びない、そもそも数字の読み方がわからず一歩を踏み出せない──そんな悩みを抱える方は多いものです。投資スタイルが多様化する今、戸建て賃貸は家族層の長期入居が期待できる一方、物件価格や維持コストが重く、慎重な判断が欠かせません。本記事では利回りの基礎から物件選定、資金計画までを順番にひもとき、初心者でも実践しやすい手順を示します。読み終えるころには、戸建て賃貸 利回りを数字で比較し、自分に合った投資計画を描けるようになるでしょう。
戸建て賃貸の特徴と需要動向
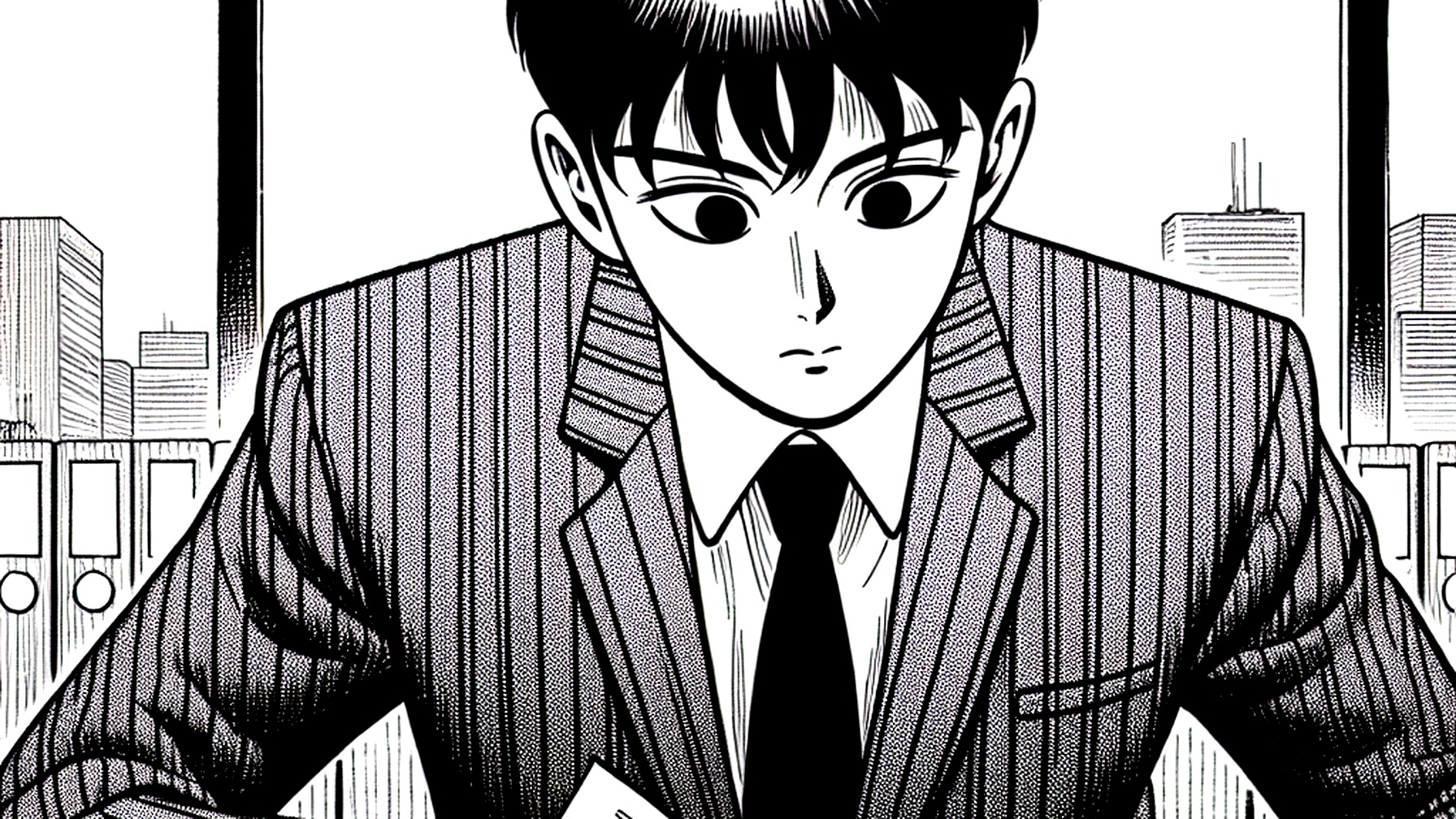
ポイントは、戸建て賃貸が「ファミリー長期入居」と「土地資産性」を両立できる点です。さらに、戸建志向の高まりが追い風となり、安定収益につながります。
まず、総務省住宅・土地統計調査によると、2020年から2025年にかけてファミリー層の持ち家志向は弱まり、賃貸戸建ての需要が緩やかに上昇しました。都市近郊で庭付きの生活を望む子育て世帯が増えたことが背景にあります。マンションと比べて上下階の騒音トラブルが少ない点も支持を集めました。つまり、入居期間が平均して7年以上と長く、空室リスクを下げやすいのが大きな魅力です。
一方で建物のメンテナンス費はマンションより高く、屋根や外壁を自分で負担する必要があります。賃料に占める経費比率が20%を超えるケースも珍しくなく、表面利回りだけで判断すると実際の手残りが想定以下になる恐れがあります。また、人口が減少しているエリアでは戸建ての賃貸需要が限定的になるため、立地選定が成否を分ける要素となります。
日本不動産研究所の2025年10月調査では、東京23区のワンルームマンション表面利回りが4.2%、アパートが5.1%でした。これに対し、都内戸建て賃貸の平均は4.8%とアパートよりやや低い数値です。しかし長期入居による原状回復費の削減と、土地値の下支えを勘案すれば、実質利回りはアパート並みに引き上げられる余地があります。
利回りの計算方法を押さえる
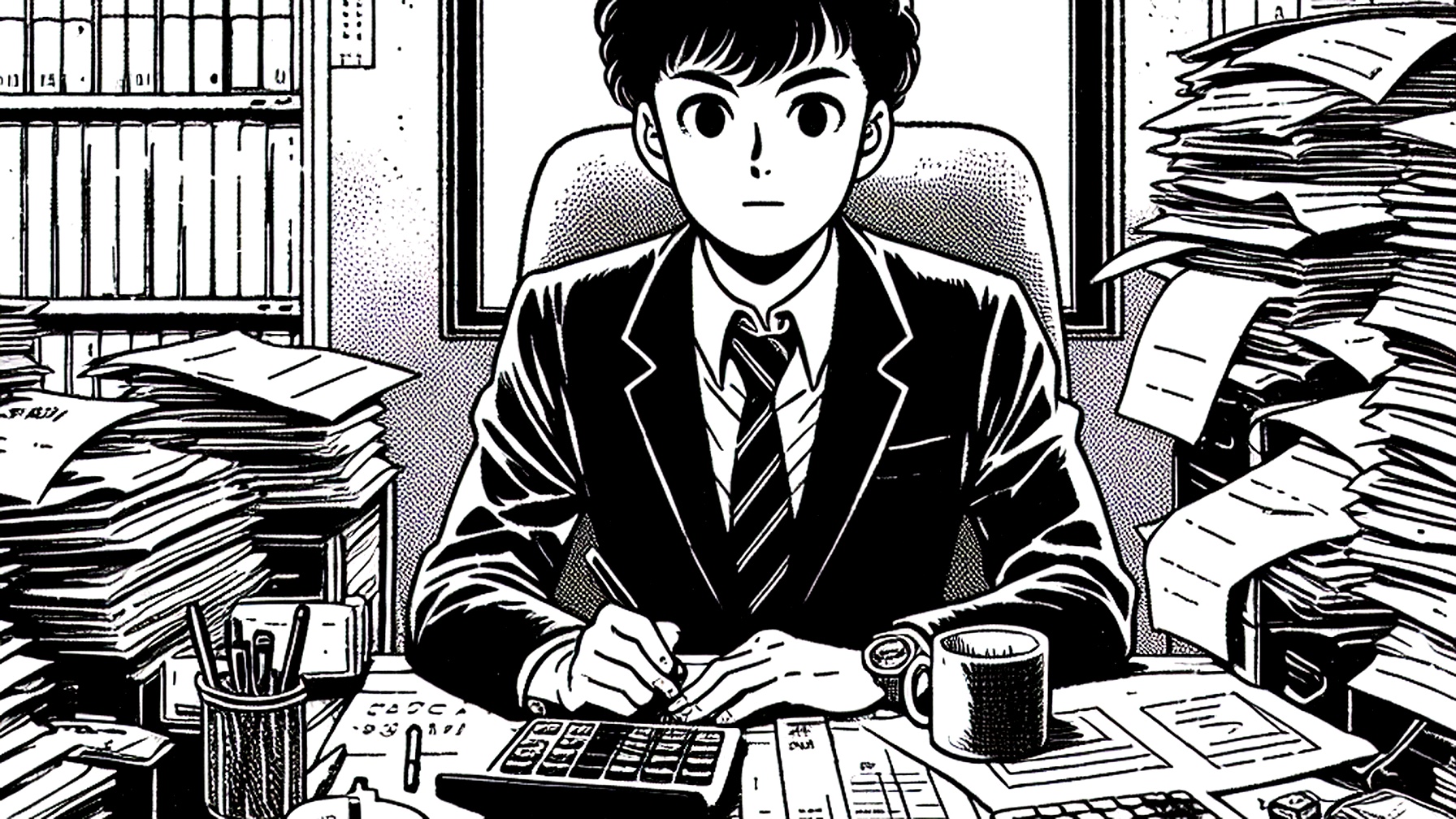
重要なのは、戸建て賃貸 利回りを「表面」と「実質」に分けて把握することです。特に実質利回りを正しく計算できれば、リスクを定量的に比較できます。
表面利回りは年間賃料総額を物件取得総額で割るシンプルな指標です。たとえば年間賃料144万円、物件価格2,800万円なら5.1%になります。一方、実質利回りはここから固定資産税、火災保険、修繕積立、管理委託料などを差し引きます。年間経費が賃料の25%(36万円)なら、手残りは108万円です。取得総額が同じ場合、実質利回りは3.9%まで低下します。
さらに融資を利用すると、ローン金利と元本返済がキャッシュフローに影響します。現在の住宅ローン金利は変動で1.1%前後、投資用ローンは1.8〜2.5%が目安です。元本返済はキャッシュアウトである一方、残債を減らす資産形成効果があります。シミュレーションでは、金利上昇2%、空室率10%、修繕一時負担100万円といった厳しめ条件でも耐えられるかを確認してください。ある意味、ここをクリアできる案件こそ、長期で利益を残せる物件といえます。
最後に減価償却の影響も見逃せません。木造戸建ての場合、法定耐用年数は22年ですが、中古購入なら残存耐用年数で計算できます。築15年の物件を購入した場合、残存耐用年数は7年、もしくは4年で任意選択できることがあります。短期で償却を進められれば所得税の節税余地が広がり、実質利回りの向上につながります。税理士と相談し、最適な方法を選びましょう。
立地と物件選定で変わる収益性
まず押さえておきたいのは、戸建て賃貸では「土地の資産性」と「周辺の生活利便性」を同時に満たす立地が鍵になる点です。とくに地方都市圏では小学校区の人気が賃料に直結します。
通勤30分圏内の駅から徒歩15分以内、かつスーパーと公園が1キロ圏内という条件をそろえると、家賃と入居期間が安定する傾向があります。国土交通省の「土地総合情報システム」によれば、駅徒歩が10分伸びると平均賃料は8%下がるため、多少価格が高くても利便性を優先する方がトータルでは得策です。
物件形状も重要です。建物延べ床90〜100㎡、3LDK以上の間取りは子育て世帯のニーズを満たし、狭すぎず広すぎないため修繕費が抑えられます。また、駐車場2台分を確保できれば地方でも強みを発揮します。逆に旗竿地や前面道路が狭い物件は、将来の売却価格が伸びにくく、担保評価も低くなるリスクがあります。
空室リスクを減らすには、エリアの人口動態をチェックすることが欠かせません。総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」で転入超過が続く自治体は、将来にわたり需要が見込めます。実は、転入超過率がプラス1%以上の市区町村では、戸建て賃貸の平均入居期間が10年を超えるとの調査結果もあります。数字で裏づけることで、感覚に頼らない判断が可能になります。
資金計画と融資のポイント
ポイントは、自己資金比率と長期固定費をバランスさせ、安定したキャッシュフローを確保することです。「融資枠いっぱいに借りて高利回りを狙う」戦略は、金利上昇局面で大きなリスクになります。
自己資金として物件価格の20〜30%を用意すると、金融機関の審査が通りやすく、金利優遇を受けられるケースが増えます。たとえば2,800万円の物件に30%入れると自己資金は840万円です。頭金を積むことで月々の返済額が約3万円下がり、年間36万円のキャッシュフロー改善が期待できます。これが実質利回りを0.8ポイント引き上げる効果を生むこともあります。
融資期間は「建物残存耐用年数+10年」を目安に交渉すると、返済額を抑えつつ金利負担を低減できます。2025年時点で日本政策金融公庫の不動産投資向け融資は最長25年、金利2.2%前後が一般的です。固定か変動かで迷う場合は、金利上昇1.5%まで許容できる返済比率をシミュレーションし、リスク許容度に合わせるとよいでしょう。
また、2025年度も継続している「住宅省エネ2025キャンペーン」の補助金は、新築戸建ての断熱性能向上に最大50万円が支給されます。省エネ性能が高いと入居者の光熱費が下がり、賃料維持につながるため、補助金を活用して建物性能を底上げする戦略は合理的です。期限は2026年3月末の予算消化までと発表されているので、スケジュール管理を徹底してください。
まとめ
ここまで、戸建て賃貸 利回りを高めるための基礎知識と実践手順を解説してきました。利回りは表面ではなく実質で判断し、厳しめのシミュレーションに耐える物件を選ぶことが肝心です。立地選定では生活利便性と人口動態を数字で確認し、資金計画では自己資金比率と融資条件を丁寧に比較しましょう。行動を起こす際は、まず候補エリアの家賃相場と転入超過率を調べ、1件でも多くの戸建てを現地で見学することをおすすめします。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 国土交通省 土地総合情報システム – https://www.land.mlit.go.jp
- 総務省統計局 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.stat.go.jp
- 日本政策金融公庫 資金調達ガイド – https://www.jfc.go.jp
- 環境省 住宅省エネ2025キャンペーン – https://www.env.go.jp

