不動産投資を始めたいけれど、鉄筋コンクリートのマンションは高すぎる。そんな悩みを抱える方にとって、木造アパートは魅力的な選択肢です。建築費が比較的安く、融資も組みやすい一方で、耐久性や空室率が気になるという声も多く聞きます。本記事では、木造アパートのメリットを数字と事例で検証し、2025年度に利用できる支援制度まで含めてわかりやすく解説します。読み終えたときには、木造アパート投資の実践的な判断基準が手に入り、次の行動へ踏み出す自信が得られるはずです。
木造アパートが再評価される背景
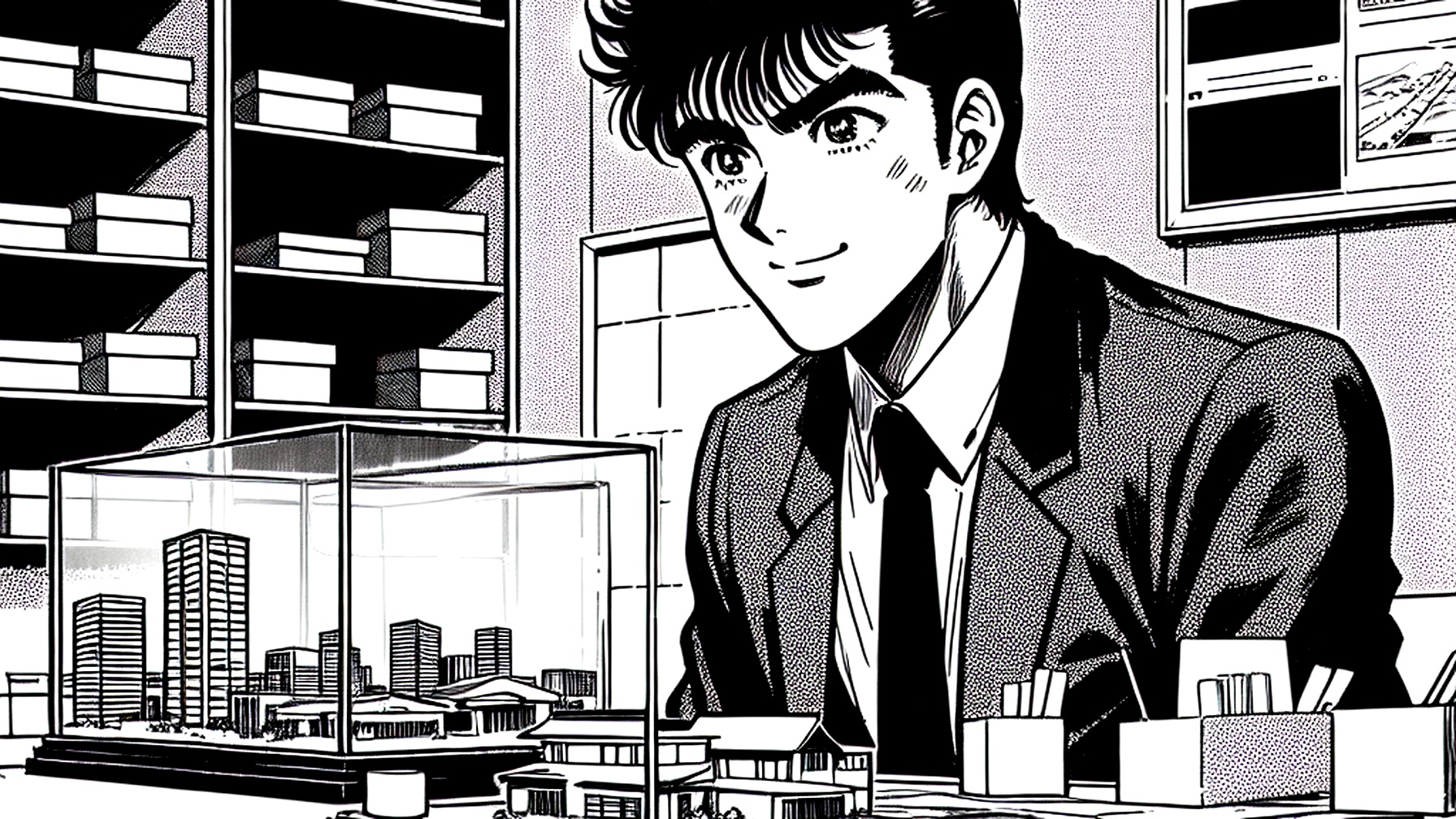
まず押さえておきたいのは、木造アパートが近年再び注目を集めている理由です。国土交通省住宅統計によると、2025年8月時点の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント改善しました。この改善幅は、地方小規模物件よりも都市近郊の木造アパートで大きいことが分析からわかります。つまり、需要が底堅いエリアでは木造でも十分に勝負できる環境が整ってきたのです。
背景には工法の進化があります。現代の木造アパートは耐火性能が一昔前とは比べものにならず、準耐火構造の採用で都市計画区域内でも建てやすくなりました。また、木材価格高騰の反動で2024年以降は価格が落ち着き、建築コストが読めるようになった点も投資家を後押ししています。さらに、SDGsの流れから国や自治体は木造建築を推奨しており、環境配慮型の新築計画が補助対象になりやすい状況です。
加えて、物件規模が比較的小さいため、初心者でも自己資金一千万円未満で参入しやすいことが魅力になります。規模が小さいということは、リフォーム費用も抑えられ、出口戦略を柔軟に描ける点につながります。一方で、法定耐用年数が短いという課題もありますが、減価償却を早く取れるという側面もあり、キャッシュフローにはプラスです。
コスト面で得られる具体的メリット
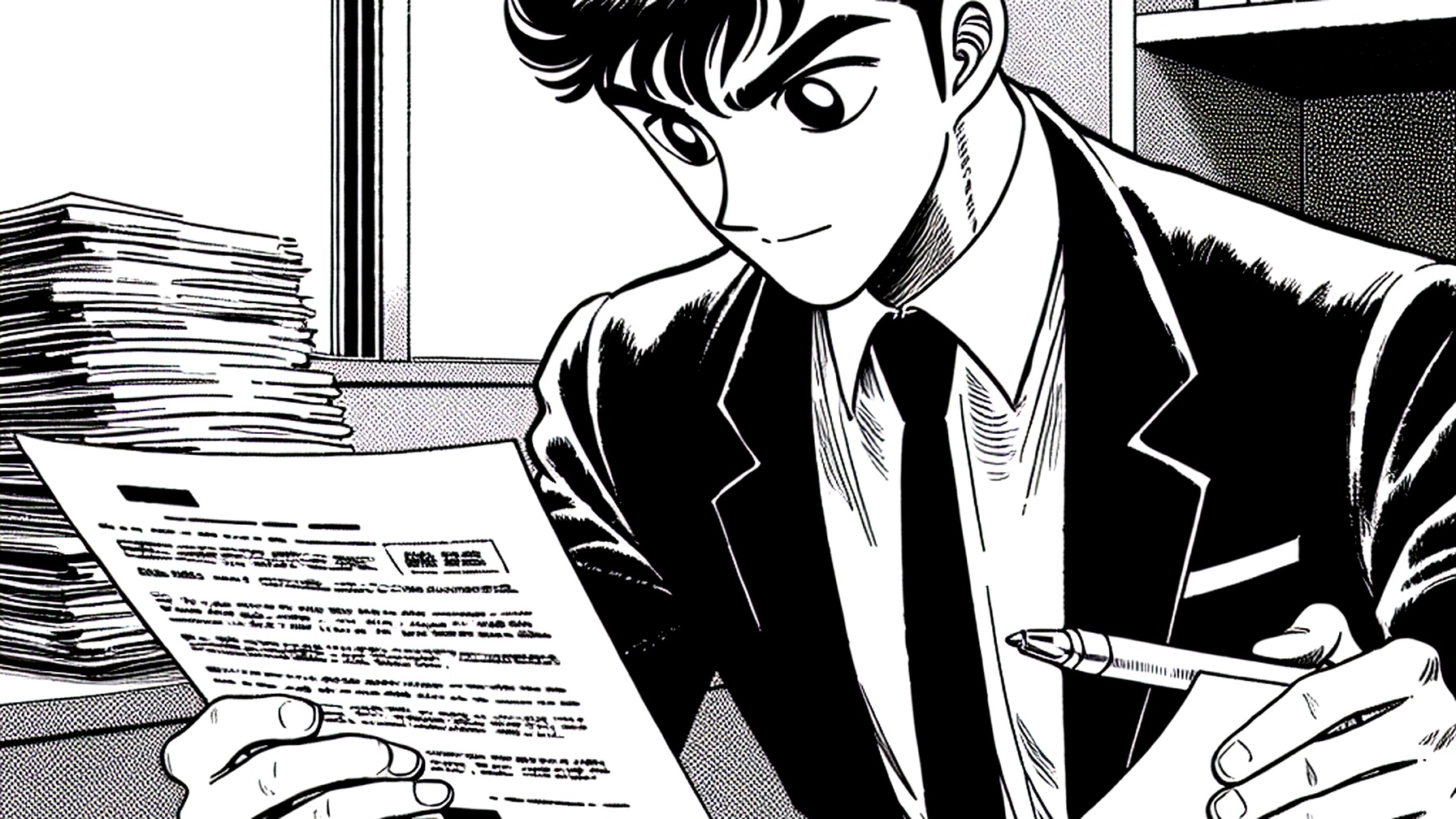
ポイントは、初期費用とランニングコストの両方で優位性があることです。木造アパートは鉄筋系に比べ、建築単価がおおむね30%低く抑えられます。例えば延床200㎡、6戸タイプの新築で比べると、鉄骨造の建築費がおよそ9,000万円のところ、木造なら6,000万円台で収まる事例が多く報告されています。これにより、自己資金を少なくしつつ、融資審査も通りやすい傾向が見られます。
運営コストも忘れてはいけません。木造は外壁や屋根の修繕周期が短いといわれますが、実際には10〜12年ごとの再塗装で済むケースが一般的で、コストは総延床1㎡あたり約2,000円と鉄筋系より低水準です。また、共用部の電気保安や給水ポンプ管理など鉄筋マンションでかかる専門メンテナンスが不要な分、年間の固定費を5〜10%程度抑えられる点が収益性に直結します。
さらに、木造アパートは固定資産税評価額が低めに設定される傾向があります。固定資産税は評価額×税率で計算されるため、表面利回りが同じでも手残りが増えるしくみです。東京都内23区のモデルケースでは、築浅木造の固定資産税が鉄骨造の75%程度で済んだという実測データもあります。金利がやや高くても、トータルコストで見れば木造が有利に働く状況が多いのです。
入居者ニーズと木造の快適性
実は、木造は入居者からも一定以上の支持を得ています。国交省の「賃貸住宅市場アンケート」2025年度版によると、木造物件を選んだ理由の上位には「室内が暖かい」「家賃が手頃」「自然素材の安心感」が挙げられました。特に断熱性能が高い新築木造は、冬場の光熱費が抑えられる点で若年層に好評です。
騒音リスクを懸念する声も確かにあります。しかし、床衝撃音を吸収する二重床や遮音シートの採用が進み、建築基準法の性能表示だけでなく独自に遮音等級を示すデベロッパーも増えました。これにより、木造でも上下階の生活音トラブルは大幅に減っています。物件選定時に遮音材の仕様や壁厚を確認すれば、クレーム対策は十分に可能です。
また、コロナ禍を経てリモートワークが定着し、室内の温もりや調湿性を評価する入居者が増えました。木造は木材が湿度を吸排出する性質を持ち、結露やカビの発生を抑えやすい点が健康志向の層に響いています。このように、単に家賃が安いから選ばれるのではなく、快適性そのものが木造アパートの差別化要因になりつつあるのです。
税制・融資で生かせる2025年度の制度
重要なのは、制度面での後押しを理解し、賢く利用することです。2025年度も国交省の「サステナブル賃貸支援事業」は継続され、一定の省エネ基準を満たす木造賃貸に対して1戸あたり最大50万円の補助が受けられます(申請期限: 2026年3月末)。補助率は工事費の1/3以内ですが、断熱材や高効率給湯器の導入で要件を満たす設計はそこまで難しくありません。
加えて、地方自治体の単独補助を併用できるケースがあります。東京都は2025年度も「木密地域防災化助成」を続行し、準耐火木造に限り上限100万円を上乗せしています。これらを組み合わせると、表面利回りが1%近く改善する試算もあり、融資審査で有利に働く実例が増えています。
融資面では、民間金融機関に加え「住宅金融支援機構フラット35賃貸プロ」が引き続き利用可能です。省エネ性能を確保した木造賃貸の場合、金利0.25%の優遇を10年間受けられる特例が2025年も延長されました。金利差が0.25%でも、7,000万円の借り入れなら10年間で約100万円の利息削減となるため、キャッシュフロー向上に直結します。
なお、補助金や優遇金利は年度ごとに予算枠があります。申請手続きは工事着工前が原則なので、土地仕入れと建築プランの確定スケジュールを先に固め、余裕を持って金融機関や行政窓口に相談してください。
リスクを抑える運営ポイント
木造アパートのメリットを享受するには、リスクコントロールが欠かせません。築年数が進むと、構造部の劣化や家賃下落リスクが顕在化します。そこで、5年ごとに大規模修繕計画を見直し、長期修繕費を毎月の家賃収入から積み立てる仕組みを導入しましょう。これにより、突発的な支出を平準化できます。
次に、エリア分析を怠らないことが需要維持のカギとなります。総務省人口推計2025年版では、20〜39歳人口が増加するのは全国でわずか15市区に限られると示されています。木造アパートを当該エリアの駅徒歩10分以内に絞るだけで、10年後の空室リスクを大幅に抑制できます。
家賃設定では、相場より1割高い賃料を狙うより、長期入居を促すインセンティブを組み込む方法が効果的です。具体的には、2年更新時に家賃据え置きを確約する代わりに、退去時のクリーニング費用を入居者負担にする方式が広がっています。これなら運営コストを抑えながら、入居者に安心感を提供できます。
最後に、火災保険と地震保険の適切な組み合わせが欠かせません。木造は保険料が高いというイメージがありますが、耐火等級を取得すれば鉄骨造と同水準まで下げられます。保険会社による料率差が大きいため、最低でも3社は見積もりを取り、条件を比較しましょう。
まとめ
本記事では、木造アパートのメリットをコスト、入居者ニーズ、制度活用、リスク管理の四つの視点で整理しました。建築費と固定費の低さ、省エネ補助や金利優遇、そして快適性を求める入居者の支持が合わさり、木造アパート投資は2025年以降も有力な選択肢になります。大切なのは、エリア選定と長期修繕計画を前提に、補助金や融資制度をフル活用する姿勢です。まずは試算表に補助金と金利優遇を反映させ、手残りキャッシュフローを具体的に確認してみてください。行動を起こすことで、木造アパート メリットを最大化する道が開けるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年8月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 サステナブル賃貸支援事業 2025年度概要 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 東京都 防災都市づくり部 木密地域防災化助成 2025年度版 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp
- 住宅金融支援機構 フラット35賃貸プロ 商品概要 2025.4改訂 – https://www.jhf.go.jp
- 総務省 人口推計 2025年版 – https://www.stat.go.jp/data/jinsui

