不動産価格が高止まりする今、「まずは手頃な築古アパートで始めたい」と考える人が増えています。しかし築年数が古い物件には空室や修繕費の不安も付きまとい、最初の一歩を踏み出せずにいる方も多いでしょう。本記事では、初心者でも理解しやすい形で築古アパート投資の特徴、物件選びのコツ、購入手順、運営のポイント、そして2025年度に活用できる制度までを網羅します。読み終えるころには、具体的な行動計画を描けるようになるはずです。
築古アパート投資の魅力とリスク
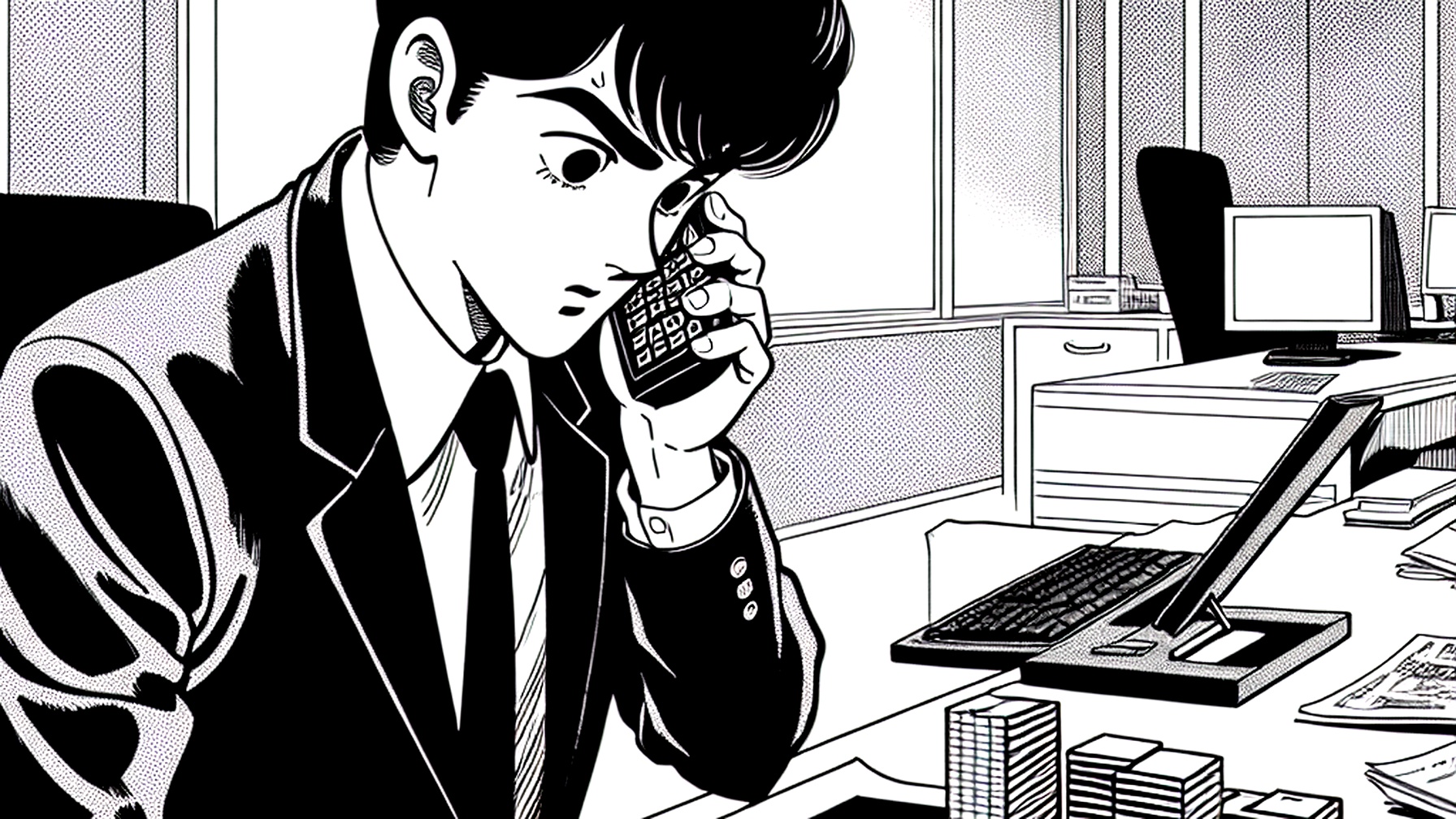
重要なのは、低価格ゆえの高利回りと、将来の修繕コストを天秤にかけて判断することです。新築比で三分の一程度の価格で購入できるケースも珍しくありませんが、築年が古いほど設備の更新費用は増えます。
まず魅力を整理すると、購入価格を抑えられる点が大きいです。たとえば同じ家賃収入を得られる物件でも、新築の表面利回りが5%程度にとどまる一方、築25年超のアパートなら10%前後を狙える例があります。固定資産税評価額も下がっているため、年間税負担が軽くなる効果も見逃せません。
一方で、リスクとして最初に挙がるのが空室率です。国土交通省住宅統計によると、2025年8月の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント改善したものの、依然として高水準です。築古ほど競合物件が多くなるため、リノベーションや家賃設定で差別化できなければ入居付けに苦戦します。また築30年を超えると屋根や配管の大規模改修が必要になることも多く、数百万円単位の支出を伴います。
つまり、高利回りの裏に隠れたコストと手間を正しく見積もり、リスクに備えた資金計画を立てることが成功の前提になります。
物件選びでまず押さえておきたいポイント
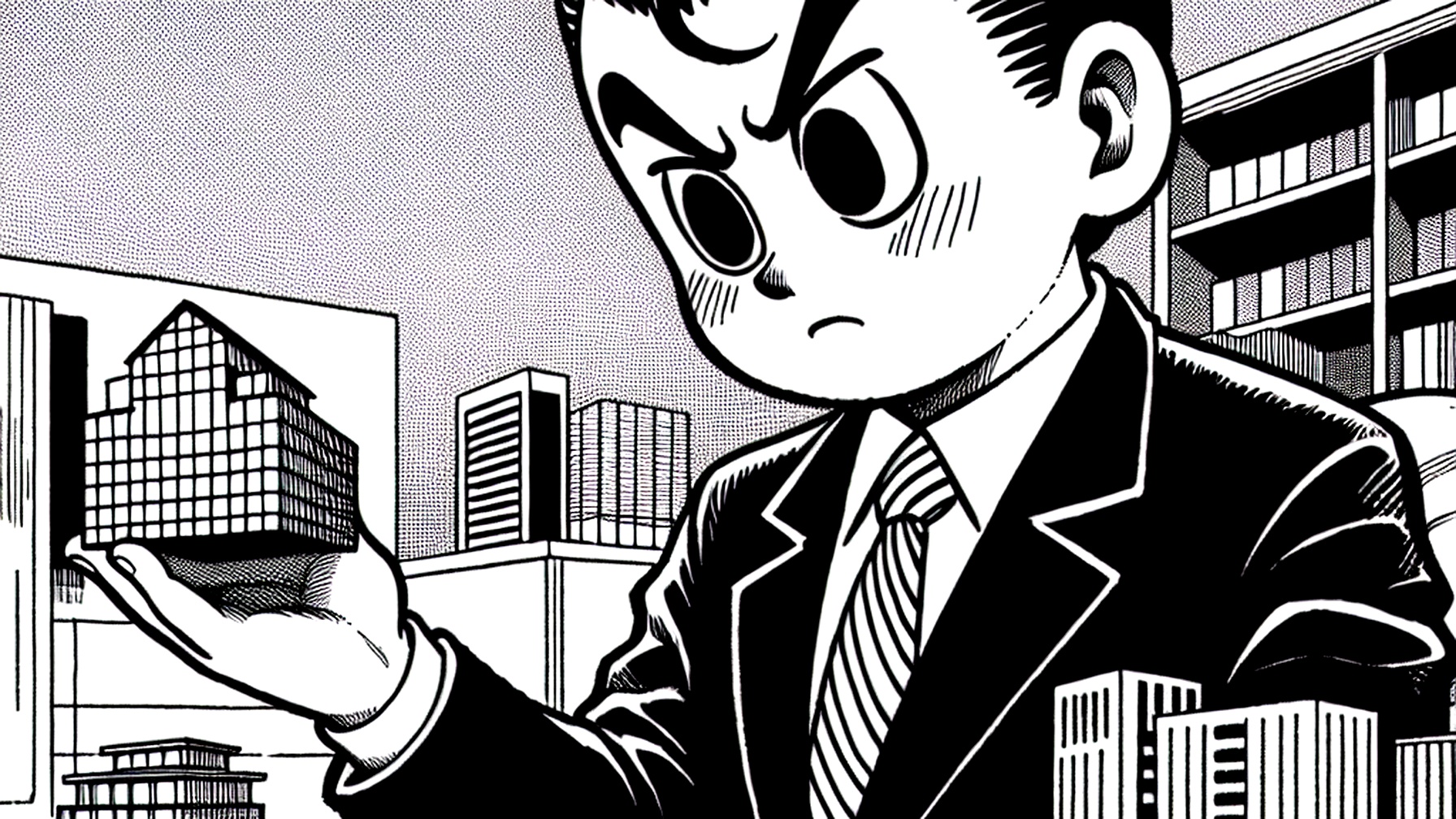
ポイントは、築年数よりも建物の構造と立地で選別する姿勢です。表面利回りだけを基準にすると、「安かろう悪かろう」の物件にあたる危険があります。
最初に確認したいのが構造です。木造アパートは価格が安い一方、法定耐用年数22年を過ぎると銀行融資が出にくくなります。鉄骨造(軽量鉄骨)は耐用年数34年のため、築25年程度でも15年以上の融資期間を確保でき、キャッシュフローに余裕が生まれます。RC造(鉄筋コンクリート)はさらに強固ですが、修繕費が高額になる傾向があるので総費用で比較しましょう。
次に立地ですが、駅徒歩圏や主要道路沿いが理想といわれるものの、実は「就職先が集中するエリア」と「家賃を払える単身者の人口動態」が合致するかが鍵です。総務省人口推計の転入超過ベスト10市区は毎年ほぼ固定化しており、そうした地域では築30年超でも稼働率90%以上を保つデータがあります。反対に郊外で人口減少が進む地域では、新築でも空室リスクが高まります。
また、現地調査では昼と夜の雰囲気を両方見ることが欠かせません。日中に閑散としていても、夜間は大学生や若手社会人で賑わうエリアもあります。ドラッグストアやスーパーの新規出店状況も人口維持の指標になるため、周辺商業施設の動きを追いましょう。
購入までのステップと資金計画
実は、築古アパートは購入手順そのものより資金計画の精度で成否が分かれます。以下の流れをイメージすると迷いが減ります。
- 物件情報収集
- 融資可能額の事前審査
- 現地調査・収支シミュレーション
- 売買契約・決済
まず、ポータルサイトで目星をつけたら、金融機関に簡易審査を申し込み資金枠を確認します。自己資金は物件価格の20%を目安にすると返済比率が下がり、金利も有利になりやすいです。加えて、修繕積立として家賃の10%を毎月プールする計画を立てると、予期せぬ故障にも対応できます。
返済期間と金利タイプの選択も重要です。たとえば金利2.0%・期間20年と1.5%・期間15年では、月々の返済額はほぼ同じでも総支払額が約300万円変わるケースがあります。資産の回収期間を短くするか、手元キャッシュを厚くするか、目的に合わせてシミュレーションを重ねましょう。
さらに仲介手数料、登録免許税、不動産取得税などの諸費用は総額の7〜9%前後が目安です。購入直後に現金が枯渇すると運営が立ち行かないため、決済時点で家賃の6か月分程度を運転資金として残すと安心です。
運営で差がつくリノベーションと管理戦略
まず押さえておきたいのは、「最初に部屋を見に来た入居希望者を逃さない内装づくり」です。築古物件でも、白を基調にした壁紙と明るい照明で清潔感を出すだけで内見成約率が2倍になるという管理会社の統計があります。
リノベーションでは水回りが最優先です。ユニットバスとトイレの交換は一室70万〜100万円が相場ですが、家賃を5,000円上げられれば投資回収期間は約14年です。対面キッチンやロフト追加は人気があるものの、エリアの家賃帯を超えると空室が長期化するため注意が必要です。
管理形態は自主管理と委託管理に大別されます。自主管理は費用を抑えられますが、トラブル対応で休日がつぶれることも珍しくありません。委託管理は家賃の3〜5%が相場ですが、入居付けや家賃回収をプロに任せられる安心感があります。物件が遠方の場合や本業が忙しい人は、フル委託で時間を買う選択も合理的です。
最後に、定期的な点検とデータ管理が欠かせません。エネルギー消費量や修繕履歴をクラウドで可視化すると、大規模修繕のタイミングを予測しやすくなります。これにより余裕を持った資金繰りが可能となり、突発的な支出で慌てるリスクを抑えられます。
2025年度の制度活用と出口戦略
基本的に、築古アパート投資では税制優遇を最大限に利用することが利益の源泉になります。所得税の青色申告特別控除65万円は2025年度も継続しており、帳簿をきちんと作成するだけで手取りを増やせます。減価償却費は建物価格を耐用年数で割って計上しますが、築年数が耐用年数を超えている場合は「残存耐用年数」を短縮でき、初年度から大きな節税が可能です。
さらに、2025年度住宅省エネ改修補助金は、中小大家でも利用しやすい上限200万円(工事費の3分の1以内)のメニューがあり、断熱窓や高効率給湯器の導入で活用できます。申請は工事請負業者が代行できるため、手間はほとんどかかりません。省エネ性能を高めると入居者募集でアピールできるうえ、ランニングコスト削減にもつながります。
出口戦略としては、売却益狙いと長期保有の二択だけではありません。築古アパートを取り壊して更地にし、戸建て分譲用地として売却する「土地転用」も選択肢になります。2025年の首都圏地価は前年比1.8%上昇(国土交通省地価調査)しており、駅近の土地需要は堅調です。土地値に近い価格で購入できる物件なら、将来の建て替えや売却で元本を回収しやすくなります。
結論として、制度活用によるキャッシュフロー向上と、複数の出口を想定した長期戦略を同時に描くことが、築古アパート投資を安定ビジネスに変える鍵といえます。
まとめ
築古アパート投資は、手頃な価格で高利回りを狙える一方、空室と修繕費のリスク管理が欠かせません。構造と立地を見極め、詳細な資金計画を立てたうえでリノベーションと管理を最適化すれば、安定収益を実現できます。さらに2025年度の税制優遇や省エネ補助金を活用し、出口戦略を複線的に準備することで、将来の選択肢が広がります。今日から物件情報の収集と融資枠の確認を始め、具体的な行動に移してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅局「住宅・土地統計調査」 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省「2025年度 住宅省エネ改修補助金概要」 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 国土交通省「地価調査(2025年)」 – https://www.mlit.go.jp/tdm
- 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行「金融システムレポート2025年4月」 – https://www.boj.or.jp

