不動産投資に興味はあるものの、数千万円の物件を買う勇気は出ない――そんな悩みを抱える人は少なくありません。REIT(リート)なら、証券会社の口座さえあれば数万円から不動産オーナーの一員になれます。中でも300万円を目安にする人が多いのは、少額とはいえ分散が効き、家計への負担も抑えやすいからです。しかし、株や投資信託と同じように価格は日々動き、想定外の損失を被る可能性もあります。本記事では300万円を投じる際にありがちな誤解や「REIT 300万円 デメリット」と検索される理由を整理し、2025年10月時点の最新制度を踏まえたリスク対策まで丁寧に解説します。読み終えたとき、あなたは自分に合った投資判断ができるはずです。
REITとは何か:小口で不動産に投資する仕組み
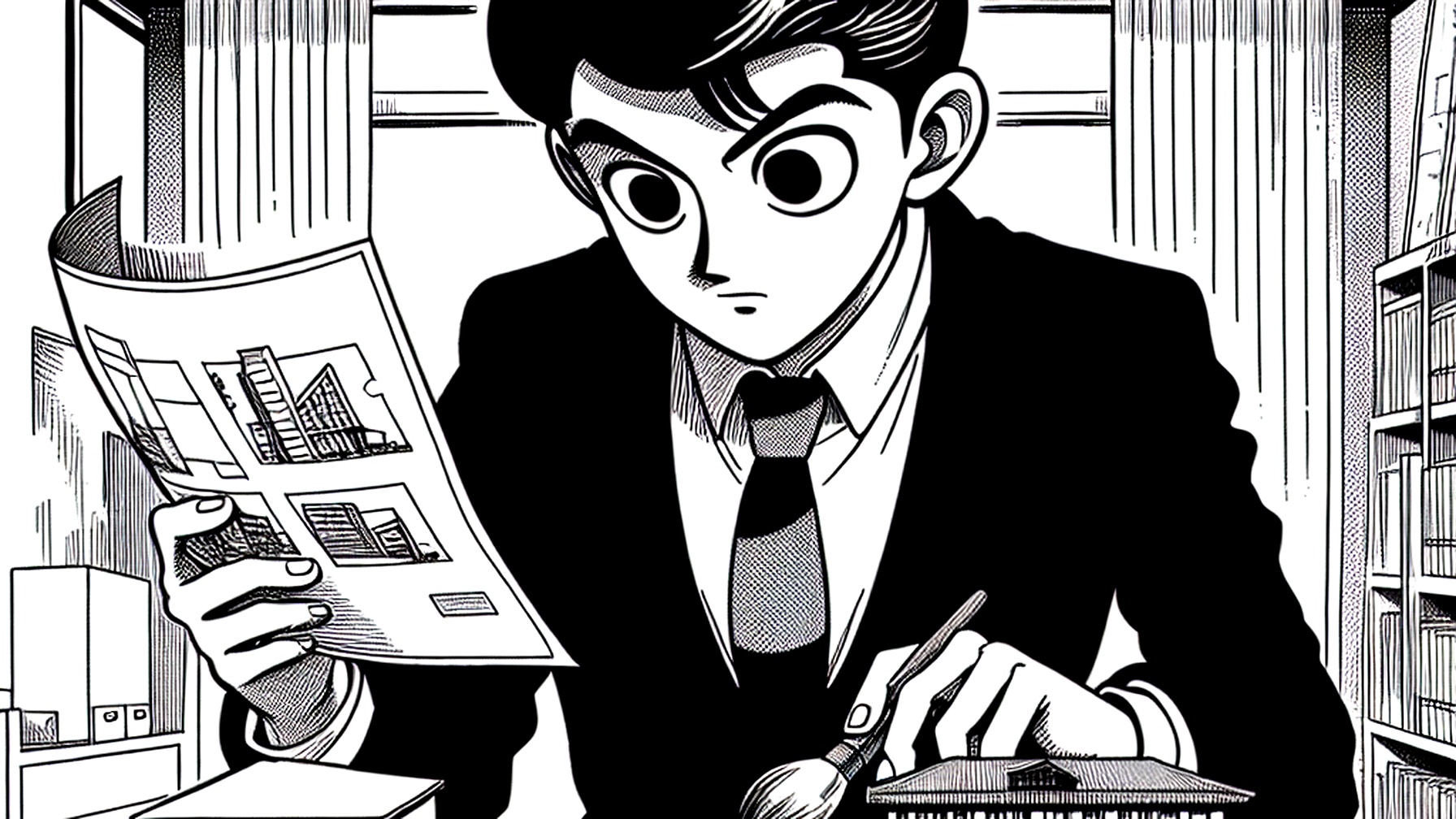
まず押さえておきたいのは、REITが不動産を複数まとめて証券化した商品だという点です。投資家は証券取引所でその受益証券を売買し、家賃収入や物件売却益が分配金として受け取れます。東京証券取引所のデータでは、2025年9月末時点で上場J-REITは69銘柄、時価総額は約20.5兆円に達しています。つまり、一口数万円で大規模オフィスや物流施設に間接的に投資できるわけです。
さらに、収益の90%以上を分配することで法人税が軽減される「投資法人」形態を取るため、配当利回りは2.5〜4.5%と国内株式平均を上回ることが多いです。一方で借入比率(LTV)が物件価格の50%前後に達する銘柄もあり、金利上昇の影響を受けやすい点は覚えておきましょう。
300万円で買える銘柄選びと期待利回り
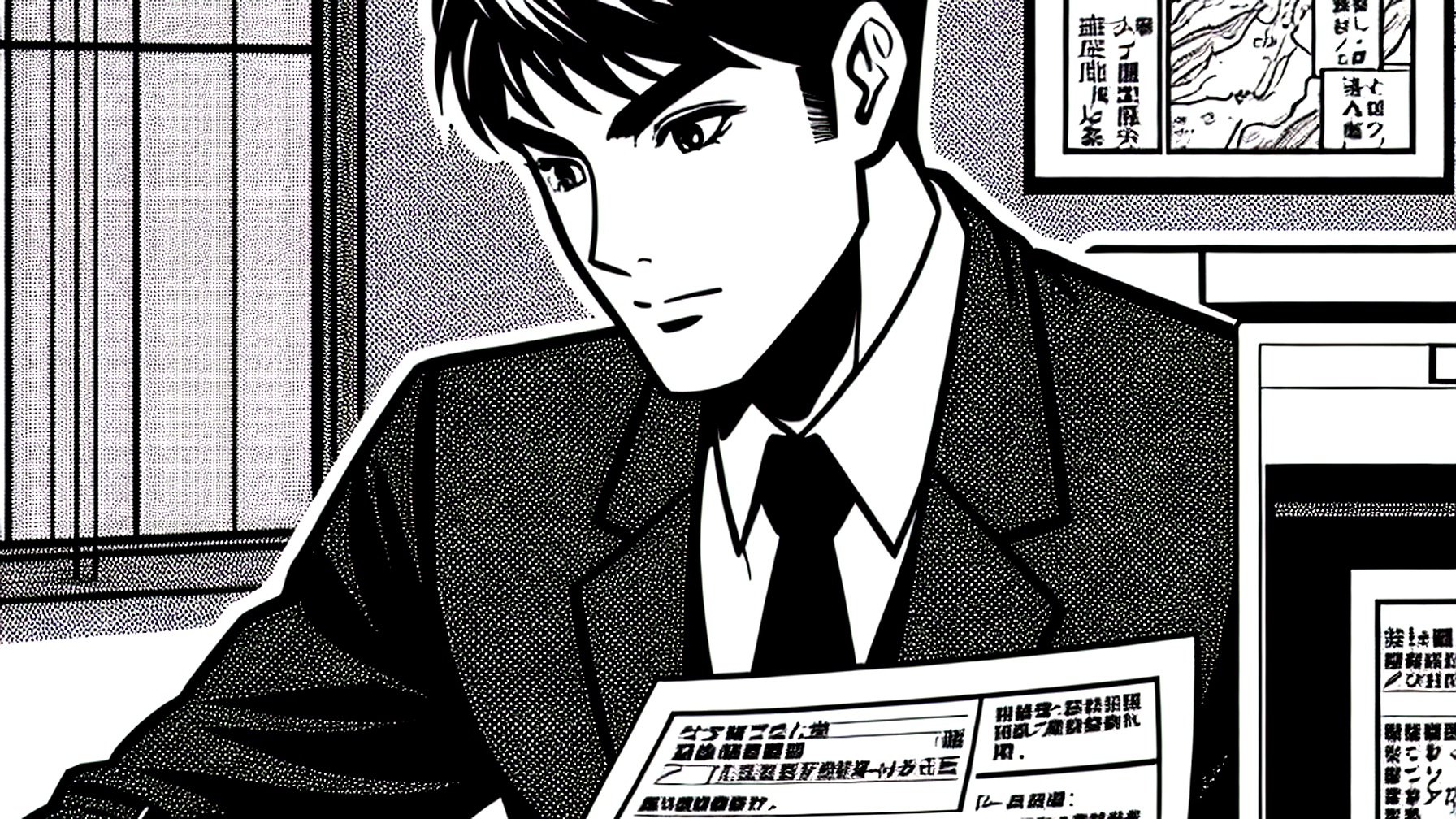
ポイントは、300万円でどの程度の分散が確保できるかです。仮に一口15万円の銘柄なら20口、平均利回り4%なら年間分配金は12万円前後となります。配当課税は20.315%なので手取りは約9万6千円です。銀行普通預金の金利が0.05%に満たない現状を考えると魅力的に映ります。
しかし、銘柄の投資対象がオフィス中心か、住宅中心か、あるいは物流特化かで景気変動への感度が大きく異なります。例えば、オフィス系は2023~2024年のテレワーク定着で空室率が一時的に上昇し、分配金を減配した銘柄もありました。300万円を1銘柄に集中させると、こうした事業リスクをもろに受けます。そこで3~5銘柄に振り分け、用途と立地をバラけさせる方法が現実的です。
加えて、インフラファンドを組み合わせると利回りは上がるものの、太陽光パネルの廃棄費用や売電価格の下落リスクも抱えるため、初心者はJ-REITに絞った方が管理しやすいでしょう。つまり、300万円という予算は「分散」と「理解しやすさ」を両立できるギリギリのラインだといえます。
見落としがちなデメリットとリスク管理
重要なのは、配当だけに目を奪われて価格変動を甘く見ることです。REIT市場は時価総額が株式市場より小さいため、海外金利や為替のニュースだけでも大きく揺れます。2023年10月の米金利急騰時には、東証REIT指数が月間で8%下落しました。300万円を一括で買っていた場合、評価額は24万円近く減った計算になります。
次に、借入金利の上昇リスクです。REITの多くは短期借入やリファイナンスで低金利を利用していますが、日本銀行が2024年にマイナス金利政策を解除したあたりから調達コストはじわじわ上がっています。分配金の一部が利払いに消えるため、表面利回りは維持していても手取りが減る可能性があります。
また、「REIT 300万円 デメリット」と検索される最大の理由が流動性への誤解です。確かに株式と同様に売買は即日可能ですが、成行注文が集中すると値が飛ぶことがあります。特に優良銘柄ほど長期保有の投資家が多く、出来高が限定的になりやすい点は注意が必要です。
最後に、自然災害リスクです。国交省の資料では、2020年代に入ってREIT物件の保険料が平均15%上昇しています。台風や地震で物件が損傷すると、修繕費が利益を圧迫し、減配につながるケースもあるのです。これらのリスクを踏まえ、定期的にポートフォリオを見直す仕組みを作りましょう。
税制と2025年度の制度変更点
実は、税制面でも見逃せないポイントがあります。2025年度税制改正大綱では、NISA(少額投資非課税制度)の非課税限度額が年間360万円、総枠1,800万円で据え置かれました。REITも上場株扱いで投資枠に組み込めるため、300万円のうち一部をNISA枠に入れると分配金と譲渡益が非課税になります。ただし、非課税保有期間は無期限化されたものの、年内の買付枠を翌年に繰り越せない点は変わりません。
一方で、所得税の「申告分離課税」20.315%は2025年度も継続され、損益通算や繰越控除の仕組みもそのままです。つまり、課税口座のREITで損失が出ても、株式や投資信託の利益と相殺できます。これを活用すれば、価格変動リスクを一定程度ヘッジできるわけです。
また、REITの分配金は配当控除の対象外なので、総合課税に切り替えて節税する余地はほぼありません。給与所得が高くて税率が高い人ほど、NISAをフル活用する効果が大きくなります。
ポートフォリオにどう組み込むか
まず、自身の資産配分全体を考えたうえでREITの比率を決めましょう。金融庁の家計資産調査によると、日本人の平均的な金融資産構成は預貯金52%、株式13%、投資信託5%、その他30%前後です。仮に総資産1,000万円なら、300万円のREIT投資は全体の30%を占め、株式と合わせるとリスク資産比率が40%を超えます。リスク許容度を超えないか慎重に確認してください。
さらに、購入タイミングを分散させるドル・コスト平均法を取り入れると、価格変動の影響を和らげられます。例えば毎月10万円ずつ30カ月かけて買い付ける方法なら、急な下落局面でも一度に大きな含み損を抱えにくいです。
加えて、分配金再投資を行うと複利効果が期待できます。東証REIT指数のトータルリターンは、2003年の指数化以来、年平均で約4.6%(2025年9月末時点)ですが、分配金を受取り消費している場合は年3.1%程度に落ち込みます。つまり、再投資するかどうかで長期パフォーマンスに1%以上の差が生まれるわけです。
最後に、REIT特有の情報収集源として各投資法人の決算説明資料や運用報告書を必ず確認しましょう。物件の稼働率やLTV、平均残存賃貸期間など、株式より細かい指標が安定性を測るカギとなります。
まとめ
本記事では、300万円という現実的な予算でREITを始める際のメリットだけでなく、価格変動、金利上昇、流動性、災害といったデメリットを整理しました。結論として、リスクを正しく把握し、銘柄と買付時期を分散し、NISAや損益通算を活用することで、REITは堅実なインカム源になり得ます。まずは家計全体のバランスを確認し、毎月のキャッシュフローに無理のない範囲から少額で試すことが第一歩です。今日の学びを行動に移し、長期的な資産形成の選択肢としてREITを上手に取り入れてみてください。
参考文献・出典
- 東京証券取引所 – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 不動産投資市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 資金循環統計 – https://www.boj.or.jp
- 財務省 租税特別措置法等適用状況 – https://www.mof.go.jp
- 総務省 家計調査 – https://www.stat.go.jp

