円安が長期化し、資産運用の選択肢として不動産投資に注目が集まっています。しかし「不動産投資 デメリット 円安時代」という言葉が示すように、為替が大きく動く局面では思わぬ落とし穴も生まれます。物件価格の上昇、資材費の高騰、融資条件の変化など、初心者には見えにくいリスクが複数重なります。本記事では円安がなぜデメリットを増幅させるのかを整理し、2025年10月時点で活用できる制度を踏まえながら、実践的な対策まで解説します。読み終えたとき、自分に合ったリスク管理のヒントが手に入るはずです。
円安が不動産投資に与える基本的な影響
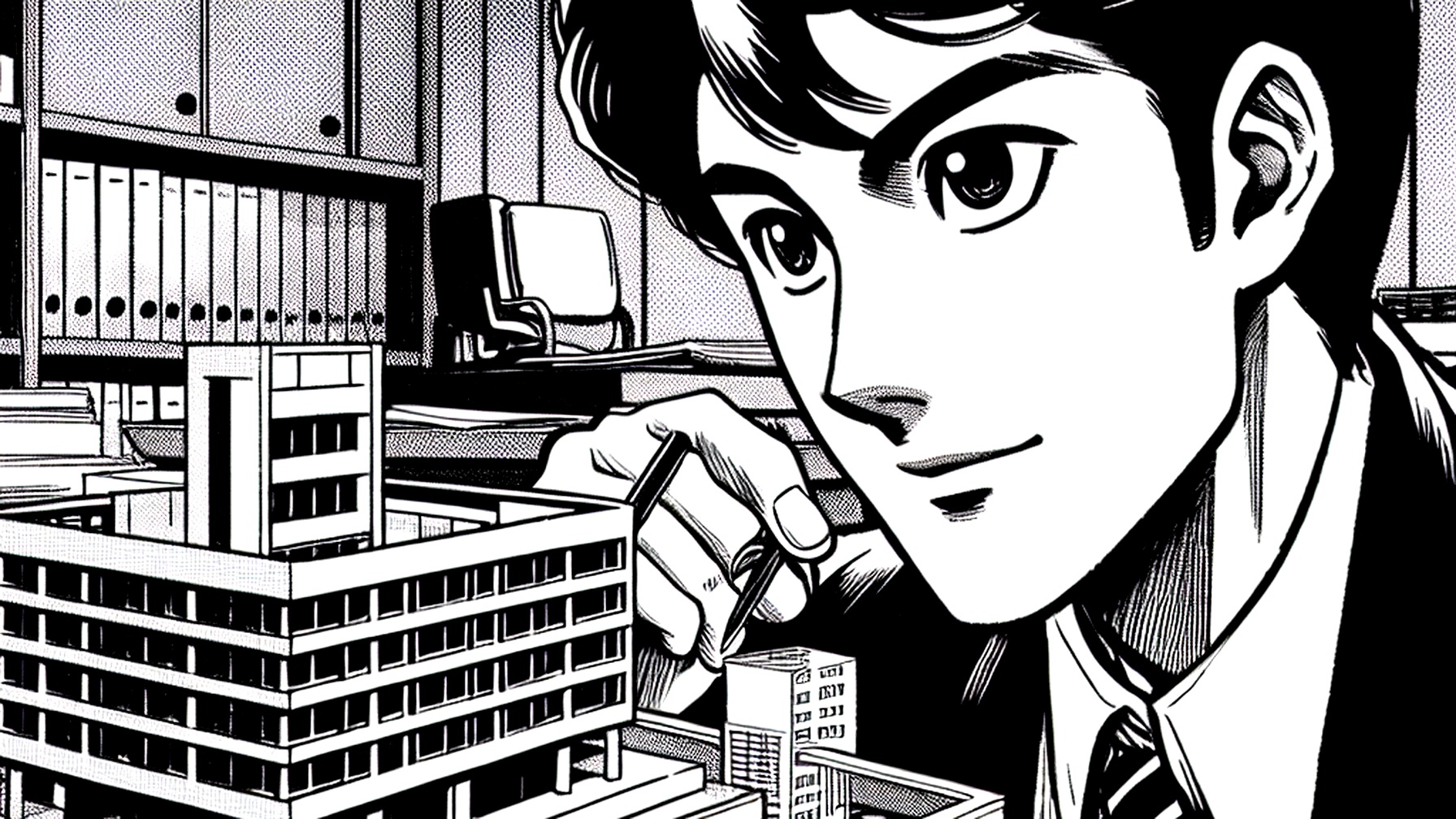
重要なのは、円安が国内と海外の資金の流れを同時に動かす点です。日本銀行が2025年7月に公表した資金循環統計によると、海外投資家の不動産取得額は前年同期比で12%増えています。為替差益を期待した資金が流入すると、都市部の物件価格が押し上げられ、利回りは低下しやすくなります。つまり、同じ家賃収入でも物件価格が高ければ投資効率は下がるのです。
一方で、建築資材の多くは輸入に依存しています。国土交通省の建設総合統計では、2025年上期の資材コスト指数が前年より8%高く、リフォームや大規模修繕にかかる費用が上昇傾向にあります。取得後のランニングコストが膨らむと、キャッシュフローが計画より悪化する可能性が高まります。
さらに、金融機関の融資姿勢も微妙に変化します。国内金利が低位でも、海外の金利上昇を背景に調達コストが上がり、変動金利型ローンの上乗せ幅が広がるケースが見られます。借入期間の長い不動産投資では、0.3%の金利差が30年間で数百万円の追加負担につながるため、為替と金利をセットで見る視点が欠かせません。
想定外コストというデメリット
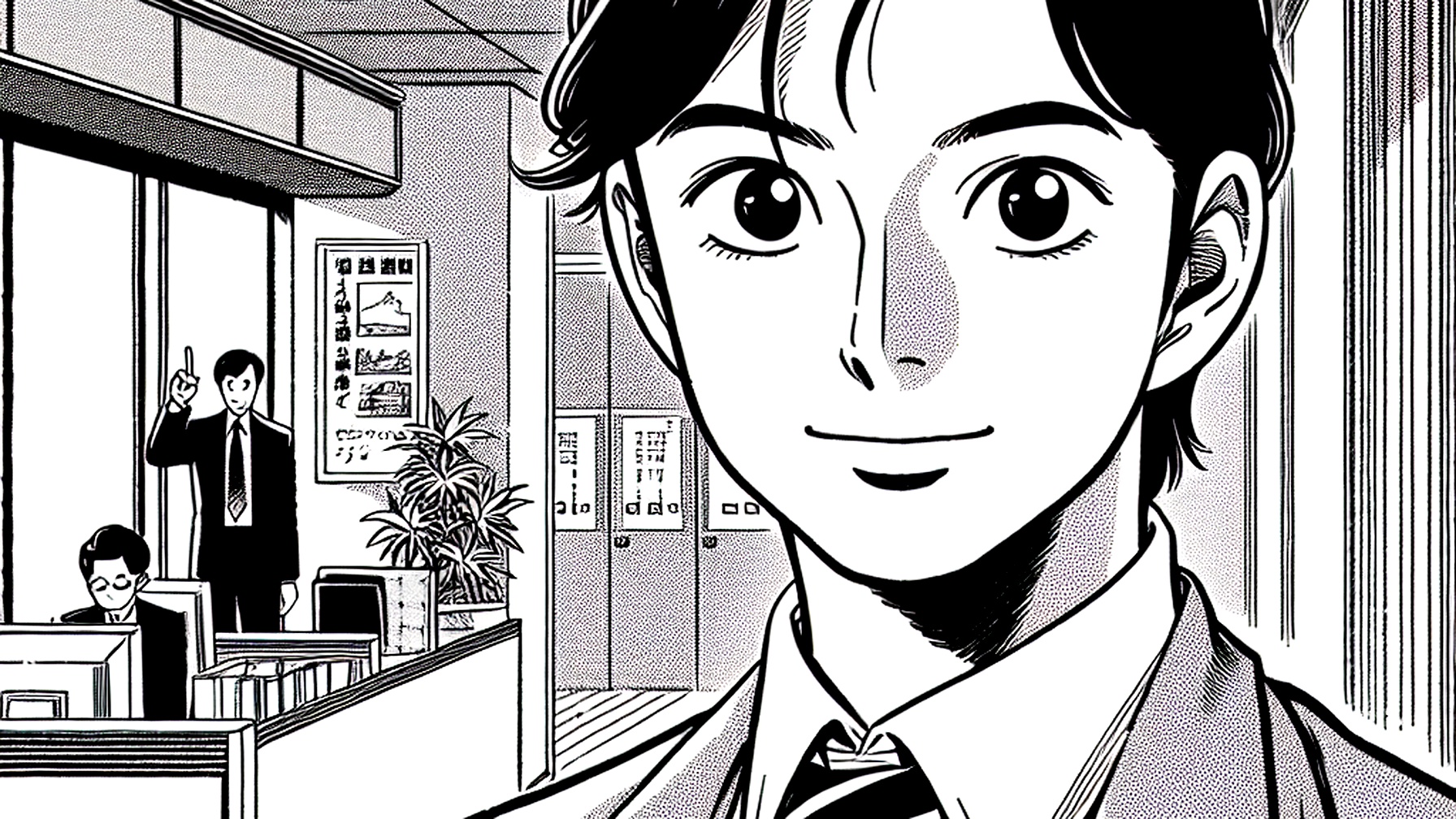
まず押さえておきたいのは、円安が直接関係しないように見える費用も連鎖的に増える点です。修繕費や保険料などは見えにくいものの、見積もり段階から差が出ます。例えば、築20年・木造アパートの外壁塗装は2023年時点で延べ1,000万円前後が一般的でしたが、2025年には1,150万円程度が標準価格といわれます。
保険料も上昇しています。損害保険料率算出機構のデータでは、2025年度の火災保険改訂により、築古物件の保険料が平均6%上がりました。為替で資材が高くなると、保険会社は修繕費見込みを引き上げるためです。
さらに忘れがちなのが空室対策費です。海外資金が流入して賃料相場が急騰すると、地方や郊外では家賃の二極化が生じやすくなります。家賃を上げられないエリアでは、インターネット無料や家具付きなど付加サービスが求められ、その原資はオーナー負担になります。結果として収益を押し下げる「想定外コスト」が発生しやすいのです。
為替リスクと外国人投資家の動き
実は、円安局面のもう一つのデメリットは市場の変動性そのものです。外国人投資家は為替前提が崩れると一気に撤退する可能性があり、流動性の高い都心部でも価格調整が起きます。2025年4月の東京商業不動産指数は前月比で1.7%下落しましたが、その背景には米ドル建ての投資利回り悪化を理由にした売却が報告されています。
こうした急変にさらされると、売却出口を想定していた投資家は計画を修正せざるを得ません。特に変動金利でレバレッジを高めている場合、家賃が維持できても物件価格が下がると評価額が下がり、追加担保を求められるケースもあります。
言い換えると、円安が続く局面でも「次に円高に転じたらどうするか」というシナリオを持つことが不可欠です。為替リスクを直接ヘッジするのは難しいものの、借入比率を抑えたり、出口戦略を複数用意したりすることで、影響を和らげることができます。
キャッシュフロー悪化を防ぐ資金計画
ポイントは、多めの自己資金と長期の運転資金を同時に確保することです。不動産投資では自己資金2割が一般的と言われますが、円安時代は3割を基準にすると安全度が高まります。日本政策金融公庫の2025年度実績では、自己資金30%以上の案件は審査通過率が約1.5倍に向上しました。
また、運転資金として家賃収入の6か月分を別口座に確保しておくと、突発的な修繕や空室に耐えやすくなります。これは空室率15%・修繕率10%を同時に想定した保守的な試算に基づきます。
さらに、固定金利と変動金利の組み合わせも有効です。固定部分で金利上昇リスクを抑えつつ、変動部分を短めに設定して元本を早く減らすと、金利リセット時の負担を軽減できます。こうした複合的な資金計画が、円安の波に左右されにくいキャッシュフローを生み出します。
2025年度の制度活用でリスクを下げる
まず利用を検討したいのは、2025年度も継続中の「小規模住宅用地に対する固定資産税の減額特例」です。敷地200平方メートル以下の部分について評価額が最大1/6に軽減されるため、戸建てやアパート投資ではランニングコストを抑えやすくなります。適用には住居専用の要件があるので、用途変更を伴う場合は市町村に確認しましょう。
次に、2025年度税制改正で延長された「不動産取得税の住宅用特例」も注目です。新築住宅に限られますが、課税標準が50%に圧縮されるため、取得時のキャッシュアウトを抑制できます。なお、投資用でも賃貸住宅として届出を行えば対象になり得るため、購入前に都道府県税事務所で確認する価値があります。
さらに、資金調達面では「住宅金融支援機構の賃貸住宅融資(2025年度)」が利用可能です。省エネ基準に適合した物件なら金利が年0.3%優遇されます。円安で上がった建築コストを省エネ性能で吸収しつつ、金利優遇でキャッシュフローを守るという二重の効果が期待できます。制度には完工期限が設定されているため、スケジュール管理が重要です。
まとめ
ここまで円安時代における不動産投資のデメリットを整理し、資金計画と制度活用による対策を紹介しました。価格高騰や修繕費増といった直接的なコストだけでなく、為替変動による市場の揺らぎが長期運用に影響することが分かります。結論として、自己資金を厚くし、複数の出口戦略を持ち、2025年度の税制特例を最大限活用することが、リスクを抑えつつ安定収益を実現する鍵です。この記事で得た視点をもとに、まずは購入候補物件の収支シミュレーションを見直してみてください。
参考文献・出典
- 日本銀行 資金循環統計 2025年7月速報版 – https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjexp.pdf
- 国土交通省 建設総合統計 2025年上期 – https://www.mlit.go.jp/statistics/
- 損害保険料率算出機構 火災保険参考純率改定 2025年度 – https://www.giroj.or.jp/
- 東京証券取引所 不動産指数 2025年4月 – https://www.j-reit.jp/
- 日本政策金融公庫 融資実績レポート 2025年度 – https://www.jfc.go.jp/

