いきなり大きな借り入れをしてマンションを丸ごと購入するなんて、自分には無理だと感じていませんか。実は、一棟マンション投資は区分マンションよりも空室リスクを分散でき、長期で安定した家賃収入を得やすい方法です。しかし高額な取引だからこそ、正しいプロセスを知らずに始めると致命的な損失を招きかねません。本記事では「一棟マンション 始め方」をテーマに、準備から資金計画、物件選定、2025年度の最新制度活用までを体系的に解説します。読了後には、自分に合った投資戦略を描き、最初の一歩を踏み出す自信が得られるはずです。
一棟マンション投資のメリットとリスク
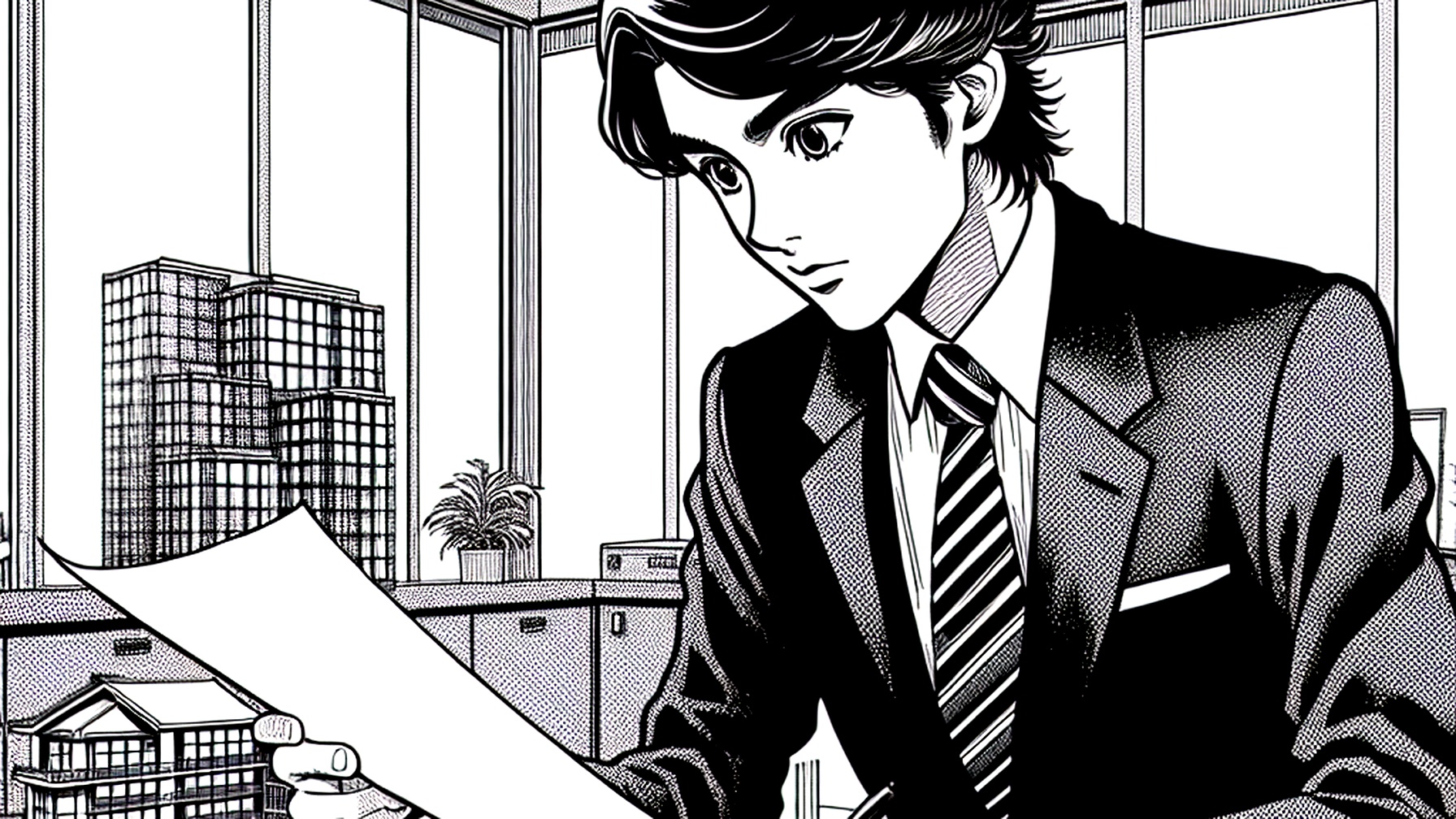
ポイントは、収益源が複数戸に分散されることと、運営の自由度が高いことです。その一方で、借入規模が大きくなるため資金計画の甘さが命取りになります。
まずメリットから整理しましょう。一棟所有の場合、空室が発生しても他の部屋が稼働していればキャッシュフローを維持できます。また、共用部の改修や賃料設定を自ら主導できるので、入居者ニーズに合わせた柔軟な運営が可能です。区分所有よりも土地が広くつくため、将来の建替えや売却時に土地値が下支えとなる点も見逃せません。
一方で、リスクは資金調達のハードルが高いことに尽きます。自己資金が少ないと金利が上がり、返済負担が重くなります。さらに、災害や修繕費の急増が発生すると、月々のキャッシュフローが一気に赤字へ転落する恐れがあります。つまり、表面利回りだけではなく、長期の修繕計画と出口戦略まで織り込んだ収支設計が不可欠です。
加えて、立地選定を誤ると取り返しがつきません。総務省統計局の人口移動報告では、2025年時点で地方の25%近くが5年連続人口減を記録しています。需要が細るエリアで新規投資を行えば、空室率と賃料下落のダブルパンチを受ける危険が高まるでしょう。
購入までのステップを理解する
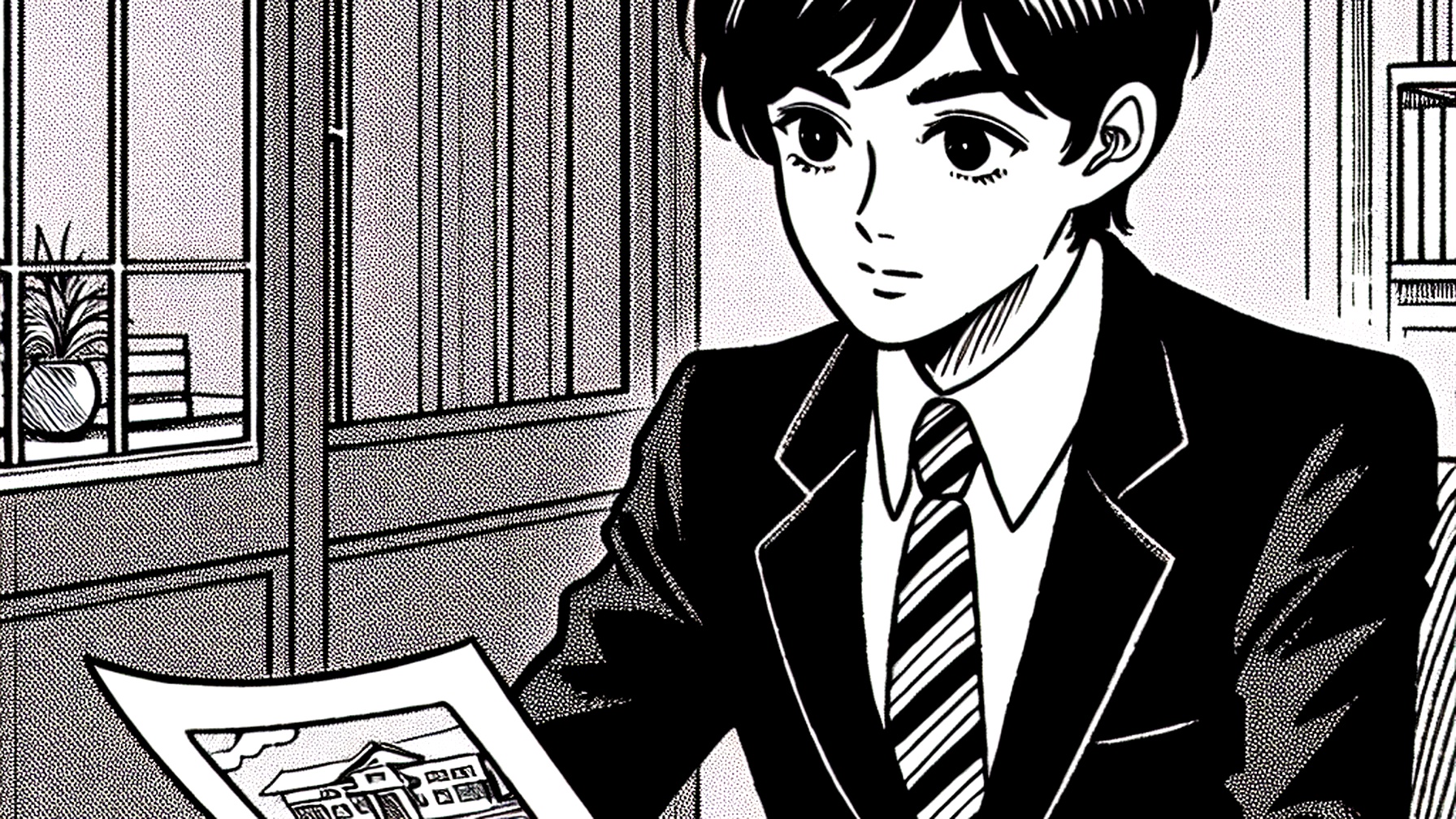
まず押さえておきたいのは、物件検索より先に融資戦略を立てることです。金融機関の融資条件によって、買える物件の規模や利回りが大きく変わるからです。
最初のステップは、自己資金と年収から借入可能額の目安を算出する作業です。多くの地方銀行では、年収の10倍から12倍が上限とされ、自己資金は物件価格の20%程度が望ましいと案内されています。この比率を頭に入れつつ、複数の金融機関へ事前相談を行うと、個別の金利や期間が具体的に見えてきます。
次に行うのが、レントロール(家賃表)と修繕履歴の精査です。築15年を超える物件は、大規模修繕の実施有無が収益の安定性を左右します。売主の提示資料に欠落があれば、不動産鑑定士や建築士へインスペクションを依頼し、将来の修繕費を見積もるようにしましょう。
最後に、買付証明書を提出し、融資承認後に売買契約へ進みます。この段階で焦って手付金を支払うと、ローン特約が付いていてもトラブルになるケースが散見されます。契約条件と解除条項を一文ずつ確認し、専門家のチェックを受ける姿勢が安全策となります。
融資と資金計画の立て方
重要なのは、返済比率と金利変動に耐えうるキャッシュフローを確保することです。具体的には、年間家賃収入に対する元利返済額を50%以内に抑えると、空室率20%でも黒字を維持しやすくなります。
たとえば、物件価格1億円、自己資金2,500万円、融資7,500万円で金利2.0%、期間25年と想定しましょう。この場合、年間返済額は約382万円です。一方、家賃収入が年間800万円なら返済比率は47.8%に収まり、経費と空室を差し引いても手元に100万円前後のキャッシュが残ります。金利が1%上昇した場合でも、返済比率はおよそ55%と許容範囲内におさまります。
日本銀行のマクロ統計によれば、2025年上期の不動産向け平均貸出金利は1.84%で、前年より0.09ポイント上昇しています。今後も緩やかな金利上昇が続くと想定すると、固定金利型や期間選択型の利用を検討し、金利上昇リスクを分散する姿勢が合理的です。
自己資金を厚くする余裕がない場合は、追加担保を活用する手もあります。自宅や別の投資物件を共同担保に入れれば、融資枠が拡大し金利も優遇されるケースがあります。ただし、万一の返済不能時には担保を処分されるリスクが高まるため、家族構成やライフプランまで含めて慎重に判断しましょう。
物件選びで押さえるべき2大ポイント
実は、立地と建物スペックのバランスを見極めるだけで、物件選定の失敗は大幅に減らせます。片方でも欠けると、想定利回りは簡単に崩れてしまいます。
立地については、駅距離と生活利便施設の双方を検証します。国土交通省の「都市計画基礎調査」では、駅から徒歩10分圏内の賃料は、15分圏外に比べ平均12%高いと報告されています。加えて、スーパーや病院が徒歩圏にある物件は退去率が低い傾向です。つまり、共用部の豪華さよりも、周辺インフラの充実度を優先したほうが長期収益につながります。
建物スペックでは、耐震基準と設備更新時期を最重視しましょう。1981年6月以降の新耐震基準を満たすRC造であれば、地震保険料も割安になりやすいです。また、給排水管やエレベーターのリニューアル履歴があれば、突然の大規模修繕に備えやすくなります。設備更新が未実施なら、購入価格の5%前後を修繕積立金として別途確保しておくと安心です。
さらに、2025年10月現在の新築マンション平均価格は東京23区で7,580万円と過去最高を更新しています(不動産経済研究所)。この価格上昇は中古市場にも波及し、築浅RC一棟物件の取引価格は前年比で4%ほど上がっています。価格が高止まりの局面では、築20年前後の物件にターゲットを広げ、利回りと将来価値のバランスを取る戦略が有効でしょう。
2025年度の支援制度と税制優遇を活用する
まず押さえておきたいのは、減価償却による節税効果です。RC造の法定耐用年数は47年で、築25年なら残存年数は22年となりますが、中古取得の場合は「耐用年数×0.2+年数」の簡便法が選べます。これにより、帳簿上の償却費を圧縮し、キャッシュフローを改善できます。
2025年度も引き続き適用される「不動産取得税の軽減措置」は、課税標準から土地評価額の半額が控除される仕組みです。適用期限は2026年3月31日までと発表されているので、取得時期の調整が可能なら活用したいところです。また、新築後5年以内のマンションを取得した場合、固定資産税の1/2減額が3年間受けられる特例も継続中です。これらは投資用物件でも要件を満たせば利用できます。
環境性能を向上させる工事を行う場合は、国土交通省の「賃貸住宅省エネ改修等推進事業(2025年度)」が利用可能です。補助率は工事費の1/3以内、上限300万円と比較的小規模ですが、LED照明や高効率給湯器の導入でランニングコストが下がり、募集広告の訴求力も高まります。
さらに、法人で取得する場合は「中小企業経営強化税制」の即時償却を活用できる場合があります。適用には設備投資計画の認定が必要なため、税理士と早めに相談し、提出書類を整えておくとスムーズです。これらの制度は年度ごとに要件が更新されるため、国土交通省の公式サイトで最新情報を確認しながら進めましょう。
まとめ
ここまで、一棟マンション投資の魅力とリスク、購入プロセス、融資戦略、物件選定の勘所、そして2025年度の制度活用までを整理しました。最大の教訓は、数字と現場の両面からリスクを可視化し、想定外の事象に備えることです。まずは自己資金額と返済比率を基準に物件価格の上限を設定し、立地と建物スペックのチェックリストを作成してください。そして制度や減価償却を賢く活用し、キャッシュフローの余裕を生み出しましょう。今日の学びをもとに、専門家の助言も取り入れながら、第一歩を踏み出すことをおすすめします。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 都市計画基礎調査 – https://www.mlit.go.jp/toshi/
- 日本銀行 「貸出・預金動向」 – https://www.boj.or.jp
- 総務省統計局 人口移動報告 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅省エネ改修等推進事業 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/

