多くのオーナー予備軍が抱える悩みは、「土地をどう活用すれば税負担を減らせるのか」という一点に集約されます。特に相続が視野に入る年代になると、不動産の評価額や現金化の難しさが気に掛かり、専門家に相談する前に情報を集めたいと感じる方が増えます。本記事では、相続対策の基本からアパート経営の実務、2025年度に有効な制度までを体系的に整理しました。読み進めることで、土地を守りながら収益も得る仕組みが見えてくるはずです。
相続税の基本を押さえる
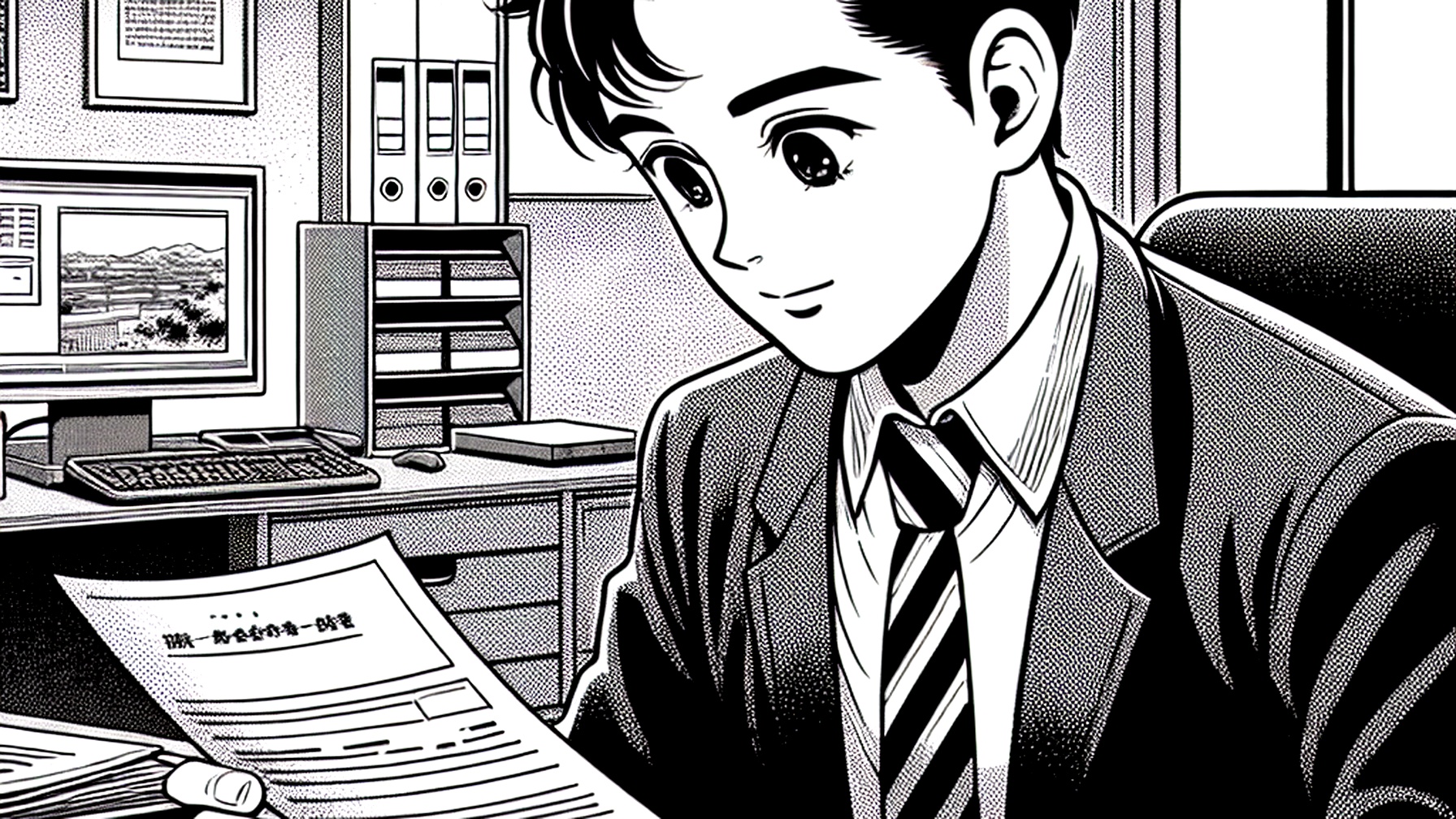
まず押さえておきたいのは、相続税の計算構造と評価方法です。相続税は現金より不動産のほうが評価額が低くなる傾向があり、課税対象を圧縮しやすい点が知られています。土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基に計算されるため、市場価格の八割前後に収まるケースが多いのです。さらに2025年度も「小規模宅地等の特例」が継続しており、一定の条件を満たせば評価額を最大80%減額できる点は見逃せません。
一方で、特例に頼り切ると他の相続人とのバランスを欠く恐れがあります。例えば、長男が居住用宅地を取得して減額を享受すると、次男や三男が受け取る金融資産の取り分が相対的に減少する可能性が高まります。言い換えると、特例は家族構成や遺産分割の方針とセットで考える必要があるというわけです。相続対策は節税と公平性を両立させる設計が何より重要になります。
収益物件としてのアパートの魅力
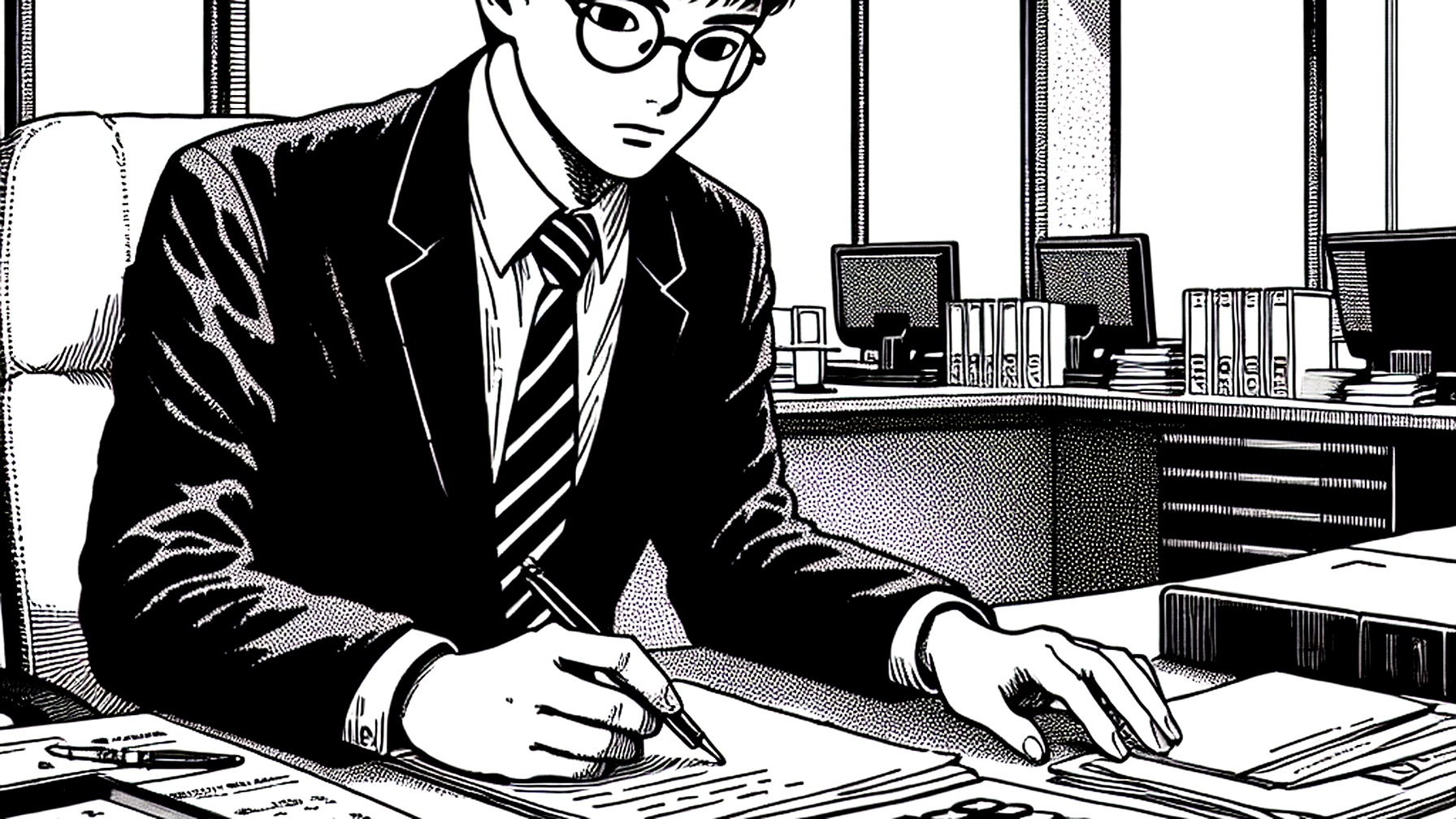
重要なのは、節税と収益化を同時に図れる点でアパートが光るという事実です。建物を建てると土地は「貸家建付地」となり、評価額がさらに20%前後下がります。ここに空室リスクを織り込んでも、建築費を含めた初期投資が30年前後で元を取れる試算なら、キャッシュフローと評価圧縮の両方でメリットが得られます。
国土交通省住宅統計の2025年8月データによれば、全国平均のアパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント改善しました。つまり、供給過多といわれる市場でも、立地と設備を選べば十分に勝算があります。例えば駅徒歩10分以内で築浅の木造アパートの場合、平均空室期間は50日未満にとどまるという管理会社の集計もあります。
また、アパート経営はインフレ耐性が高い点も見逃せません。物価が上がれば家賃もじわりと追随し、固定金利で融資を組んでいれば実質的な返済負担が軽くなる構造が働きます。毎月の家賃収入がローン返済と管理費を上回るいわゆる「プラスキャッシュフロー」を確保できれば、将来の修繕費や退去時の原状回復費を自己資金で賄える好循環が生まれます。
土地活用が相続対策になる理由
ポイントは、遊休地のままでは課税上のメリットが乏しいという点です。更地は固定資産税が住宅用地の約六倍になるため、所有し続けるだけでキャッシュアウトが続きます。一方、アパートを建てれば固定資産税は最大1/6に軽減され、相続税評価も下がります。つまり、土地を活かすことで税コストそのものを抑えられるわけです。
加えて、建設コストを含めた借入金が生じることで、純資産額が圧縮される「負債控除」も働きます。たとえば1億円の土地に7000万円のアパートを建て、8000万円の融資を受けると、純資産は実質2000万円ほどに下がります。これは相続税の課税標準にも直接影響するため、計画的な借入はあえて活用すべき手段といえます。
もっとも、土地活用が相続対策として成立する前提は、長期的に収益を確保できることにあります。人口動態や将来の用途変更も念頭に置き、出口戦略までイメージしておく必要があります。売却を視野に入れるなら、木造よりRC造(鉄筋コンクリート)のほうが評価が安定しやすいものの、建設費と利回りのバランスを慎重に計算することが欠かせません。
アパート経営で失敗しないためのポイント
実は、収益計画よりも前に「家族会議」を開くことが成功率を左右します。誰が管理を担い、誰が将来の売却や建替えを決定するのかを明確にしなければ、後になって意見が割れ、運営が停滞するリスクが高まるからです。家族信託を使って運営権を集中させる方法もありますが、2025年時点では司法書士と税理士のダブルチェックが推奨されています。
次に、収支シミュレーションは三つのシナリオを作ると安心です。楽観ケースでは空室率10%、標準ケースでは20%、悲観ケースでは30%とし、金利上昇も最大+2%まで見込むようにします。これにより、実際の運営が標準より悪化しても赤字転落を防ぐ目安が把握できます。築後10年ごとの大規模修繕費を家賃収入の10%程度積み立てておけば、急な出費にも慌てずに済みます。
さらに、管理会社選びは「募集力」「修繕提案力」「収支報告の透明性」に注目します。家賃保証をうたうサブリース契約は安定に見えますが、途中で保証額が下げられるケースが増えているため、契約条項を細部まで確認することが不可欠です。オーナーと管理会社がWIN-WINでないと、長期的な資産価値は守れません。
2025年度の制度と資金計画
まず押さえておきたいのは、2025年度も住宅取得等資金の贈与非課税枠が最大1000万円で継続している点です。これを使って子世代がアパート建設資金の一部を負担すれば、将来の相続財産を減らしつつ次世代への資産移転が進みます。また、低利の「特定事業用資産買換え資金貸付制度」は不動産オーナー向けに利用実績が伸びており、固定金利1.2%台で20年超の融資も可能です。
資金計画では自己資金を二割以上確保するのが鉄則です。自己資金が多いほど融資条件は有利になり、実効利回りも向上します。逆に十分な現金予備費がないまま満額融資を受けると、空室増加や金利上昇に耐えられず、相続対策どころか資産を失うリスクが高まります。
最後に、2025年10月時点で有効な補助制度として「長期優良住宅化リフォーム推進事業」があります。耐震・省エネ性能を高める改修に対し最大250万円の補助が出るため、築古アパートのバリューアップや相続税評価額の見直しと組み合わせれば、投資効率を高めつつ入居者満足度も底上げできます。
まとめ
結論として、相続対策でアパート経営と土地活用を選ぶ意味は、「評価額の圧縮」「収益の創出」「家族資産の円滑な承継」の三つを同時に達成できる点にあります。税制や制度を正しく活かし、現実的な収支シミュレーションと家族間の合意形成を怠らなければ、土地は負債ではなく強力なキャッシュマシンへ変わります。今日からできる第一歩は、土地の潜在価値を数値で把握し、専門家チームとともに具体策を練ることです。将来の相続をチャンスに変える行動を始めましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅局 – https://www.mlit.go.jp
- 財務省「相続税に関する統計」 – https://www.mof.go.jp
- 総務省統計局「住宅・土地統計調査」 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁「相続税のあらまし(2025)」 – https://www.nta.go.jp
- 独立行政法人住宅金融支援機構 – https://www.jhf.go.jp

