円安が続くと海外旅行や輸入品が高くなるのと同じように、国内で物件を買う投資家にも思わぬ影響が及びます。最近「日本の不動産は割安だ」と海外マネーが流入し、価格が上昇していると聞くと、初心者ほど「今こそ買い時」と考えがちです。しかし急速な円安局面では、購入価格だけでなく修繕費やローン返済など、見落としやすいコストが増える可能性があります。本記事では円安時代に不動産投資へ参入する際のデメリットを整理し、その背景と対策をわかりやすく解説します。仕組みを理解しておけば、慌てることなく冷静な判断ができるでしょう。
円安が不動産投資に与える基本的な影響
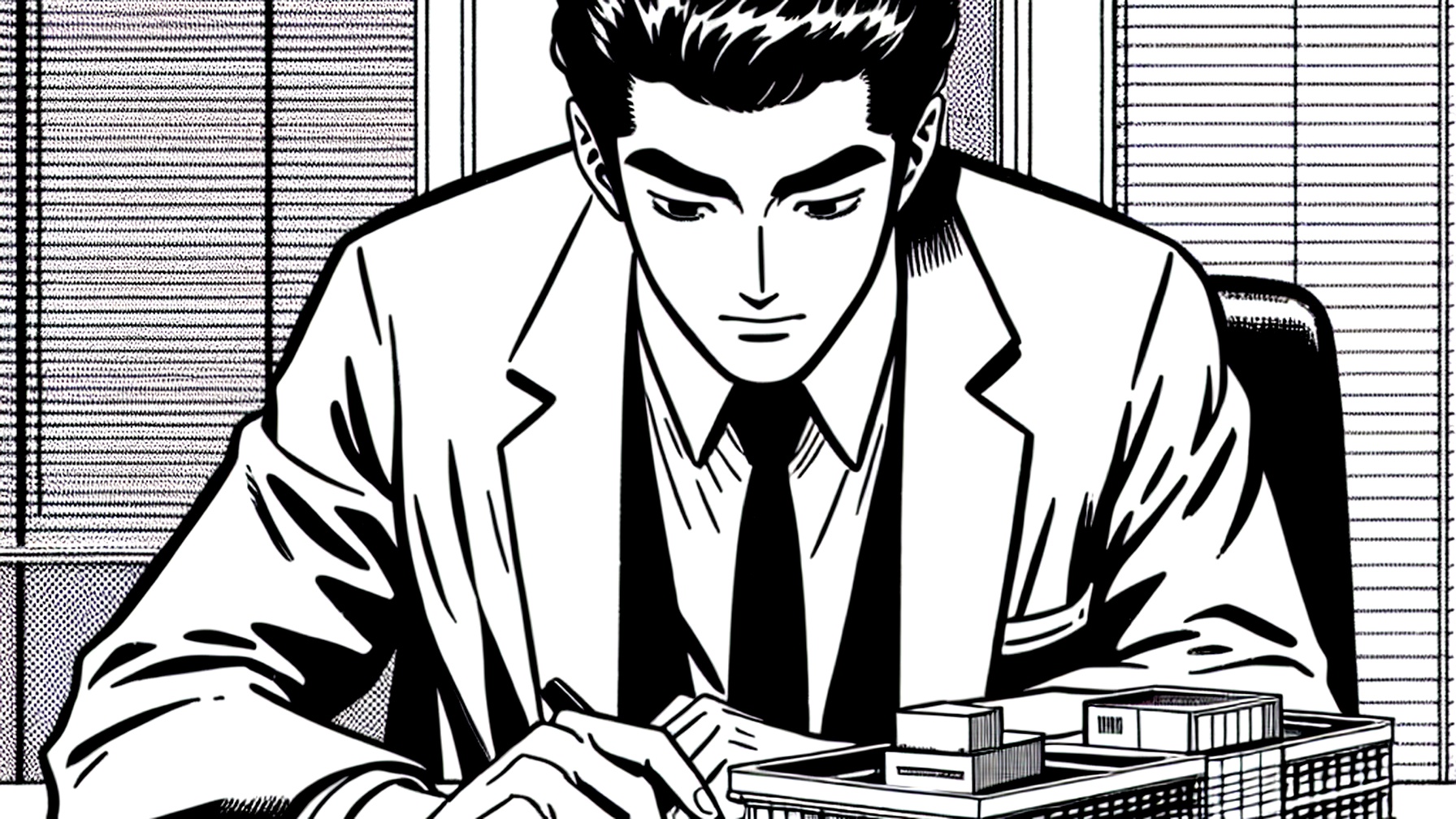
重要なのは、円安が国内外の資金フローを変え、物件価格と運営コストを同時に押し上げる点です。日本銀行の為替統計によると、2025年7月の対ドル相場は1ドル170円台で推移し、10年前より約40%の円安となりました。この状況が長期化すれば、海外投資家が相対的に安い日本の物件を買い進める一方、日本人にとっては仕入れ価格が上がりやすくなります。
まず価格への直接的な影響を見てみましょう。円建ての不動産はドル換算で割安に映るため、外国人が都心部の商業ビルや高級マンションを買い増し、その結果として国内投資家も高値で競る構図が生まれます。都心六区のオフィスビル指数は2024年から2025年にかけて約6%上昇しましたが、国土交通省の地価動向報告では「海外需要の増加」が主因とされています。
一方で賃料はすぐには上がりません。賃貸契約は2年更新が多く、転居コストも高いため、家賃は地価ほどのスピードで動かないのが現実です。つまり物件価格が急騰しても家賃収入は横ばいになりやすく、利回りは縮小します。円安が長期化すると、買値だけ高くキャッシュフローが細るという二重苦が起こりやすいのです。
購入時コストが増える仕組み
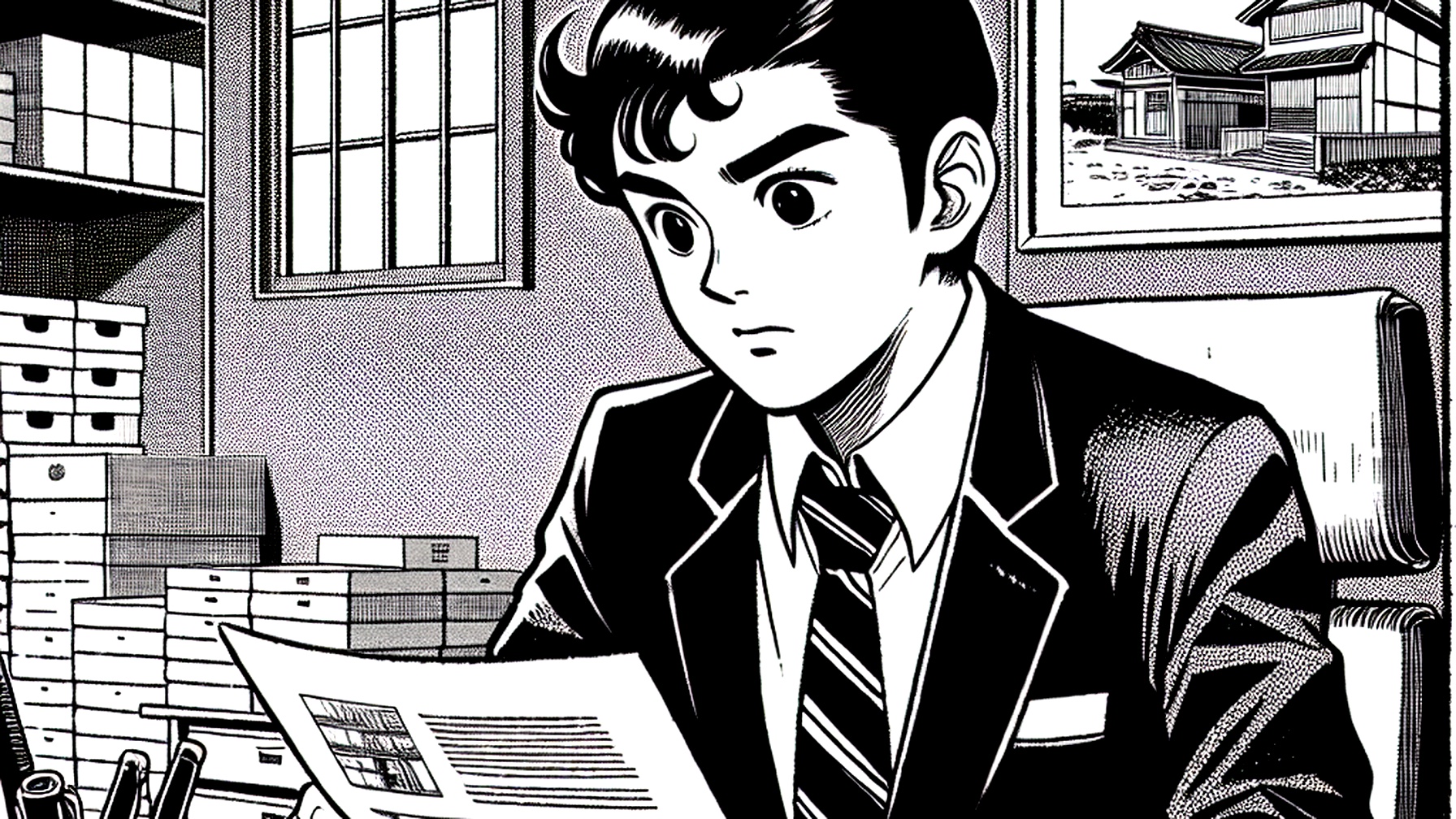
ポイントは、物件価格だけでなく諸費用まで膨らむという事実です。不動産取得には仲介手数料、登記費用、火災保険料などが付き物ですが、これらの多くは物件価格に比例して決まります。たとえば仲介手数料は「価格×3%+6万円+税」が上限ですから、価格が1億円から1億2千万円に上がれば手数料も約60万円増える計算になります。
さらに、円安で建築資材が高騰すると新築物件の販売価格が底上げされ、中古物件の相場も引っ張られる傾向があります。財務省の貿易統計では2025年上半期の木材輸入単価が前年同期比18%高く、鉄鋼材も12%高い水準でした。こうしたコスト上昇分が新築価格に転嫁され、それを指標に中古価格が上がるという連鎖が起こるのです。
また、2025年度の登録免許税や不動産取得税の軽減措置は自宅用住宅が中心で、投資用物件には基本的に適用されません。結果として投資家は税負担をそのまま支払う必要があります。物件価格がわずかに上がるだけでも、税金と手数料が重なれば現金支出は想像以上に膨らむため、自己資金を薄く見積もると購入後すぐに資金繰りが苦しくなるリスクがあります。
賃料収入と返済のバランスが崩れるリスク
まず押さえておきたいのは、利回り低下が返済計画に直撃する点です。不動産投資ローンの多くは変動金利で、指標となる短期プライムレートは日銀の金融政策に左右されます。2025年4月にマイナス金利が解除された後、主要地銀の店頭変動金利は一部で0.5%上昇し、今後も利上げ局面が続くと見込まれています。
家賃が上げにくい一方で金利が上昇すると、毎月のキャッシュフロー(手取り収支)は圧迫されます。具体例として、金利1.5%で1億円借り入れた場合の月返済額は約34万円ですが、2.0%に上がると約37万円へ増加します。年間では36万円の負担増となり、家賃1室3万円の値上げを12室分決めてもようやく相殺できる計算です。現実には空室や入居者の同意が障害となり、思うように賃料を上げられません。
さらに円安による輸入インフレで生活費が上昇すると、賃借人の家計余力が削られます。総務省家計調査では、2025年1〜6月の実質可処分所得は前年同期比2.3%減少しました。借り手の財布が厳しくなれば、強気の賃料設定には応じにくく、長期入居を促すために賃料を据え置く必要も出てきます。その結果、返済比率が高まって自己資金の持ち出しが起こるリスクが増大します。
修繕・管理コスト上昇という落とし穴
実は運営段階でも円安の影響は色濃く残ります。建物を長期保有するなら、外壁塗装や配管交換など大規模修繕が避けられません。国土交通省の建築物リフォーム・リニューアル調査では、マンションの大規模修繕費は10年前より平均17%上昇しており、その主因は資材の輸入価格と人件費の高騰です。
たとえば外壁塗装に欠かせない塗料の原材料は化学樹脂や鉱物顔料で、いずれも輸入依存度が高いと言われます。円安で材料費が上がれば工事費全体も上乗せされ、見積もりが当初計画を超過するケースが続出します。管理会社の人件費も上がれば、共用部清掃や設備点検費の値上げ要請が届くことも珍しくありません。
修繕積立金を毎月積み立てている場合でも、想定を超える値上げは資金不足を招きます。もし追加拠出が難しいと工事時期を遅らせがちになり、結果として物件価値の下落や空室率の上昇を招く悪循環に陥ります。円安局面では「修繕費は10年後の物価で払うもの」と意識し、余裕ある積立計画を立てることが重要です。
デメリットを乗り越えるための具体的な視点
ポイントは、為替リスクを織り込んだ長期シナリオを作ることです。第一に自己資金比率を高め、ローン残高を抑えることで金利上昇の影響を小さくできます。頭金を30%以上入れると返済比率が下がり、金利が1%上がってもキャッシュフローが黒字で残る余地が大きくなります。
次に、賃料上昇余地のあるエリアを選ぶことが有効です。総務省の住民基本台帳人口移動報告では、東京都心や福岡市など人口流入が続く都市圏では賃料が上向く傾向があります。将来の家賃改定が見込みやすい地域を選ぶことで、利回り低下の影響を和らげられます。
最後に、物件取得後も定期的に金利や修繕費の見積もりを更新し、ストレスシナリオを作成しましょう。具体的には「金利+1%」「修繕費+20%」「空室率20%」など複数の条件で試算し、最悪でも手元資金が尽きない計画を維持することが肝心です。結論として、円安時代のデメリットは事前準備と保守的な試算で相当程度コントロールできます。
まとめ
ここまで円安時代に不動産投資を行う際のデメリットを整理しました。物件価格と諸費用の上昇、賃料と返済のミスマッチ、修繕・管理コストの高騰という三つの側面が大きなリスクになります。また金融政策の転換で金利が上がるとキャッシュフローが急速に悪化する可能性があるため、頭金を厚くし、賃料上昇余地のあるエリアを選ぶなどの対策が欠かせません。読者のみなさんには、安易に「円安で海外勢が買うなら自分も」と飛びつくのではなく、数字を丹念に積み上げ、不測の事態にも耐えうる計画を作る行動を強くおすすめします。
参考文献・出典
- 日本銀行 為替相場統計 – https://www.boj.or.jp/statistics/market/forex/index.htm
- 国土交通省 地価動向報告 – https://www.mlit.go.jp/
- 財務省 貿易統計 – https://www.customs.go.jp/toukei/
- 総務省 家計調査 – https://www.stat.go.jp/data/kakei/
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.stat.go.jp/data/idou/
- 国土交通省 建築物リフォーム・リニューアル調査 – https://www.mlit.go.jp/common/001566585.pdf

