都市部でRC造(鉄筋コンクリート造)の賃貸マンションを検討しているものの、「税金が複雑で手を出しにくい」と感じていませんか。実はRC造は木造より高価ですが、耐用年数が長く減価償却も有利に組み立てやすいため、キャッシュフローと節税の両面で魅力があります。本記事では、2025年9月時点で有効な税制をもとに、初心者でも理解できるようにRC造物件の税金を基礎から解説します。読み終えるころには、購入前に押さえるべき費用計算のコツと、将来の相続対策まで見通せるようになります。
RC造の基本と投資家が注目すべき理由
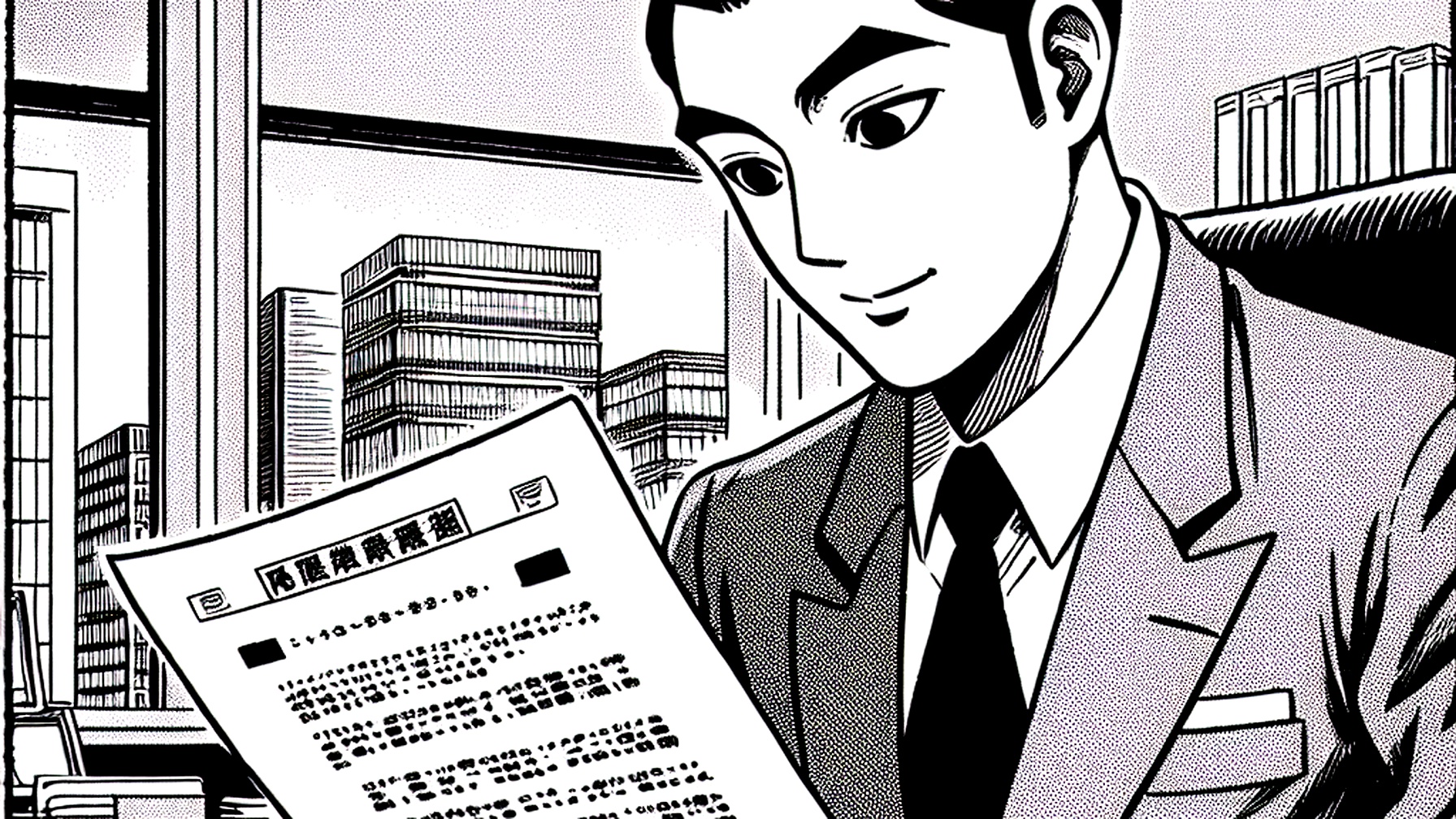
まず押さえておきたいのは、RC造の構造的な特徴とそれが税金に与える影響です。RC造は鉄筋とコンクリートを一体化させた工法で、国土交通省の住宅着工統計によると都市部の集合住宅の約六割を占めています。耐用年数は税法上47年と長く、木造の22年と比べて約2倍です。つまり建物価値が下がりにくく、長期ローンを組みながら安定した賃貸経営を行いやすい仕組みになっています。
一方で建築コストは木造より二〜三割高いことが多く、取得時に多額の資金が必要になります。しかし固定資産税の評価額は構造や築年数で徐々に下がるため、所有期間が長いほどランニングコストの負担感は緩和されます。また耐火性能が高いため、火災保険料が木造の六〜七割に抑えられるケースも珍しくありません。保険料の節約分を税引き後キャッシュフローに反映できる点は見落としやすいので注意しましょう。
減価償却が生むキャッシュフローの仕組み

重要なのは、RC造の減価償却費が現金支出を伴わない「経費」になることです。減価償却とは建物価値を耐用年数で按分し、毎年経費計上して税負担を軽くする制度を指します。RC造の定額法で計算すると、例えば建物価格1億2千万円なら年間約255万円を経費化できます。課税所得から控除されるため、実際のキャッシュは手元に残りやすく、ローン返済に充てる余力が高まります。
さらに、2025年度も適用される「加速度償却」はエネルギー効率向上等計画認定を受けた設備が対象です。RC造マンションで高効率給湯器や断熱材を採用すると、初年度に通常の1.2倍まで償却できる場合があります。ただし認定には設計段階での申請が必須で、工事後の申請は認められません。将来の売却時には帳簿価額が低くなることで譲渡所得が増えるというデメリットもあるため、出口戦略とセットで検討することが求められます。
実は減価償却を最適化するだけで、表面利回り6%台のRC造でも自己資金回収期間を1〜2年短縮できることがシミュレーション上確認できます。税務戦略がキャッシュフロー改善に直結する点を理解することが、RC造投資成功への第一歩となります。
賃貸経営にかかる税金と2025年度のポイント
ポイントは、賃貸収入に対して課される所得税と住民税を正しく把握し、先回りで資金を確保することです。家賃収入から必要経費を差し引いた不動産所得が課税対象となります。国税庁の統計によると、2024年申告分の不動産所得は平均240万円ですが、専業投資家ほどその変動幅は大きくなります。RC造の場合、修繕積立金が高めに設定されることが多く、適切に経費処理すれば実効税率を数パーセント下げられる余地があります。
2025年度税制改正大綱では、不動産所得が三百万円以下で赤字が継続する場合の損益通算制限が議題となりました。しかし現時点では導入が見送られ、従来どおり給与所得や事業所得と通算できます。赤字を意図的に作る過度な節税は税務調査で否認される可能性があるため、家賃設定や修繕計画は実態に即して立てることが重要です。
消費税にも注意が必要です。賃貸住宅の家賃は非課税ですが、駐車場収入やオフィス部分があると課税売上になります。課税売上が一千万円を超えた場合、翌々年から課税事業者になるため、仕入税額控除の適否が変わります。複数棟を持つ場合は課税売上高の管理を徹底し、課税事業者選択届出書の提出時期を税理士と相談しましょう。
売却・相続時に差がつく税務戦略
まず押さえておきたいのは、RC造の長期保有は譲渡所得税の軽減を受けやすいことです。所有期間が5年超であれば、長期譲渡所得として約2割の税率になります。購入後すぐに売却する短期譲渡は税率が4割超に跳ね上がるため、インフレ局面での早期売却は慎重に検討しましょう。
相続面では、固定資産税評価額が時価の七〜八割になる傾向があるため、現金よりも遺産総額を圧縮できます。2025年度の基礎控除は3千万円プラス法定相続人×600万円で据え置かれており、配偶者控除も変更はありません。しかし相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるルールが強化されています。生前対策としては賃料収入を子ども名義の管理会社へ移転する「管理受託方式」などが有効ですが、実態のある業務委託契約が前提になることを忘れないでください。
贈与税については、2025年度改正で年110万円の暦年贈与について連年加算ルールが見直されました。連年贈与を装う形で相続財産を減らす手法はリスクが高まっています。RC造物件の取得名義を子どもと共有にするなど、贈与と取得を一体で設計する方法がより安全といえます。
税務調査に備える記録と専門家活用法
実は、税務調査で最も指摘が多いのは「家事関連費の按分」と「修繕費と資本的支出の区分」です。例えば外壁塗装が三年分割払いの契約になっている場合、支出時の一括経費計上が否認されるリスクがあります。工事見積書や写真を保管し、目的と内容を説明できる状態にしておくことが、結果的に節税の正当性を守る鍵になります。
また、クラウド会計ソフトと不動産管理アプリを連携させることで、家賃入金と経費支出を自動仕訳できます。金融機関ごとの手数料差額も集計しやすくなり、経営改善の指標として活用できます。国税庁が推奨する電子帳簿保存法の要件に合わせてデータ保存すれば、紙での保管スペースも削減できます。
専門家の活用も欠かせません。税理士と司法書士が連携し、購入から運営、売却までをトータルでサポートする「ワンストップ型顧問契約」は年間報酬が家賃収入の1〜2%が目安です。費用はかかりますが、適切な節税により十分回収できるケースが多いのが実情です。セカンドオピニオンとして別の税理士に申告書をレビューしてもらう方法も、万一のリスクを下げるうえで有効です。
まとめ
RC造の不動産投資は初期費用が高い反面、耐用年数の長さと減価償却の大きさが資金計画にゆとりをもたらします。賃貸収入にかかる所得税や住民税を正確に見積もり、2025年度の税制改正点を押さえることで、長期的なキャッシュフローを安定させることが可能です。売却や相続を視野に入れた出口戦略を早めに設計し、専門家と連携しながら記録と申告を適正に行えば、節税と資産防衛の両立が実現します。この記事を参考に、自分の投資目的に合わせた具体的な資金シミュレーションを作成し、次の一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省 住宅着工統計 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 財務省 2025年度税制改正大綱 – https://www.mof.go.jp
- 独立行政法人 住宅金融支援機構 資金計画資料 – https://www.jhf.go.jp

