投資用のマンションやアパートに興味はあるものの、「本当に黒字になるのか」「どの数字を確認すれば良いのか」と迷う人は多いはずです。実は、収益の行方は最初に行う収支計算でほぼ決まります。本記事では、初心者が戸惑いがちな計算手順を丁寧に解説し、数字を根拠に物件を選べるようになるまでをゴールに設定しました。読み終える頃には、購入前に取るべきステップが頭の中で整理され、行動に移す自信が湧くでしょう。
収支計算に必要な数字を揃える
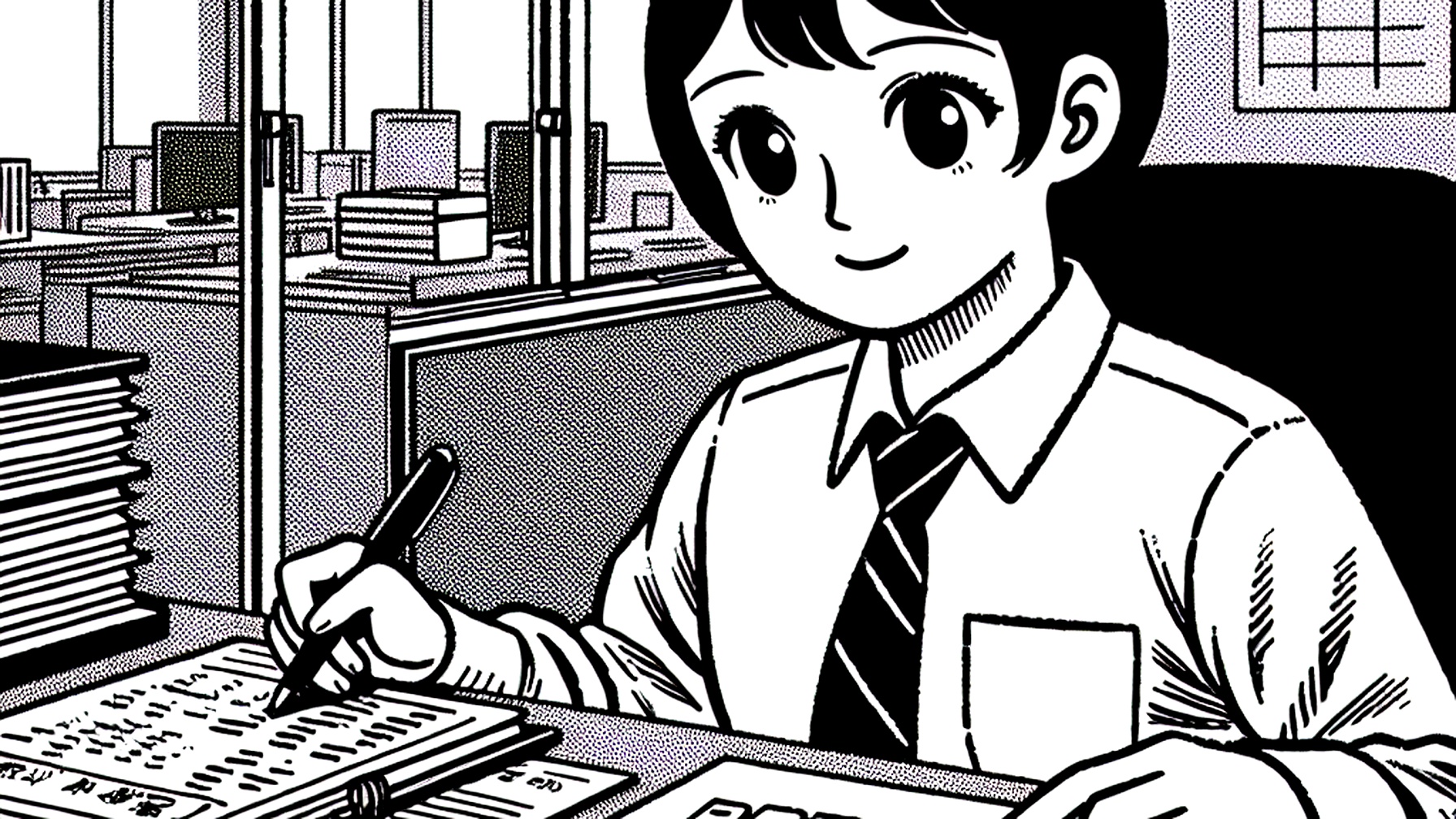
まず押さえておきたいのは、収支計算に使う数字をいかに正確に集めるかです。物件価格や家賃は誰でも確認できますが、購入時諸費用や将来の修繕費を甘く見積もると後で赤字になります。国土交通省の「不動産価格指数」によると、2025年上期の中古マンション価格は前年同期比で4%上昇し、初期費用も連動して増加傾向です。したがって、物件価格の6%前後に当たる仲介手数料や登記費用のほか、金融機関手数料や火災保険料も合算し、購入総額を算出する姿勢が欠かせません。
一方で、支出の中でも見落とされやすいのが長期修繕費です。総務省統計局の住宅・土地統計調査では、築20年超物件の約3割が大規模修繕を実施しています。つまり、購入時に予備費を積んでおかないと、家賃収入が出る前に多額の支払いに追われる危険があります。物件の規模や築年数によりますが、年間家賃収入の10%を修繕積立に充てる計画を先に立てておくと、急な出費にも耐えやすくなります。
家賃収入の見積もり方
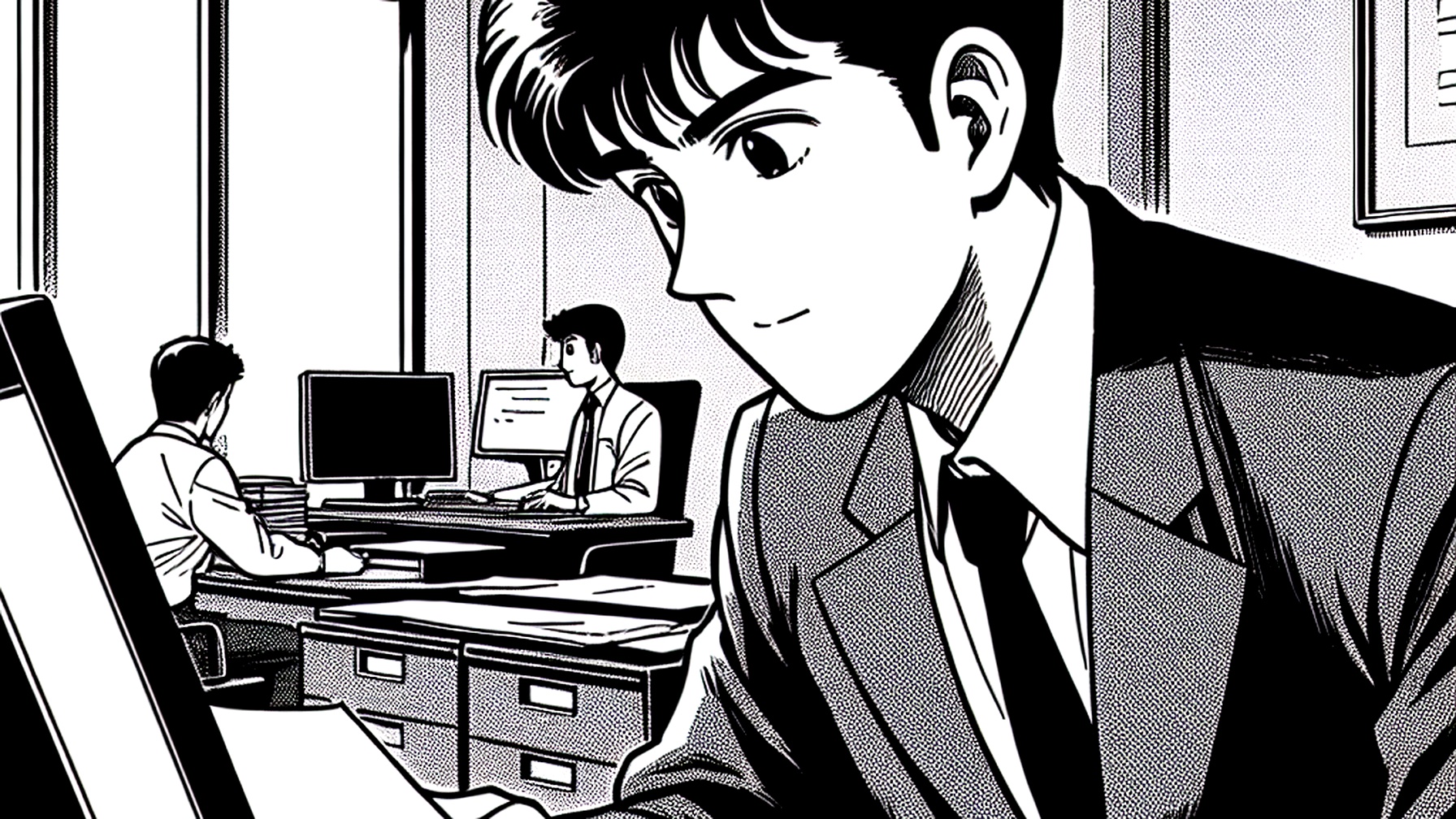
重要なのは、現在の賃料だけでなく将来の下落リスクまで見込むことです。レインズマーケットインフォメーションの2025年7月データでは、都心ワンルームの成約賃料は前年比1.2%上昇しています。しかし、人口減少局面であることに変わりはなく、郊外エリアでは横ばいから微減が続いている点に注意が必要です。賃料の将来予測には、直近3年の成約事例と周辺の新築供給予定を掛け合わせ、緩やかな下方調整を行うと保守的な計算ができます。
空室率も軽視できません。日本不動産研究所の賃貸住宅空室率調査によれば、2025年4月の23区平均空室率は4.0%ですが、地方都市では10%近い地域もあります。つまり、エリアや築年数に応じて空室期間を想定し、満室稼働ベースから5〜15%を差し引いた実質家賃収入を使うほうが安全です。高い利回り表示に惑わされず、保守的な数字で試算する姿勢が、安定経営への近道になります。
経費と減価償却の考え方
ポイントは、経費の中でも税務上認められる項目を正しく把握することです。固定資産税、管理委託料、修繕費、水道光熱費、火災・地震保険料などは毎年発生します。2025年度税制では、新築賃貸住宅に対する固定資産税の半額軽減措置(3年間)が継続中ですが、築後4年目以降は通常税率に戻るため、長期の収支計画では標準税額を用いておくと過度な期待を避けられます。
減価償却費は実際に現金支出を伴わないため、キャッシュフロー計算で利益と現金の差を理解する鍵になります。木造アパートの場合、法定耐用年数は22年ですが、中古取得なら残存年数を使い分割償却が可能です。たとえば築10年物件を2,000万円で取得し、建物割合を60%とすると償却総額は1,200万円です。残存年数12年なら年100万円を経費にでき、課税所得を圧縮できます。つまり、実効税率20%の個人であれば年間20万円の節税効果が望める計算です。
ただし、償却期間が終わると一気に課税額が増える点も頭に入れておく必要があります。物件の出口戦略が未定の場合、法人化や買い替え時期を早めるなど、税負担を平準化する工夫をあらかじめ検討すると良いでしょう。
キャッシュフローシミュレーションの手順
ここで、実際の「収益物件 収支計算 手順」を具体的にまとめます。次の流れで表計算ソフトに入力すると、一目で黒字か赤字かが判定できます。
1. 購入価格と諸費用を合算し、総投資額を確定 2. 家賃収入を満室想定と実質想定の二本立てで入力 3. ローン条件(金利、返済期間、元利均等か元金均等か)を設定 4. 税引き前収支として、家賃収入から経費と返済額を引く 5. 減価償却費を経費に加算し、所得税・住民税を試算 6. 税引き後キャッシュフローを年次ベースで10〜30年分作成
上記を行う際、金利は2025年9月の日本銀行短期プライムレート1.6%に対し、金融機関が上乗せする店頭変動金利2.3%前後を採用すると現実的です。また、金利上昇リスクを想定し、シミュレーション上は+1%のストレステストを行うと安心です。ストレスをかけても毎月のキャッシュフローがプラスなら、堅実な投資と判断できます。
さらに、10年後の売却シナリオも併せて試算しましょう。国土交通省「土地総合研究所」の将来予測では、都心5区の住居系地価は年平均0.5〜1.0%伸びが続くと見込まれますが、地方はマイナス予想です。売却益を当てにするのではなく、家賃収入だけで返済を完了できるかどうかを主要判断軸に置くと、景気変動に強いポートフォリオが構築できます。
収支計算を活かした物件選び
実は、数字を作っただけでは投資は成功しません。そのシミュレーション結果を基に、どのような立地や築年数の物件を狙うかが肝心になります。キャッシュフローが安定している物件は、利回りだけを見ると一見平凡でも、空室率や修繕費が低いケースが多いのが特徴です。東京都心の築浅ワンルームで表面利回り4%でも、実質利回りが3.5%を維持できるなら、築古高利回り物件より総キャッシュが多く残る可能性があります。
一方で、資金効率を高めたい場合は、地方中核都市のファミリータイプも選択肢です。総務省の住民基本台帳人口移動報告では、2024年から2025年にかけ転入超過となった政令市は12市あり、大学や工業団地の新設が家賃を底支えしています。ただし、将来の人口見通しが減少に転じる地点なのかを、自治体の長期人口ビジョンで確認しておくとリスクを抑えられます。
購入候補が見つかったら、作成済みの計算シートに数字を当てはめ、複数物件を横並びで比較します。返済比率、自己資金回収年数、累積キャッシュフローの曲線など、客観的な指標で順位付けすることで、感情に左右されない選択が可能になります。数字が語る事実を優先し、営業トークはエビデンスとして使う姿勢が、長期的な成功をもたらします。
まとめ
本記事では、収支計算に必要な数字の集め方から、家賃収入の見積もり、経費・減価償却の考え方、シミュレーション作成の流れ、そして物件選びへの応用までを順に解説しました。結論として、購入前に保守的な前提で10年以上のキャッシュフローを組み、金利上昇や空室リスクに耐えられる物件だけを選ぶことが、失敗を防ぐ最短ルートです。読者の皆様には、今日から実際の物件情報を数字に落とし込み、自分の投資基準を明文化する行動を取ることを提案します。そうすれば、景気や制度が変わっても揺るがない投資判断軸が手に入り、安心して資産形成への一歩を踏み出せるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 日本不動産研究所 賃貸住宅空室率調査 – https://www.reinet.or.jp
- レインズマーケットインフォメーション – https://www.reins.or.jp
- 日本銀行 短期プライムレート統計 – https://www.boj.or.jp
- 土地総合研究所 不動産価格予測レポート – https://www.reinet.mlit.go.jp

