空室が不安でアパート経営に踏み出せない、あるいは家賃下落で本当に利益が出るのか疑問に感じている人は多いでしょう。実は、基本のやり方を押さえるだけで収益性は大きく変わります。本記事では国土交通省の最新データや2025年度の制度をもとに、物件選びから資金計画、運営管理までを具体的に解説します。読み終えたころには、自分に合ったアパート経営の第一歩が明確になっているはずです。
アパート経営で収益を生む仕組み
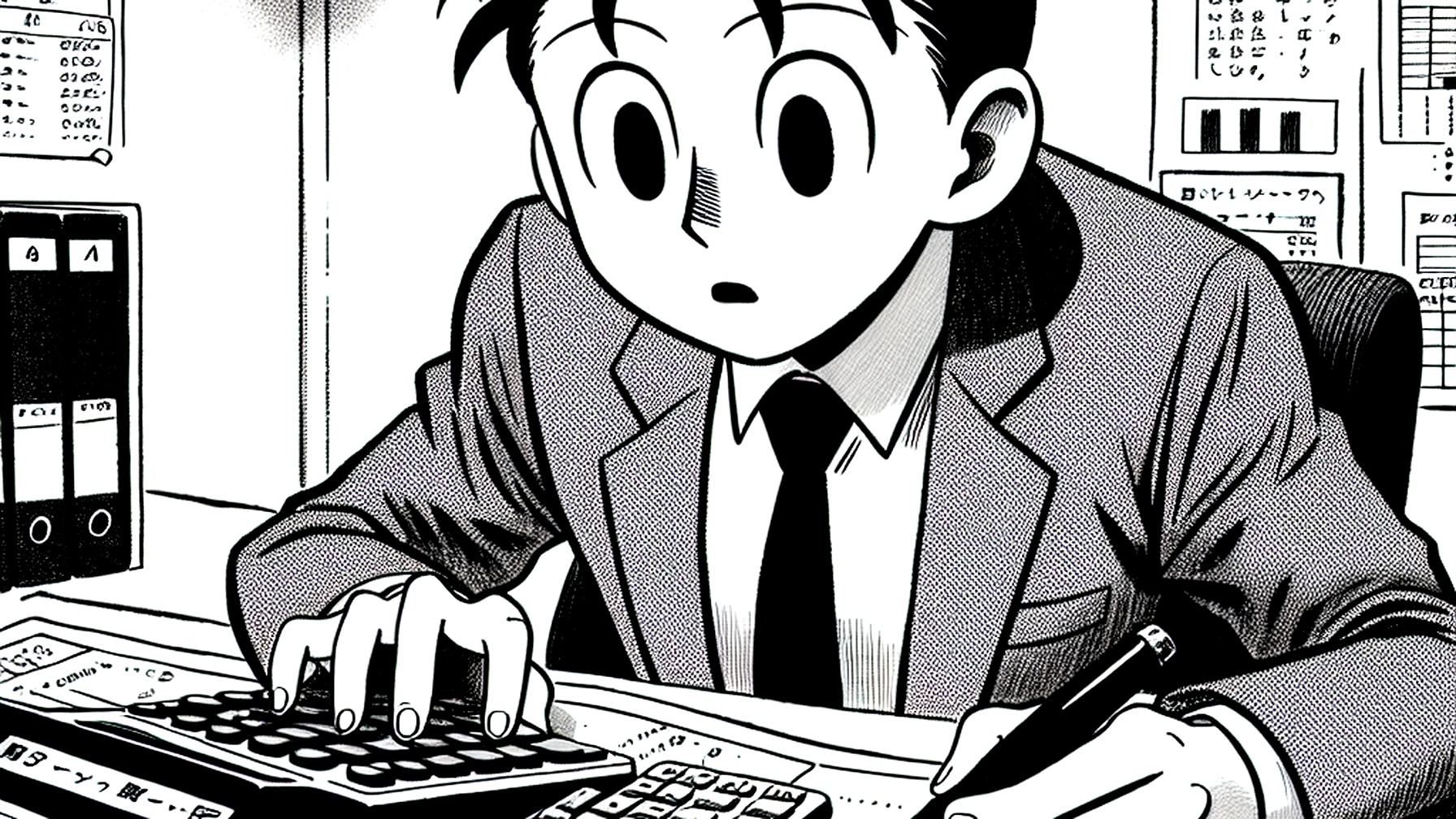
ポイントは、家賃収入から経費と返済を差し引いたキャッシュフローを正しく把握することです。見かけの利回りだけでは安全性を判断できません。
まず表面利回りは「年間家賃÷物件価格」で計算しますが、諸経費を含まないため実態とかい離しがちです。修繕費・管理委託料・固定資産税を加味した実質利回りこそ、収益性を評価する土台になります。また、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%(国交省)と依然二割を超えています。この数字を参考に、家賃収入の8〜10%は空室損失として見込むと保守的です。
次にローン返済です。現在の投資用アパート融資は固定1.8〜2.3%が主流で、変動より金利上昇リスクを抑えやすい状況です。返済比率(元利返済÷家賃収入)は50%以内に収めると、空室時の赤字を抑えやすくなります。
最後にキャッシュフローの指標として「年間手残り額÷自己資金」を計算すると、自己資金の回収速度が見えます。目安として5〜7年で自己資金を回収できる物件は、長期運用でリスク許容度を保ちやすいと言えます。
物件選びで差がつく収益性
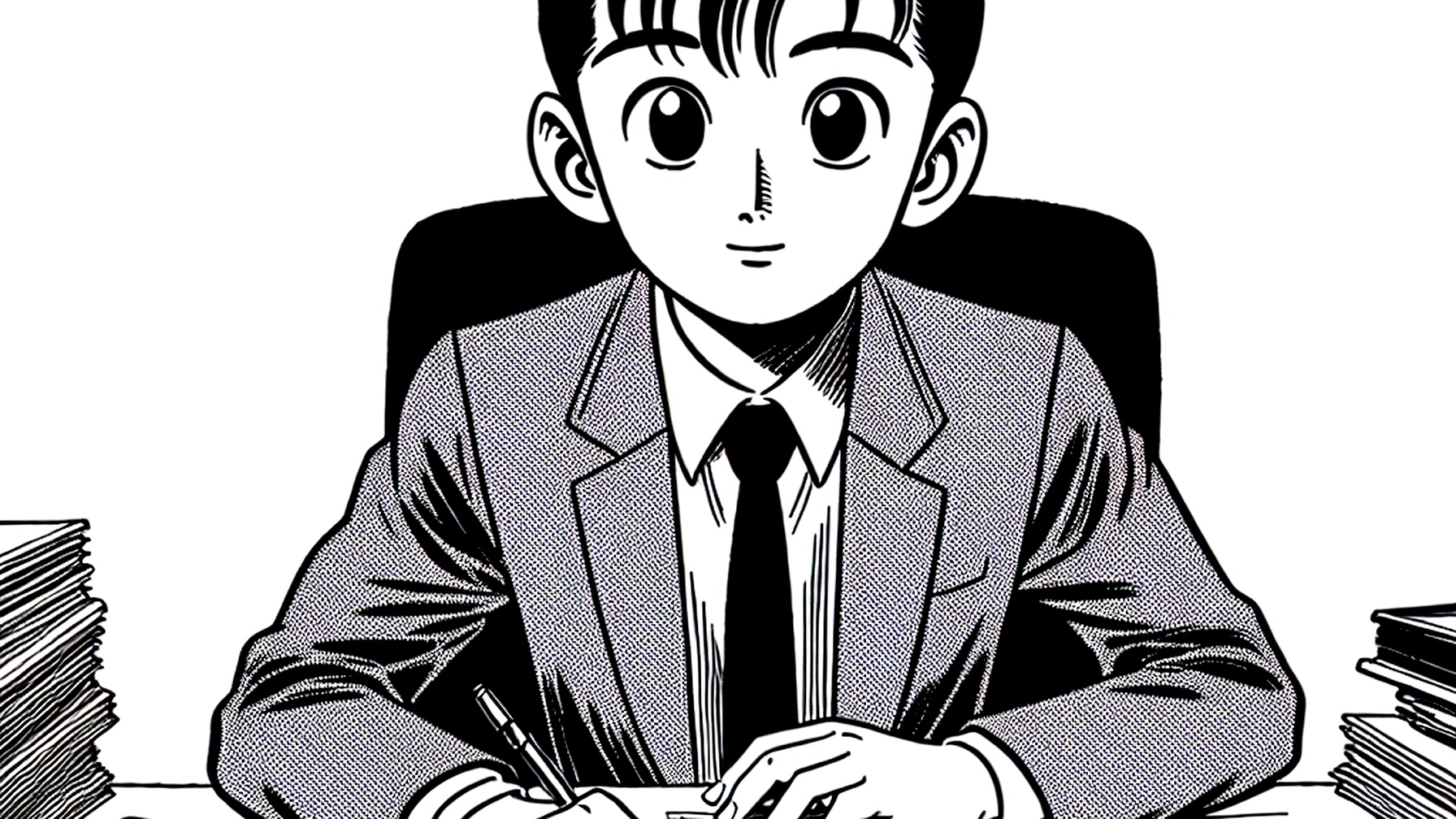
まず押さえておきたいのは、立地とターゲットの整合性です。同じ利回りでも需要層が異なれば実質空室率に差が出ます。
都心駅徒歩10分圏の築20年木造アパートは価格が高い反面、単身者需要が底堅く、3%台の利回りでも安定キャッシュフローを確保しやすいです。一方で郊外駅徒歩20分、築浅物件は見た目の利回りが7%でも、周辺人口が減少していれば空室が長引く可能性があります。つまり、数字と人口動態の両輪で判断することが肝要です。
2025年の総務省推計では、地方都市でもJR主要駅から徒歩15分以内のエリアは単身世帯がわずかに増加しています。このデータを参照し、駅近の中規模都市を狙う戦略は現実的です。また、大学近くのアパートは4月の入退去に偏るため、家賃を年間平均で見ると利回りが1ポイント下がる傾向があります。季節変動を織り込む姿勢が、大きな差を生みます。
建物構造も忘れがちな要素です。RC造(鉄筋コンクリート)は木造より修繕周期が長く、長期保有なら収益性が安定します。ただし取得価格が高いので、表面利回りが同じでも自己資金回収には時間がかかります。ライフプランと照らして選びましょう。
資金計画と融資戦略のやり方
実は、融資条件次第で収益性は大きく上下します。金利だけでなく、自己資金割合や融資期間も総返済額に影響します。
自己資金は物件価格の20〜30%を用意すると、地方銀行や信用金庫の審査を通りやすくなります。たとえば3,000万円のアパートを自己資金600万円、金利2.0%、期間25年で借りると、月返済は約12.7万円です。空室率10%を想定しても月の手残りは4〜5万円確保でき、年間で60万円のキャッシュフローとなります。
融資期間を30年に延ばすと月返済は11万円台に下がり手残りは増えますが、総返済額は200万円ほど増加します。金利上昇局面では長期固定の安全性が光るものの、利払いコストが膨らむ点を念頭に置きましょう。金利タイプ別にシミュレーションを行い、最悪シナリオでも自己資金が枯渇しないラインを確認してください。
さらに、金融機関はエリアや築年数で融資姿勢が変わります。築25年を超える木造は期間が15年に制限されるケースが多く、返済比率が高くなるため総合利回りが目減りします。このように物件属性と融資条件をワンセットで検討することが、堅実なやり方です。
運営管理で実現する長期安定収益
重要なのは、募集力と維持管理の質が空室期間を左右する点です。購入後の運営こそ収益性を決める核心部分と言えます。
管理会社を選ぶ際は、募集窓口の数と担当者の提案力を確認します。単に仲介店舗数が多いだけでなく、SNSやオンライン内見を活用しているかが2025年の集客では鍵です。国交省「賃貸市場動向調査」でも、オンライン内見導入物件の平均空室期間は47日で、非導入物件より9日短い結果が出ています。
維持管理では、築10年前後で必ず外壁と屋根の点検を行いましょう。50万円程度の小規模補修を先行して実施すると、大規模修繕を数年先送りでき、トータルコストが抑えられます。また、室内設備のうちエアコンと給湯器は10〜12年で交換時期を迎えます。入れ替えを先延ばしにすると募集競争力が落ち、実質利回りが低下するため注意が必要です。
入居者トラブルの早期対応も収益に直結します。騒音・ゴミ出し問題を放置すると退去連鎖が起き、空室率が上昇します。管理会社と週次で情報共有し、評判サイトの口コミを月1回確認するだけでも退去予防につながります。
税務と補助制度の最新ポイント
まず、2025年度も不動産所得は給与所得と損益通算が可能です。赤字が出た年は繰越控除で3年間相殺できるため、初年度に設備更新を集中させても税負担は抑えられます。
減価償却は築年数で耐用年数が短くなる中古アパートが有利です。木造築22年以上なら耐用年数は4年となり、経費計上を加速できます。ただし毎年のキャッシュフローは潤いますが、売却時の譲渡所得が膨らむので長期戦略を決めておきましょう。
2025年度の「賃貸住宅省エネ改修支援事業」は、断熱改修や高効率給湯器の設置費用の三分の一(最大120万円)を補助します。補助を受けるとエネルギー性能表示が可能になり、学生向けやファミリー層への訴求が強化されます。期限は2026年3月申請分までなので、来春の繁忙期を見据えて今秋から計画を立てるとよいでしょう。
加えて、地方自治体独自の空き家対策補助金を活用し、アパート一室をサテライトオフィスに転用する事例も増えています。用途変更により共用部改修費の一部を負担してくれる自治体があり、収益源の分散を図れる点が魅力です。制度は地域により異なるため、必ず市区町村の公式サイトで確認してください。
まとめ
ここまで、アパート経営の収益性を高めるやり方を立地選び・資金計画・運営管理・税務の四つの視点で整理しました。表面利回りにとらわれず実質キャッシュフローを試算し、金融機関と物件属性をセットで考えることが成功への近道です。さらに、管理品質と省エネ改修を通じた価値向上が長期安定収益を支えます。いま行動を起こせば、2030年代の人口減少局面でも競争力を保つ物件へ育てられるでしょう。まずは一物件を想定し、今回紹介したシミュレーションを実践してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 人口推計(2025年1月) – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 賃貸市場動向調査2025 – https://www.mlit.go.jp
- 環境省 賃貸住宅省エネ改修支援事業概要2025 – https://www.env.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート2025年6月 – https://www.boj.or.jp

