不動産投資に興味はあるものの、「利回りだけでなく税金対策まで考えるのは難しそう」と感じていませんか。特に堅牢なRC造(鉄筋コンクリート造)の物件は価格が高めで、初心者にはハードルが高い印象があります。しかし実は、RC造ならではの耐久性や減価償却期間の長さを上手く使えば、安定した家賃収入と節税の両立が可能です。本記事では、2025年9月時点で有効な税制を前提に、RC造物件の選び方から具体的な節税手法までを丁寧に解説します。読み終えるころには、数字に強くなくても自分でシミュレーションできるようになるでしょう。
RC造が選ばれる理由と市場動向
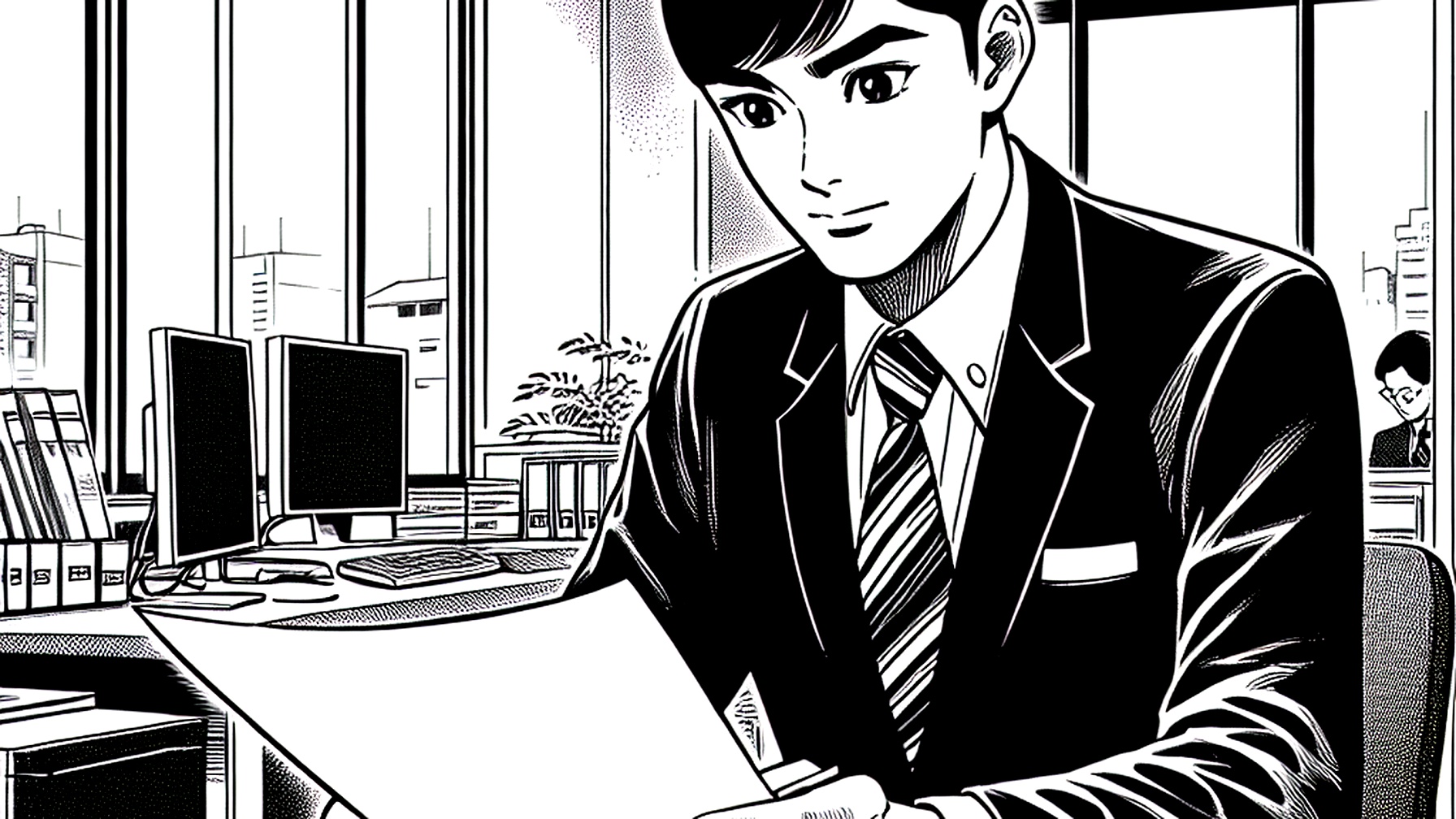
まず押さえておきたいのは、RC造が木造や鉄骨造に比べて市場でどのような位置づけにあるかという点です。国土交通省「住宅市場動向調査2024」によると、首都圏の新築賃貸マンションの約65%がRC造で、空室率は全構造平均より1.8ポイント低いと報告されています。つまり耐火性と遮音性が高いRC造は、賃料がやや高くても入居者から選ばれやすいのです。
一方で建築コストは木造の1.5倍前後になるため、表面利回りだけを見ると数字は見劣りします。しかし法定耐用年数が47年と長く、長期保有を前提にすれば資産価値の目減りが緩やかです。加えて高い耐久性が修繕費の変動を抑え、将来のキャッシュフローを安定させます。こうした特徴が金融機関の評価につながり、融資期間を長く取りやすい点も見逃せません。
さらに、人口減少が続く地方でも主要駅近くのRC造マンションは値下がり幅が小さい傾向があります。総務省統計局の「住宅・土地統計調査」では、築30年を超えるRC造の流通価格は築同年の木造比で平均25%高いという結果も出ています。立地と構造を組み合わせて長期の需要を見込める点がRC造最大の魅力と言えるでしょう。
RC造物件の節税メカニズムを理解する
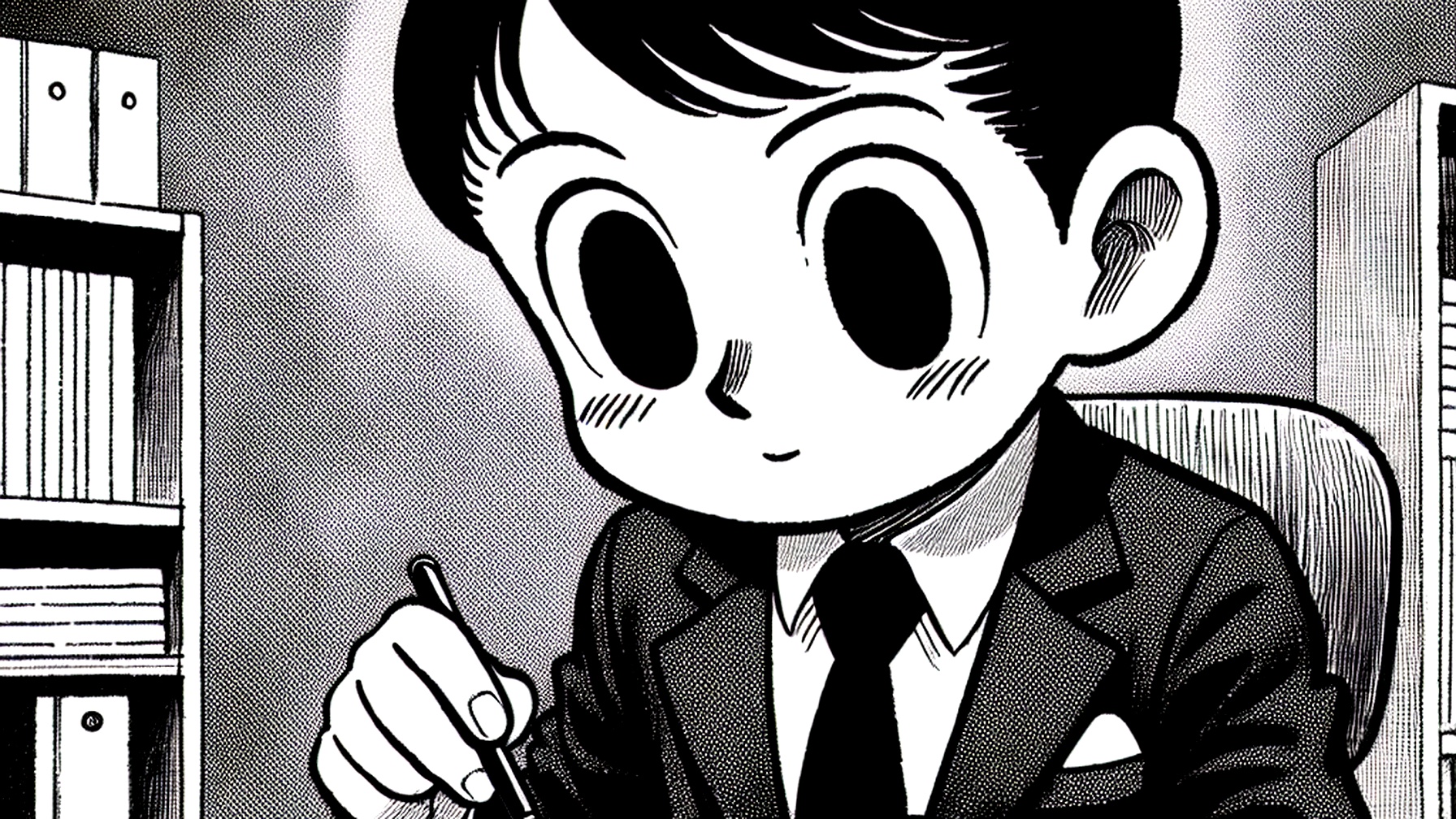
ポイントは、減価償却による所得圧縮効果を的確に利用することです。RC造の法定耐用年数は47年ですが、中古で購入した場合は「簡便法」により短縮できるため、取得年数が経過した物件ほど節税効果が高まります。たとえば築20年のRC造なら残存耐用年数は27年ですが、簡便法を使えば「47年−経過年数×0.2」で計算し、実務上は約14年で償却できます。償却費が大きくなる分、課税所得を圧縮しやすくなるのです。
また、青色申告特別控除65万円(2025年度現行)を活用すれば、経理をきちんと行うだけでさらなる節税が可能です。青色申告には複式簿記が求められますが、市販の会計ソフトを使えば作業は難しくありません。複数物件を所有する場合でも、経費と減価償却を正確に計上することで、損益通算の効果を最大化できます。
さらに、RC造の新築を法人で建てた場合には消費税還付の余地があります。賃貸経営は本来非課税売上ですが、建設時に課税売上を生む事業(たとえば駐車場運営)を組み合わせる方法が典型です。ただし、2024年から導入された適格請求書等保存方式(インボイス制度)により要件が厳格化されたため、還付狙いだけのスキームは実務的に難しくなっています。税理士と相談し、実態に即した運営計画を立てることが肝要です。
ファイナンスとキャッシュフローの計算方法
重要なのは、表面利回りではなく手取りキャッシュフローで判断する姿勢です。日本銀行「貸出・預金動向」(2025年8月速報)によれば、投資用不動産ローンの平均金利は変動型で年1.9%、固定型で年2.7%と依然低水準にあります。RC造は融資期間を30年以上確保できるケースが多く、元利均等返済なら毎月返済額を抑えながら長期のインカムゲインを享受できます。
具体的には、家賃収入から空室損・運営費・返済額・税金を差し引いた後に手元に残る現金を算定します。運営費は管理費や修繕費を含めて家賃収入の15%前後を見込むのが一般的です。国土交通省「賃貸住宅修繕費調査2024」では、RC造の平均修繕費は木造より年4万円/戸ほど高いものの、大規模修繕周期が長いためトータルコストはほぼ同水準と示されています。
シミュレーションでは、金利上昇リスクと空室率の悪化シナリオをあらかじめ織り込むことが大切です。たとえば空室率20%、金利上昇2%でもキャッシュフローがプラスであれば、保守的な計画として安心感があります。Excelやクラウドツールで複数シナリオを作成し、最悪ケースで自己資金が枯渇しないかを確認しましょう。
節税効果を高める運用テクニック
まず収益と経費のタイミングをコントロールすることで、税負担を平準化できます。代表例は決算期の変更です。法人を3月決算から12月決算に変えるだけで、繁忙期の退去が多い3月の原状回復費を当期経費に計上しやすくなります。また、長期修繕計画を作り、損金算入できる修繕と資本的支出を区分すれば、節税と物件価値維持を同時に達成できます。
一方で、減価償却が終了したあとに節税メリットが薄れる点は見逃せません。その対策として、築年数の異なる複数物件を段階的に購入し、償却期間をずらす方法が有効です。こうすれば毎年の償却費が平準化され、所得のジャンプを避けられます。加えて、2025年度も継続する小規模企業共済やiDeCoを併用すれば、家賃所得が増えても全体の税率を下げやすくなります。
RC造ならではの運用として、屋上や共用部を太陽光発電に転用し、売電収入を得ながらグリーン投資減税(2025年度〜2027年度)を受ける方法もあります。この制度では、適合設備を取得し即時償却または税額控除5%の選択が可能です。環境性能が高まれば入居者の満足度も向上し、結果として空室対策にも寄与します。
2025年度の税制と活用できる制度
実は2025年度税制改正で、不動産所得の損益通算に大きな変更はありませんでした。そのため、赤字を給与所得と通算できる現行ルールが維持されています。ただし、高額所得者を対象にした「上限1,000万円控除見直し」が検討段階にあるため、将来の改正動向には注意が必要です。
一方で、住宅性能向上計画認定マンションへの固定資産税減額措置は、2025年度も新規認定から5年間、税額が1/2になる特例が継続しています。RC造で長期優良住宅の認定を受ければ、ランニングコストを抑えつつ入居者へのアピールポイントにもなります。新築を検討する際は、設計段階で省エネ基準適合と認定取得費用を織り込むとよいでしょう。
2025年度から導入された「賃貸住宅断熱改修促進補助金」も見逃せません。一定の省エネ基準を満たす外壁改修に対し、工事費の1/3(上限300万円)が補助されます。既存RC造の外壁塗装やサッシ交換と合わせて申請すれば、実質的な修繕費を抑えながら資産価値を高められます。補助金は年度予算に限りがあり、申請受付は2026年3月末までの予定です。
まとめ
RC造による不動産投資は、耐久性と金融機関からの高い評価を武器に、長期安定経営と節税を両立できる方法です。減価償却の活用、適切なファイナンス、そして最新の税制・補助金を組み合わせれば、表面利回り以上の手取りキャッシュフローを実現できます。まずは中古RC物件の収支シミュレーションを作り、青色申告やグリーン投資減税などの制度を最大限に活用しましょう。行動を起こした人だけが、時間とともに得られる複利のメリットを享受できます。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2024 – https://www.mlit.go.jp/report_jutakudoukou2024
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.html
- 国土交通省 賃貸住宅修繕費調査2024 – https://www.mlit.go.jp/report_shuzen2024
- 日本銀行 貸出・預金動向 時系列データ – https://www.boj.or.jp/statistics/dl/depo/
- 国税庁 所得税基本通達 令和6年版 – https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/令和6年版/

