円安が続くと輸入品の値上がりや海外投資マネーの流入など、経済全体にさまざまな影響が生まれます。不動産投資を考える人の中には「円安は賃料収入にプラスでは?」と期待する声もありますが、実はデメリットも少なくありません。本記事では、円安時代における不動産投資の代表的なリスクを整理し、その背景をデータに基づいて解説します。あわせて、初心者でも取り組める対策まで紹介するので、最後まで読むことで“見落としがちな落とし穴”を避けやすくなります。
円安が投資家に与える基本的な影響
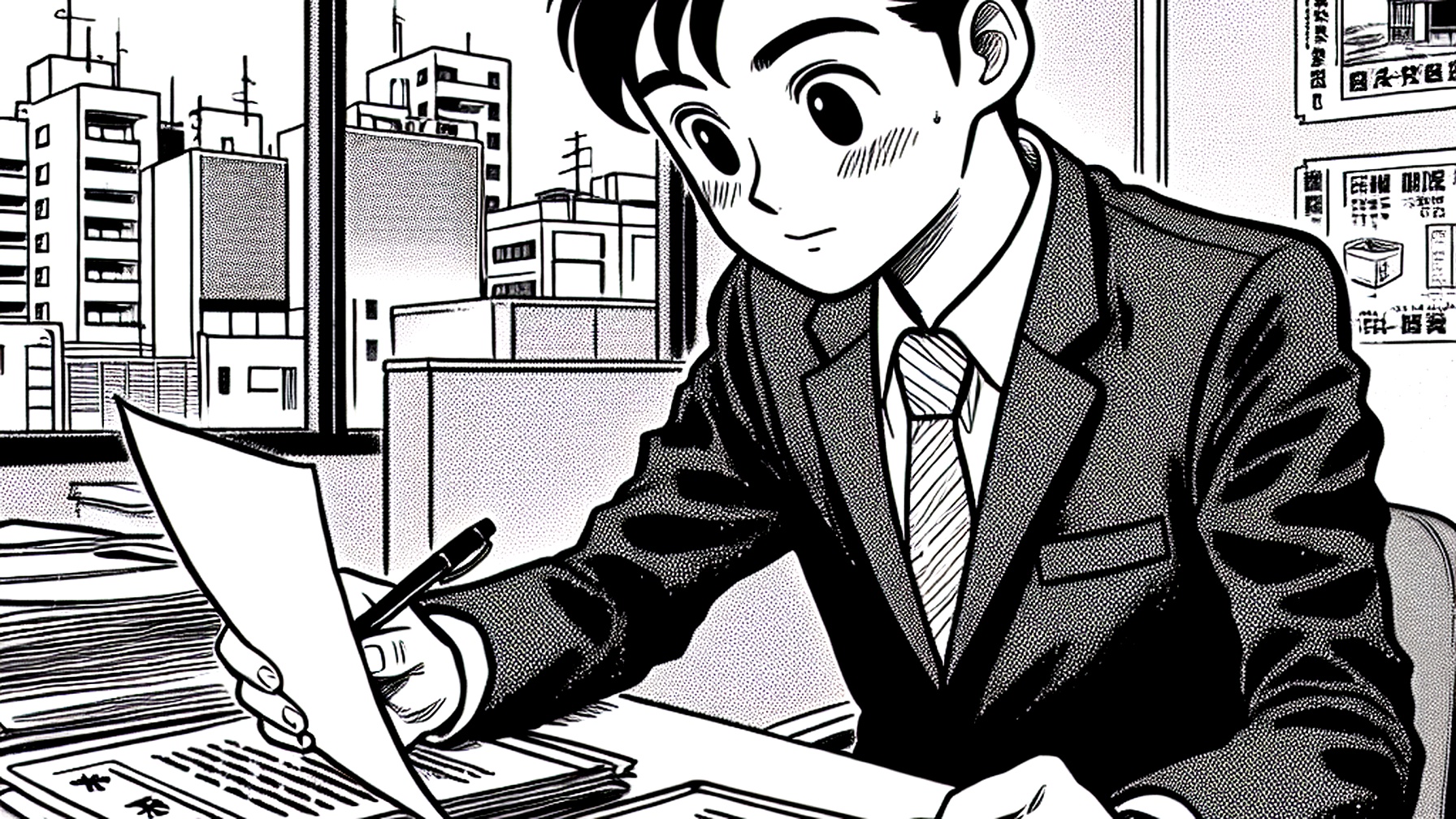
まず押さえておきたいのは、円安によって外国人投資家が日本の不動産を割安に感じやすくなる点です。財務省の為替統計によれば、2024年末から2025年夏にかけて円は対ドルで約20%下落しました。海外資金の流入自体は物件価格の押し上げ要因となりますが、国内投資家にとっては仕入れ価格の高騰を招きやすく、利回りの低下に直結します。
さらに、円安はエネルギーや資材の輸入コストを押し上げるため、建築費や修繕費の上昇を招きます。国土交通省の建設物価調査でも資材価格は2023年比で約12%上昇しており、賃料が同じ水準でもキャッシュフローが縮小しやすくなります。つまり、円安は「入口(購入価格)」と「出口(維持コスト)」の両面で国内投資家を圧迫するのです。
一方で、インバウンド需要の増加を背景に短期賃貸やホテル運営が好調という声もあります。しかし、都市計画法や旅館業法の規制強化が進む今、物件用途を変更するには行政手続きや追加投資が不可欠です。楽観的な収益予想だけで参入すると、規制コストを見落として計算外の赤字を抱えるリスクがあります。
資材価格の高騰がもたらすコスト増
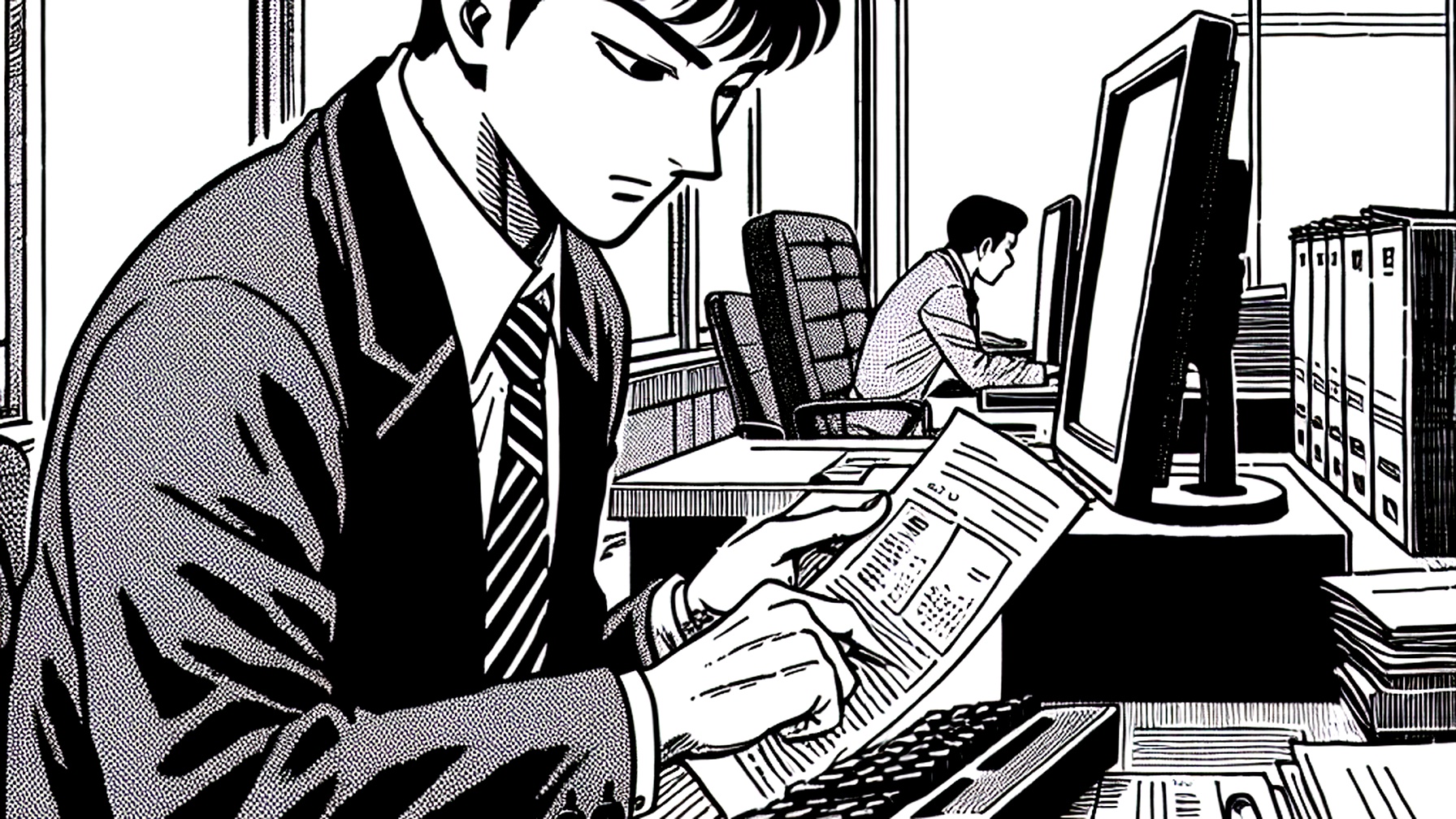
重要なのは、円安と同時進行で世界的な資源価格高騰が続いている点です。日本銀行の「企業物価指数」によると、2025年4月時点で建築用鋼材は前年同月比9.8%の上昇となりました。新築や大規模修繕の見積もりは数年前より数百万円単位で膨らむケースが目立ち、想定利回りを大きく削る要因になっています。
修繕積立金を十分に確保していない区分マンションでは、突発的な工事費の支払いが区分所有者に一括請求されることも珍しくありません。また、木造アパートでは屋根や外壁の塗装費が10年前の1.5倍近くに高騰し、家賃が伸び悩むエリアではオーナーの持ち出しが増えやすい状況です。
言い換えると、円安時代の不動産投資は「保有コストをどうコントロールするか」が生き残りの鍵になります。新規購入だけでなく、既存物件の長期修繕計画を精査し、資材価格の変動シナリオを複数用意する姿勢が欠かせません。修繕費の見積もりを複数社から取り、値上げリスクを分散させることも有効です。
金利とインフレがキャッシュフローを圧迫
実は、円安が続くと日本でも長期金利がじわじわ上昇しやすくなります。2025年6月の日本銀行・長期国債利回りは1.1%台まで上昇し、10年固定型住宅ローン金利も平均1.75%前後に達しました。わずか0.3%の金利上昇でも、3000万円を25年返済で借りた場合の総返済額は約130万円増える計算です。
また、円安は輸入物価を押し上げ、消費者物価指数(CPI)にも波及します。総務省の統計では2025年7月時点のCPI上昇率が4.1%となり、光熱費や生活必需品の値上げが家計を直撃しました。家賃の引き上げ交渉が難しい賃貸市場では、実質的な手取りが目減りし、空室率が上がる懸念が高まります。
ポイントは、金利とインフレが同時に進むと「家賃は上げにくいのに返済と運営コストが膨らむ」というサンドイッチ状態が生じることです。ストレス耐性を高めるためには、元利均等返済より元金均等返済を選ぶ、あるいはフラット35S(2025年度)の省エネ金利引き下げを活用して固定コストを下げるなど、保守的な資金計画が求められます。
外国人投資家との競合リスク
円安時代には海外ファンドや個人富裕層が日本の不動産市場に積極参入します。JLLの市場レポートによると、2024年の外国人投資額は前年比35%増となり、特に都心Aクラスオフィスビルと宿泊施設に資金が集中しました。人気エリアの価格上昇は国内投資家の参入障壁を高めるだけでなく、地方物件にも波及し利回りの目減りを招きます。
さらに、外国人投資家は自己資金比率が高いため、価格交渉でも優位に立ちやすい特徴があります。融資を前提とする国内個人投資家は、取引スピードと条件面で後れを取りやすく、結果として競り負けるリスクが高まります。物件を確保できたとしても、購入価格が割高になると、出口戦略で想定益を出しにくい点が悩ましいところです。
そこで、情報の鮮度と仲介ネットワークの質が勝敗を分けます。オンライン物件データだけでなく、管理会社や金融機関との連携を通じて未公開情報を早期に得る工夫が欠かせません。また、短期的な価格競争が激しい都心部だけにこだわらず、人口減少が緩やかな政令指定都市近郊や、再開発計画が進む準都心エリアに目を向ける戦略も有効です。
デメリットに負けないための具体的対策
まず、キャッシュフローの安全余裕を確保するために、自己資金比率を30%以上へ引き上げるとともに、運営開始後6か月分の返済・運営費を現金で確保しておくことが理想的です。この“緩衝地帯”が金利上昇や空室のダメージを吸収します。
次に、資材高騰対策として長期修繕計画の見直しを行い、屋根や外壁など寿命が読める部位は早めに契約し、固定単価で発注しておくとコストの読みやすさが向上します。加えて、2025年度の「省エネ適合住宅補助金」(戸当たり最大60万円、2026年3月交付申請期限)は断熱改修や高効率給湯器の導入に使えるため、光熱費削減と資産価値向上を同時に狙えます。
さらに、収益源の多角化としてサブリースや民泊に飛びつく前に、自治体の用途規制や旅館業法の手続きコストを必ず精査してください。必要書類や設置基準を満たす改修費が賃料アップ幅に見合うかどうか、シミュレーションで確認する姿勢が重要です。
最後に、為替リスクをヘッジする選択肢として外貨建てローンや為替予約を組み合わせる方法があります。ただし、為替の読み違いは逆にコストを膨らませるため、専門家と相談しながら適切な期間・額を設定しましょう。
まとめ
円安時代の不動産投資は「価格上昇で売却益を狙える」というメリットが強調されがちですが、実際には仕入れ価格の高騰、資材費と金利の上昇、外国人投資家との競合など多面的なデメリットが存在します。重要なのは、これらのリスクを事前に数値化し、自分の資金力とリスク許容度に合った手を打つことです。自己資金比率を高め、修繕計画を精査し、補助金や固定金利を活用することで、円安による圧迫をかなり緩和できます。今日からできるのは「現状のキャッシュフローを洗い出し、金利1%上昇でも耐えられるか」を確認することです。早めの対策が、数年後の安定収益につながります。
参考文献・出典
- 財務省 – https://www.mof.go.jp
- 日本銀行 企業物価指数 – https://www.boj.or.jp/statistics
- 国土交通省 建設物価調査 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 統計局 消費者物価指数 – https://www.stat.go.jp
- 住宅金融支援機構 フラット35金利情報 – https://www.flat35.com
- JLL Japan 不動産投資市場レポート – https://www.joneslanglasalle.co.jp

