親や祖父母からの資産をどう受け継ぐかは、多くの家庭にとって切実なテーマです。相続税の負担を抑えつつ、家族へ安定収入も残したい――そんな願いをかなえる方法の一つが「相続対策 マンション投資 中古」です。本記事では、相続のしくみから節税効果、物件選び、2025年度の最新制度までを丁寧に解説します。読み終えるころには、初心者でも中古マンション投資を使った相続対策の基本戦略が理解できるはずです。
相続と中古マンション投資の基本を押さえる
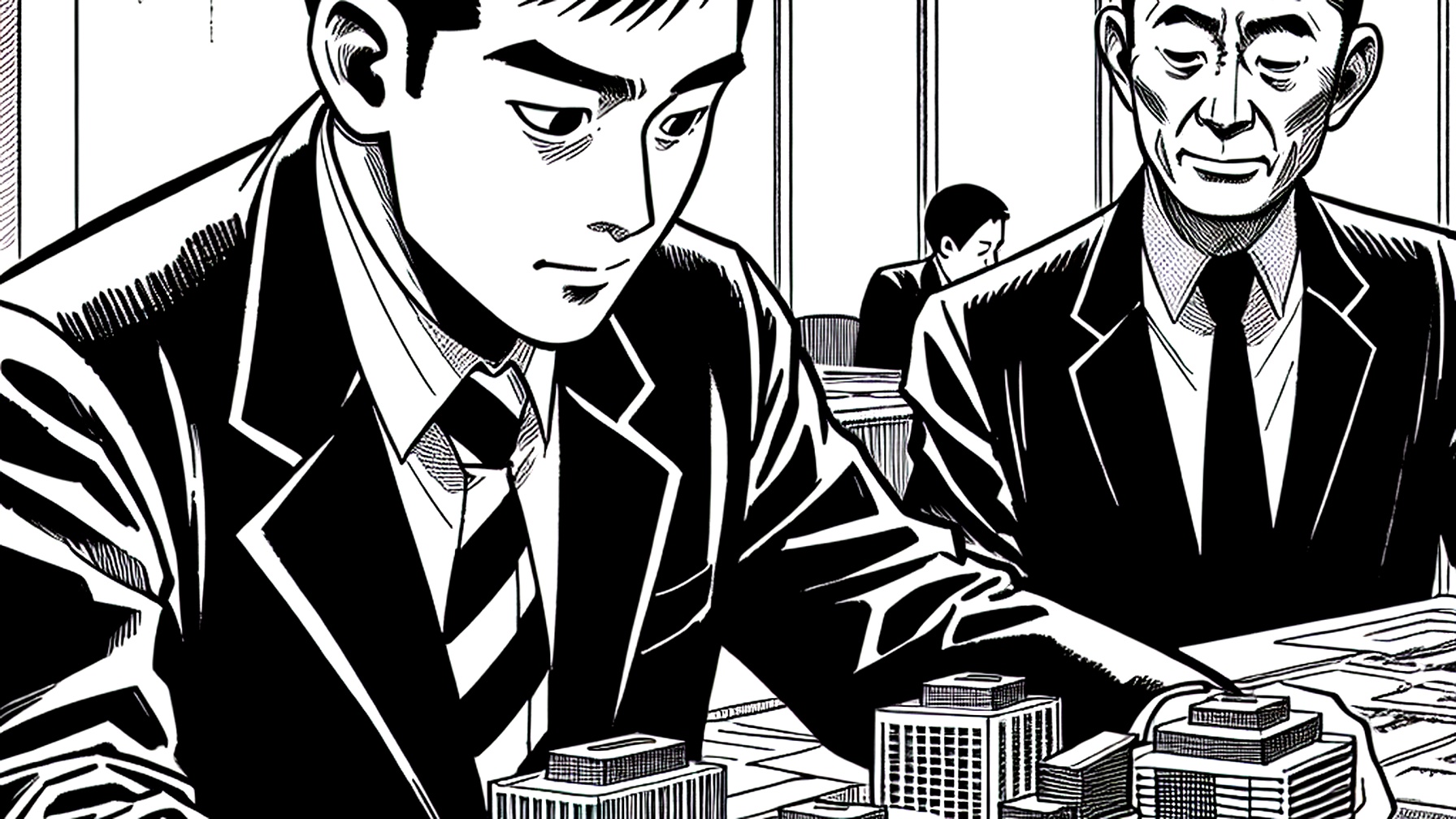
まず押さえておきたいのは、相続税は現金より不動産のほうが評価額を下げやすいという点です。不動産は「路線価」や「固定資産税評価額」で算定され、市場価格の70〜80%になるケースが一般的です。つまり、同じ1億円でも現金で持つより中古マンションで保有したほうが課税対象額が小さくなります。
一方で、新築より中古を選ぶ利点は、物件価格がすでに下落局面を経ているため、購入後の価値変動リスクが抑えられる点にあります。築20年程度の都心ワンルームなら、建物部分の減価償却も進んでおり、家賃と価格のバランスが安定しています。その結果、キャッシュフロー(手取り収支)が読みやすく、長期保有にも耐えやすい資産になるわけです。
国税庁の統計によると、2023年度の相続財産に占める不動産の割合は46.4%でした。相続対策として不動産を活用する世帯が多いのは、こうした評価額圧縮のメリットが大きいからです。中古マンションであれば、購入時点で実勢価格が明確になり、金融機関の融資審査でも想定賃料を提示しやすい点が評価されています。
節税メリットを最大化するしくみ
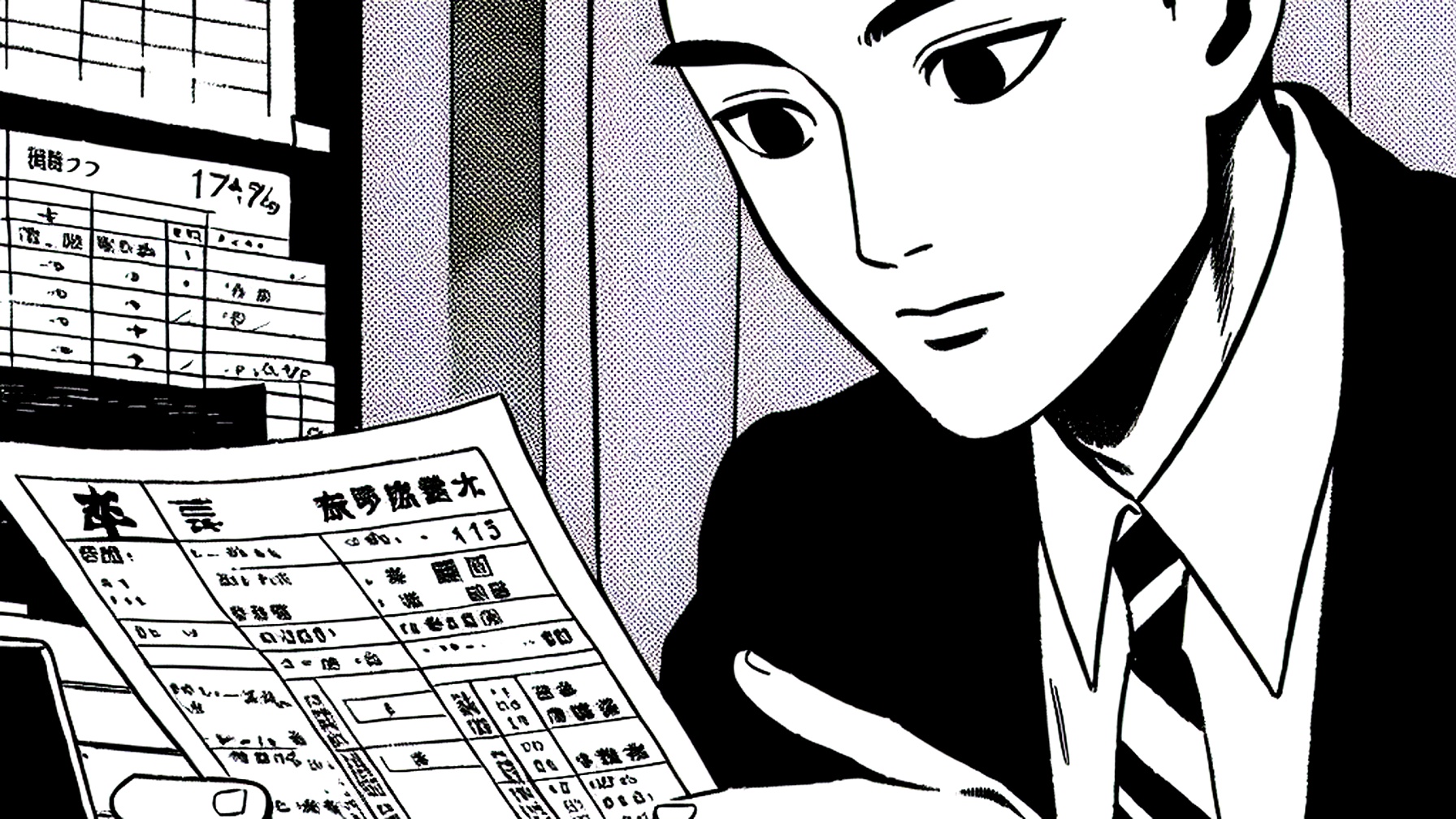
重要なのは、評価額を下げるだけでなく、所得税や住民税も軽減できる点です。中古マンションの建物部分は残存耐用年数を基に短期間で減価償却できます。例えば、鉄筋コンクリート造(法定耐用年数47年)の築25年物件を取得した場合、残存耐用年数は「47年−経過年数×0.2」の簡便法を使うと、おおむね9年となります。この9年で建物価格を償却できるため、年間の不動産所得を圧縮し、給与所得と損益通算することが可能です。
また、相続発生後に子どもへ収益を分散させる「共有持分移転」も効果的です。生前に持分を少しずつ贈与すれば、年間110万円の基礎控除枠を使い、贈与税負担を抑えられます。そのうえで、家賃収入を共有者間で按分すれば、所得税も世帯全体で平均化できます。ただし、持分が複雑になると売却時に全員の同意が必要になるため、贈与のタイミングと比率を慎重に設計することが欠かせません。
2025年度も引き続き、相続税の「小規模宅地等の特例」は自己居住用宅地に限り適用され、賃貸マンションには認められません。したがって、賃貸用不動産では評価減と減価償却を組み合わせて節税効果を高める戦略が主流になります。税理士と連携し、取得前から相続発生後までのシミュレーションを行うことが、結果的に最も大きな節税につながるでしょう。
資産評価とキャッシュフローのバランス
ポイントは、節税ばかりに目を向けてキャッシュフローを軽視しないことです。国土交通省「不動産価格指数」によると、築20年前後の区分マンション価格は過去10年で年平均2%程度の上昇にとどまっています。一方、東京23区の平均家賃は同期間で年1.4%ペースで上昇しました。つまり、価格の伸びより家賃収入の安定度が中古物件の魅力と言えます。
キャッシュフローを測るうえで注目したい指標が「実質利回り」です。家賃収入から管理費、修繕積立金、固定資産税などを差し引き、購入総額で割った数字が目安となります。都心の築20年ワンルームなら4.0〜4.5%、地方中核都市では6%前後が目標です。金融機関の融資金利が2025年現在で1.2%台と低水準にあるため、この利回りでも月々の手取りは十分プラスになりやすい構造です。
ただし、空室リスクや大規模修繕費を見落とすと収支が急変します。空室率は保守的に10%で試算し、入退去時の原状回復費用も1回につき家賃の1〜2か月分を見込むべきです。また、築30年を超えるとエレベーターや配管更新が現実味を帯び、1戸あたり数十万円の負担がかかることがあります。あらかじめ長期修繕計画書を確認し、積立金不足がないかチェックすることが欠かせません。
失敗しない物件選びと運営のポイント
実は、相続対策を目的とする場合でも、空室が出にくい立地は最優先事項です。JR・地下鉄駅から徒歩7分以内、商業エリアまで30分圏内、昼夜の人口推移が安定している地域を選ぶと、家賃下落と空室を同時に抑えられます。総務省「住民基本台帳人口移動報告」では、若年単身層の都心回帰が続いており、東京都心三区・大阪中心部・名古屋駅周辺などは依然として転入超過が顕著です。
中古マンションでは「管理組合の健全性」が資産価値を左右します。管理費・修繕積立金の延滞率が5%以内、総会の出席率が50%以上なら運営が安定しているサインです。また、長期修繕計画が12年先まで詳細に記載されている物件は、金融機関の評価も高く、融資期間を延ばしやすくなります。融資期間が長いほど月々の返済負担が軽くなり、キャッシュフローも厚くなります。
運営面では、家賃を1年ごとに見直す柔軟性が欠かせません。新築との差別化として、宅配ボックス設置や高速インターネット導入など、10万円前後の設備投資で空室期間を短縮できる事例が多数あります。少額でも効果的なアップグレードを毎年行い、競合物件と差を付けることで、長期保有時の収益安定につながります。
2025年度の法制度と金融環境を読む
まず、2025年度税制改正では相続税の基礎控除枠(3,000万円+600万円×法定相続人)は維持される見通しです。したがって、中古マンション投資による評価減メリットは引き続き有効です。また、国土交通省が推進する「住宅省エネ改修補助金」は2025年度も継続し、築20年以上のマンションで省エネ性能を高める改修工事に対して最大60万円が支給されます。リフォーム費用を抑えつつ、資産価値を上乗せできる好機と言えます。
金融面では、金融庁の報告によると地方銀行の投資用不動産向け融資残高は微増傾向にあり、審査基準も安定しています。一方で、返済比率(年間返済額÷年間賃料収入)は原則50%以下を求める銀行が増えました。つまり、利回りが低すぎる物件では融資期間が短くなり、キャッシュフローが圧迫される恐れがあります。購入前に金融機関と事前相談し、返済比率と融資期間のバランスを確かめることが肝心です。
加えて、インボイス制度導入に伴い、課税事業者を選択するオーナーも増えています。賃貸住宅の家賃は非課税ですが、共用部分の電気料や広告費など仕入れ税額控除を活用できる場合があるため、課税・免税の損益分岐を税理士と試算すると良いでしょう。制度や補助金は毎年更新されるため、2025年9月時点の情報に基づき、取得後も継続的に確認する姿勢が求められます。
まとめ
この記事では「相続対策 マンション投資 中古」をテーマに、評価額圧縮のしくみ、キャッシュフロー管理、物件選び、2025年度制度までを解説しました。評価額を下げて相続税を抑えるだけでなく、安定収入を得ながら家族に資産を残せるのが中古マンション投資の強みです。まずは信頼できる税理士と資金計画を練り、立地と管理状態に優れた物件を丁寧に選びましょう。小さく始めて経験を積めば、将来の相続も家計も安心感が大きく高まります。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.stat.go.jp
- 金融庁 金融機関向け資料 – https://www.fsa.go.jp

