不動産投資の初心者が最初に悩むのは、「物件選びよりも前に利回りをどう考えればよいのか」という疑問ではないでしょうか。数字の意味を正しく理解しないまま購入を急ぐと、予定より手残りが少なく後悔するケースが後を絶ちません。本記事では、利回りを見るときに「何を」確認すべきかを基礎から解説します。読み終える頃には、表面利回りと実質利回りの違い、公的データの探し方、そして利回りを高める具体策まで俯瞰できるようになります。
利回りを語る前に押さえたい基本用語
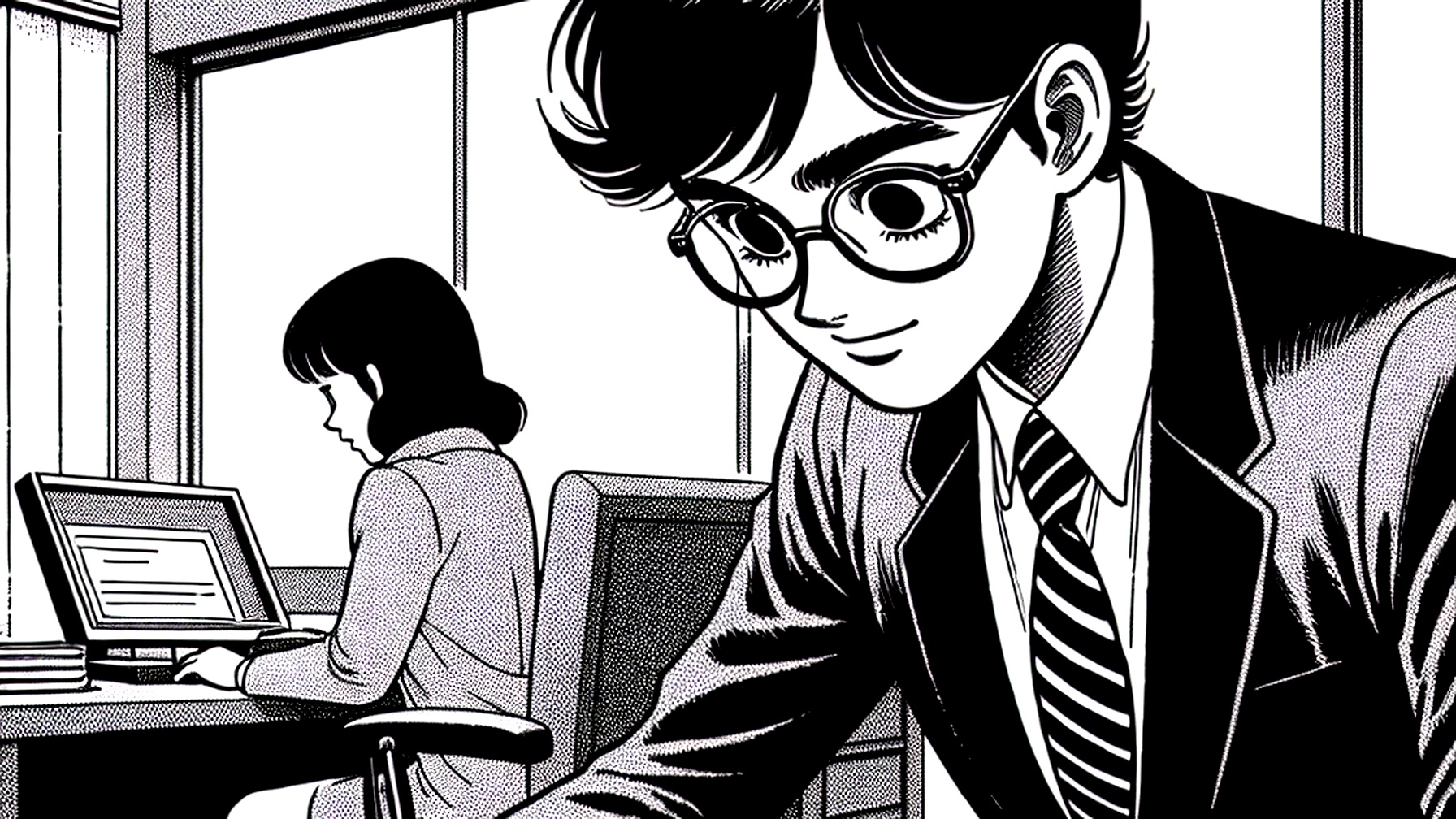
まず押さえておきたいのは、利回りという言葉が複数の計算式を含む点です。一般的に広告で大きく表示されるのは「表面利回り」で、年間家賃収入を物件価格で割っただけの単純な指標です。しかし管理費や修繕費、空室期間などのコストは考慮されていません。そのため投資判断を誤らないよう、表面利回りの裏にある前提条件を必ず確認する習慣が求められます。
次に、「実質利回り」という用語を理解することが重要です。これは表面利回りから諸費用を差し引き、実際に手元に残るキャッシュフローを反映させた指標です。金融機関の返済額や固定資産税まで入れる場合もあり、計算方法にばらつきがある点に注意が必要です。言い換えると、実質利回りこそ投資家が本当に気にすべき「現実の収益率」を示します。
最後に、利回りは市場環境で大きく変動する事実を覚えておきましょう。日本不動産研究所の2025年9月調査によると、東京23区の平均表面利回りはワンルーム4.2%、ファミリータイプ3.8%、木造アパート5.1%でした。数字だけを見るとアパートが魅力的に感じますが、木造は修繕費がかさむ傾向があるため、単純比較は禁物です。
表面利回りと実質利回りを見分けるコツ
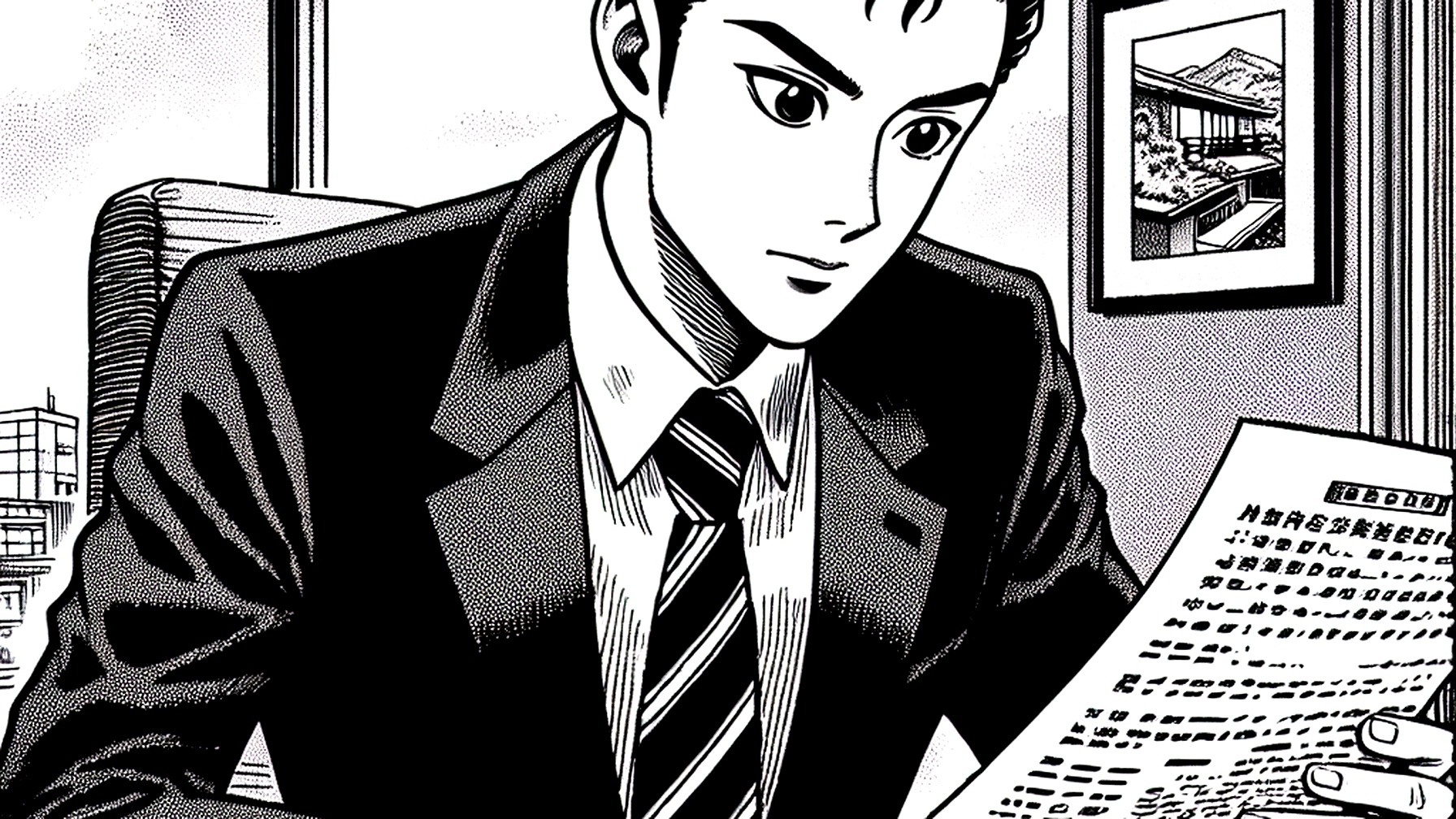
重要なのは、表面利回りと実質利回りの差額がどの程度かを把握することです。差が大きい物件ほど、広告に隠れたコスト負担が大きいと推測できます。たとえば表面利回り7%と表示されていても、実質利回りが4%しかない例は珍しくありません。この差を埋める作業が購入前のデューデリジェンス(詳細調査)です。
まず、家賃の下落リスクを見積もる必要があります。築年数が経過すると賃料が年間2〜3%ずつ下がるエリアもあります。国土交通省「賃貸住宅市場景況調査」によれば、2024年から2025年にかけて築20年超物件の平均賃料は1.8%下がっています。将来の賃料を保守的に見積もることで、実質利回りのブレ幅を小さくできます。
次に、空室率を想定しましょう。東京23区でも平均空室率は4〜5%ですが、ワンルームの供給過多地域では10%を超える区もあります。実際の計算では、空室期間を年間で0.5〜1か月分差し引くと現実的です。これにより、利回り8%の広告でも実際は6.5%程度になることが見えてきます。
また、経年劣化による大規模修繕費も忘れがちなコストです。マンションなら長期修繕計画、アパートなら外壁塗装や屋根防水を10〜15年ごとに実施するとして、年間家賃収入の5〜7%を積み立てる試算が一般的です。これを含めて計算すれば、実質利回りはさらに0.5〜1ポイント下がることが多いです。
家賃収入を左右する四つの要素
ポイントは、利回りを構成する家賃収入が四つの要素に左右される点を理解することです。第一は立地で、駅徒歩時間や商業施設の数が賃料の天井を決めます。第二は物件の間取りと専有面積で、ターゲット層に合っているかが鍵となります。第三は建物の築年数と管理状態で、汚れた共用部は即座に賃料下落につながります。第四は周辺の競合物件数で、同種住戸が多ければ家賃は下がる傾向が強まります。
立地について具体例を挙げると、東京都心五区の駅徒歩5分圏では、築10年未満ワンルームの平均賃料が月11万円前後です。一方で同じ築年数でも駅徒歩10分を超えると9万円台へ下がります。この差は年間で24万円となり、表面利回りに換算すると0.5〜0.7ポイントの差異が生じます。
間取りも侮れません。単身者向けワンルームで25平方メートル未満の部屋は、30平方メートル前後の部屋に比べ退去率が高い傾向があります。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の統計では、20〜25平方メートル帯の平均入居期間は2.6年、25〜30平方メートル帯は3.4年でした。入退去コストが増えれば実質利回りがさらに下がるため、面積は数字以上に重要です。
周辺競合については、自治体の公開している都市計画図や総務省の住宅・土地統計調査を活用すると精度が上がります。将来の新築供給を把握すれば、賃料下落を事前に読めるため、利回りの長期安定に寄与します。
投資家が活用すべき公的データと金融商品の動向
実は、利回りを見極める材料は公的機関に多く存在します。国土交通省の「不動産取引価格情報」は、近隣の成約事例を地図上で確認でき、周辺水準と比べて家賃が割高か判断できます。また総務省の「住宅・土地統計調査」では、人口推移や世帯構成を把握でき、将来需要の予測に役立ちます。これらを活用すれば、広告の利回り数字が適正かどうか根拠を持って検証できます。
金融機関の融資条件も利回りに直結します。2025年9月時点で、主要地方銀行の投資用ローン金利は変動で年2.1〜3.0%が主流です。金利が1%上昇すると返済負担が年間およそ30万円(借入3000万円・残期間25年の場合)増えるため、実質利回りは0.7ポイント程度低下します。固定か変動かは自身のリスク許容度と合わせて選択しましょう。
さらに、2025年度も継続している「住宅ローン減税(投資用物件は対象外)」との混同に注意が必要です。制度を誤解して利回り試算にメリットを含めてしまうと、実績と乖離します。公的優遇策を検討する際は、投資用で適用されるかどうかを必ず金融機関に確認してください。
利回りを高める運用と出口戦略
まず押さえておきたいのは、購入後の運用次第で利回りを上げる余地が残されていることです。代表的なのはリフォームによる家賃アップです。築15年のワンルームに10万円の照明と壁紙を追加しただけで月額賃料が2000円上がる例があります。年間で2万4000円、投資回収は5年以内となり、利回りが0.3ポイント改善します。
次に、管理会社の見直しも効果的です。管理手数料を家賃の5%から3%へ下げられれば、年間家賃収入600万円の場合で12万円のコスト減になります。これは実質利回りを0.2ポイント押し上げる計算です。複数社に見積もりを取り、サービス内容と費用のバランスを比較しましょう。
出口戦略も利回りに匹敵する重要事項です。売却時に想定より高く売れれば、総合的な投資利回り(IRR)が向上します。2025年時点で都心区分マンションの平均売買価格は3年前より7%上昇していますが、郊外は横ばいです。購入時に再販需要の高いエリアを選ぶことで、キャピタルゲイン(売却益)とインカムゲイン(家賃収入)の両取りが狙えます。
最後に、保有期間中の借り換えも検討の価値があります。金利が0.5%下がるだけで、3000万円残高なら年間およそ8万円の利息削減となり、実質利回りを0.2ポイント以上改善します。金融機関のキャンペーン情報を定期的にチェックしておくと好機を逃しません。
まとめ
本記事では「利回り 不動産投資 何を」確認すべきかを中心に解説しました。表面利回りはあくまで目安であり、空室率や修繕費を加味した実質利回りこそ判断の基準となります。立地や間取り、金融機関の条件、公的データの活用など多面的に検証することで、数字の裏にあるリスクとリターンが見えてきます。記事で触れたポイントを一つずつ実践し、納得のいく利回りを確保して、長期的に安定した不動産ポートフォリオを築いてください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 国土交通省 不動産取引価格情報 – https://www.land.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅市場景況調査 – https://www.mlit.go.jp
- 日本賃貸住宅管理協会 統計データ – https://www.jpm.jp

