築年数の古いアパートやマンションでも、適切に手を入れれば安定した家賃収入を生むことをご存じでしょうか。家賃相場が伸び悩む一方で物件価格は高止まりしている現在、「収益物件 築古物件」というキーワードは初心者投資家の強い味方になります。本記事では、築古物件の特徴、市場の動向、リスク管理から資金計画、2025年度に活用できる税制までを網羅的に解説します。読み終えるころには、築古物件を活用した投資戦略のイメージが具体的に描けるはずです。
築古物件の定義と2025年の市場動向
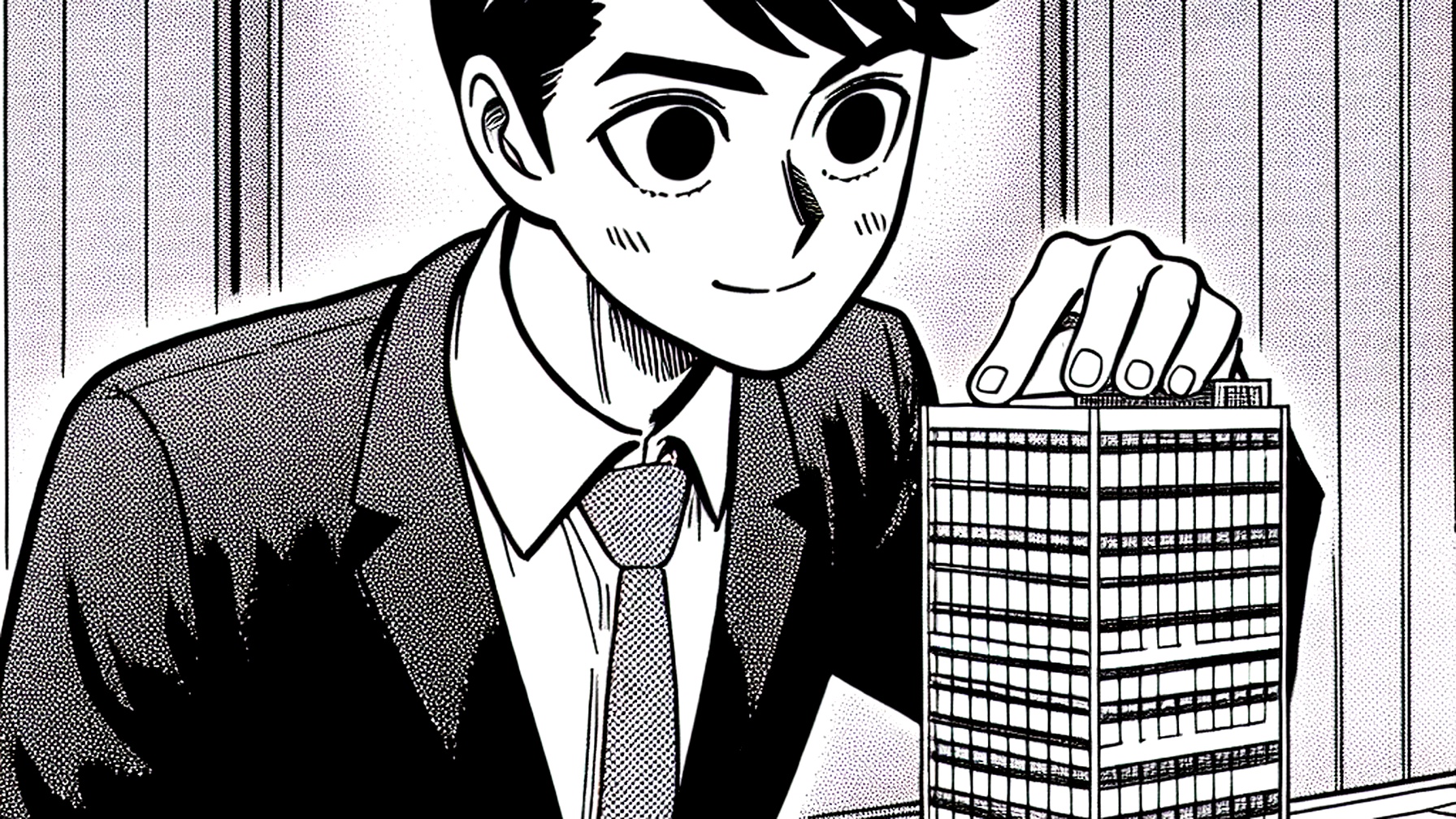
まず押さえておきたいのは「築古物件」の定義です。一般に鉄筋コンクリート造(RC)で築25年以上、木造で築20年以上の賃貸住宅を指します。国土交通省の「住宅市場動向調査2024」によると、全国の賃貸ストックの約48%がこの範囲に含まれ、賃貸需要が底堅い都市部では今も新規投資の対象になっています。
一方で、新築や築浅物件は建築コスト高騰の影響を受けて価格が上昇し、利回りが低下する傾向です。逆に築古物件は価格が相対的に安く、改装コストを考慮しても表面利回りが平均8~10%と高水準を維持しています。日本不動産研究所の2025年上期レポートでも、首都圏築古アパートの期待利回りは平均9.1%と報告されました。つまり、適切な運営ができれば高いキャッシュフローを狙いやすい市場環境にあるのです。
築古物件を収益化する三つのメリット
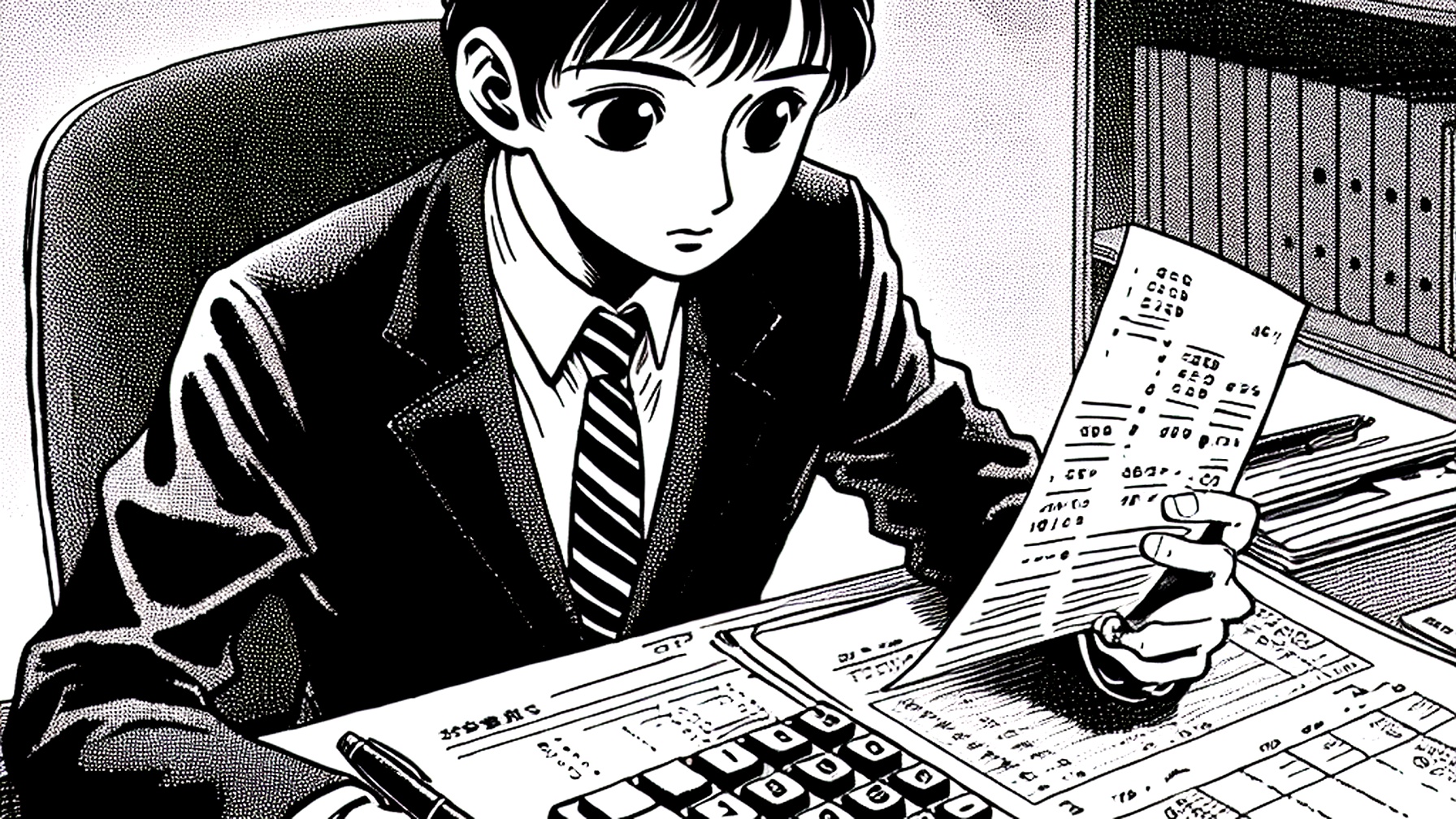
重要なのは、築古物件ならではの優位性を正しく理解することです。第一に、取得価格が抑えられるため、自己資金を少なくスタートしやすい点が挙げられます。例えば都内23区内の築30年RCマンション一室が2,000万円で購入できるケースは珍しくありませんが、同立地の築浅物件は3,000万円を超えることが多いのが現状です。
第二に、土地値が下支えするケースが多い点です。築年数が進んでも土地自体の価値は大きく変わらないため、最悪の場合は更地売却による出口も見込みやすくなります。固定資産税評価額を基にした試算では、建物価値がゼロに近い築30年の木造アパートでも、総価格の50%程度が土地値という例がありました。
第三に、リノベーションで賃料アップを狙える余地が大きいことです。日本賃貸住宅管理協会の2025年調査では、築25年以上のワンルームを20万円程度の表装工事で月3,000円、50万円規模の設備更新で月1万円前後の賃料増を実現した事例が報告されています。小規模な工事でも入居率改善につながりやすいため、費用対効果を計算しながら計画的に投資することが肝心です。
リスクとリノベーション戦略をどう組み立てるか
リスク管理のポイントは大きく二つあります。まず物件の物理的劣化リスクです。築古物件では給排水管や屋上防水、電気容量不足などが隠れたコストになりやすいので、購入前のインスペクション(建物状況調査)は必須です。2025年時点で全国に2,300社以上ある既存住宅状況調査技術者のネットワークを活用すれば、10万円前後で詳細な報告書が手に入ります。
次に、賃貸市場の競合リスクです。リノベーションは単に新しくするだけではなく、ターゲットを明確に設定することが大切です。例えば大学周辺なら高速Wi-Fiと家具付きプラン、ビジネス街ならワークスペース重視の間取り変更が効果的です。差別化ポイントを一つ加えるだけで、同エリア平均より長期入居率を10%改善した例もあります。
また、リフォーム費用を単年で回収しようとすると高額な改修を躊躇しがちですが、耐用年数延長を見込んで5~7年で償却する計画を立てると投資判断がしやすくなります。国税庁の耐用年数表によれば、木造アパートの残存耐用年数は「22年-築年数」で計算可能です。築古物件の場合、この短い耐用年数を活用して定額法より早く減価償却を進め、キャッシュフローを厚くする戦略も取れます。
資金計画と融資を通すためのコツ
まず自己資金は物件価格の20〜30%を目安に用意すると、金融機関の評価が高まります。2025年現在、地方銀行や信用金庫のアパートローン金利は変動型で年1.5~3.0%程度が主流ですが、築古物件は評価が厳しくなるため、家賃収入の余裕度(DSCR=返済余裕率)を1.3以上に設定すると審査が通りやすくなります。
そのうえで、返済期間を建物の残存耐用年数より長く設定できるか交渉することも重要です。例えば、RC造の法定耐用年数は47年ですが、築30年の物件なら残り17年しかありません。ここでリフォームによる「用途延長計画書」を提示すれば、期間を25年に伸ばせた事例があります。返済期間を延ばすと月々の返済額が減り、キャッシュフローが安定します。
金利タイプの選択も慎重に行いましょう。日銀の長期金利ターゲットがプラス0.5%へ拡大されたことで、固定金利がじわじわ上昇しています。変動金利との差が0.5%を切るなら、将来的な上昇リスクを抑えるために10年固定型を検討する価値があります。シミュレーションでは、3,000万円を2.0%固定で25年返済すると総返済額は約3,800万円ですが、変動1.5%から3%へ段階的に上昇した場合は約4,100万円となり、結果的に固定の方が得になるケースも見受けられます。
2025年度に活用できる税制・補助制度
ポイントは、投資家が活用できる制度を正確に押さえることです。2025年度も「住宅耐震改修促進税制」と「高効率給湯器設置による固定資産税減額措置」は継続予定です。賃貸住宅であっても、一定の耐震基準適合工事や省エネ設備導入を行えば、固定資産税が3年間おおむね1/2に軽減されます。東京都の場合、耐震改修後は上限120㎡まで半額となるため、年間20万円前後のコスト削減効果が得られることもあります。
さらに、中小企業経営強化税制(2025年度改正)を活用すれば、賃貸業でもエネルギー効率化設備への投資額を即時償却または税額控除10%から選択できます。太陽光パネルやLED共用灯の導入は、ランニングコスト削減に直結するうえ、減価償却による節税も同時に実現可能です。
ただし、補助金や税制は申請期限や要件が細かいため、事業計画書と見積書を早めに準備することが重要です。自治体によっては追加補助が設定される場合もあるので、物件所在地の住宅政策課へ相談し、最新情報を確認してから工事を発注しましょう。
まとめ
築古物件は取得価格の低さとリノベーション余地の大きさが魅力ですが、劣化や空室といったリスクも隣り合わせです。本記事で紹介したように、インスペクションで物理的リスクを把握し、ターゲットを意識した改修で差別化を図れば、表面利回りだけでなく実質的なキャッシュフローも安定します。さらに、2025年度の減税措置を活用すれば、税引後の手取りを高めることも可能です。築古だからと敬遠せず、データと計画を武器に一歩踏み出してみてください。堅実な資産形成への道が開けるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2024 – https://www.mlit.go.jp
- 日本不動産研究所 不動産投資家調査2025年上期 – https://www.reinet.or.jp
- 日本賃貸住宅管理協会 賃貸住宅市場景況感調査2025 – https://www.jpm.jp
- 国税庁 耐用年数省令 – https://www.nta.go.jp
- 総務省 固定資産税の減額措置に関する Q&A(2025年度版) – https://www.soumu.go.jp

