中古マンションで安定収入を得たいものの、本当に稼げるのか、空室や老朽化の不安が尽きない。私も15年以上前、初めて購入するときは同じ疑問を抱えました。実は、中古でもリスクを読み解き、数字で判断すれば、初心者でも堅実にプラスを積み上げることは可能です。本記事では、2025年時点の市場データをもとに、収益構造、物件選び、資金計画、リスク管理までを順序良く解説します。読み終える頃には、自分に合った投資ステップが具体的に描けるはずです。
中古マンション投資の魅力と市場動向
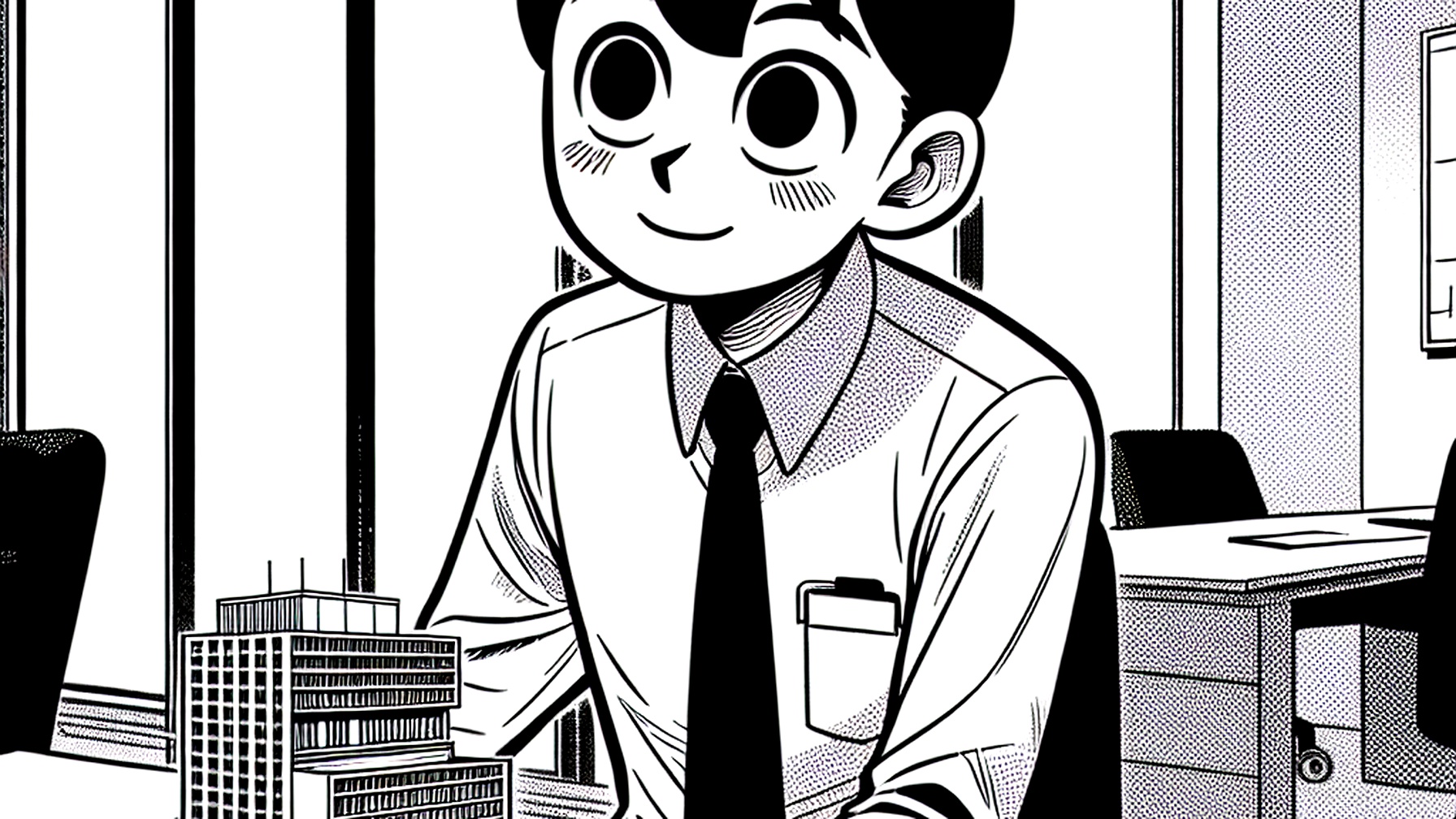
まず押さえておきたいのは、新築との価格差を活かしながら家賃水準を確保できる点です。さらに人口集中が続くエリアを選べば、需給バランスが崩れにくいという強みもあります。中古マンション投資が初心者に適しているのは、この二つの要素で利回りとリスクの両面をコントロールしやすいからです。
不動産経済研究所によると、2025年9月時点の東京23区の新築マンション平均価格は7,580万円でした。対して、築15年前後のワンルームは同じエリアでも3,000万円台で購入できる例が珍しくありません。この価格ギャップが利回りを押し上げ、自己資金を抑えた投資を可能にします。また、想定賃料は築年より立地に連動するため、収益性が新築に対して大きく劣らないのです。
中古の魅力は、過去の賃貸履歴を確認できる点にもあります。管理組合の議事録や入居率の推移をたどれば、空室リスクを数字で把握できます。つまり、将来の収支を机上の空論ではなく実績ベースで描けるのです。一方で、修繕積立金の不足や配管劣化など、築年数ゆえの課題も見過ごせません。
人口動態を見ても、投資可能なエリアは限定されます。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2035年まで東京23区の単身世帯は年平均0.8%で増加すると予想されています。この指標はワンルーム需要の裏付けとなり、賃料下落リスクを抑えます。反対に、地方都市の中には単身世帯が減少する予測地域もあるため、数字を確認したうえで立地を絞ることが重要です。
収益を生むキャッシュフローの仕組み
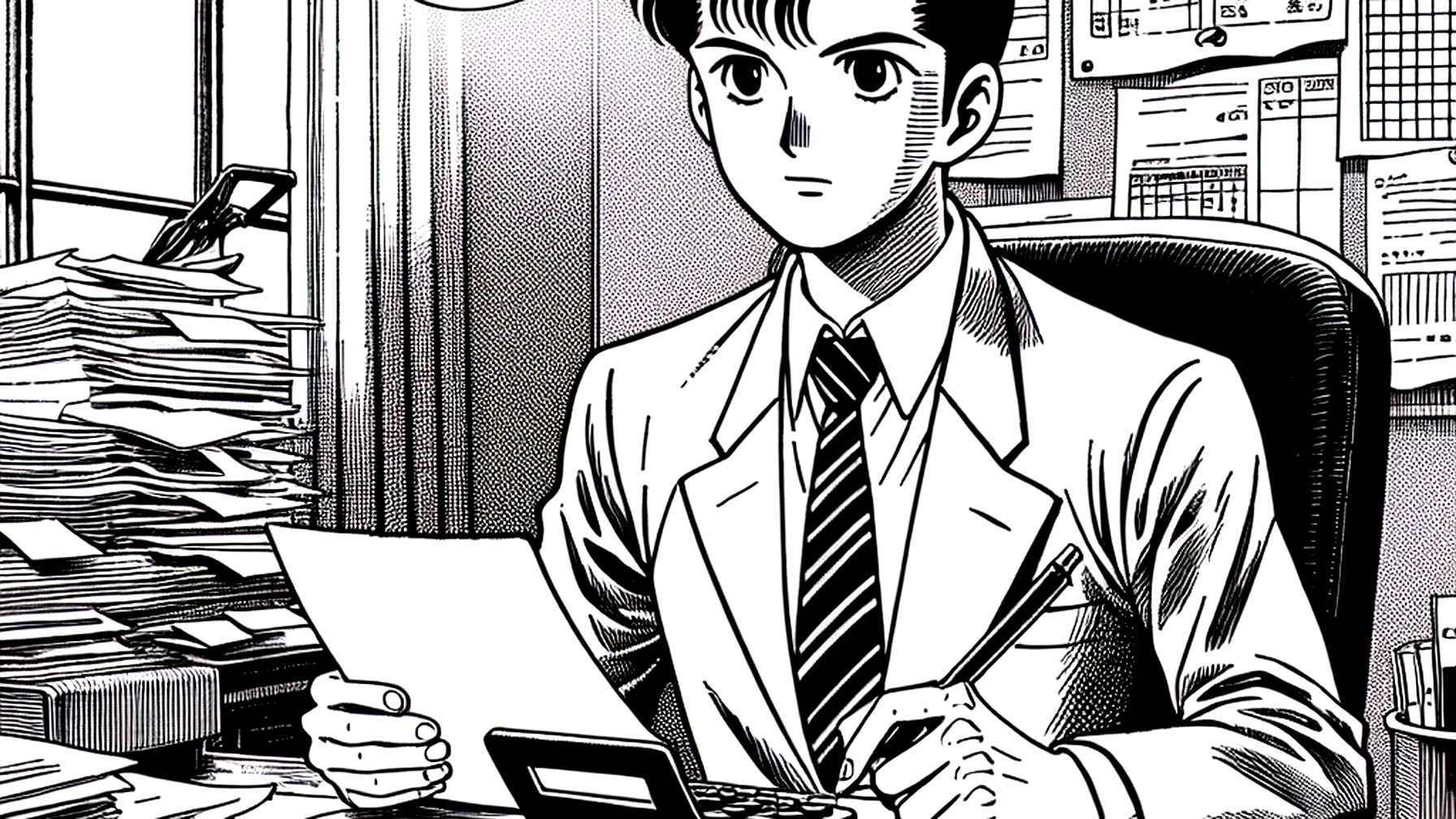
重要なのは、毎月残るキャッシュフローを正しく計算することです。表面利回りだけを見て判断すると、実際の手取りと大きく乖離します。ここでは、中古マンション特有のコスト構造を整理しながら、稼げる仕組みを具体的に見ていきます。
家賃収入は立地と間取りでほぼ決まります。東京都心の築15年ワンルームでは、平均賃料が月9万円前後です。年間家賃は108万円となり、購入価格3,000万円の場合、表面利回りは3.6%に留まります。しかし、後述の経費を差し引いても、融資条件次第で毎月1万〜2万円のプラスを確保できるケースが少なくありません。
支出で最も見落とされがちなのが管理費と修繕積立金です。この二つで月額1.5万円前後かかる物件は珍しくありません。さらに、管理会社への手数料が賃料の5%前後、固定資産税・都市計画税が年間10万円程度発生します。つまり、表面利回りよりもネット利回りを見なければ、本当の収益力はつかめません。
たとえば、金利1.8%、期間30年、借入2,400万円で購入した場合、月々の返済は約8.5万円です。先ほどの東京都心ワンルームを想定すると、収入9万円から返済を差し引き0.5万円の赤字になります。しかし、自己資金を30%入れて借入を2,100万円に抑えると、返済が7.4万円に減り、手取りは1.1万円の黒字に転じます。資本構成と金利交渉がキャッシュフローを左右する好例です。
成功へ導く中古物件の選び方
実は、稼げるかどうかの7割は物件選定で決まります。立地、築年数、管理状態の三つを総合評価しないと、後で修繕コストに苦しむことになります。ここでは具体的なチェックポイントを、現地調査の流れに沿って解説します。
まず、最寄り駅から徒歩10分以内を目安にしましょう。賃貸検索サイトの上位表示条件は徒歩分数で決まるため、検索にヒットしやすい物件は空室期間が短くなります。特に職住近接を求める単身者は徒歩5分以内にプレミアムを感じ、賃料を1割上乗せしても成約する傾向があります。つまり、距離は単なる利便性ではなく収益を底上げする指標なのです。
築年数は20年以内に絞ると、主要構造部分の大規模修繕が一巡している場合が多く、今後10年ほどは大きな工事が発生しにくいというメリットがあります。ただし、修繕積立金が不足していれば将来の一括徴収リスクが高まります。管理組合の長期修繕計画を確認し、積立金残高が推奨水準の70%以上あるかを必ずチェックしてください。これは後々の想定外出費を防ぐ最も確実な方法です。
消防法や建築基準法に適合しているかも重要です。例えば、共用部におけるオートロックの追加や非常ベルの交換が必要になると、区分所有者全員で費用を負担することになります。現地でインターフォンや階段の幅などを測り、最新基準と照らし合わせれば、追加コストの芽を早期に摘むことができます。また、管理会社の報告書に記載された指摘事項は、購入後すぐに修繕が必要な箇所のヒントになります。
資金計画と2025年度の融資・税制優遇
まず押さえておきたいのは、購入前に金利と自己資金を柔軟に組み合わせ、月々の手取りを瞬時に試算できるシートを作ることです。2025年度も中古マンション向け融資は「収益還元」を重視する流れが続いており、資産背景よりも物件力を示せるかが審査の鍵となります。
都市銀行は借入金利1.5%前後と低いものの、個人年収や勤続年数に厳しい審査基準を設けています。一方、信用金庫やノンバンクは2%台ですが、家賃収入による返済可能性を重視するため、自己資金10%程度でも融資が可決する例があります。つまり、金利差だけでなく融資上限や手数料を総合した実質コストで比較することが不可欠です。
税制面では、耐用年数を過ぎた中古マンションでも、残存耐用年数または4年のいずれか長い期間で減価償却が可能です。年間経費が増えることで給与所得との損益通算が成立し、所得税と住民税の軽減効果が期待できます。国税庁のモデルケースでは、減価償却費120万円を計上すると課税所得が同額減り、税率20%なら24万円の現金が手元に残る計算です。税還付はキャッシュフローを押し上げる追加の収益源といえます。
さらに、2025年度も継続する「小規模不動産特定共同事業法」の登録事業者が提供する優遇金利プランを活用すれば、管理費込みで返済負担率を3%程度改善できる場合があります。ただし、適用条件として長期修繕計画書の提出を求められるため、購入前にデータを揃えておく必要があります。また、火災保険の一括払いによる長期割引を併用すると、初年度のネット利回りが0.2%向上する効果も見込めます。
リスク管理と出口戦略
重要なのは、収入が途切れたり修繕が重なったりしても資金繰りが回る設計をしておくことです。さらに、購入時点で売却の出口を意識すると、投資期間中の意思決定がぶれません。最後に、代表的なリスクと対処法を整理します。
空室リスクは、家賃を下げて成約するのではなく、募集開始のタイミングを前倒しすることで回避しやすくなります。繁忙期二カ月前から広告を出すと、平均空室期間が1.1カ月短縮されたという管理会社のデータがあります。1カ月の空室は年間利回りを約0.8ポイント押し下げるため、この差は大きいです。また、家具家電付きプランを導入すると短期契約需要を取り込めます。
修繕コストは、区分所有者で前もって積立金を増額する提案を行うことで平準化できます。もし総戸数の三分の二が賛成すれば規約改定が可能です。早期に増額すれば、一時金徴収を回避でき、キャッシュフローの乱れを抑えられます。私の経験では、1戸当たり月3,000円の増額で大規模修繕積立不足を8年で解消できました。
出口戦略としては、築30年を迎える前後が転売の好機です。金融機関の耐用年数評価が厳しくなる前に売却すると、購入時と同等かそれ以上の価格で成約する例もあります。首都圏の中古ワンルーム成約データを見ると、築29年でも築20年と比べて価格が5%程度しか下落していません。つまり、需要が堅い間に手放せば、家賃収入に加えてキャピタルゲインも狙えるのです。
まとめ
ここまで、中古マンション投資で稼ぐための市場分析、キャッシュフロー、物件選び、資金計画、リスク管理を順序立てて解説しました。要するに、立地重視の目線と数字に基づく資金設計があれば、初心者でも安定収益を実現できます。記事を参考に、まずは候補エリアの賃料相場と融資条件を調べ、試算シートを作成するところから一歩を踏み出してください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国立社会保障・人口問題研究所 – https://www.ipss.go.jp
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp

