アパート経営に興味はあるものの、どの手順で進めれば安全なのかと悩む人は多いものです。自己資金やローン、空室リスクなど考えるべき要素が多く、情報が断片的だと迷いやすくなります。本記事では、収益性を高める具体的なやり方を初心者にも分かりやすく整理しました。最新の統計や2025年度の制度を踏まえつつ、物件選びから運営管理まで順を追って解説します。読み終えるころには、自分に合った投資戦略を描けるようになるはずです。
アパート経営で収益が生まれる仕組み
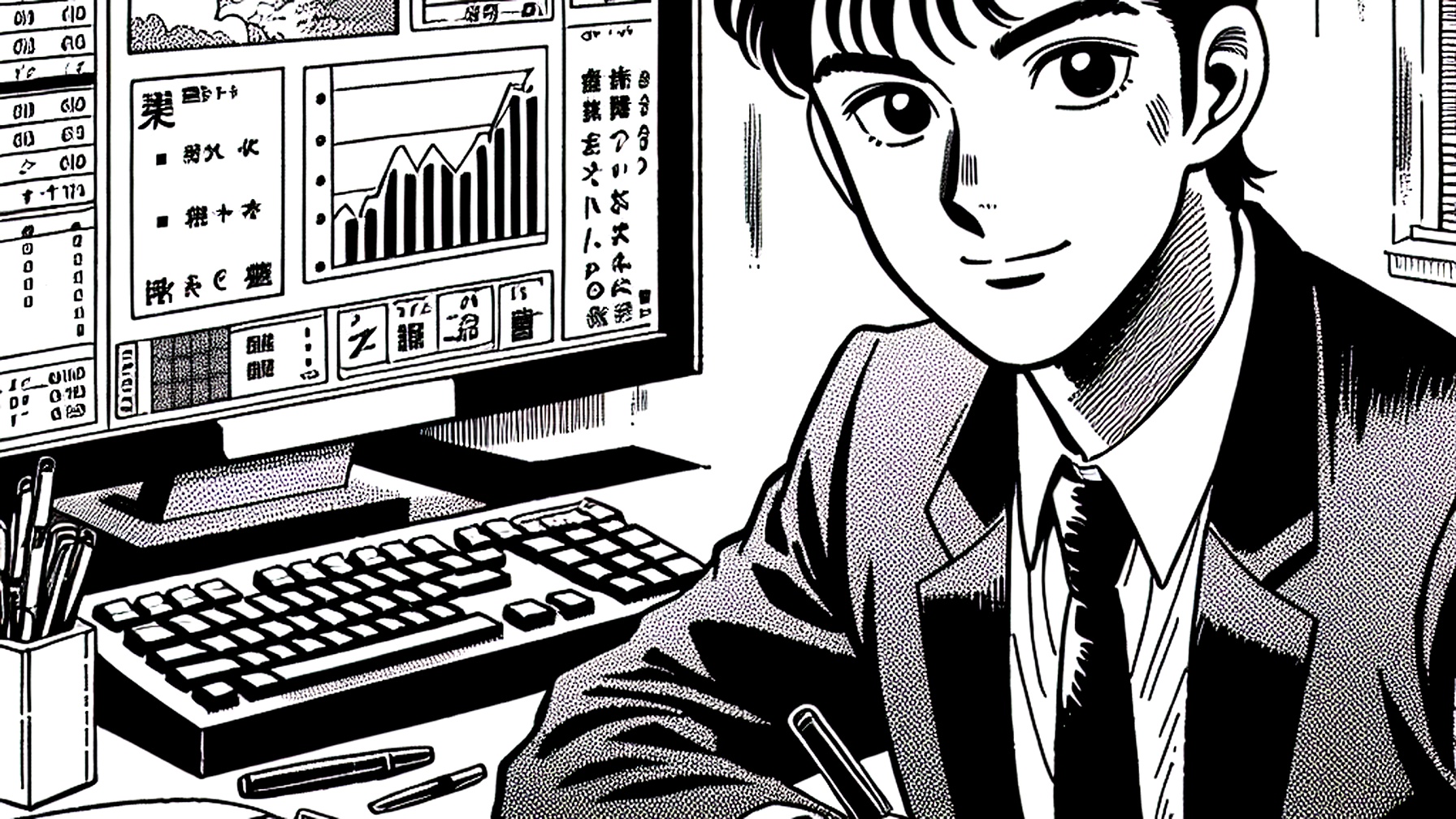
重要なのは、家賃収入と経費のバランスを理解し、キャッシュフローを長期視点で把握することです。実は、表面利回りだけでは本当の収益性を測れません。
まず家賃収入は、入居率で変動する点を押さえましょう。国土交通省の住宅統計によると、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で、前年より0.3ポイント改善しました。しかし地域差は大きく、都市部の駅近で10%台、人口減少が進む地方で30%台というデータもあります。つまり、自分の投資エリアの実質空室率を調べることが出発点になります。
次に経費を洗い出します。固定資産税、管理費、修繕費、ローン利息が代表例です。固定資産税は新築アパートなら「2025年度 固定資産税の住宅用地特例」により、建物が完成した翌年度から3年間は税額が1/2に軽減されます。これを踏まえてキャッシュフロー計算書を作り、月次・年次の手取り額を予測します。
最後に投資額との比較です。利回りの指標として広く使われるネット利回り(手取り÷物件価格)を算出し、同条件の他物件や他エリアと照らし合わせます。この時、将来の家賃下落と修繕費上昇を年1〜2%ずつ織り込むと、過度に楽観的なシミュレーションを避けられます。
物件選びで押さえるべき立地と間取り
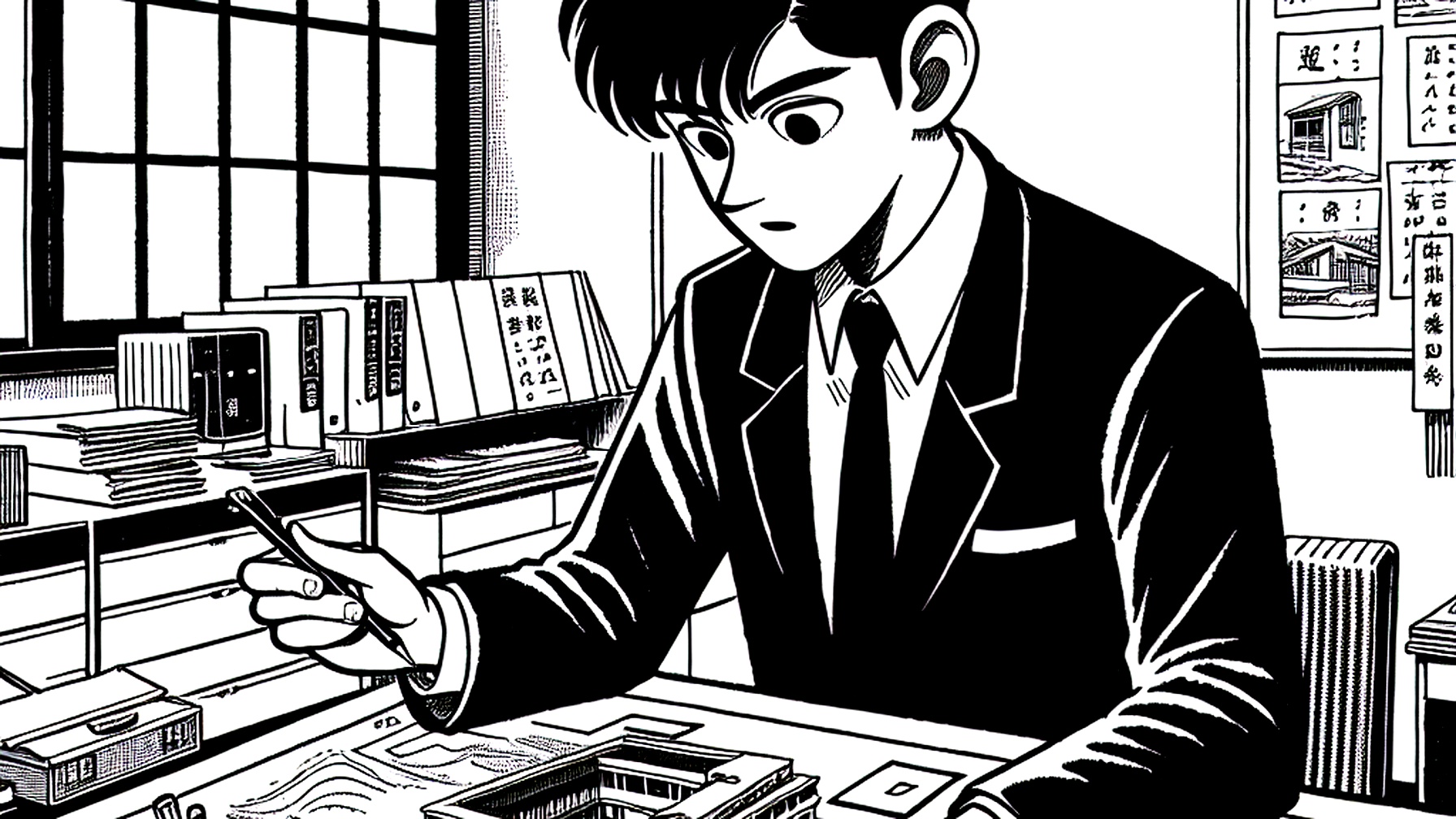
ポイントは、入居者のニーズに合った立地と間取りを選び、長期安定の賃貸需要を確保することです。
一つ目は立地です。駅徒歩10分圏内や大学、病院の近くなど、人口動態に左右されにくいエリアを優先しましょう。都心の地価は高く初期投資は増えますが、空室期間が短く家賃も下がりにくい傾向があります。一方で郊外は利回りが高く見えるものの、人口減少や再開発計画の有無で将来の収益性が変わります。自治体が公開する将来人口推計を確認し、安定しているかをチェックすると安心です。
二つ目は間取りです。単身向けのワンルームは回転率が高く、リフォーム費も少額で済みます。しかし平均入居期間は2〜3年で、頻繁な募集広告費がかかります。ファミリー向けの2LDK以上は入居期間が5年以上と長めですが、修繕費が上がる点に注意が必要です。ターゲット層の年齢やライフスタイルを意識し、賃料水準と競合物件の設備を比較したうえで決定しましょう。
最後に、周辺インフラの将来計画も重要です。市区町村の都市計画マスタープランで道路拡幅や再開発予定を確認すれば、資産価値が下がりにくい物件を選べます。また、災害リスクが低い場所を選ぶことは保険料と修繕コストを抑える意味でも有効です。
資金計画と融資のポイント
まず押さえておきたいのは、自己資金と融資比率のバランスです。自己資金を2〜3割入れると、融資審査が通りやすく、月々の返済負担も抑えられます。
融資先はメガバンク、地方銀行、信用金庫で金利と期間が大きく異なります。2025年9月時点では、変動金利が年1.3〜1.8%、長期固定が年2.0〜2.6%程度が主流です。金利差が0.5%でも、5000万円を25年返済すると総返済額が約400万円変わるため、必ず複数行を比較しましょう。
返済期間は建物の法定耐用年数が目安になります。木造アパートは22年、鉄骨造は34年ですが、金融機関は残存耐用年数で判断するため、中古物件ほど期間が短くなりがちです。耐用年数が短いと毎月の返済額が増えるため、築古物件を選ぶ際は利回りが高くても返済負担に耐えられるかを検証する必要があります。
また、将来の金利上昇リスクを軽減する方法も考えておくと安心です。例えば、変動金利で借りる場合は手元に6か月分以上の返済額を留保し、金利が2%上がった場合のシミュレーションも作成します。さらに、家賃収入の範囲で元金返済を早める「繰上返済」を計画的に行うと総返済額を抑えられます。
運営コストを抑える管理のやり方
実は、運営フェーズでのコスト最適化が収益性を大きく左右します。家賃を上げるより、経費を1%下げる方が手取り額に直結しやすいからです。
管理方法には、自主管理と管理会社委託があります。自主管理は手数料がかからない代わりに、クレーム対応や賃料督促の手間が発生します。初心者は管理会社へ委託し、経験を積みながら一部業務を自分で行うハイブリッド方式を検討すると負担を軽減できます。委託手数料は家賃の3〜5%が相場で、空室時は発生しないプランを選ぶと固定費を下げられます。
修繕費の積立も欠かせません。目安として年間家賃収入の7〜10%を修繕積立に回すと、給排水管や屋根、防水の大規模修繕に備えられます。小規模修繕はまとめて発注することで単価が下がるため、複数戸を一括で施工する「バルク発注」を活用すると効果的です。
入居者募集は、家賃を下げる前に広告戦略を見直します。写真をプロに依頼して物件の魅力を伝え、初期費用を抑えたフリーレント1か月を導入すると反応が上がるケースが多いです。空室が長期化する前に管理会社と対策会議を行い、改善策をスピーディーに実行する仕組みを整えましょう。
2025年度税制と補助制度の活用法
まず押さえておきたいのは、税制優遇を正しく理解し、合法的に手取りを増やすことです。結論として、制度を知らないことは実質的な損失につながります。
2025年度も新築賃貸住宅に対する固定資産税の1/2軽減措置が継続しています。これにより、完成後3年間は税負担が半減するため、キャッシュフローの改善幅は年間数十万円に及びます。また、登録免許税は「住宅用家屋の軽減措置」が適用され、所有権保存登記の税率が0.15%に下がります。取得時の諸費用を抑えれば、自己資金を他の用途に回せます。
さらに、一定の省エネ基準を満たす賃貸住宅には「2025年度 省エネ賃貸住宅促進補助金」が利用可能です。断熱性能等級4以上の新築アパートを対象に、戸当たり上限60万円の工事費補助が受けられます。高性能設備は入居者の光熱費を下げ、競争力向上にもつながります。
経費計上の面では、減価償却が最大の節税ポイントです。木造アパートの定額法なら年間4.6%を経費にでき、築年数が進むほど割合が高くなります。加えて、青色申告特別控除65万円を受けると、損益通算で所得税を圧縮できます。帳簿作成はクラウド会計ソフトを利用すれば時間短縮が可能です。
最後に、インボイス制度への対応も忘れないでください。2023年に始まった同制度は、2025年10月から2年前置きだった経過措置が縮小されます。課税事業者として登録し、消費税の処理を適正に行わないと、将来の物件売却時に余分な納税が発生する恐れがあります。税理士と早めに相談し、適切な申告体制を整えましょう。
まとめ
アパート経営で収益性を高めるには、空室率や経費を織り込んだ精密なシミュレーションが欠かせません。立地と間取りをニーズに合わせ、融資条件を最適化し、運営コストを継続的に削減することで安定したキャッシュフローが実現します。さらに、2025年度の税制優遇や補助金を活用すれば手取り額は一段と伸びます。今日できる第一歩として、投資エリアの空室率と金融機関の金利を調べ、自分だけの収支計画を作成してみてください。行動を積み重ねれば、不動産投資は着実に資産形成の柱となります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅局「住宅・土地統計調査」https://www.mlit.go.jp
- 総務省「人口推計」https://www.stat.go.jp
- 財務省「令和7年度(2025年度)税制改正の概要」https://www.mof.go.jp
- 環境省「省エネ賃貸住宅促進補助金 事業概要」https://www.env.go.jp
- 日本銀行「金融経済統計月報」https://www.boj.or.jp

