アパート経営を始めたいものの、どの街を選べば安定収益を得られるのか分からず不安を抱えていませんか。立地が悪いだけで、入居者募集に苦戦し手元資金が減ってしまう事例は後を絶ちません。本記事では「アパート経営 立地選定 ステップ」という視点から、初心者でも実践しやすい手順を詳しく解説します。読み終える頃には、数字と現地調査を組み合わせた再現性の高い判断軸が身につき、物件選びで迷う時間を大幅に短縮できるはずです。
立地選定が収益を左右する理由
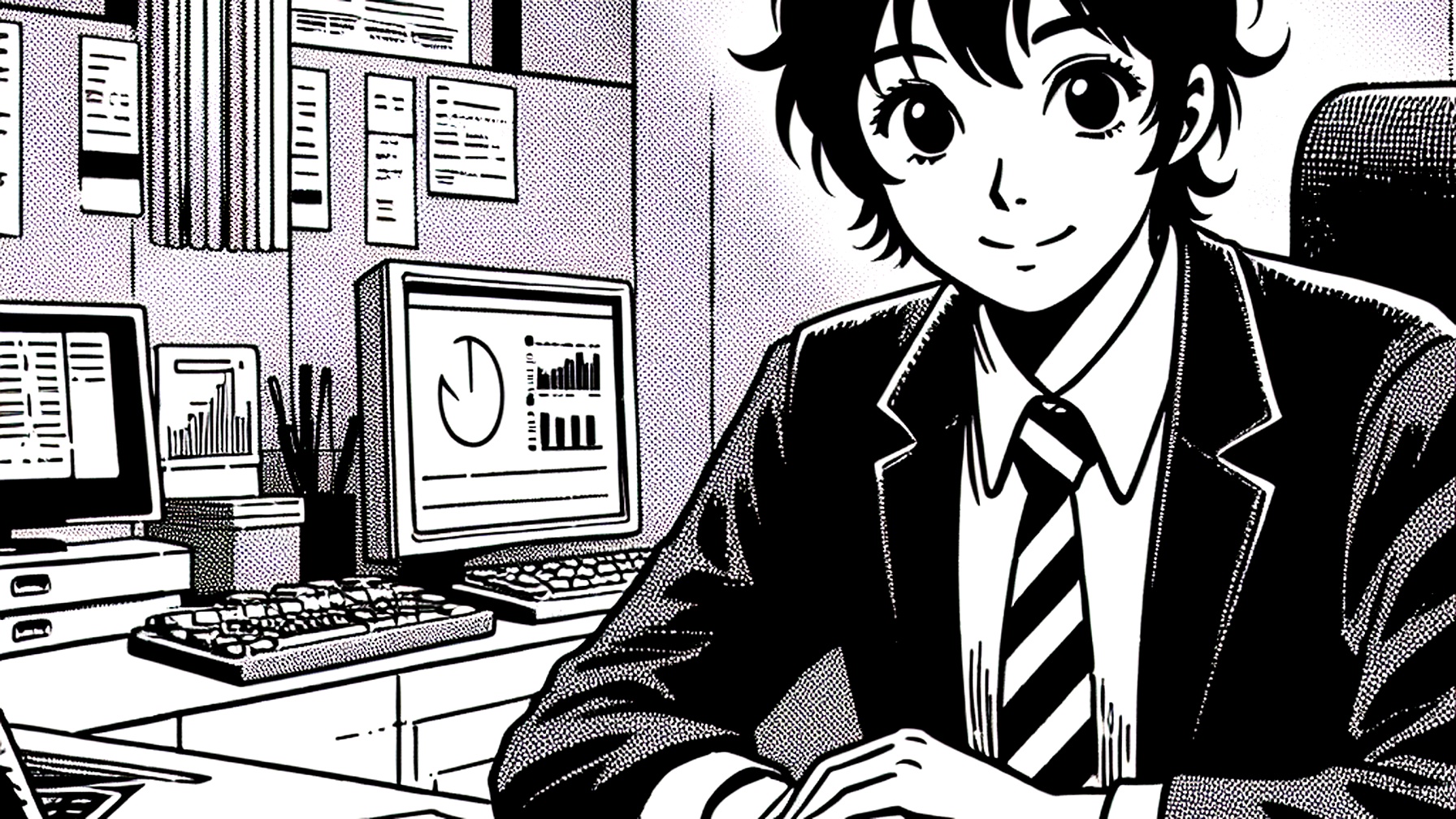
重要なのは、立地が家賃水準と空室率という二つの核心指標を直接コントロールする点です。国土交通省住宅統計によると、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%ですが、都心三区では8%台にとどまり、地方郊外では30%に達する地域もあります。つまり同じ建物性能でも、場所によって稼働率には三倍近い差が生じるわけです。
まず家賃水準を決めるのは周辺の平均所得と競合物件の質です。平均所得が高いエリアでは賃料が維持されやすく、修繕費を家賃に転嫁しやすいので長期保有戦略と相性が良くなります。一方、所得水準が低い街で高額なリノベーションを行っても家賃上昇には限界があるため、費用回収が難しくなります。
また融資審査においても立地は重視されます。金融機関は将来の担保価値を重視し、市場規模が縮小するエリアには慎重です。結果として、好立地であれば低金利かつ長期融資が受けやすく、キャッシュフローにゆとりが生まれます。こうした資金繰りの差は、運営を続けるうちに雪だるま式に広がるため、最初の立地選定が成功の分水嶺となるのです。
需要と供給を数字でつかむステップ

まず押さえておきたいのは、統計データを用いて需給バランスを確認することです。国勢調査の人口推計と総務省の将来人口推計を突き合わせ、20〜39歳の若年層が10年後も維持される地域かどうかを見ます。若年層が2%以上減少する見込みの市区町村では、新築でも5年後に想定外の空室が生まれる傾向があります。
次に、国交省「土地総合システム」や都道府県の住宅着工統計から、直近3年間の新規アパート供給戸数を取得します。供給増加率が人口増加率を上回る場合、競合過多のシグナルと判断できます。例えば人口横ばいの中核市で供給戸数が15%増えていれば、5年後の空室率は現在より高まるリスクが高いと考えられます。
最後に、家賃相場サイトだけでなく、国土交通省「賃貸住宅実態調査」の中央値にも目を通します。現地で掲示されている募集家賃が統計値より5%以上高い場合、成約ベースでは値下げ余地があると見るのが無難です。こうして複数の公的データを組み合わせれば、感覚に頼らない一次スクリーニングが可能になります。
生活利便性を歩いて確認するステップ
ポイントは、統計では拾いきれない日常の利便性を自分の足で検証することです。最寄り駅までの徒歩分数は距離よりも歩行環境で印象が変わります。信号が多い、坂道が多いといった要素は、図面上の「徒歩8分」を体感の10分以上に伸ばすことがあるため、昼と夜の両方で実際に歩いてみると差が分かります。
さらに、スーパーやドラッグストアの営業時間を確認してください。近年は24時閉店が増えていますが、住宅街によっては21時で閉まる店舗も多く、帰宅時間の遅い単身者には不便です。生活施設が早く閉まる街では、家賃を下げないと入居者が集まりにくい傾向が見られます。
加えて、自治体のハザードマップを現地で照合します。洪水や土砂災害の警戒区域内では、保険料が上がるだけでなく、感度の高い入居者が敬遠することがあります。2025年度の水害対策補助制度が適用されれば外構工事の一部費用を抑えられますが、区域指定そのものは変わらないため、根本的なリスク低減にはなりません。
将来計画とリスクを読み解くステップ
実は、立地評価で見落とされがちなのが行政の将来計画です。都市計画マスタープランや鉄道会社の中期経営計画には再開発や駅改良の情報が盛り込まれています。例えば2025年度に始まった東急線沿線の駅前再整備では、完成後に坪単価が平均12%上昇した事例があります。このように公式資料の公開段階で動くことで、相場が上がる前に仕込むチャンスが生まれます。
一方で、公共施設の統廃合計画が出ているエリアでは、人口流出が加速するリスクがあります。小学校が統合される地域は子育て世帯の需要が減り、ファミリー向け間取りの稼働率が低下しやすいのです。開発の追い風と衰退の逆風を見極めるには、自治体議会の議事録や広報誌まで読み込み、情報鮮度を保つ姿勢が欠かせません。
また、2025年9月時点で有効な「地域再エネ促進区域」に指定されると、太陽光発電設備の設置に助成が出る自治体があります。屋上へのパネル設置で共用部電気代を削減できれば、実質利回りが0.3〜0.5ポイント改善することもあるため、プラス要素として評価すべきです。
立地データを投資判断に落とし込む
まず立地選定で得た情報を、家賃設定と長期シミュレーションに反映させることが大切です。空室率を全国平均ではなく、対象エリアの平均値から2ポイント高めに設定すると、想定外の収支悪化を防げます。
次に、金融機関へ提出する事業計画書にも立地データを組み込みます。人口推計や再開発計画を引用し、入居需要の根拠を示すことで、融資担当者の不安を払拭できます。結果として融資期間が延びたり、金利が0.2%下がる事例も珍しくありません。
最後に、購入前には必ず現地でのヒアリングを実施します。不動産管理会社や近隣店舗のスタッフに「最近の空室状況」や「新築物件の家賃設定」を尋ねると、机上データとのギャップが浮き彫りになります。そのうえで、期待利回りがリスクプレミアムを上回るかどうかを確認し、買付申込へ進むかを判断しましょう。
まとめ
立地選定は「統計データで需給を測る」「現地で生活利便性を体感する」「将来計画を読み解きリスクを見抜く」という三つのステップを踏むことで、再現性高く判断できます。数字と肌感覚の両輪をそろえれば、空室率21.2%という全国平均の波に飲まれることなく、安定したアパート経営が可能です。今日から各種統計をダウンロードし、週末に候補地を歩いてみることが、成功への第一歩となります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年7月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 国勢調査・将来人口推計 2025年版 – https://www.soumu.go.jp
- 国土交通省 土地総合システム – https://www.land.mlit.go.jp
- 東京都 都市計画マスタープラン 2025 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 環境省 地域再エネ促進区域制度ガイド 2025年度版 – https://www.env.go.jp

