不動産投資に興味はあるものの、「中古マンションを買って本当に失敗しないだろうか」と不安を抱く方は多いものです。価格の高騰、新築物件の供給不足、金利上昇リスクなど、2025年の市場は一見ハードルが高く感じられます。しかし視点を変えると、中古マンションには新築にはないメリットがあるのも事実です。本記事では15年以上現場を見てきた立場から、失敗を回避するためのチェックポイントを具体的に解説します。読み終えたとき、あなたは「中古でも安心して投資できる」と自信を持てるはずです。
中古マンション投資が注目される理由
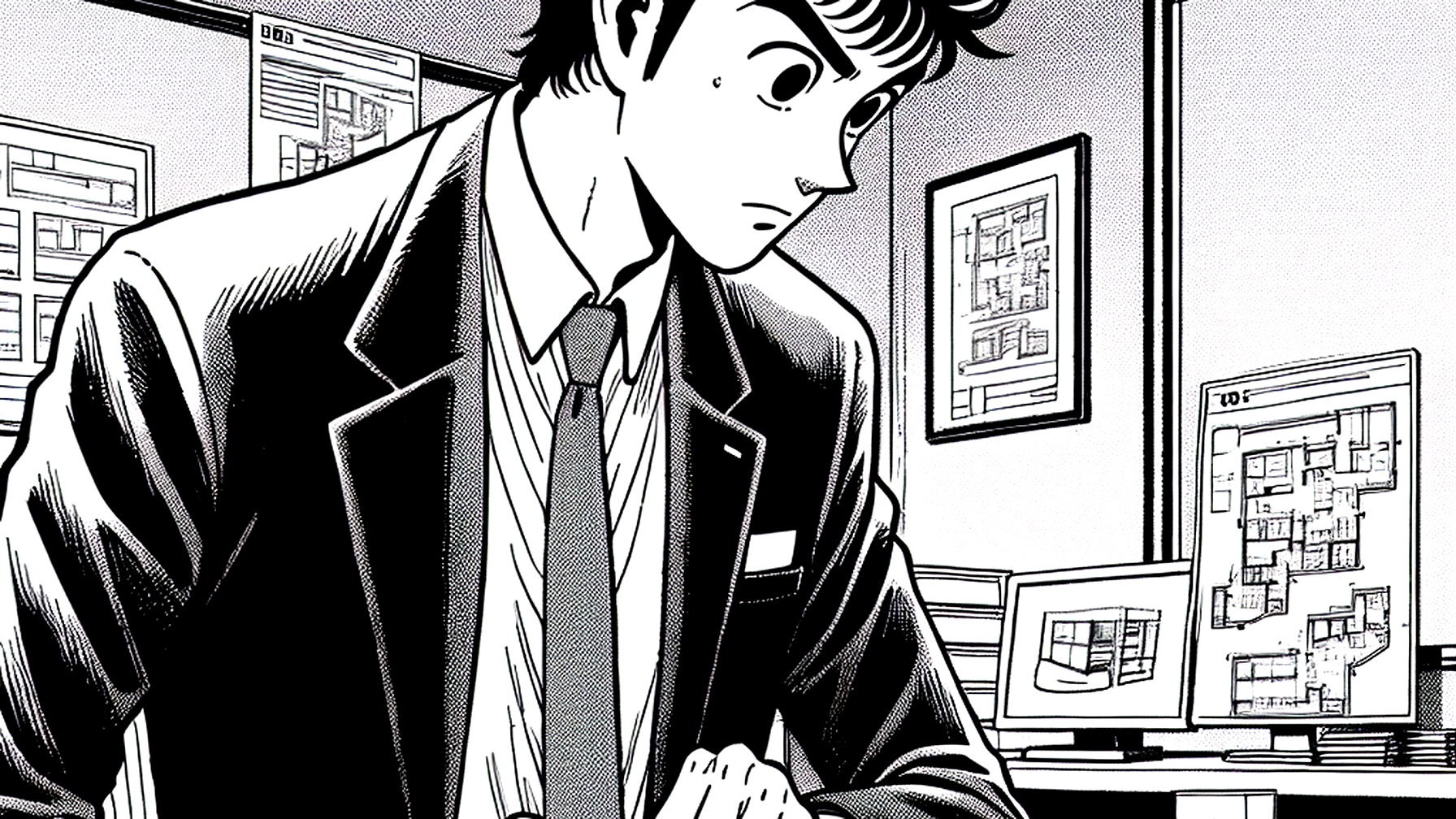
重要なのは、なぜ今中古マンションなのかを理解することです。新築価格が上昇する一方、中古は築年数によって価格が緩やかに下がるため、利回りを確保しやすいという背景があります。
まず東京23区の新築分譲平均価格は2025年9月時点で7,580万円と、5年前より約16%上昇しています(不動産経済研究所)。対照的に築15年前後の中古区分は平均4,600万円前後で推移し、賃料相場が大きく下がらないエリアも多いのが特徴です。つまり同じ家賃収入を得るなら中古の方が投資効率が高くなる計算です。
また中古は完成物件なので、実際の共用部分や周辺環境を確認できる点が安心材料になります。新築のパンフレットだけではわからない日当たりや騒音は、実際に現地に立つことで把握できます。将来の修繕積立金の推移も過去の議事録から推測できるため、長期のランニングコストを読みやすい点も魅力です。
一方で築年数が進むほど大規模修繕の負担が増え、買い手の融資条件が厳しくなるというデメリットも避けられません。ここをどう見極めるかが、マンション投資 中古 失敗しない最大のカギになります。
まず押さえておきたい物件選びの基準
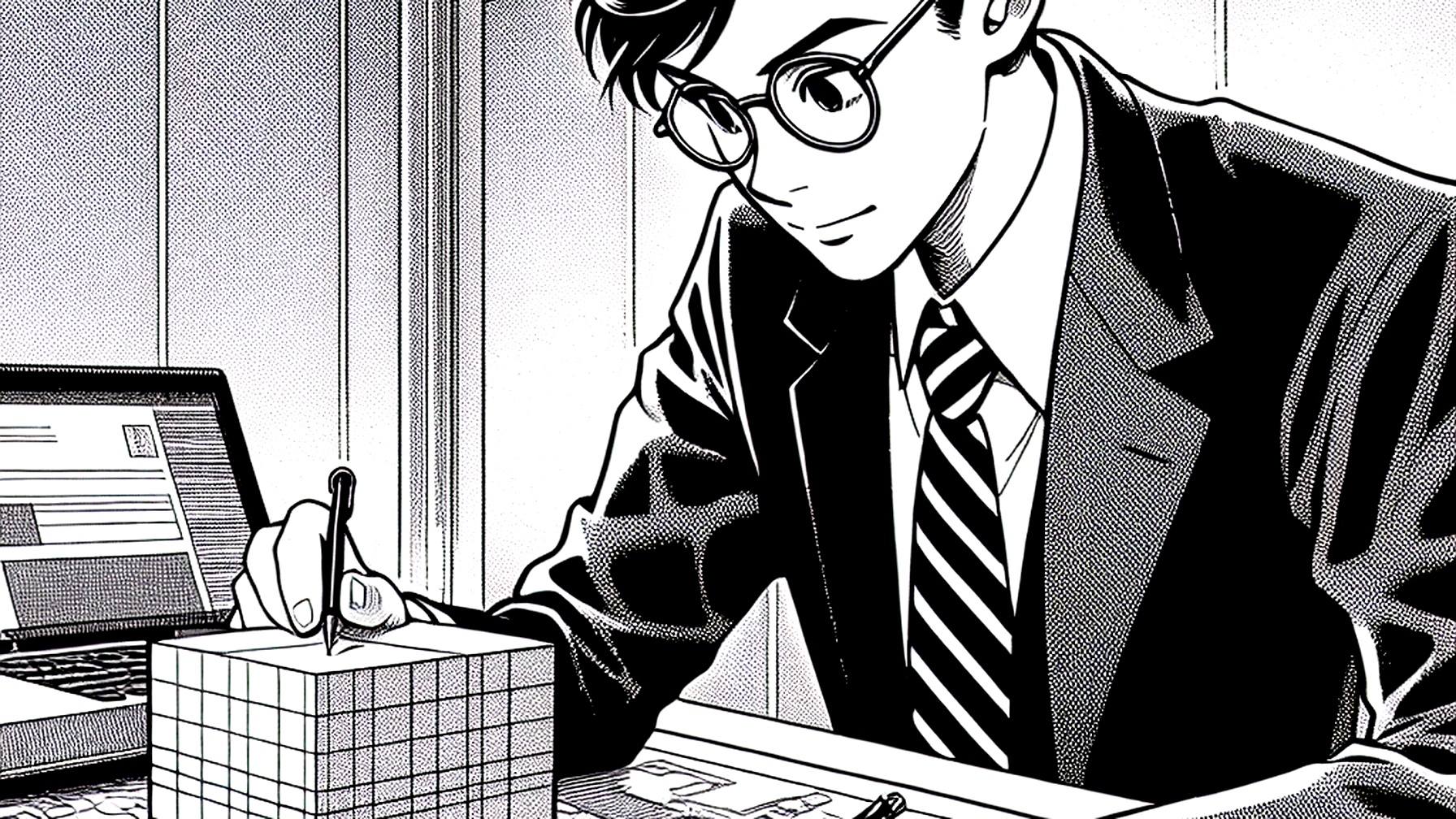
ポイントは「立地」「管理」「価格」の三要素を同時に満たす物件を探すことです。どれか一つでも欠けると空室や想定外の支出につながります。
立地で最優先なのは駅徒歩7分以内という基準です。総務省の住宅・土地統計調査によると、徒歩10分を超えると賃料が8%前後下落する傾向が見られます。さらに単身者向けならコンビニやスーパーが200m圏内にあるかも確かめてください。
管理状態は過去の修繕履歴に注目します。築20年で二回目の大規模修繕を済ませている物件は、管理組合が機能しているサインです。逆に「次回修繕資金が不足」と総会議事録に記載があれば要注意です。修繕積立金の値上げが予定されているケースでは、購入後のキャッシュフローが圧迫されるためです。
価格は周辺の成約事例と比較するのが王道ですが、もう一歩踏み込んで「購入後5年以内に売却できる価格」を逆算しておくと安心です。具体的には同じ築年数の物件賃料と利回りから収益還元価格を計算し、そこから3%程度の下落を見込む方法が実務的です。この想定売却価格より割安なら、出口戦略に余裕が生まれます。
購入前に必須の収支シミュレーション
実は、多くの初心者が購入直後に後悔するのは「計画より支出が多かった」という一点です。そのほとんどがシミュレーション不足に起因します。
収支計算では、ローン返済、管理費、修繕積立金、固定資産税、賃貸管理手数料、火災保険料まで網羅してください。とくに修繕積立金は築年数に応じて5年おきに1.5倍程度へ引き上げられることが多く、ここを見落とすと後年の手残りが激減します。
金利シナリオは最低でも「現状維持」「0.5%上昇」「1.0%上昇」の三段階を設定するとリスクに強い計画になります。2025年時点で都市銀行の変動金利は1.1%前後ですが、日銀の政策変更次第で上昇する可能性があります。1.0%上昇を想定した計算でキャッシュフローが月1万円以上確保できるなら、ほぼ安全圏といえます。
最後に空室リスクです。郊外エリアの単身用は平均空室率8〜10%とされています(レインズデータ)。6週間の空室を年間1回発生すると仮定し、その家賃を差し引いたうえで黒字になるかを必ず確認しましょう。この段階で赤字になるなら、購入見送りまたは価格交渉が妥当です。
運用フェーズで失敗しない管理と出口戦略
基本的に、購入後の運用で収益を伸ばす方法は「入居者満足度を高め長期入居を促す」これに尽きます。とはいえ高額な設備更新を続けていては本末転倒なので、小規模で効果的な改善策を選ぶことが重要です。
例えば玄関のスマートロック化は3万円程度で導入でき、セキュリティ面の印象を大きく向上させます。また照明をLEDに替えるなどランニングコストを下げる工夫は、入居者とオーナーの双方にメリットがあります。こうした改善は退去時の原状回復を兼ねて行うと費用効率が高まります。
出口戦略では「賃借人付き収益物件」として売却する方法を検討してください。住宅ローン控除を活用したい実需の買主より、利回りを評価する投資家の方が価格を高く提示するケースが増えているためです。健全な管理が続いている物件は利回り下落幅が小さいため、購入時より高値で売れる例も珍しくありません。
結論として、管理を手抜きしないオーナーの物件は資産価値が維持され、出口でも選択肢が広がります。購入時の利回りだけでなく、運用と売却まで含めた総合収益で判断する姿勢が欠かせません。
2025年度の制度と税務ポイント
まず押さえておきたいのは、2025年度も「住宅ローン控除」は原則として居住用が対象であり、賃貸目的の区分所有には適用されません。一方、賃貸経営に関する減価償却や損失通算は従来通り利用できます。
減価償却では、木造は22年、鉄筋コンクリート造は47年が法定耐用年数です。中古取得時には残存年数を計算し、それに1.5を掛けた年数が償却期間になります。築30年のRC造なら「47−30=17年」、これを1.5倍しても法定残存期間の17年を下回るため17年で償却できます。短期間で経費計上できるため、所得が高い投資家には節税メリットが大きい点を覚えておいてください。
また2025年度税制改正で創設された「長期保有賃貸住宅の修繕積立特別控除」(5年間の時限措置)は、中古取得後に10年以上保有する予定の物件にも適用可能です。ただし対象となるのは国交省が定める長期修繕計画を組合が策定しているマンションに限られるため、購入前に確認しましょう。
固定資産税については経年による評価額の下落が続くため、築20年以上では年数千円規模で負担が軽減するケースもあります。利回り計算の際は、自治体の評価証明書を取り寄せ、実際の税額を見積もることで精度が上がります。
まとめ
中古マンション投資で失敗しないためには、購入前の物件選定と収支シミュレーション、購入後の管理と出口戦略を一貫して考えることが何より大切です。立地と管理状態に妥協せず、慎重な数字の検証を行えば、金利や空室の変動にも耐えられる投資計画が作れます。さらに2025年度の税制を味方につければ、キャッシュフロー改善と節税を両立させることも可能です。これらのポイントを押さえ、次の物件探しでは「中古でも失敗しない」と自信を持って一歩踏み出してください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 東日本不動産流通機構(レインズ)マーケット情報 – https://www.reins.or.jp
- 国税庁 所得税基本通達 – https://www.nta.go.jp

