不動産投資に興味はあるけれど、数千万円の物件を直接買うのは怖い。そこで手軽な選択肢として浮上するのがREIT(リート)です。しかし「少額で分散投資できる」と聞いて飛びついた友人が、思ったほど配当が伸びず後悔している姿を見て、あなたも不安を感じていないでしょうか。本記事ではREITの代表的なデメリットを最新データとともに整理し、リスクを理解したうえで賢く活用する方法を丁寧に解説します。読み終えたころには、REITを選ぶべきか直接物件を買うべきか、自分なりの基準がはっきりするはずです。
REITの仕組みをおさらいし、デメリットの土台を確認
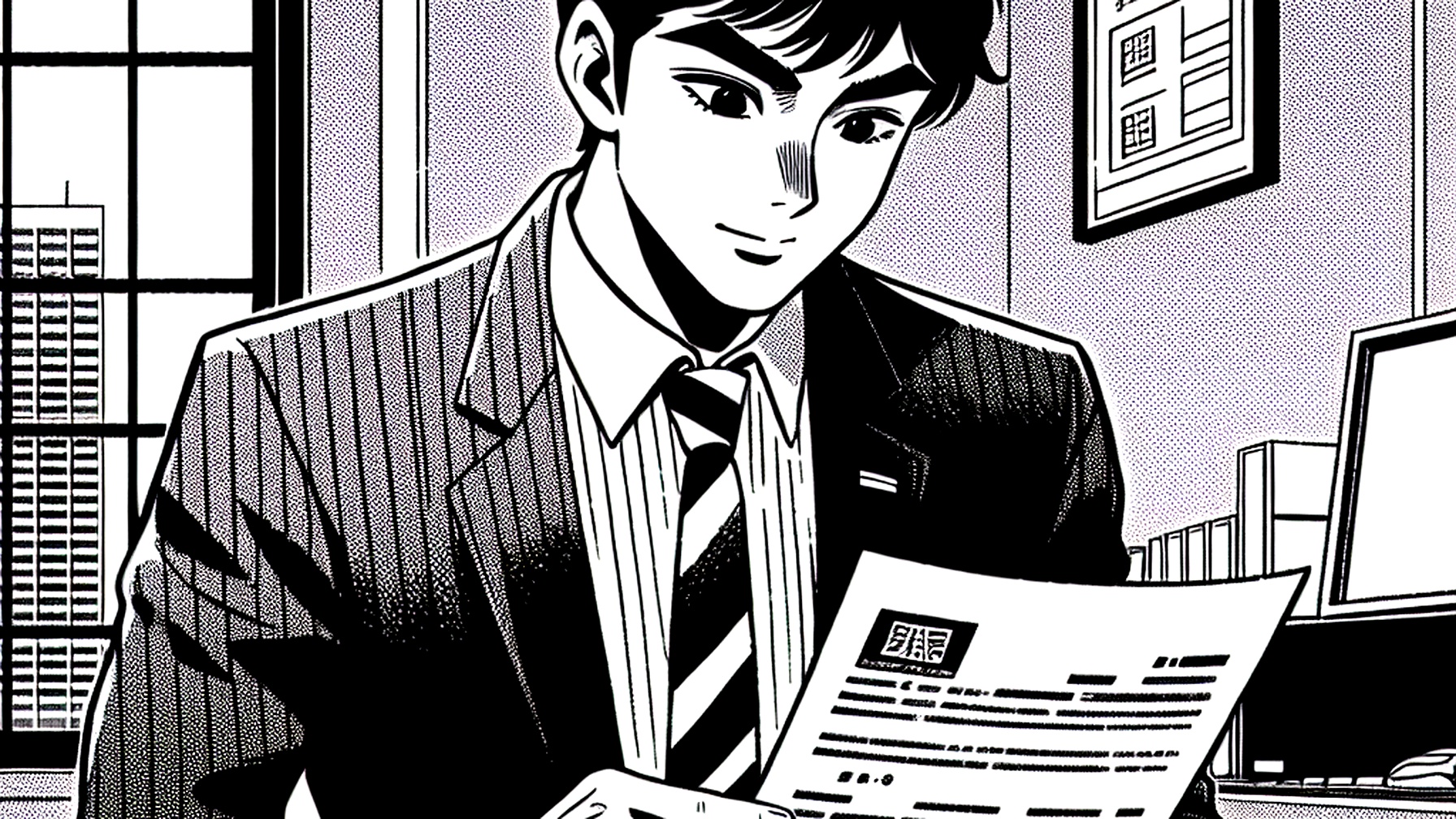
まず押さえておきたいのは、REITが不動産を直接保有するのではなく、投資家から集めた資金で複数物件を運用し、その賃料や売却益を分配する仕組みだという点です。言い換えると株式と似た証券化商品であり、証券取引所で日々価格が動きます。この構造がもたらす利便性と同時に、後述するさまざまな不利益の出発点にもなります。
実は2025年9月時点で上場しているJ-REITは69銘柄、総資産は約21兆円と東証資料に記載されています。都心オフィスや物流施設への投資割合が高い一方、ホテル系はコロナ後の回復で分配金が戻りつつある段階です。こうした資産構成や運営方針が投資家に見えやすい反面、「分散しているから安全」と短絡的に考えると、リスクを軽視しがちになります。
またREITの運用会社は物件を取得・管理する際に外部から借入れ(レバレッジ)を行います。金融庁の2025年度統計では平均LTV(総資産に占める借入比率)が46%で、低金利なら収益を押し上げるものの、金利上昇局面では逆風です。これらの基本構造を理解することが、後述するデメリットを正しく評価する第一歩となります。
価格変動リスクと金利感応度は意外に大きい
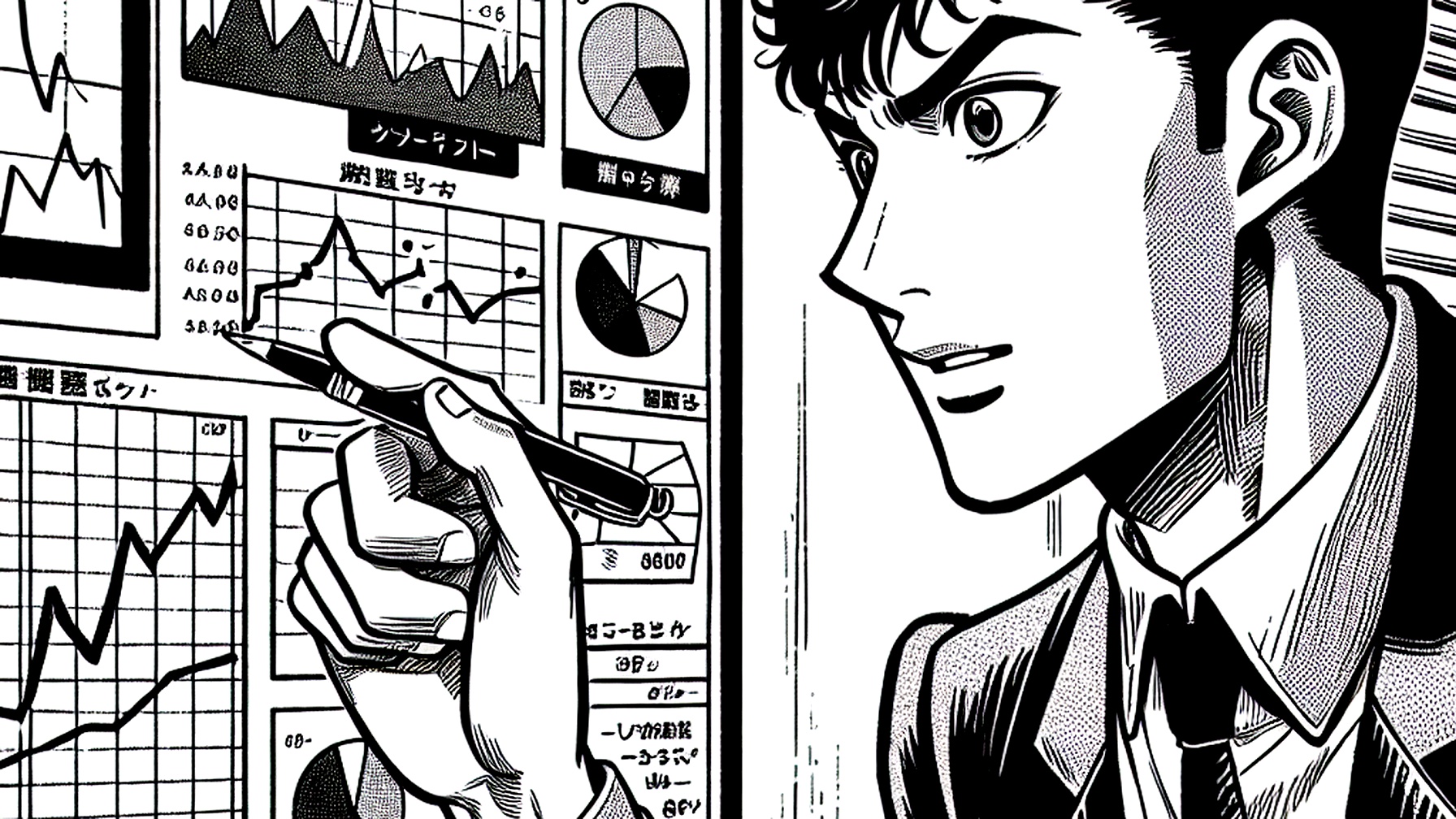
ポイントは、REITが「不動産らしさ」と「株式らしさ」を併せ持つため、思った以上に価格変動が激しいことです。東証REIT指数は2024年10月に年初来高値の2,200ポイントを付けた後、日銀の政策修正を受けて2025年3月には1,930ポイントまで下落しました。半年でおよそ12%の値幅が生じた計算になります。
まず価格変動の主因として、長期金利の動向が挙げられます。REITの配当利回りは株式の配当利回りより高いとされますが、10年国債利回りが1%台後半へと上昇した2025年春には、相対的な魅力が薄れ株式と同様に売られました。一方で現物不動産は短期的に価格が動きにくいため、REITの方がボラティリティ(変動率)が高い点に注意が必要です。
さらに市場のセンチメントも影響します。物流特化型REITに需要が集中すると、NAV倍率(一口当たり純資産価格との比率)が1.3倍を超え、物件の実勢価格から乖離したケースもありました。つまり、市場が盛り上がるほど割高で買ってしまうリスクが潜在します。逆に暴落局面では割安になるため、タイミングを見計らえる投資家には妙味があるものの、長期保有だけを想定している初心者には難易度が上がるのです。
分配金が安定しない理由を数字で読み解く
重要なのは、REITの分配金が法律上「利益の90%以上を配当すれば法人税が実質ゼロになる」という仕組みによって高水準を保っているものの、安定を保証するものではない点です。国土交通省の2025年度レポートによれば、上場REITの一口当たり分配金は平均で前年比3%増でしたが、個別には前年比20%以上減少した銘柄も存在します。
まず、賃料収入の変動が直接響きます。オフィス系REITでは、テレワーク定着のあおりを受け、空室率が2023年秋の6%から2025年夏には8%台へ上昇しました。空室が増えれば当然賃料収入が減り、分配金が下がります。またホテル系REITはインバウンド需要で急回復したものの、変動賃料契約が多いため景気後退期には減配リスクが顕著です。
次に、修繕費や物件の入れ替えコストも分配原資を圧迫します。築年数が進むと大規模修繕が必要になり、一時的にキャッシュフローが細るケースがあります。さらに物件売却損が出た場合、会計上の評価損は配当余力を削ります。つまり、表面利回りだけを見て銘柄を選ぶと、実際の分配金が計画より下振れする可能性が高まるのです。
物件の老朽化と追加投資リスクは投資家も無縁ではない
実はREIT投資家は間接的とはいえ、保有物件の老朽化リスクを避けられません。運用会社は長期的な資産価値を守るために、定期的なCAPEX(資本的支出)を行います。日本不動産研究所の2025年調査では、築20年超え物件の増加に伴い、J-REIT全体の修繕積立金は前年度比15%増えました。この出費は分配金の原資に影響するうえ、場合によっては増資による希薄化を招きます。
また築古物件を抱えたREITは、不動産価値の下落でNAVが縮小するリスクがあります。たとえば築25年の郊外オフィスを多く持つ銘柄は、評価減を反映してNAVが3%目減りした例が報告されています。評価減が続けば格付け機関がレーティングを引き下げ、借入金利が上がる可能性もあります。金利負担が高まれば分配金はさらに下がり、悪循環に陥る恐れがあります。
一方で新規取得やリノベーションを積極的に行うREITは成長余地がありますが、新規投資資金を確保するための増資が避けられません。増資で発行口数が増えれば、一口当たり分配金が希薄化しやすくなります。投資家は物件ポートフォリオの築年数分布や、運用会社の修繕方針、増資履歴を定期的にチェックすることが求められます。
2025年度税制で見落としがちな注意点
まず押さえておきたいのは、REITの分配金は「配当所得」として課税され、2025年度も20.315%(所得税・住民税・復興特別所得税)で源泉徴収される点です。これ自体は株式と同じですが、損益通算や住民税申告方法によって手取りが変わるため注意が必要です。
たとえばNISA(少額投資非課税制度)の新しい成長投資枠では、上場REITも非課税対象になります。非課税保有限度額は生涯1,800万円ですが、分配金課税をゼロにできる一方、損失が出ても課税口座の株式とは通算できません。損失リスクを十分に理解しなければ、節税どころか損失補填が難しくなる場合があります。
また外国REITを円建てETFで購入すると、分配金に現地課税がかかり、日本の課税と二重になることがあります。租税条約に基づき確定申告で外国税額控除を受ければ解消できますが、手続きの手間と控除上限の存在がデメリットです。加えて相続税評価額は上場株式と同じ時価評価となり、急落時を除き現金より高く評価される傾向があります。相続対策としては必ずしも有利とは言えません。
2025年度税制改正ではREITに対し新たな優遇や不利変更はありませんが、10万円を超える売買で金融所得課税一体化の議論が進んでいます。将来制度が変わった場合、課税コストが増減するリスクを踏まえてポートフォリオを検討する姿勢が大切です。
まとめ
ここまで、価格変動の大きさ、分配金の不安定さ、物件老朽化による追加投資、税制面の落とし穴という四つの観点からREIT デメリットを整理しました。REITは少額で不動産に分散投資できるメリットがある一方、市場の変調や金利上昇に敏感な金融商品です。投資を検討する際は、指数のボラティリティ、運用会社のLTVや築年数分布、そして税制変更の可能性をセットで確認しましょう。そのうえで、自分のリスク許容度と投資期間に合った比率で組み込めば、ポートフォリオ全体のバランスを保ちながら資産形成を進められます。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 不動産市場動向報告2025年度版 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁 J-REIT年次報告2025 – https://www.fsa.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料2025年3月 – https://www.boj.or.jp
- 日本不動産研究所 不動産投資インデックス2025 – https://www.reinet.or.jp

