不動産投資を始めたいけれど、新築は価格が高くて手が出ない――そんな悩みから「マンション投資 中古 選び方」を検索した方も多いでしょう。実は中古マンションには初期費用を抑えつつ利回りを高めやすいメリットがあります。ただし、見極めを誤ると修繕費や空室で苦労するのも事実です。本記事では立地や築年数だけでなく、2025年度の最新制度を活用した資金計画まで総合的に解説します。読み終えたころには、あなた自身で“買ってよい物件”と“避けるべき物件”を仕分ける力が身につくはずです。
中古マンション投資が注目される理由
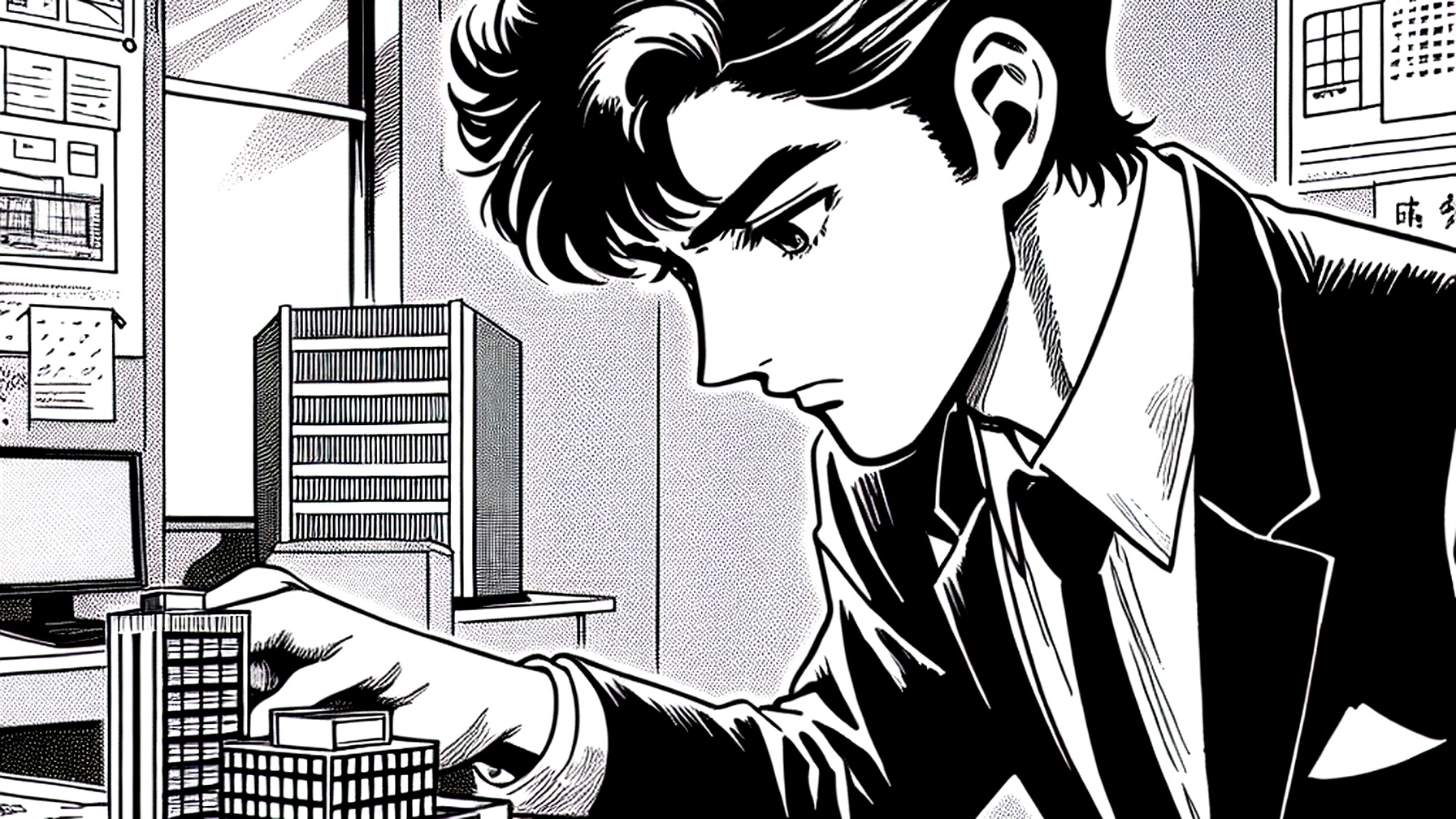
まず押さえておきたいのは、中古マンションの投資環境がここ数年で大きく変わった点です。不動産経済研究所のデータによると、2025年上半期の首都圏中古マンション成約価格は平均4,780万円で、新築の約63%にとどまります。価格差が大きいぶん、同一エリアでも利回りを確保しやすい構造になっています。
一方で、建物の劣化や設備更新の負担が重くのしかかるリスクは避けられません。しかし、築20年前後の物件でも管理状態が良ければ、家賃水準は新築比80%程度で推移する事例が多く見られます。つまり、購入価格と家賃下落率のバランスを見極めれば、想定以上のキャッシュフローを得ることが可能です。
さらに、2025年度の住宅ローン金利は依然として低水準を維持しており、変動金利で1%前後、固定でも1.5%前後が主流です。初期コストと調達コストの両方を抑えやすい現在は、中古マンション投資の“仕込みどき”といえるでしょう。
立地判断で外さないための視点
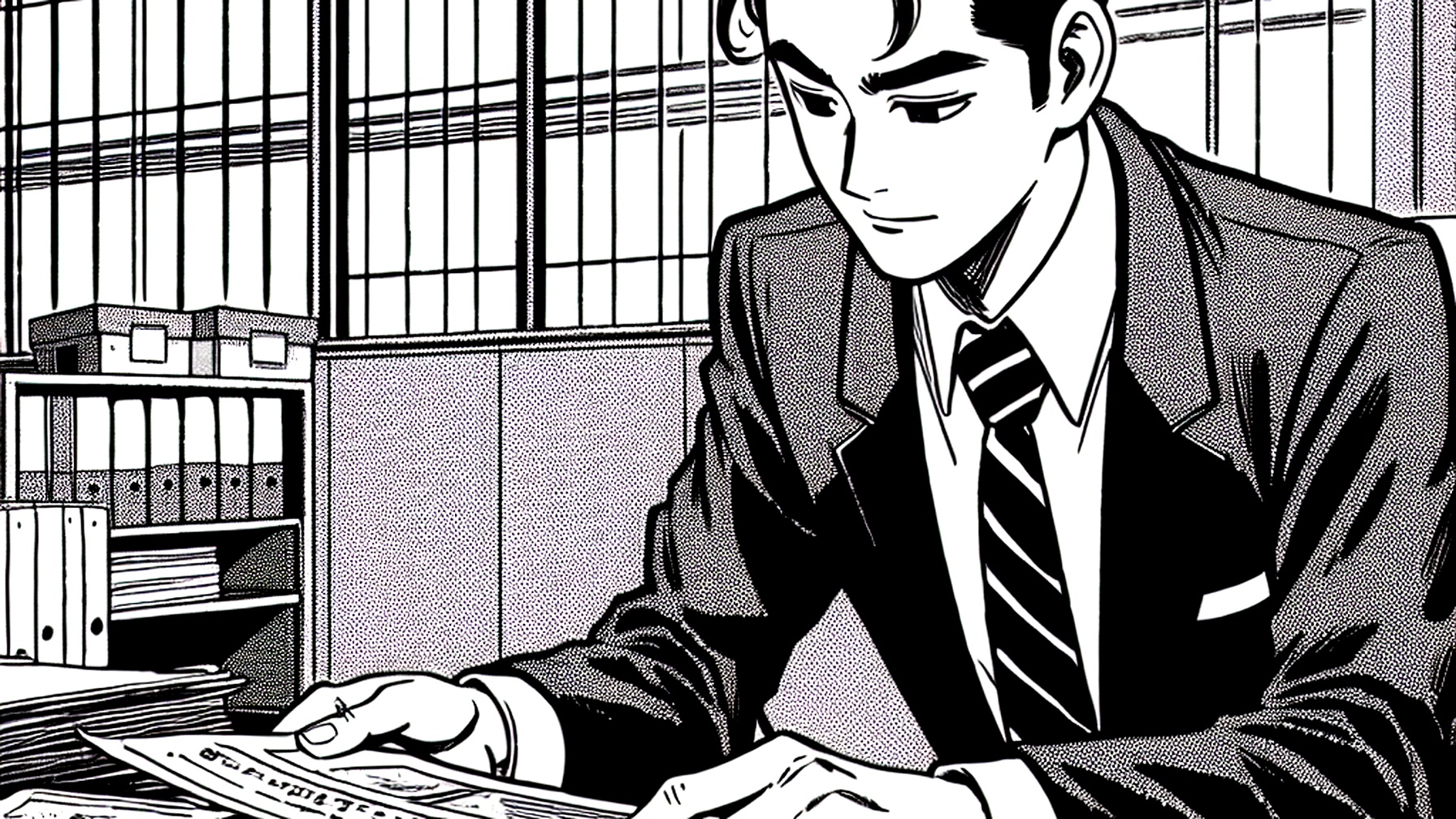
ポイントは、人口動態と交通インフラの二軸を同時に確認することです。市区町村単位の人口は総務省「住民基本台帳」に無料公開されており、過去5年の増減率を見るだけでも十分な指標になります。増加傾向のエリアでは空室期間が短縮され、安定経営につながります。
次に鉄道やバスのダイヤ改正を把握します。国交省の資料では、2023年以降に終電繰り上げが進み、郊外駅の実質的な利便性が低下した路線も存在します。帰宅時間の選択肢が減る地域では、若年単身層が敬遠する傾向が強まり、結果として賃料下落を招きやすいのです。
加えて、再開発情報も欠かせません。例えば、東京・品川周辺では2028年に品川新駅エリアの街開きが予定されており、周辺中古マンションの売り出し価格は既に前年比+6%で推移しています。将来的な資産価値上昇を狙うなら、再開発計画の有無を行政の公開資料で確認する習慣をつけましょう。
物件の築年数と修繕履歴を読むコツ
実は、築年数よりも大規模修繕のタイミングが収支を左右します。マンションはおおむね12~15年周期で外壁や屋上防水の工事が行われ、そのたびに修繕積立金の不足問題が顕在化します。国交省の「マンション総合調査」によれば、築30年超の物件のうち32.5%が積立金不足を抱えています。
購入前に確認する書類は「長期修繕計画」と「総会議事録」です。計画表に次回工事の費用と実施年度が明記されていれば、将来の出費を具体的に織り込めます。また議事録で滞納率や反対意見の多寡をチェックすることで、管理組合の健全度を測れます。反対が多い物件は合意形成に時間がかかり、修繕が遅れて資産価値を下げる恐れがあります。
築25年を超える物件でも、直近で大規模修繕を終えているケースなら、今後10年程度は大きな支出が発生しにくい点が魅力です。つまり、「築古=危険」と単純に切り捨てず、修繕履歴と積立金残高をセットで評価する姿勢が重要なのです。
資金計画と2025年度の制度活用
基本的に、投資用ローンは自己資金2割以上を入れると金利優遇を受けやすくなります。たとえば、都市銀行A社では自己資金20%超で金利0.2%の優遇が適用され、35年返済なら総支払額で約280万円の差が生まれます。
2025年度も続く「住宅ローン減税(投資用は対象外)」と混同しがちですが、個人で購入して賃貸に出すケースでも、適用できる所得控除は限られます。重要なのは、不動産所得の赤字を給与所得と損益通算できる制度が存続している点です。減価償却費やローン利息を計上すると、実質手取りが向上する可能性があります。
また、賃貸経営向けの補助としては、国交省の「賃貸住宅省エネ改修支援事業」が2025年度も継続中です。窓の断熱改修や高効率給湯器の導入に対し、工事費の1/3・上限100万円を補助する内容で、入居者満足度の向上と空室対策を同時に図れます。資金計画に上乗せすることで、将来の家賃アップを現実的に狙えます。
管理体制と出口戦略をセットで考える
重要なのは、入居者募集から売却まで一貫して見通すことです。管理会社の選定基準として、入居付けスピードと原状回復費の算定基準を比較すると、年間コストのブレを小さくできます。たとえば、同じ家賃水準でも原状回復費が平均より25%高い会社を選ぶと、5年で累計50万円以上の差が出ることも珍しくありません。
出口戦略は「賃料維持型」と「キャピタルゲイン型」に大別できます。賃料維持型では築浅に近い状態を保つための小まめなリフォームが必要です。一方、キャピタルゲイン型では再開発や人口増エリアで値上がりを待ち、5~7年で売却するプランが有効です。どちらを選ぶにせよ、購入時点で売却ターゲット(個人、法人、海外投資家など)を想定しておくと、リフォーム仕様や管理方針に迷いがなくなります。
最後に、不動産仲介会社との関係構築も無視できません。売却時に専任媒介を依頼することで広告露出を最大化しつつ手数料を抑える交渉が可能になります。つまり、買う段階から“売るときに協力してくれる相手”を選ぶことで、投資全体のリスクとコストを引き下げられるわけです。
まとめ
ここまで、中古マンション投資で失敗しないための視点を五つ紹介しました。価格差と低金利を生かしつつ、人口動態や再開発といった将来価値を見極める姿勢が不可欠です。さらに、修繕履歴と管理体制を丁寧にチェックし、2025年度の省エネ補助制度を組み込むことでキャッシュフローを底上げできます。行動に移す際は、紹介した公的データを活用しながら、物件ごとに収支シミュレーションを徹底しましょう。今日から情報収集を始めれば、数か月後には自信を持って購入判断ができるはずです。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省「マンション総合調査」 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅省エネ改修支援事業 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 日本銀行 金融機関貸出金利統計 – https://www.boj.or.jp

