不動産投資に興味はあるものの、「本当に儲かるのか」「損をする人はなぜ失敗するのか」と不安を感じる方は多いでしょう。特にネット上ではメリットばかりが強調されがちですが、実際には思わぬデメリットに直面して苦しむ投資家も少なくありません。本記事では、2025年9月時点の最新情報を交えながら、不動産投資 デメリット なぜという疑問に答えます。読了後には、自分に合ったリスク許容度を見極め、後悔しない判断ができるようになるはずです。
投資なのに「儲からない」ことが起こる根本原因
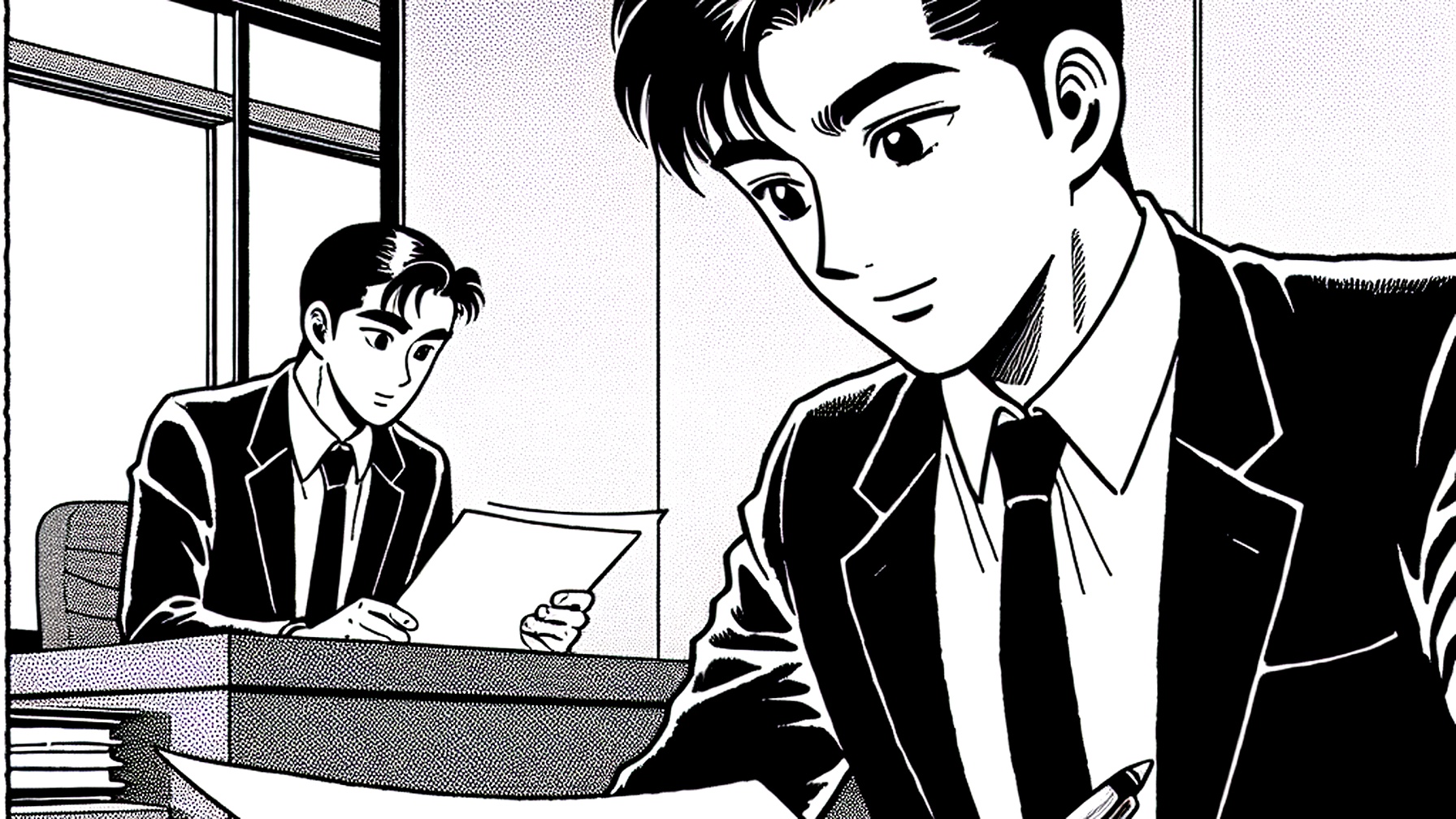
まず押さえておきたいのは、不動産投資は元本が保証されないれっきとした投資商品である点です。株式や投資信託と異なり、月々の家賃収入があるため安全に見えますが、収益は空室率や修繕費で簡単に吹き飛びます。実は、国土交通省が2025年3月に公表した「賃貸住宅市場動向調査」では、築20年超の物件で平均空室率が17%に達していました。家賃収入が1割減るだけでも年間キャッシュフローは大きく悪化するため、期待利回りがそのまま実現することは稀です。
一方で、不動産価格は景気の波を強く受けます。2020〜2022年にかけては低金利とインフレ期待で価格が高騰しましたが、2024年以降は市場全体で取引件数が減少し、地方では価格調整が始まりました。つまり、購入価格が高止まりしている局面で安易に飛びつくと、家賃下落と資産価値下落の二重苦を背負いかねません。これが「投資と名が付くのに儲からない」最大の理由です。
空室リスクが家計を直撃するメカニズム
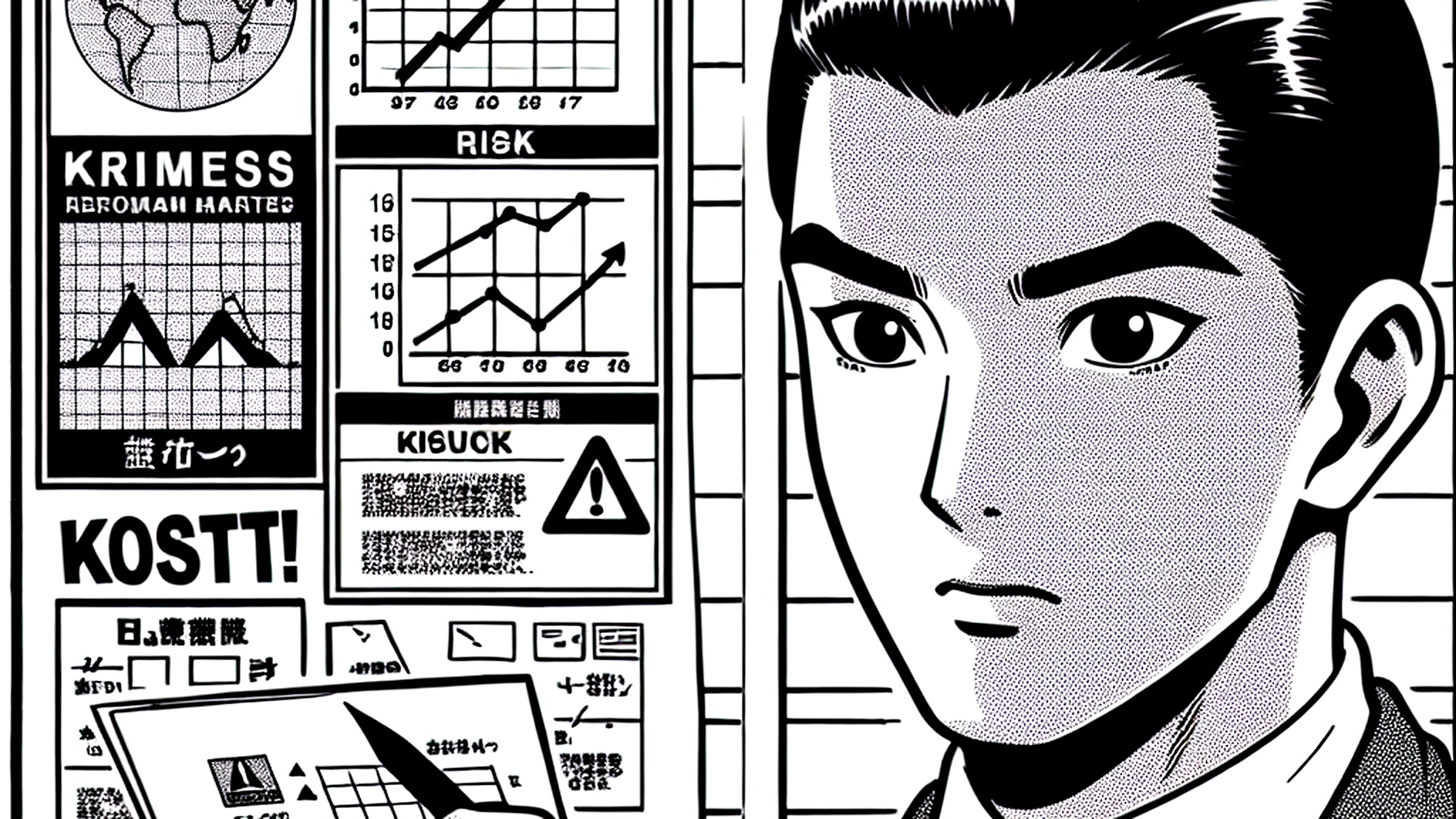
重要なのは、空室が続くと単に家賃が入らないだけでなく、広告費やリフォーム費が追加で発生する点です。平均的な1Kマンションの場合、募集広告費は家賃1〜2カ月分が相場です。さらに、壁紙や床の補修など原状回復費に20万円前後かかることも珍しくありません。空室期間が3カ月を超えると、年間収支は一気に赤字に転落しやすくなります。
また、総務省の2025年7月の人口推計によれば、地方都市部でも20〜39歳の若年層人口は年率1%超で減少しています。入居者ターゲットが縮小すれば、空室リスクは今後も高まる見通しです。投資家ができる対策は、駅徒歩10分以内や生活利便施設が近い物件を選び、物件の競争力を高めることに尽きます。それでも0%にすることはできないため、シミュレーション時に最低でも10%の空室率を織り込む姿勢が欠かせません。
キャッシュフローを圧迫する維持費と税金の落とし穴
ポイントは、表面利回りだけで判断すると維持費の重さに後で気付くということです。不動産取得後は固定資産税・都市計画税が毎年かかり、マンションなら管理費・修繕積立金も発生します。東京都23区の築15年ワンルームであれば、管理費と修繕積立金の合計は月1万円超が一般的で、固定資産税等は年間7万円前後です。家賃8万円としても、手取り利回りは単純計算で2%台まで落ち込みます。
さらに、築年数が進むほど大規模修繕の負担が増えます。国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」では12年周期で外壁や屋上防水の更新を推奨しており、区分所有者負担が一度に数十万円に上る例もあります。また、2025年度も継続する「住宅ローン減税」は原則自己居住用が対象であり、投資用物件には適用されません。これらのコストを意識せずに購入すると、家賃収入でローン返済はできても、税金や修繕積立で手元資金が枯渇しかねないのです。
売却時に待ち受ける流動性の壁
実は、不動産は買うより売る方が難しい資産です。株式のようにクリック一つで現金化できず、売却まで平均3〜6カ月はかかります。日本不動産流通機構が2025年4月に発表したデータでは、首都圏中古マンションの成約までの平均日数は89日でしたが、郊外に限れば120日超と差が開いています。しかも売り急ぐほど価格交渉で不利になり、購入時より1〜2割下げてようやく売れるケースも少なくありません。
加えて、譲渡益が出た場合は所得税・住民税合わせて20%(長期譲渡の場合)を支払う必要があります。一方、譲渡損失が出ても給与所得と損益通算できない点がネックです。投資家は出口戦略を最初に描いておかなければ、「売るに売れない」状態で資金がロックされる危険にさらされます。長期的な人口動態や再開発計画を精査し、出口まで想定して購入する姿勢が不可欠です。
制度を利用してもリスクがゼロにならない理由
まず、2025年度の不動産関連支援策として個人投資家が使える代表例は「所得税の青色申告特別控除」や「住宅取得資金贈与の非課税特例(投資用除く)」程度で、直接的な補助金は存在しません。インフレ対策で注目される「固定資産税の負担調整措置」も、評価額が急騰した一部地域が対象で投資用物件全般に恩恵が及ぶわけではないのです。
つまり、制度はあくまで税負担の一部を軽減するだけで、空室や価格下落といった本質的リスクは残ります。また、金融機関の融資姿勢は2024年以降、自己資金3割以上を求める例が増加しました。低金利を武器にフルローンでレバレッジを効かせる手法は、金融庁の監査強化で通りにくくなっています。結局のところ、健全な自己資金比率と綿密な事業計画を持つ投資家しか生き残れない、という現実を直視する必要があります。
まとめ
本記事では、不動産投資 デメリット なぜという疑問に対し、空室リスク、維持費・税金、価格変動、流動性の壁、制度の限界という5つの視点から解説しました。見えてきたのは、家賃収入が自動的に入るという期待と裏腹に、多面的なコストと不確実性が付きまとう点です。それでも不動産投資を選ぶなら、空室率10%以上、売却価格2割下落といった厳しいシナリオでシミュレーションを行い、自分の家計に耐えられるかを確認してください。最後に、物件探しよりも先に資金計画と出口戦略を描くことが、後悔しない投資への最短ルートだと強調しておきます。
参考文献・出典
- 国土交通省「賃貸住宅市場動向調査」 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局「人口推計(2025年7月)」 – https://www.stat.go.jp
- 日本不動産流通機構「月例マーケットウオッチ2025年4月」 – https://www.retio.or.jp
- 金融庁「金融レポート2024」 – https://www.fsa.go.jp

