気になる物件を見つけても「家賃収入だけで本当に利益が残るのか」と不安になる人は多いでしょう。特に築浅マンションは価格が高めなぶん、表面利回りが低く見えて手が出しづらいと感じがちです。しかし、維持費や空室リスクを含めた“実質利回り”で比べると、築浅物件のほうが堅実に資産を増やせるケースも少なくありません。本記事では「築浅 マンション投資 実質利回り」の関係を基礎から解説し、具体的な計算方法、物件選び、税制活用まで網羅します。読み終えたとき、あなたは数字に基づいて投資判断を下せるようになり、長期で収益を最大化する道筋が見えるはずです。
実質利回りを理解する
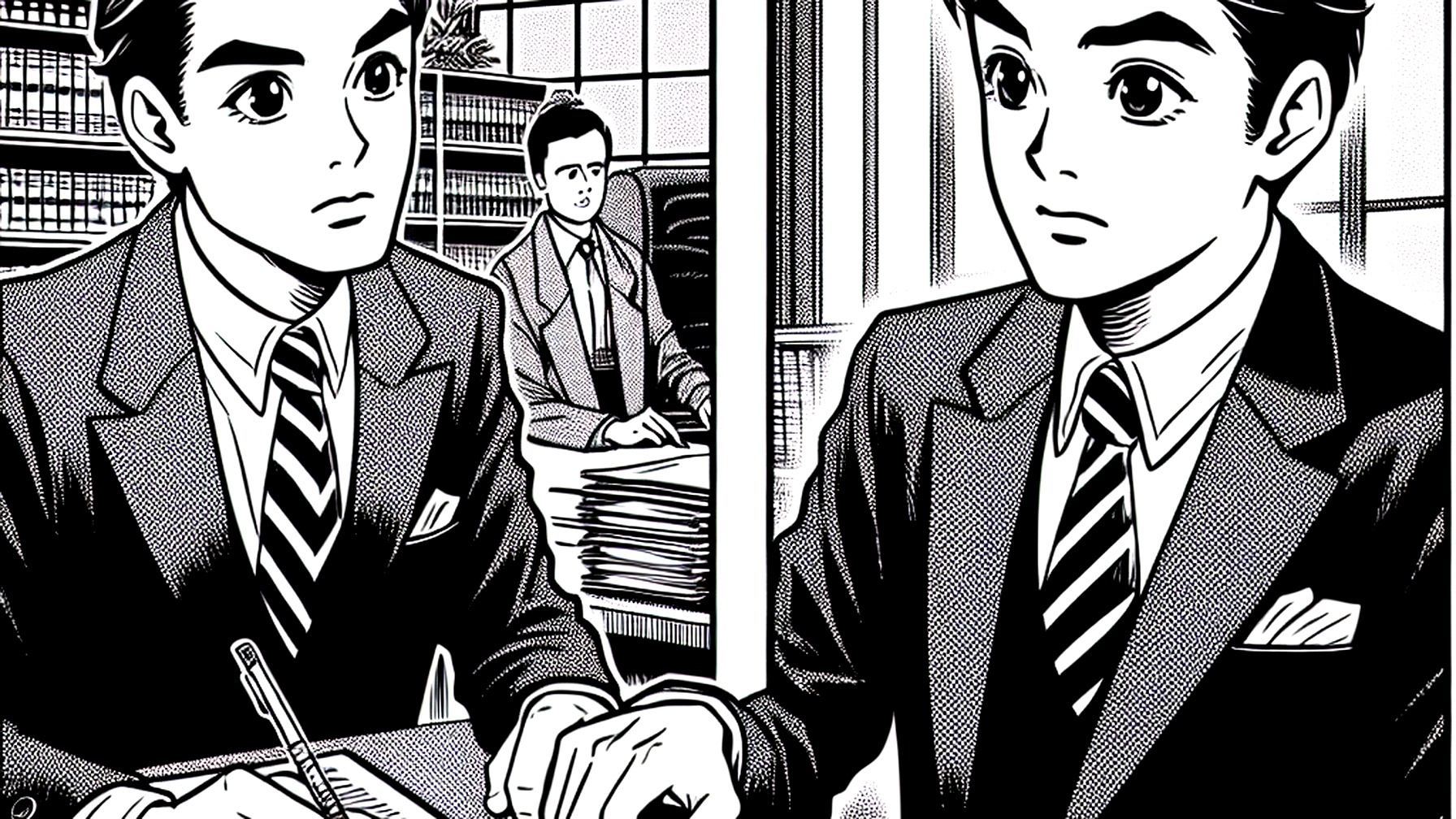
重要なのは、家賃を物件価格で割った“表面利回り”だけでは投資成否を測れない点です。管理費や修繕積立金、固定資産税、空室期間、ローン金利などを差し引いた後の利益を年率で示す指標が実質利回りになります。言い換えると、手元に残ったキャッシュをベースに投資効率を測る計算式です。
実質利回りを求める際は、まず年間家賃収入から運営費と空室損を差し引きます。そして、元本返済を除いた年間ローン利息を控除し、残ったキャッシュフローを取得総額で割ることで算出可能です。例えば月額家賃10万円の部屋を3戸保有し、年間運営費が家賃収入の15%、ローン金利1.5%で借入比率70%という前提なら、表面利回り6.0%でも実質利回りは約4.2%まで低下する場合があります。
一方で運営費や空室率を抑えられれば、表面利回りは同じでも実質利回りを底上げできます。築浅マンションがこの点で優位性を持つ理由を、次の章で詳しく見ていきましょう。
築浅物件が持つ優位性
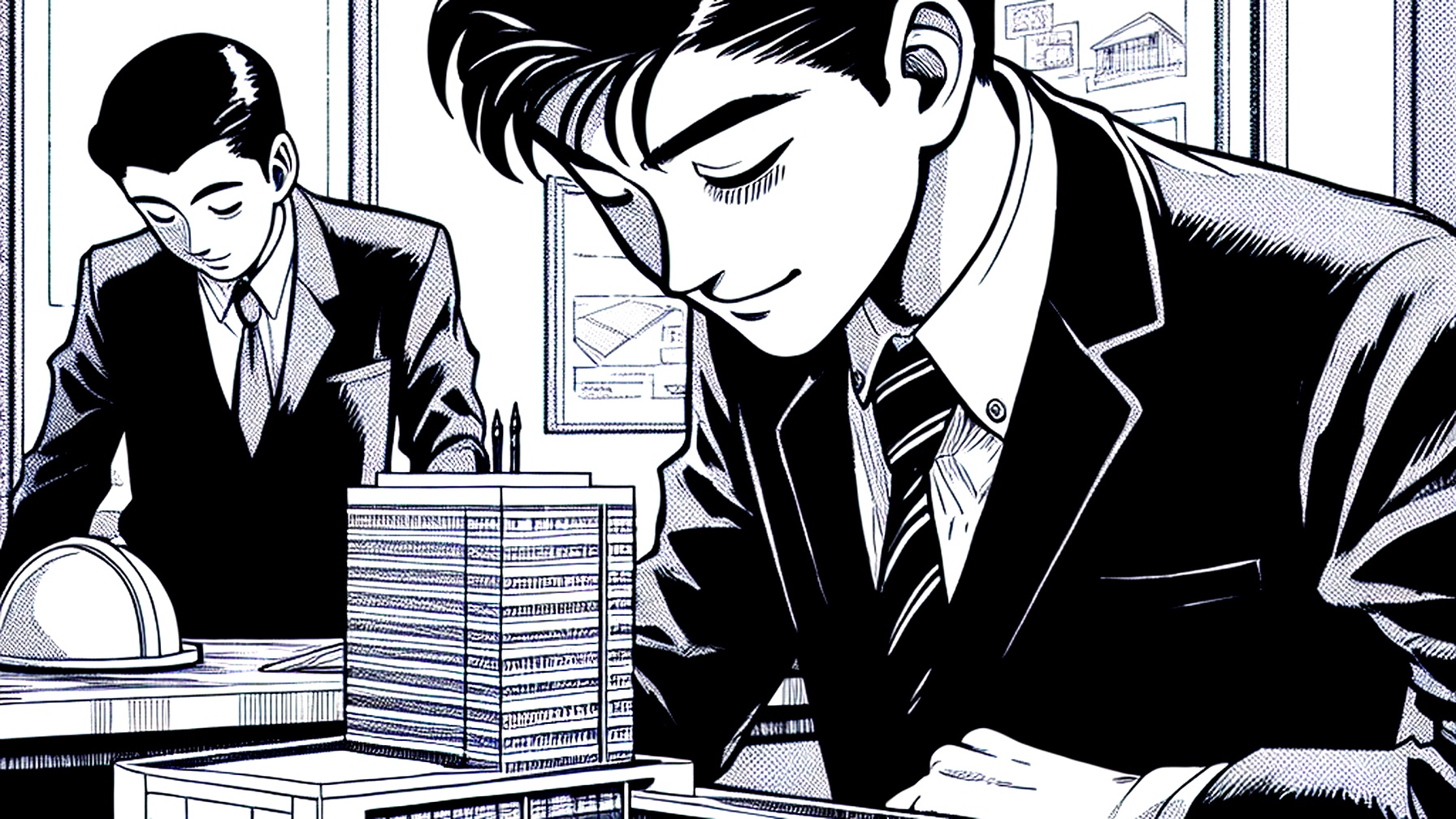
まず押さえておきたいのは、築浅マンションが修繕費と空室リスクを抑えやすい点です。新規入居者が設備の新しさを重視する傾向は、国土交通省「住宅市場動向調査2024」によれば年々高まっています。そのため、築後5年以内の物件は平均入居期間が長く、空室率が築25年以上の半分以下にとどまります。
さらに大規模修繕が当面不要なため、修繕積立金は築20年超の物件より2〜3割低く設定されているケースが一般的です。日本マンション管理士会の2025年調査では、築3年の平均修繕積立金は月180円/㎡、築25年は月270円/㎡でした。この差額が長期で見れば実質利回りに大きく影響します。
しかし、購入価格が高いと投資回収が遅れるリスクも生じます。そこで、賃料の下落幅が小さい都心部や人口増エリアを選定し、家賃下落と価格リスクを同時に抑える戦略が有効です。都心のワンルーム平均表面利回りは4.2%と低く見えますが、維持費が少ないため実質利回りは3.7%前後に踏みとどまる傾向があります。築浅物件のもつ“目に見えない余裕”が、安定収益の根拠となるのです。
数字で見る築浅マンションの投資指標
実は、数字を具体的に当てはめることで築浅マンションの優位性がより鮮明になります。例として、2025年9月の東京23区平均価格7,580万円の築3年ファミリータイプを取り上げます。家賃相場は月24万円、表面利回りは3.8%です。
ここで運営費を家賃の20%、空室率5%、ローン金利1.2%、借入期間35年、借入比率80%とします。条件を収支シミュレーションに入力すると、年間キャッシュフローは約75万円です。取得総額(諸費用込)を8,100万円とすれば、実質利回りはおよそ3.1%となります。一見低い数字ですが、耐用年数の長さとリセールバリューを考慮すると、同じ利回りでも築古物件より安全域が広がる点がポイントです。
次に築25年で価格3,800万円、家賃月15万円、表面利回り4.7%の物件を比較します。運営費25%、空室率10%、金利同条件で計算すると、年間キャッシュフローは約50万円に落ち込み、実質利回りは約2.6%です。数字はあくまでモデルケースですが、維持費と空室率の差が実質利回りを逆転させる構図が見えてきます。
このように、築浅 マンション投資 実質利回りの判断では、購入価格の高さよりも運営コストの低さが長期的な利益にどう寄与するかをシミュレーションで確認することが欠かせません。
実質利回りを高める運用術
ポイントは、初期購入後も改善できる余地を探すことです。まず、管理費と修繕積立金の使途を管理組合の総会議事録で確認し、適正水準かを検証しましょう。適正化が進めば月額数千円でも経費削減につながり、複利効果で利回りが改善します。
次に、賃貸募集のターゲットを明確化し、家具・家電の設置やインターネット無料化など競争力を強化します。国土交通省の2025年首都圏空室率レポートでは、ネット無料物件の平均空室期間は通常より12日短いと報告されています。短期空室の解消は、そのまま実質利回りの底上げに直結します。
さらに融資条件の見直しも効果的です。2025年度の住宅ローン減税は新築・築浅投資用物件の対象外ですが、投資ローン金利は個人信用力や物件評価で変動します。家賃収入が安定し、残債が減った段階で借換え交渉を行い、金利を0.3ポイント下げられれば35年総返済額が約450万円減る計算です。返済負担が軽減されれば、同じ家賃でも実質利回りは向上します。
2025年度税制と資金調達のポイント
まず押さえておきたいのは、2025年度の所得税・住民税に適用される「損益通算」のルールです。家賃収入が赤字になった場合でも、給与所得と通算可能な範囲は最大年間20万円で据え置かれています。節税効果を期待しすぎず、黒字運営を前提にシミュレーションを作ることが賢明です。
一方で、登録免許税と不動産取得税の軽減措置は築20年以内の耐火構造住宅に限定して2025年度も継続しています。築浅マンションなら取得時コストを約40万円程度抑えられる場合があり、この差額は購入初年度から実質利回りに直結します。
資金調達では、日本政策金融公庫の不動産投資向け融資は2025年4月に上限1億円へ拡充され、金利も1.4%前後で推移しています。新規参入者が自己資金不足を補う手段として検討する価値がありますが、物件キャッシュフローがプラスになるかを必ず確認する必要があります。
まとめ
築浅マンションは購入価格が高いものの、修繕費や空室率の低さによって実質利回りを安定させやすい特長があります。表面利回りだけで判断すると魅力が薄く見えますが、長期保有でのキャッシュフローとリセールバリューを加味すれば、堅実な資産形成に寄与する選択肢となるでしょう。今後は物件価格の上昇に備え、シミュレーションで運営コストを詳細に把握し、金利交渉や空室対策で利回りを磨き上げる姿勢が重要です。まずは気になる築浅物件の実質利回りを自分の手で試算し、数字で納得できる投資判断を下してみてください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省「住宅市場動向調査2024」 – https://www.mlit.go.jp
- 日本マンション管理士会連合会「マンション修繕積立金実態調査2025」 – https://www.nmkanren.org
- 日本政策金融公庫「2025年度融資制度一覧」 – https://www.jfc.go.jp

