不動産投資に興味はあるものの、「新築と中古のどちらを選ぶべきか」で立ち止まる人は多いです。価格、利回り、将来の価値など比較ポイントが多く、正解がひとつに定まらないからです。本記事では「マンション投資 新築 違い」という視点から、最新データと実務経験をもとに具体的な判断材料を提示します。読み終えたとき、あなたは自分の目標に合った選択肢を描けるはずです。
新築マンション投資の魅力と注意点
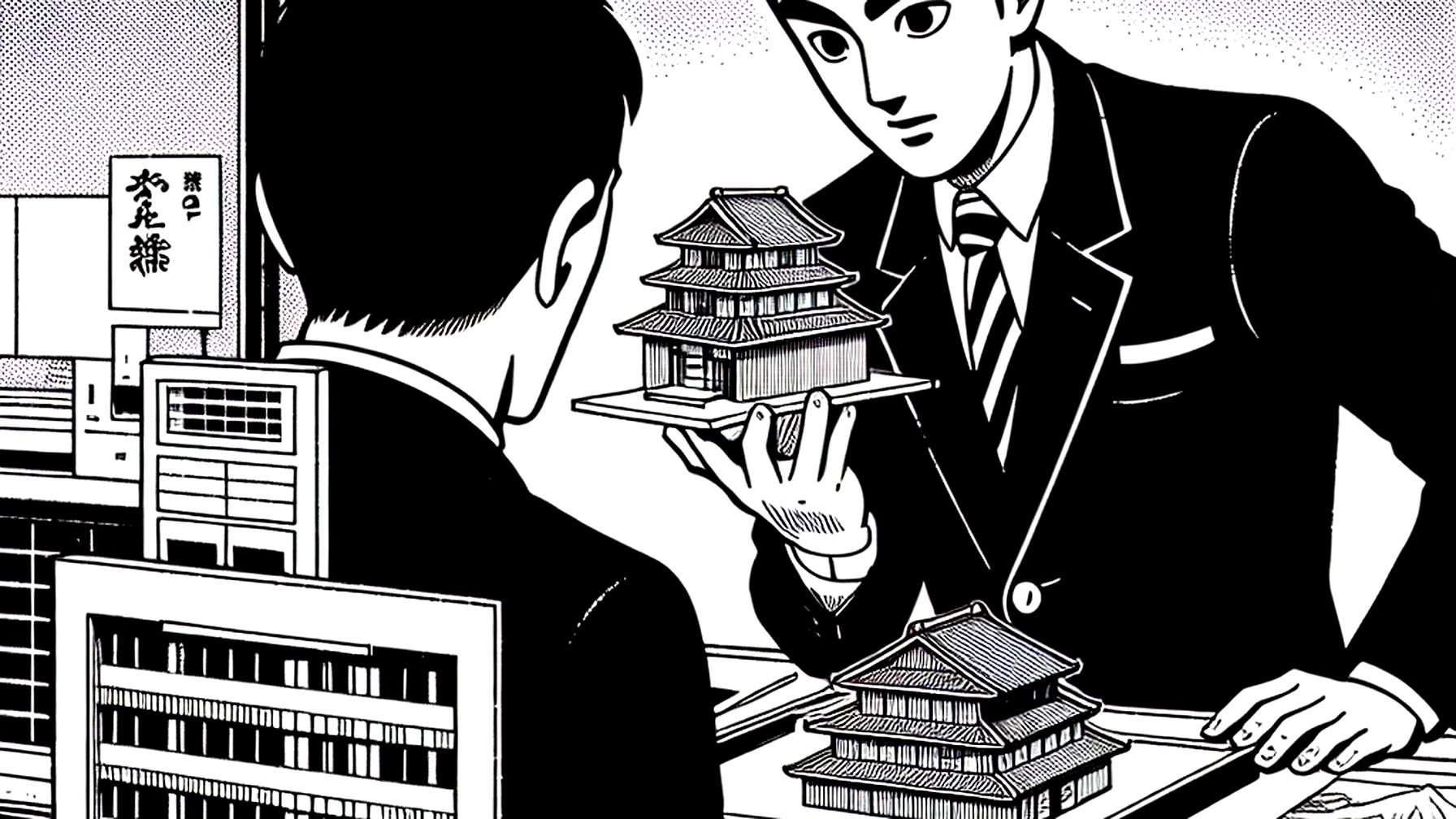
まず押さえておきたいのは、新築マンションの強みが「安心感」と「設備仕様」に集約される点です。最新の耐震基準や省エネ性に対応しているため、入居者募集で有利に働きやすいと言われます。しかし、価格が高い分だけ収益率は自然と抑えられる傾向にあります。
2025年9月のデータによると、東京23区の新築分譲マンション平均価格は7,580万円で前年比3.2%の上昇です。設備が同水準の中古より2〜3割高いケースが珍しくありません。そのため家賃を相場より大幅に上げることは難しく、実質利回りは4%台前半に落ち着きやすいのが現状です。
一方で、購入後5年間は大規模修繕費がほぼ発生せず、入居者クレームも少ないというメリットがあります。管理計画も新築時に組み込まれているため、初心者でも運営リスクを抑えやすい点は見逃せません。ただし固定資産税評価額が高い間は税負担も重くなるため、キャッシュフローが想定より圧迫される恐れがあります。
中古マンション投資の実力を再確認
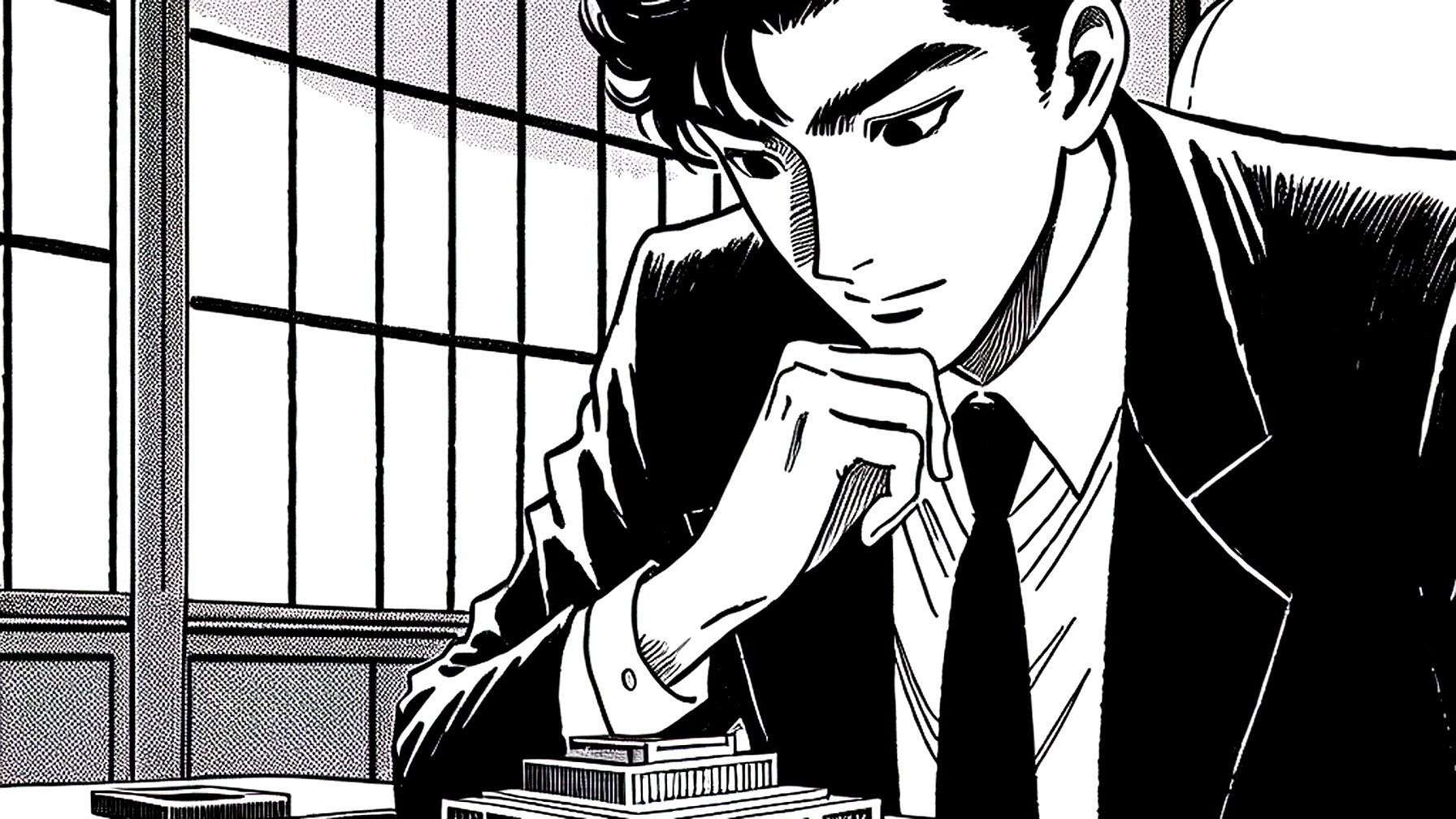
ポイントは、同じ立地なら中古の方が購入価格を抑えられるため、利回りを高めやすいことです。築15年の都心ワンルームなら3,800万円前後で取得でき、家賃が月11万円なら表面利回りは約3.5%となります。諸費用を加味しても、新築より初期投資は小さくなる傾向です。
東京都都市整備局の空室率レポートでは、築年数が20年を超えても都心5区のワンルーム空室率は平均6%台に収まっています。つまり、物件選びさえ誤らなければ、築古=高い空室リスクという単純な図式にはなりにくいのが実情です。
ただし中古は修繕履歴と管理体制のチェックが不可欠です。大規模修繕の積立金が不足している場合、数年以内に追加徴収が行われ、キャッシュフロー計画が崩れることがあります。また旧耐震基準(1981年以前)で建てられた物件は、融資期間が短くなるケースが多いため、返済額の試算をより慎重に行う必要があります。
キャッシュフローで見る新築と中古の違い
重要なのは、賃料収入と支出のタイミングを時系列で比較することです。新築は購入当初の修繕費が少ない一方、価格が高くローン返済が重いので、月々の手残りは少なくなりがちです。例えば金利1.5%、35年返済で7,500万円を借り入れた場合、毎月の元利均等返済は約24万円になります。家賃が月23万円だと、管理費や税金を含めて赤字になる可能性が高いです。
中古なら購入額が4,000万円、同条件で返済は約13万円に抑えられます。家賃11万円の場合でも、一見すると収支はトントンですが、減価償却費を経費計上できるため、実質的な税負担を下げられる利点があります。ただし築20年以上では設備故障が増え、年間30万円前後の修繕費を見込むのが現実的です。
つまり、短期的なキャッシュフローは中古が有利に見えるものの、長期スパンでは修繕計画と家賃下落率をどう織り込むかが試金石になります。新築は初期10年を黒字化しにくいものの、家賃が安定しやすく、大規模修繕までの猶予期間を活かせば中期的にキャッシュフローが改善する余地もあります。
将来価値と出口戦略をどう描くか
実は、投資家の最終的な利益を決めるのは「売却益」か「長期保有益」かという出口戦略です。新築は築5〜8年で価値が一段階下がるタイミングがあり、そこを乗り切ると価格下落は緩やかになります。逆に築浅で手放すと、分譲時価格比15〜20%の損が出るケースが多く、短期売却には向きません。
中古は購入時点ですでに減価が進んでいるため、価格変動リスクが小さく、利回りで利益を積み上げる設計になります。国土交通省の「不動産価格指数」によれば、築30年前後の区分マンション価格は横ばい傾向にあり、流動性も一定程度保たれています。出口を賃貸継続と割り切るなら中古が扱いやすいと言えるでしょう。
ただし将来の再開発やインフラ整備で周辺環境が変わると、想定外の値動きが起こることもあります。新築でも中古でも、エリアの都市計画や人口動向を定点観測し、売却時期を柔軟に調整できる体制が欠かせません。
2025年度の制度と資金調達の最新動向
まず押さえておきたいのは、2025年度も住宅ローン減税が区分所有投資用には適用されない点です。自宅用との混同に注意しましょう。その代わり、投資家が利用しやすい制度として「グリーンリノベ融資」(民間金融機関×住宅金融支援機構)が拡充されています。物件の省エネ改修を行う場合、金利が0.3%程度優遇され、借入期間も最長35年まで取れるのが特徴です。
また2025年4月から、金融庁の指針により個人向け投資用ローンの審査で「返済負担率35%上限」が一般化しました。これは年収に対する年間返済額の割合で、従来より審査が厳格になる一方、無理な融資を避けやすくなります。金利は変動でも1%前後が主流ですが、FRBの利上げ影響で今後上昇が続く可能性を考慮し、固定型の選択肢を早い段階で検討する価値があります。
さらに、中古マンションの耐震改修に対しては2025年度も自治体補助金が継続しています。例えば東京都は区分所有でも上限150万円の補助を設けており、工事完了後に助成金を受け取れます(申請期限あり)。この仕組みを活用すると、リノベ費用を抑えつつ家賃アップが狙え、投資効率が高まります。
まとめ
今回のポイントは、新築が「安心感と長期安定」、中古が「利回りと投資効率」という性格を持つことでした。初期費用を抑えたいなら中古、修繕リスクを避けたいなら新築が合いやすいと整理できます。ただしキャッシュフロー、修繕計画、出口戦略を数字で比較し、制度や金利の変化に柔軟に対応する姿勢が最終的な成果を分けます。まずはご自身の投資目的と許容リスクを明確にし、信頼できる管理会社や金融機関と連携しながら一歩踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudosankeizai.co.jp/
- 東京都都市整備局「住宅市場動向調査」 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp/
- 金融庁「2025年度 個人向けローン審査ガイドライン」 – https://www.fsa.go.jp/
- 住宅金融支援機構「グリーンリノベ融資の概要」 – https://www.jhf.go.jp/

