マンション投資に興味はあるものの、「横浜で買う場合の表面利回りは十分なのか」「東京と比べて本当に得なのか」と悩む方は多いはずです。本記事では、表面利回りの基本から横浜市内の最新相場、税制や融資を踏まえた収益向上策までを丁寧に解説します。読み終えたとき、投資判断に必要な視点と数字の裏付けが手に入り、自分の予算に合う物件を選ぶ手がかりが見つかるはずです。
表面利回りの基礎を押さえる
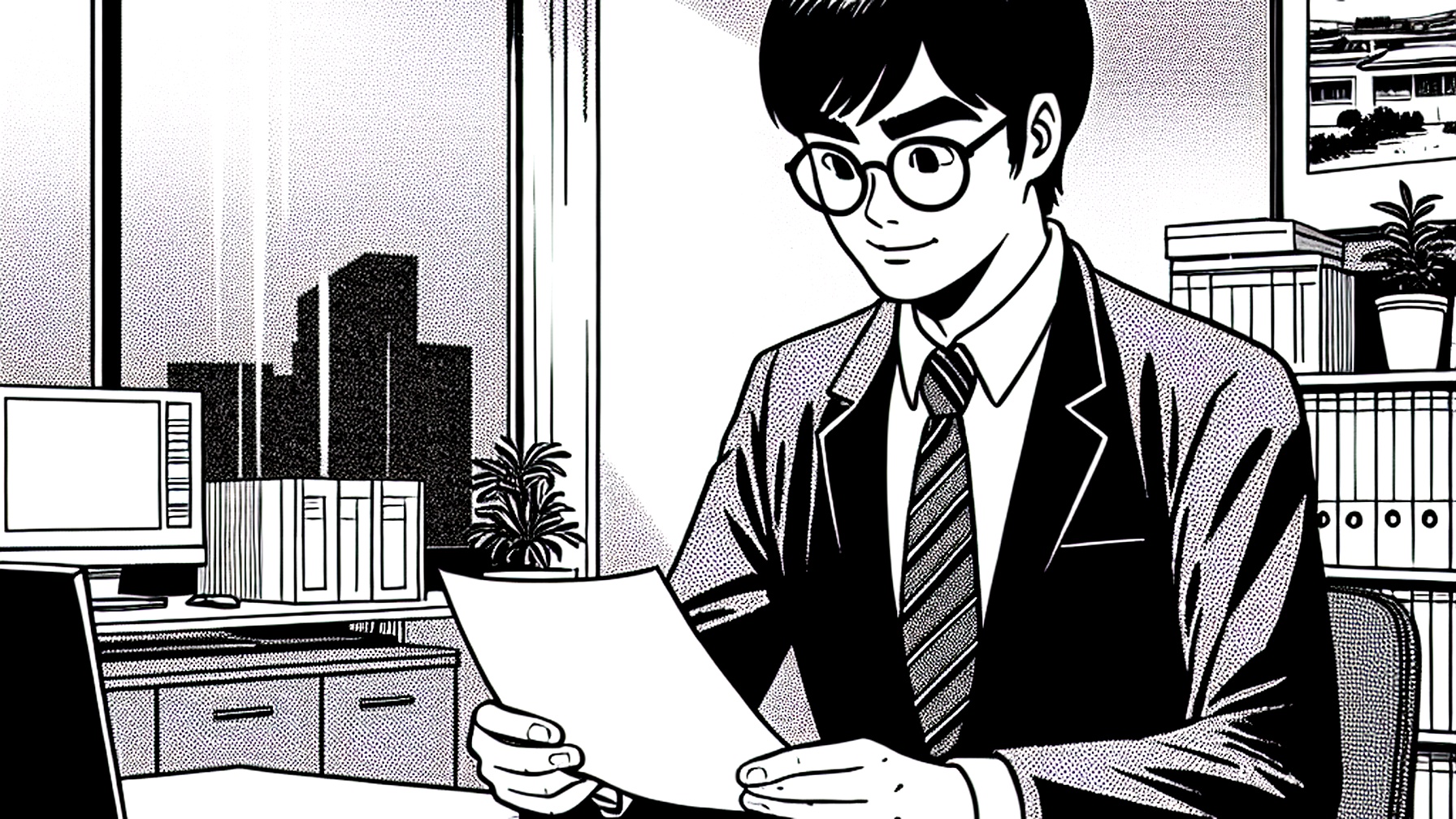
ポイントは、表面利回りが「年間家賃収入 ÷ 物件価格 × 100」で計算される単純指標にすぎないという理解です。横浜の中古ワンルームで年72万円の家賃を得て、購入価格が1,600万円なら表面利回りは4.5%となります。しかし、この数字には管理費や修繕積立金、固定資産税などのランニングコストが含まれていません。つまり、表面利回りは物件比較のスタート地点であり、最終的な投資採算を測るには実質利回り(ネット利回り)を必ず計算する必要があります。
一方で、金融機関や物件広告でまず提示されるのは表面利回りです。そのため、この指標の読み解き方を知らなければ、過大な期待を抱いてしまいます。実は横浜でも駅近の築浅物件は表面利回り4%前後が一般的で、費用を差し引くと実質利回りは3%台に下がります。まずは「表面4%なら実質3%程度」という感覚を身につけ、数字のブレを許容できるか判断しましょう。
横浜エリアの市場動向を読み解く
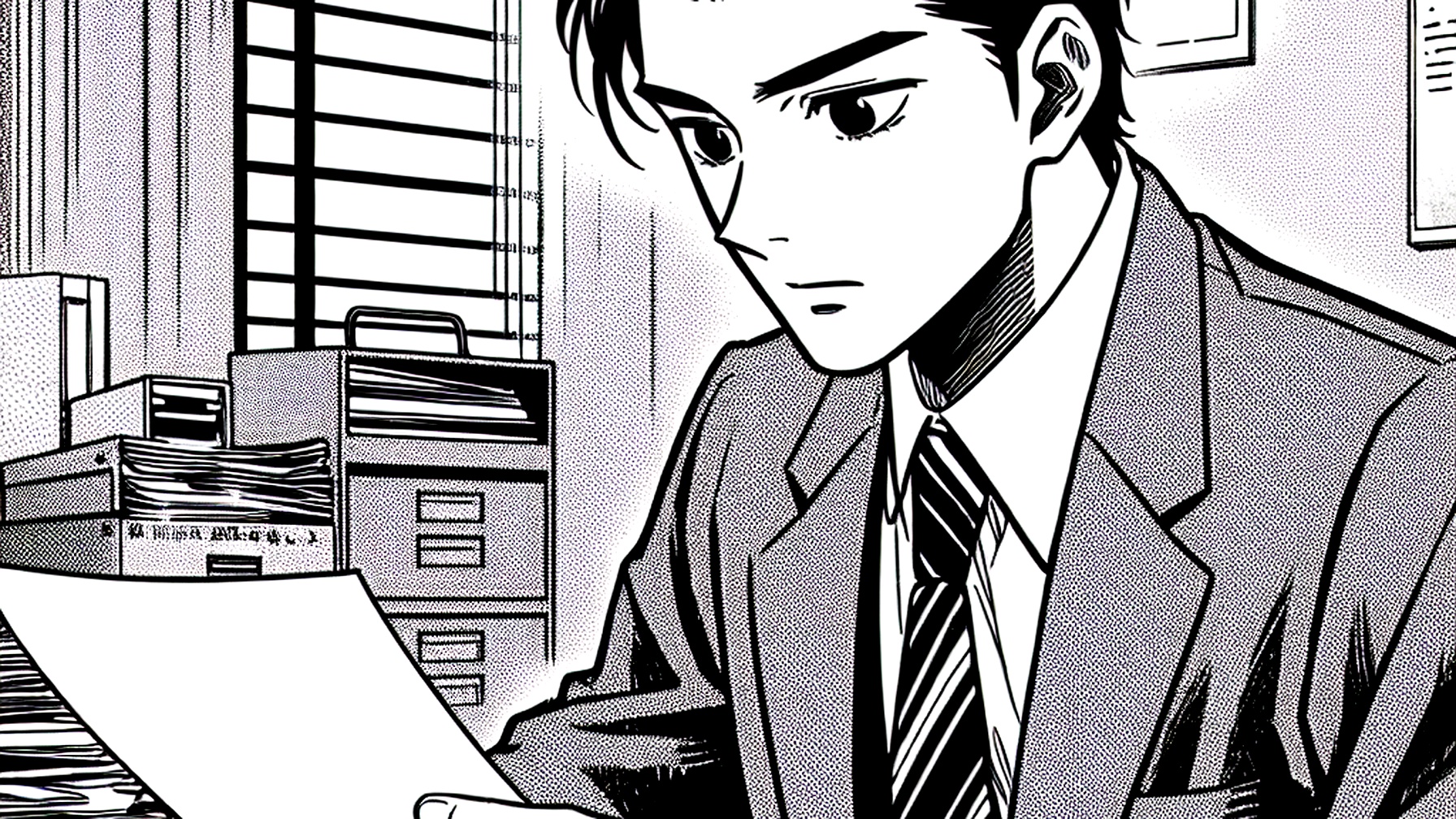
まず押さえておきたいのは、横浜市は政令指定都市として人口が増え続けている点です。横浜市統計ポータルによると、2025年1月時点の総人口は377万人で前年同月比+0.4%となりました。流入人口の多さは賃貸需要の底堅さを示し、空室リスクを抑える材料になります。また、横浜駅周辺やみなとみらい地区は再開発が進み、オフィスワーカー向けの単身賃貸需要も拡大しています。
一方で、物件価格は上昇傾向にあります。神奈川県宅建協会のデータでは、2025年9月の横浜市中区中古マンション平均単価は坪230万円で前年同期比+2.8%でした。価格上昇により表面利回りは圧縮されやすく、横浜駅徒歩10分圏のワンルームでは4%を切る事例も珍しくありません。ただし、市営地下鉄沿線の駅徒歩12分程度に目を向けると、同程度の賃料で購入価格が2割ほど安いエリアが見つかり、表面利回りは5%台まで引き上げられます。
さらに、大学キャンパスや医療施設が集まる港北ニュータウン周辺は、ファミリータイプの需要が底堅い点も注目です。家賃が高くても長期入居が期待できるため、運営コストを抑えれば実質利回りが安定しやすい特徴があります。市場動向を把握する際は「エリア別賃料水準」「築年数ごとの価格差」「長期的な人口動向」の三点を組み合わせて見ると、数字の裏にあるリスクを読み解けます。
適正な表面利回りを見極める
重要なのは、自身の投資目的と金融機関の融資条件から逆算して、必要な表面利回りを設定することです。仮に35年ローン・金利1.6%・フルローンを利用し、家賃下落2%/年、空室率10%といった保守的な前提でキャッシュフローを試算すると、横浜では表面利回り4.5%が一つの分岐点になります。この水準を下回ると、短期的な金利上昇や大規模修繕で赤字化しやすくなります。
具体例として、購入価格1,700万円・家賃月6.7万円のワンルームを想定します。表面利回りは4.7%ですが、管理費と修繕積立金で月1.2万円、固定資産税で年6万円が必要です。これらを差し引いた実質利回りは3.2%に低下します。それでも、自己資金300万円を投入して融資額を抑えれば、年間手残りが約30万円確保でき、自己資本利回りは10%前後に改善します。言い換えると、表面利回り単体ではなく「いくら自己資金を入れ、どれだけレバレッジを掛けるか」で最終的な収益性が大きく変わるわけです。
また、横浜は物件価格のばらつきが大きいため、同じエリア・築年数でも表面利回り2%台から7%台まで存在します。高利回りをうたう物件は築古で修繕履歴が不透明なケースが多く、将来の大規模修繕コストが利回りを食い潰す危険があります。適正利回りかどうか判断する際は、長期修繕計画や分譲管理組合の財務状況を必ず確認しましょう。
物件選定の具体的手順と注意点
実は、横浜で表面利回り5%超を安定して確保するには、購入・運営のプロセスを段階ごとに最適化することがカギとなります。まず、ポータルサイトで横浜市内の候補物件を30件ほどピックアップし、エリア別の家賃相場を「住宅・土地統計調査」と照合します。ここで家賃が相場より5%以上高く設定されている物件は除外し、利回りの過剰上乗せリスクを回避します。
次に、管理費と修繕積立金のバランスをチェックします。分譲マンションの場合、管理費+修繕積立金が家賃の20%を超えると実質利回りを圧迫しやすくなります。築20年を過ぎた物件では、今後10年以内に給排水管やエレベーター更新が予定されているかを確認し、追加負担がどれくらいか見積もることが不可欠です。また、サブリース契約を提案された場合は、家賃の85〜90%程度がオーナー取り分となるため、契約後の表面利回り低下を想定に入れる必要があります。
最後に、内覧時は「駅から物件までの実歩時間」と「夜間の街灯の明るさ」を確認しましょう。横浜は坂の多い街として知られ、徒歩8分表示でも体感距離が長いケースが散見されます。入居者が感じるアクセスの不便さは退去率に直結するため、表面利回りが高くても実質稼働率が低下しては意味がありません。こうした現地確認を徹底することで、数字だけでは見えないリスクを減らせます。
2025年度の税制・融資環境を活かすコツ
まず押さえておきたいのは、2025年度も「不動産取得税の軽減措置」が継続している点です。築20年以内の中古マンションを取得した場合、課税標準から1,200万円が控除され、取得税負担を数十万円単位で抑えられます。ただし適用期限は2026年3月31日登記分までなので、物件引き渡しスケジュールに注意が必要です。
融資面では、日本政策金融公庫の「生活衛生貸付」が2025年度も存続し、自己管理型の民泊運営を視野に入れる物件であれば金利1.3%台で借りられるケースがあります。また、地方銀行の一部では、横浜市内の投資用マンションを対象に、金利1.5%前後・融資期間35年という好条件を提示しています。これらの低金利を活用しつつ、資金計画段階で「金利上昇2%」「空室率20%」といったストレスシナリオを組み込み、収支が破綻しないか確認することが賢明です。
さらに、消費税インボイス制度が始まったことで課税事業者を選択するかどうかの判断が必要になりました。賃貸住宅は原則非課税売上ですが、共用部の電気代など仕入税額控除の面でメリットが生じる場合もあります。税理士に相談し、インボイス登録による実質利回りへの影響を試算してから決断するとよいでしょう。こうした制度を理解して適用可否を判断できれば、同じ表面利回りでも手残り額に差がつきます。
まとめ
この記事では、横浜におけるマンション投資の表面利回りを中心に、市場動向、適正利回りの計算方法、物件選定の手順、そして2025年度の制度活用術までを解説しました。ポイントは、表面利回りを鵜呑みにせず実質利回りで評価し、人口動態や修繕計画といった長期要因まで織り込むことです。そのうえで、不動産取得税の軽減措置や低金利融資を戦略的に利用すれば、安定したキャッシュフローを確保できます。これから横浜で物件を探す方は、今日得た視点を基に収支シミュレーションを行い、自分のリスク許容度に合う投資を進めてみてください。
参考文献・出典
- 横浜市 統計ポータル – https://www.city.yokohama.lg.jp
- 神奈川県宅建協会 市況レポート – https://www.kanagawa-takken.or.jp
- 日本不動産研究所「市況インデックス2025年9月」 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所「首都圏新築マンション価格動向2025年9月」 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省「不動産取得税の軽減措置について(2025年度版)」 – https://www.mlit.go.jp

