アパート経営に興味はあるものの、「本当にもうかるのか」「空室が続いて赤字にならないか」と不安に感じる方は多いはずです。実際、私のもとにも「収益性を上げながら失敗しないコツを教えてほしい」という相談が絶えません。本記事では、収益を左右する指標の見方から空室対策、資金計画、最新の税制まで、2025年9月時点で押さえるべきポイントを体系的に解説します。読むことで、数字の裏付けをもとに自分の投資判断に自信を持てるようになりますので、最後までお付き合いください。
収益性を決める三つの指標
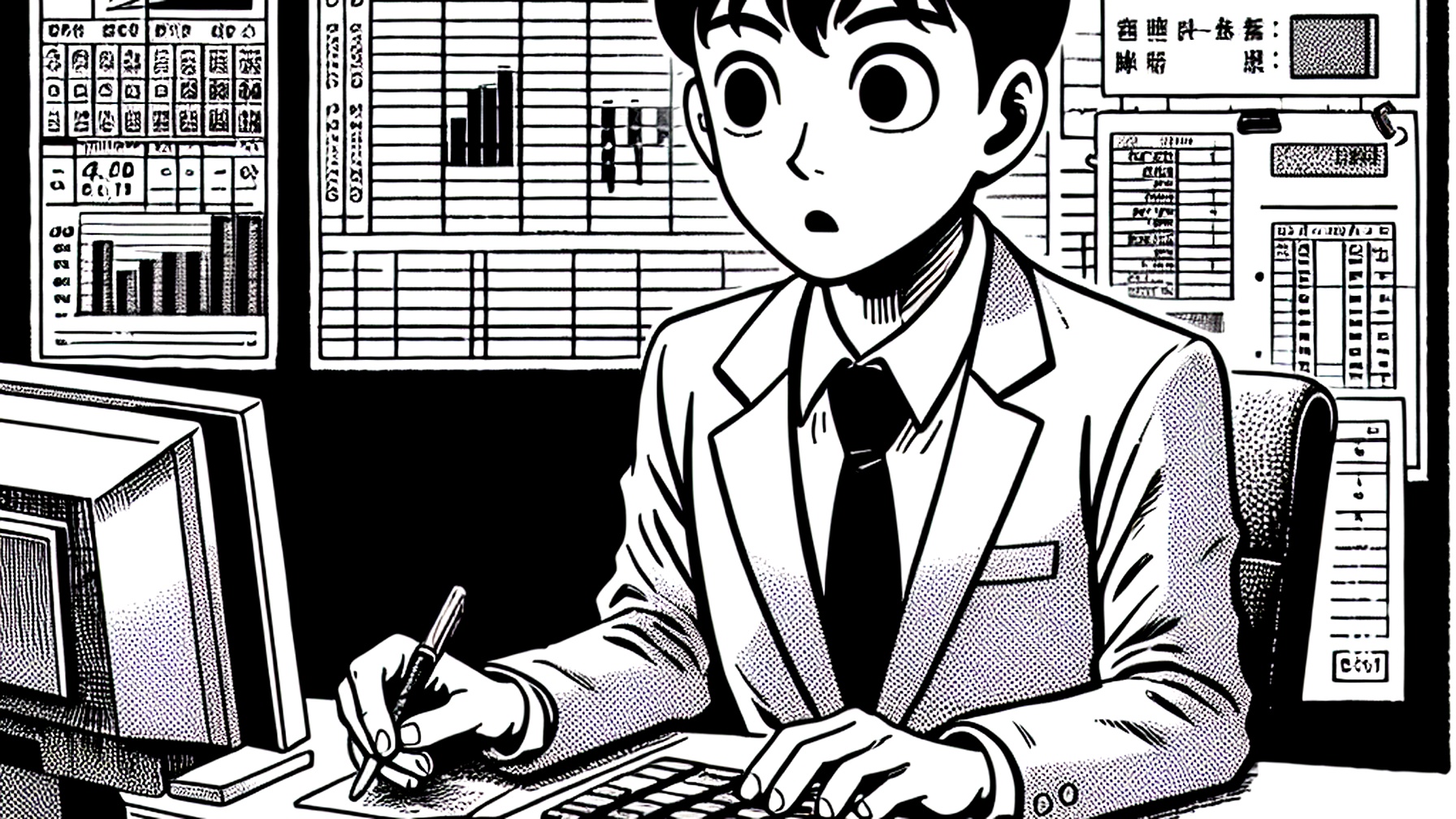
重要なのは、表面利回りだけで判断しないことです。実は、キャッシュフローを安定させるには実質利回り、NOI、CCRという三つの指標を組み合わせて確認する必要があります。
まず表面利回りは「年間家賃収入÷物件価格」で計算できますが、固定資産税や修繕費などの支出を考慮していません。そのため、購入前の比較としては便利でも、実際の収益性を測るには不十分です。一方、実質利回りは管理費や火災保険といったランニングコストを差し引くため、より現実に近い数値が得られます。
さらに、NOI(Net Operating Income)は「営業純利益」と訳され、空室損と運営費用を差し引いた後に残る金額を示します。これを元に金融機関が融資審査を行うケースも増えているので重視しましょう。最後にCCR(Cash on Cash Return)は「年間手残りキャッシュフロー÷自己資金」で求められ、自己資金の効率を測る指標です。自己資金を圧縮してCCRを高めれば、同じ資本で複数物件を運用する戦略が取りやすくなります。
つまり、購入前の机上シミュレーションでは、実質利回りとNOIで収益性を確認し、融資後はCCRで自己資金の回転率を検証する流れが欠かせません。数字を使い分ける習慣が、失敗しない第一歩になります。
空室リスクを減らす立地と設備
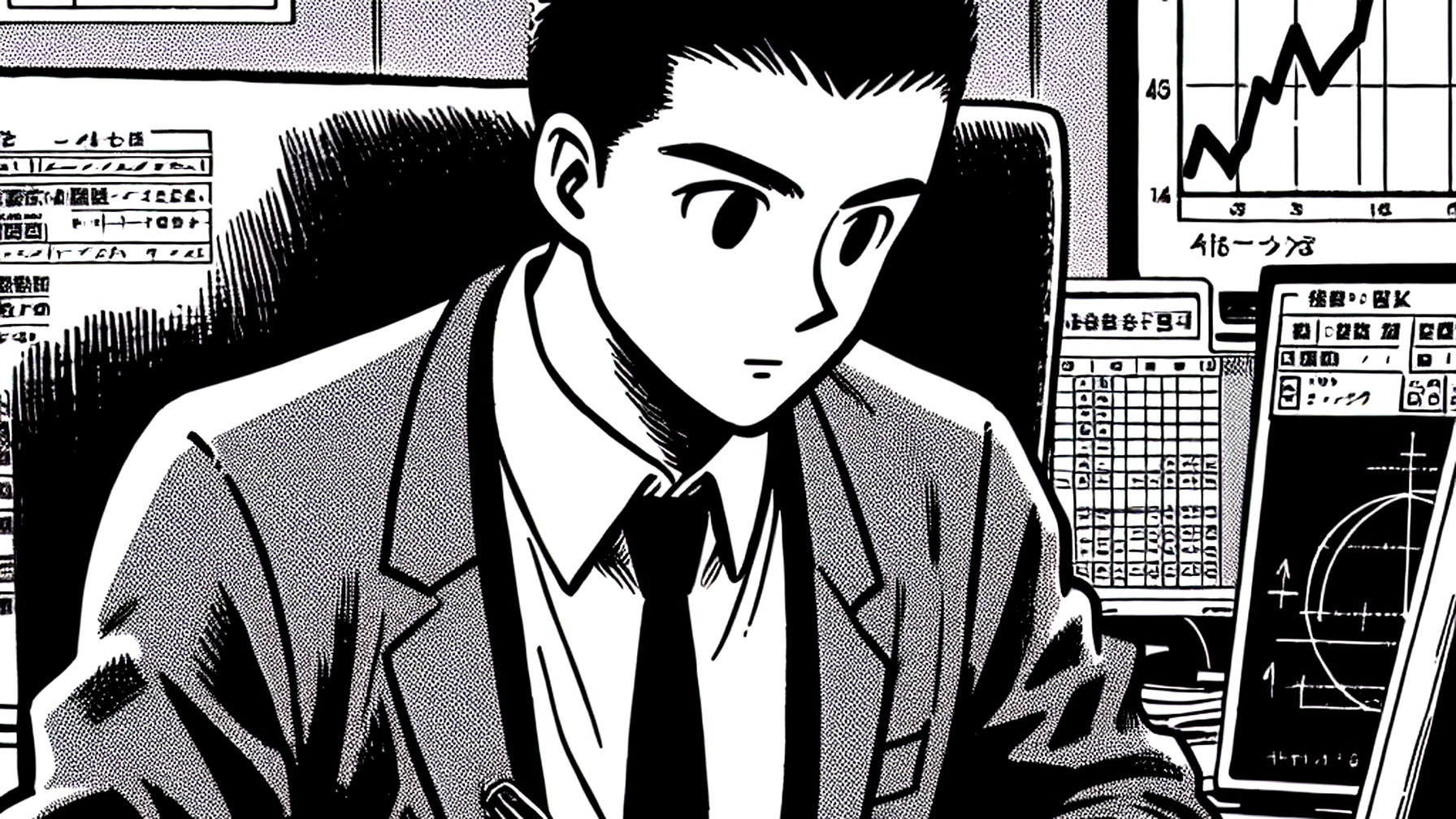
まず押さえておきたいのは、立地こそ最大の空室対策であるという事実です。国土交通省住宅統計によると、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント改善しましたが、地方郊外では依然30%を超えるエリアもあります。需要と供給のギャップは数字ではっきり表れるため、エリア選定を誤ると後から設備を充実させても埋まりにくいのが現実です。
都心駅徒歩10分以内の物件は賃料が高くても入居付けが早く、結果として実質利回りが安定します。一方、地方や郊外の物件は初期投資が抑えられる半面、人口減少の影響を強く受けるため慎重な市場調査が必須です。具体的には、総務省の将来人口推計や自治体の都市計画をチェックし、若年層の流入が見込める大学や大型工場の存続状況を確認するとよいでしょう。
設備面ではインターネット無料や宅配ボックスが標準化しつつあります。導入コストは戸当たり8〜12万円ですが、賃料を月額2,000円上乗せできれば5年程度で回収可能です。また、ペット飼育可とする場合はフローリングの傷対策にタイル調フロア材を採用すると、原状回復費が下がり長期的なコスト削減につながります。立地で勝ち、設備で差別化する。この二段構えが空室率21.2%の市場で生き残る鍵です。
資金計画と融資戦略
ポイントは、自己資金と借入金のバランスを見極めることです。多くの初心者はフルローンに魅力を感じますが、返済比率が高くなると空室や修繕時のキャッシュフローが一気に悪化します。一般的に、年間返済額をNOIの50〜60%以内に抑えると安定しやすいと言われますが、個人のリスク許容度で調整しましょう。
金融機関の融資姿勢は金利だけでなく融資期間にも差があります。例えば、某地銀では木造アパートの最長融資期間を法定耐用年数(22年)までとする一方、信金では耐用年数オーバー融資を認めるケースがあります。期間が長いほど返済額は下がるものの、総支払利息は増えるため、総返済額と月次キャッシュフローを両面で比較することが大切です。
シミュレーションでは、空室率15%・金利上昇1.5%・修繕費年平均10%増といった厳しめ条件も入れ込みます。これに耐えられる物件だけを残せば、景気変動局面でも動じないポートフォリオが作れます。また、2025年度の住宅ローン控除は居住用が対象ですが、投資用でも金利交渉材料になるため、銀行に「控除後の実質金利」を提示して交渉するのも有効です。
運営コストを抑える管理術
基本的に、収益性を押し上げる確実な方法は「支出を減らす」ことです。管理委託では、集金代行とサブリースの違いを理解しましょう。集金代行は実際の家賃回収額から管理料(3〜5%)を差し引くシステムで、空室時のリスクはオーナーが負います。サブリースは管理会社が一括借り上げし、手取り賃料が固定されるものの、平均10〜15%の手数料が発生し賃料改定条項が付く点がデメリットです。
修繕費の見積もりでは、長期修繕計画を立てることが不可欠です。外壁塗装や屋根防水は12〜15年で大規模工事が必要となり、延床面積200㎡の木造アパートでおおむね200万円を見込むと安心です。この費用を毎月分割して積立てると、資金ショートのリスクを抑えられます。
さらに、クラウド型の自主管理アプリを導入すれば、入居者からの設備故障連絡を写真付きで受け取り、修理業者をオンライン手配できます。管理会社への一次連絡を省略できるため、1件あたりの対応コストを平均3,000円削減できるとの事例もあります。運営フェーズでの小さな工夫こそが、最終的な手残りを大きく左右します。
2025年度の税制と活用ポイント
まず、2025年度も不動産所得は総合課税となり、損益通算で給与所得と相殺できる仕組みが維持されています。赤字計上による節税を主目的とする投資は推奨できませんが、減価償却を適切に活用することでキャッシュフローを安定化させる効果は大きいです。木造アパートの法定耐用年数22年を過ぎた中古物件なら、最短4年で償却可能なため、初期数年の手残りを厚くできます。
固定資産税に関しては、住宅用地の特例が2025年度も継続され、200㎡以下の部分は課税標準が6分の1に軽減されます。土地比率が高い物件ほどこのメリットが効きますが、評価額が高い都心部では税額自体が大きくなりがちなので注意が必要です。
また、2025年度から相続時精算課税制度の非課税枠が拡充され、親からの資金援助でアパートを建築するケースが増えています。制度を利用すると贈与時に贈与税が非課税となり、将来の相続税対策も一部兼ねられるため、家族で検討する価値があります。ただし、一度選択すると撤回できないため、税理士に試算を依頼したうえで慎重に判断しましょう。
まとめ
結論として、アパート経営で失敗しないためには「立地で需要を取り込み、数字で収益性を検証し、運営でコストを抑える」という三段構えが欠かせません。本記事で紹介した指標や最新の税制を使いこなせば、空室率21.2%の市場でも堅実なキャッシュフローを確保できます。まずは候補物件のNOIとCCRを計算し、厳しめのシミュレーションで耐久力を確かめることから始めてみてください。正しい準備が、長期にわたる安定経営への最短ルートになります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年7月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 将来人口推計 2023年版 – https://www.soumu.go.jp
- 国税庁 タックスアンサー 不動産所得 – https://www.nta.go.jp
- 財務省 相続時精算課税制度 Q&A 2025年度版 – https://www.mof.go.jp
- 独立行政法人 住宅金融支援機構 住宅ローン金利動向 2025年6月 – https://www.jhf.go.jp

