不動産投資を始めたいけれど、「東京でマンションを買って本当に利益が出るのか」と迷う人は少なくありません。特に表面利回りという指標が示す数字の意味を正しく理解できないまま購入すると、後で資金繰りに苦しむケースもあります。本記事では、最新のデータを用いて東京の表面利回りの現状を解説し、ワンルームとファミリー物件の違い、利回りを高める運用法、そして2025年度の制度活用まで丁寧に説明します。読み終えるころには、自分に合った投資判断の軸が明確になるはずです。
表面利回りとは何か
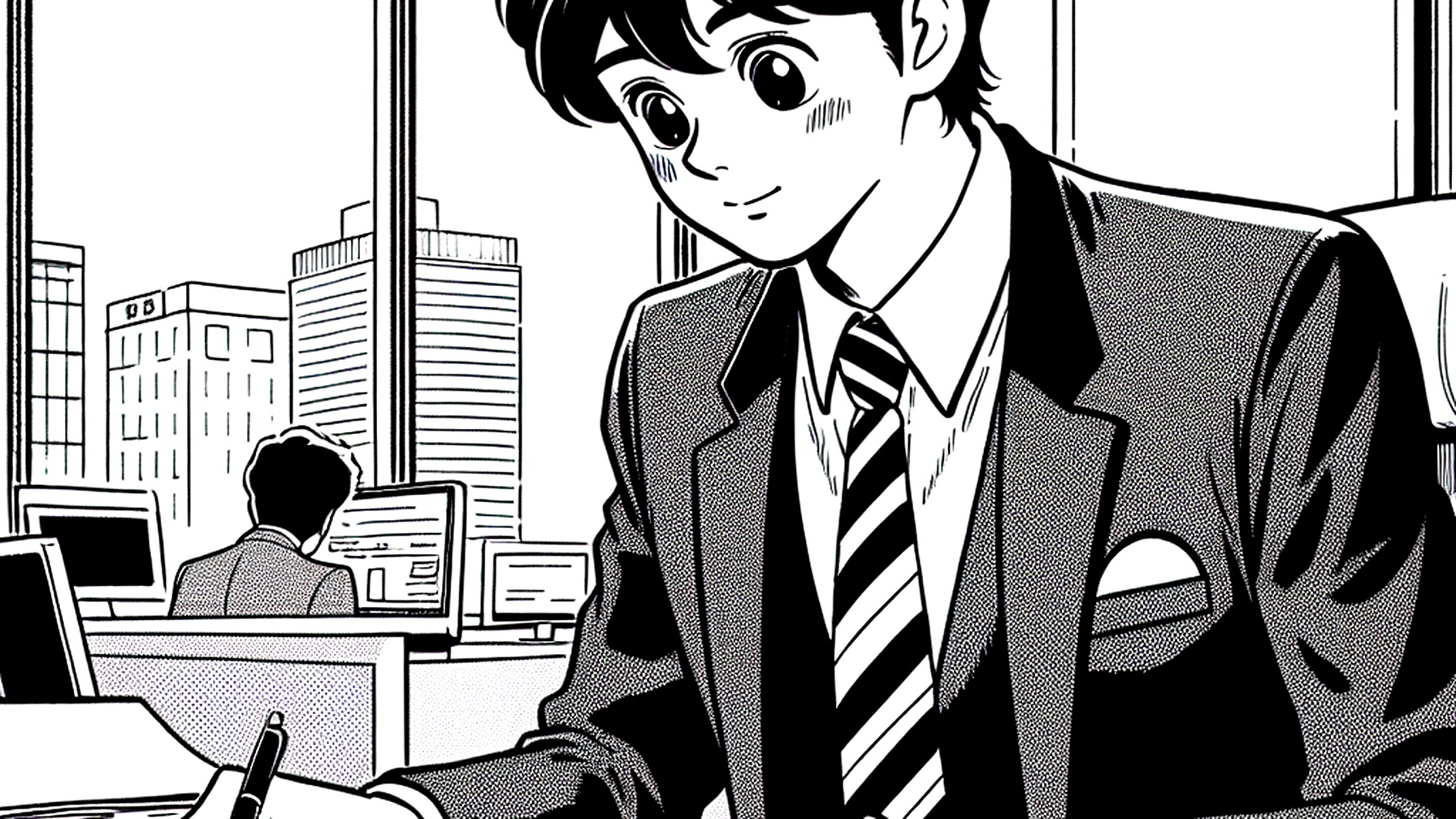
まず押さえておきたいのは、表面利回りが家賃収入の総額を物件価格で割った単純な指標だという点です。この値は税金や管理費を考慮しないため、実際の手取りを示す実質利回りとは異なります。つまり、数字が高ければ必ず儲かるわけではなく、維持費の多寡や空室リスクによって手元に残る現金は変動します。
また、表面利回りは物件同士を比較する「入り口」の数字にすぎません。たとえば、同じ4%でも管理委託費が高い物件と低い物件では、最終的なキャッシュフローが大きく違います。そのため、表面利回りと同時に固定資産税、修繕積立金、ローン金利などの諸経費を見積もり、実質利回りまで計算した上で投資判断を行う姿勢が求められます。
東京の表面利回りの現状を読み解く
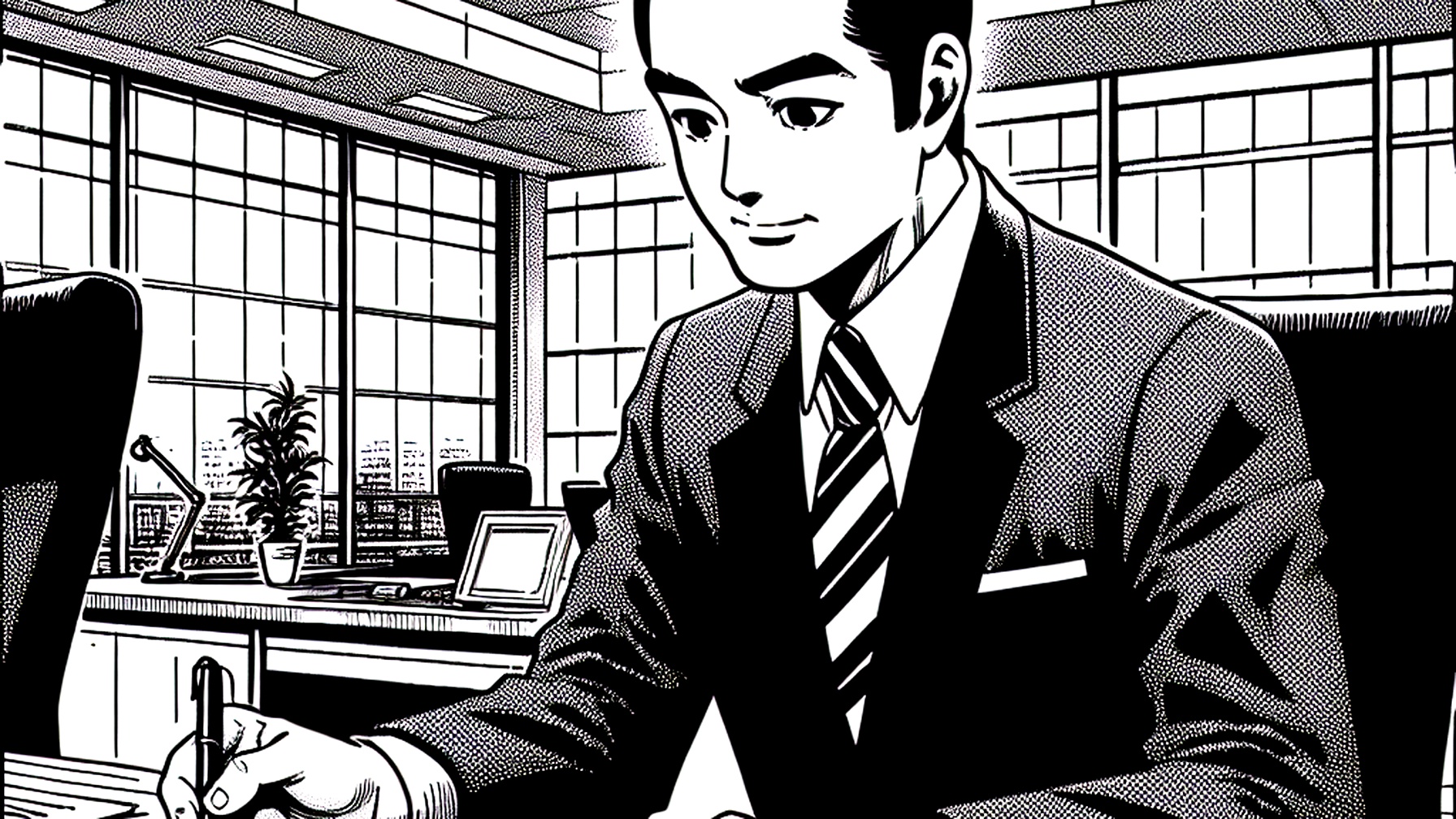
重要なのは、最新データを使って東京の市場を正確に把握することです。日本不動産研究所の2025年9月調査によると、東京23区の平均表面利回りはワンルームで4.2%、ファミリータイプで3.8%、木造アパートで5.1%となりました。前年と比べ大きな変動はなく、都心部の需要の強さを示しています。
一方で、新築マンションの平均価格は7,580万円と高値を更新し、表面利回りの数字は圧縮傾向にあります。言い換えると、購入価格の上昇が利回りの伸びを抑えているということです。しかし、都心部は人口流入が続き空室率が低いため、安定した家賃収入を期待できるのが魅力です。逆に、郊外は価格が抑えられるものの、今後の人口減少や再開発の進捗に左右されやすい点に注意が必要です。
データが示す平均利回りは参考値にすぎません。区ごとの利回りを比較すると、港区や中央区の高級エリアは3%台に留まる一方、墨田区や北区では5%近い物件も見られます。利回りの高さを追うか、空室リスクの低さを選ぶかは、投資家自身のリスク許容度によって変わるでしょう。
物件タイプ別に見る投資戦略
ポイントは、物件タイプによる収益構造の違いを理解し、自分の戦略に落とし込むことです。ワンルームは単身者が多い山手線沿線で需要が底堅く、家賃設定を適切に行えば長期の空室を避けやすい傾向があります。ただし、入居者の入れ替えが早いため、原状回復費や広告費の発生頻度は高めです。
ファミリータイプは転居頻度が低く、長期入居が期待できます。結果として修繕費の計画が立てやすく、安定したキャッシュフローが生まれやすい一方、物件価格が高額になりやすいため表面利回りは下がりがちです。実は、長期保有を前提にインカムゲインを得たい投資家には適した選択肢といえます。
築古物件をリフォームして貸し出す戦略も有効です。購入価格を抑え、リノベーションで競争力を上げれば、取得後に利回りを押し上げることができます。ただし、建物の躯体や設備の劣化による想定外の修繕リスクは見逃せません。物件調査で配管や躯体の状態を確認し、長期修繕計画が組まれている管理組合を選ぶことが大切です。
利回りを高める運用とリスク管理
まず利回り改善の基本は、家賃設定と経費削減の両輪で考えることです。周辺賃料より1,000円高いだけでも年間では大きな差になりますが、強気の値付けは空室リスクに直結します。SUUMOやレインズで成約事例を確認し、エリアの実勢賃料を基準にアップサイドを狙うのが現実的です。
経費面では管理会社の選定が鍵を握ります。管理委託料の相場は家賃の3%から5%ですが、交渉次第で下げられる場合があります。さらに、修繕積立金が適切に積み立てられているマンションを選ぶと、突発的な負担を軽減できます。つまり、購入前の調査で長期的なランニングコストを読む力が重要なのです。
資金計画ではローン金利が0.5%違うだけで、30年返済の場合に数百万円の差が生まれます。2025年9月時点の住宅ローン平均金利は変動型で0.52%、固定20年で1.25%前後です。低金利を生かして変動型を選ぶか、長期固定で金利上昇リスクを抑えるか、シミュレーションで比較してから判断しましょう。
最後に、空室リスクや家賃下落リスクに備え、家賃収入の3か月分程度の運営予備費を持つと安心です。もしキャッシュフローが悪化しても短期的に持ちこたえられれば、売却を含む次の手を冷静に検討できます。
2025年度の制度とファイナンスの最新動向
実は、2025年度は減価償却ルールが変わらない見通しで、中古マンション投資の節税効果は引き続き健在です。木造物件なら22年、RC造なら47年の法定耐用年数を超えた場合でも、残存年数の計算を利用すれば、短期間で大きな非課税利益を得られます。ただし、過度な節税目的の購入は金融機関の審査が厳しくなるため、事業計画の妥当性を示す資料を整える必要があります。
補助金については、2025年度は国土交通省の「賃貸住宅省エネ改修支援」が継続中です。一定の断熱改修を行うと上限120万円の補助が出るため、表面利回りを下げずに設備グレードを高めたいときに活用できます。この制度は2026年3月末までの契約分が対象であり、期限が明確なので早めの計画が肝心です。
金融機関では、地銀や信金が地域密着型の融資を強化しています。物件所在地が営業エリア内であれば、頭金10%から融資する事例も増えています。また、東京の利回り低下を受けて、ソーシャルレンディングやクラウドファンディング型の不動産投資サービスが台頭し、出資額100万円以下でも都心物件に間接投資できる選択肢が広がりました。これらの新しい手段は流動性を確保しやすいものの、分配金が変動する点を理解した上で活用する必要があります。
まとめ
東京でマンション投資を成功させる鍵は、表面利回りという入口の数字に惑わされず、実質利回りと長期のキャッシュフローを総合的に判断することです。ワンルームで回転型の運用を狙うか、ファミリータイプで安定志向を取るか、さらにリフォームや制度活用で利回りを上げるかは、あなたの資金力とリスク許容度で決まります。まずは平均利回り4%前後という現実を踏まえ、細かな経費と空室リスクを数字で検証する姿勢を持ちましょう。その上で、2025年度の省エネ改修補助や低金利ローンを賢く使えば、都心の高価格帯でも堅実な投資が可能になります。今日からデータに基づくシミュレーションを始め、一歩踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 賃貸住宅省エネ改修支援事業 – https://www.mlit.go.jp
- 住宅金融支援機構 金利統計 – https://www.jhf.go.jp
- 東京都都市整備局 住宅市場動向 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

