不動産投資に興味はあっても、「相続税を減らしたい」「修繕費が重荷になりそう」と二の足を踏む方は少なくありません。実はアパート経営は相続対策に有効で、修繕費の扱いを工夫すればキャッシュフローも安定します。本記事では税制、融資動向、長期修繕計画まで2025年9月時点の最新情報をもとに解説します。最後まで読むことで、アパート経営 相続対策 修繕費の三つを同時に最適化する具体的な手順がつかめるでしょう。
アパート経営が相続対策になる理由
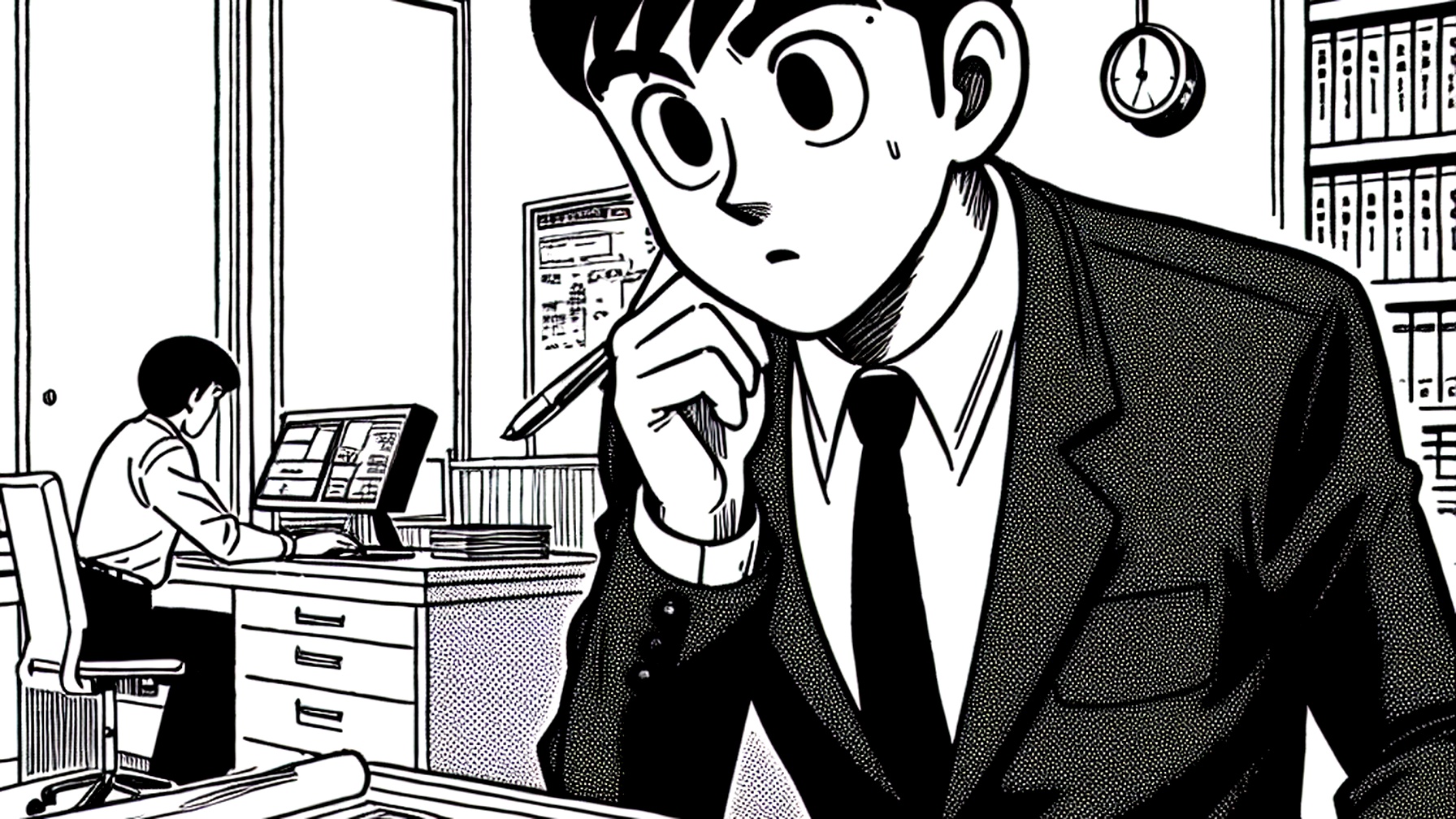
重要なのは、不動産評価額と相続税評価額の差を理解することです。更地を相続するより、賃貸アパートを建てて保有した方が評価額が3〜4割下がるケースが多く、課税対象が圧縮されます。また、賃貸物件は借入金で取得しても負債控除が可能なため、実質的な相続税圧縮効果が高まります。
国税庁の統計によると、2024年度に不動産を活用した相続対策を行った世帯の約64%が課税額を減少させました。つまり、家族に現金を残すより、資産を不動産へ組み替える方が効果的というデータが示されています。ただし、節税ばかりを追うと空室リスクに直面するため、経営としての視点が欠かせません。
さらに2025年度も相続税基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人」のまま据え置かれています。控除を超える資産規模の方ほどアパート経営による評価圧縮の恩恵が大きく、早めの計画が有利です。
修繕費の基礎知識と税務メリット
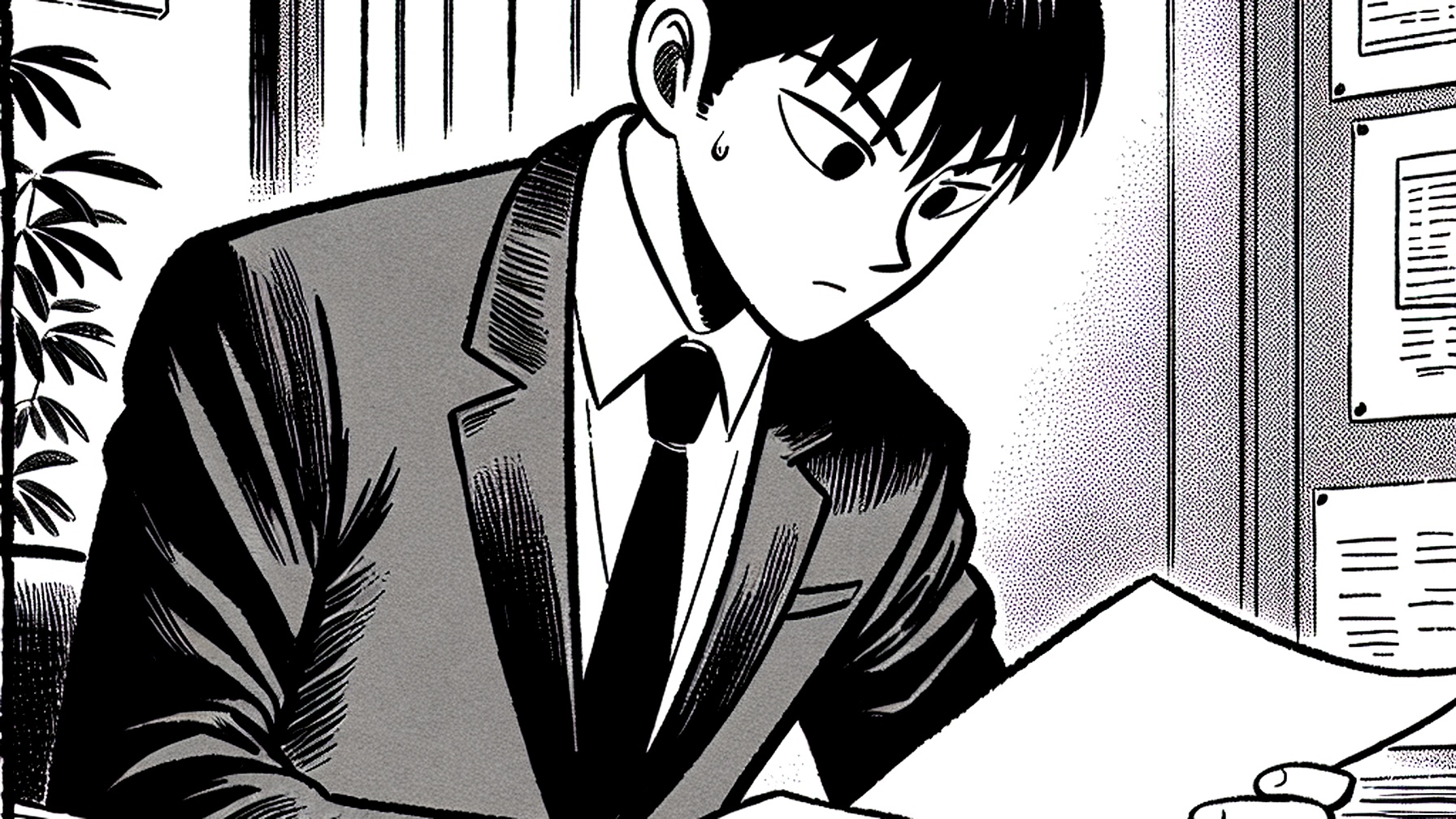
まず押さえておきたいのは、修繕費が「経費」になる点です。建物価値を維持するための修繕は全額をその年の必要経費へ計上でき、所得税と住民税の負担を軽減します。一方で資本的支出に該当する大規模改修は減価償却となり、複数年にわたり経費化されるためキャッシュフロー計算が複雑になります。
修繕費を計画的に積み立てれば、突発的な出費を避けられます。国土交通省の「長期修繕計画標準様式」では12年周期で外壁、15年周期で屋上防水の点検を推奨しています。これを基に1室あたり月3000〜4000円を積み立てる物件が多く、運営表に織り込めば急な資金ショックを抑制できます。
また税務上の留意点として、同一年に複数の修繕をまとめると経費が一時期に集中し、翌年以降の課税所得が急増する恐れがあります。数年に分散させると税負担を平準化できるため、工事時期の調整も経営者の腕の見せ所です。
キャッシュフローと予備費の設計方法
ポイントは、家賃収入の7〜8割を固定費用で賄い、残りを予備費に充てる設計です。2025年7月の全国アパート空室率は21.2%ですが、都市部に限れば平均16%前後に収まります。そこでシミュレーションでは最低でも20%の空室を見込み、金利2%上昇シナリオまで盛り込むと安心です。
家賃10万円×8室のアパートなら年間収入は960万円です。空室率20%を見込むと実収入は768万円となり、ここから返済と固定資産税を引いても200万円程度の余裕が残る設計が理想的です。この余裕部分を修繕積立と突発的な入退去費用に充当すれば、赤字転落リスクを大幅に下げられます。
金融機関は2025年度も賃料収入の50〜60%を返済原資と見る傾向にあり、自己資金2割以上を投入すれば金利優遇を受けやすい環境が続いています。つまり、堅実なレバレッジと修繕積立をセットにすることが、長期安定経営のカギとなります。
2025年度の税制と融資動向を押さえる
実は税制改正のたびに不動産投資の収支は大きく動きます。2025年度は不動産所得に対する大幅な変更はなく、青色申告特別控除65万円も継続が見込まれています。帳簿をクラウド化し電子申告を行えば控除を最大化でき、結果として手元資金を厚くできます。
一方で金融庁のガイドラインにより、融資審査では積算評価より収益還元評価を重視する傾向が強まりました。家賃下落や修繕費の計画を提出できない場合は融資枠が縮小するため、事前に長期収支表を整えることが必須です。また、環境性能を高めるリフォームに対しては、2025年度も「省エネ改修促進税制」が継続し、固定資産税の減額措置が最大120㎡まで適用可能です。期限は2026年3月31日までの工事完了分であるため、スケジュール管理が重要になります。
補助金に関しては、地方自治体ごとに小規模修繕補助が存在しますが、年度ごとに予算が変動します。公式サイトで最新情報を確認し、申請時期を逃さないようにしましょう。
長期的な資産価値を守る修繕計画
基本的に、建物は計画的に手を入れるほど維持コストが下がります。外壁を例に取ると、軽度のひび割れを早期補修すれば数十万円で済みますが、放置して内部まで劣化すると数百万円規模の大規模修繕が必要になるからです。早期対応は修繕費の総額を抑え、入居者の退去を防ぐ効果もあります。
さらに、物件の外観や共用部を綺麗に保つことで入居付けがスムーズになり、長期的な稼働率が向上します。東京都心部の賃貸市場調査(2024年)では、築20年以上でも定期的にリノベーションを行った物件は平均稼働率89%を維持していました。つまり、適切な修繕は支出でありつつ、収益を守る投資でもあるわけです。
最後に修繕計画をエビデンス化し、金融機関や相続人に共有しておくと信頼度が高まります。将来的に売却や共有分割を検討する際にも、過去の修繕履歴が明示されている物件は評価が上がり、出口戦略が立てやすくなるでしょう。
まとめ
この記事ではアパート経営 相続対策 修繕費の三つを軸に、2025年9月時点の税制と市場動向を整理しました。相続税評価の圧縮、修繕費の経費化、空室リスクを織り込んだキャッシュフロー設計を組み合わせれば、安定した資産承継が可能です。次のステップとして、家計全体のバランスシートを作り、長期修繕計画と融資条件を金融機関へ提示してみてください。行動に移すことで、不安は具体的な数字に置き換わり、着実な一歩を踏み出せるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅統計調査 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 相続税申告実態調査 – https://www.nta.go.jp
- 金融庁 モニタリングレポート2024 – https://www.fsa.go.jp
- 東京都住宅政策本部 賃貸市場レポート2024 – https://www.metro.tokyo.jp
- 環境省 省エネ改修促進税制ガイド2025 – https://www.env.go.jp

