不動産投資を始めたいものの「東京はどこも高いし、どの街を選べばいいのか分からない」と悩む人は少なくありません。価格が高騰している一方で空室リスクは抑えたい、と考えるのは当然です。本記事では、2025年9月時点で入手できる最新データを使いながら、東京の立地選定に必要な視点を整理します。人口動態、再開発計画、制度活用まで幅広く触れるので、読み終えたときには「自分に合ったエリアを見極める軸」を具体的にイメージできるはずです。
東京全体を俯瞰するデータの読み方
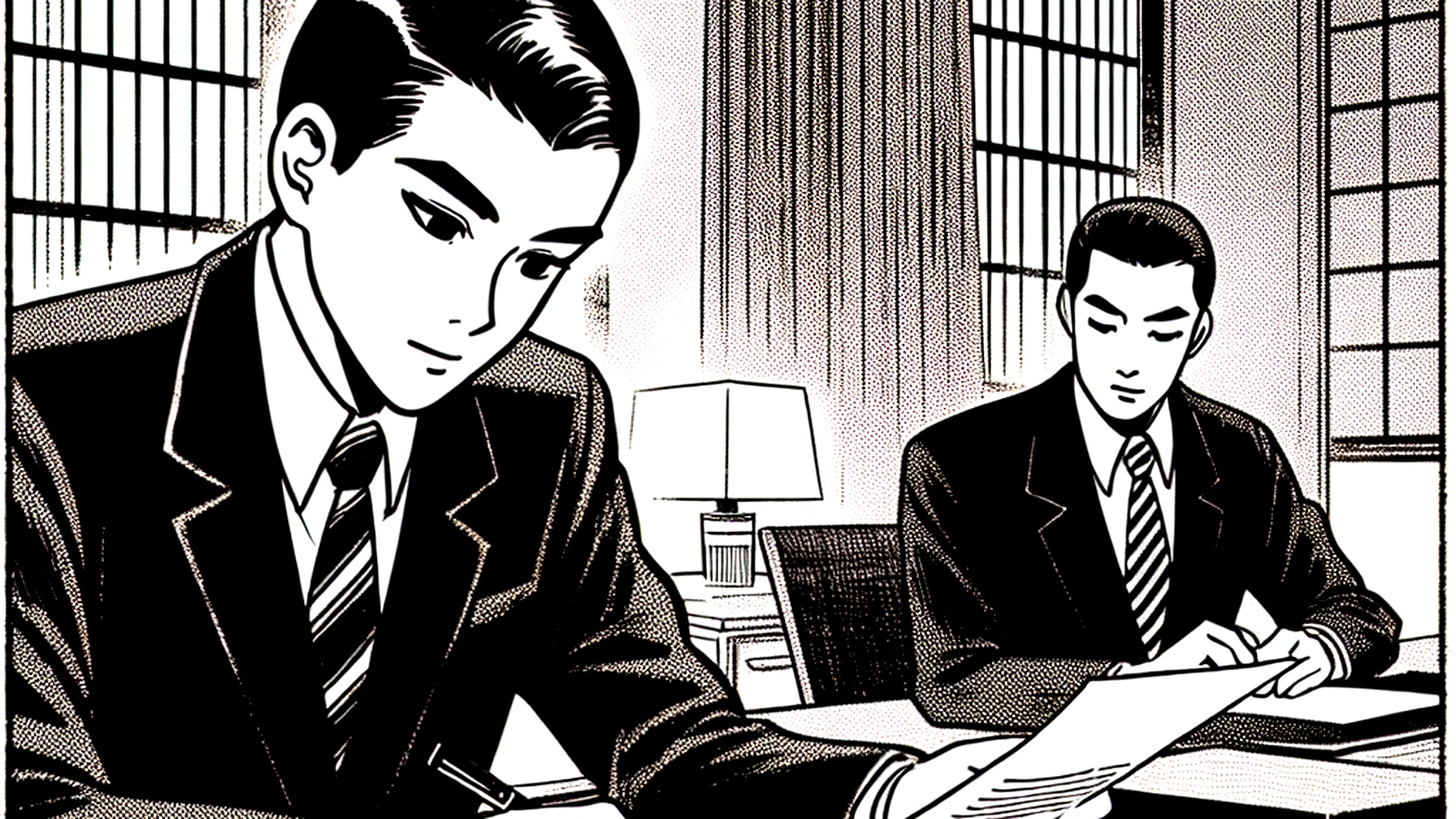
まず押さえておきたいのは、東京都全体の人口と世帯数の流れです。東京都総務局の推計では、23区は2028年前後まで緩やかな増加が続く一方、多摩地域は横ばいから微減に転じると見込まれています。つまり、都心集中はまだ続く可能性が高く、需要が安定しているエリアを探すなら23区が起点になります。
一方で、2024年度の住宅着工統計によると、賃貸住宅の供給は品川・江東・足立区など湾岸と北東部で伸びています。供給過多になったエリアでは家賃競争が激しくなるため、表面利回りだけで判断すると期待収益を下回る危険があります。需要と供給をセットで確認することが、立地選定 東京で成功する第一歩です。
また、コロナ禍以降テレワークが定着し、職住近接よりも「住環境重視」の志向が高まりました。公園の多さや教育施設の充実度といった生活利便性が評価され、世田谷区や練馬区のファミリー賃貸は入居期間が長い傾向があります。単身向けならオフィス回帰の流れを受け、大手町や虎ノ門に近い千代田・港区周辺が依然として強いことも見逃せません。
区単位の人口動態と賃貸需要を読む
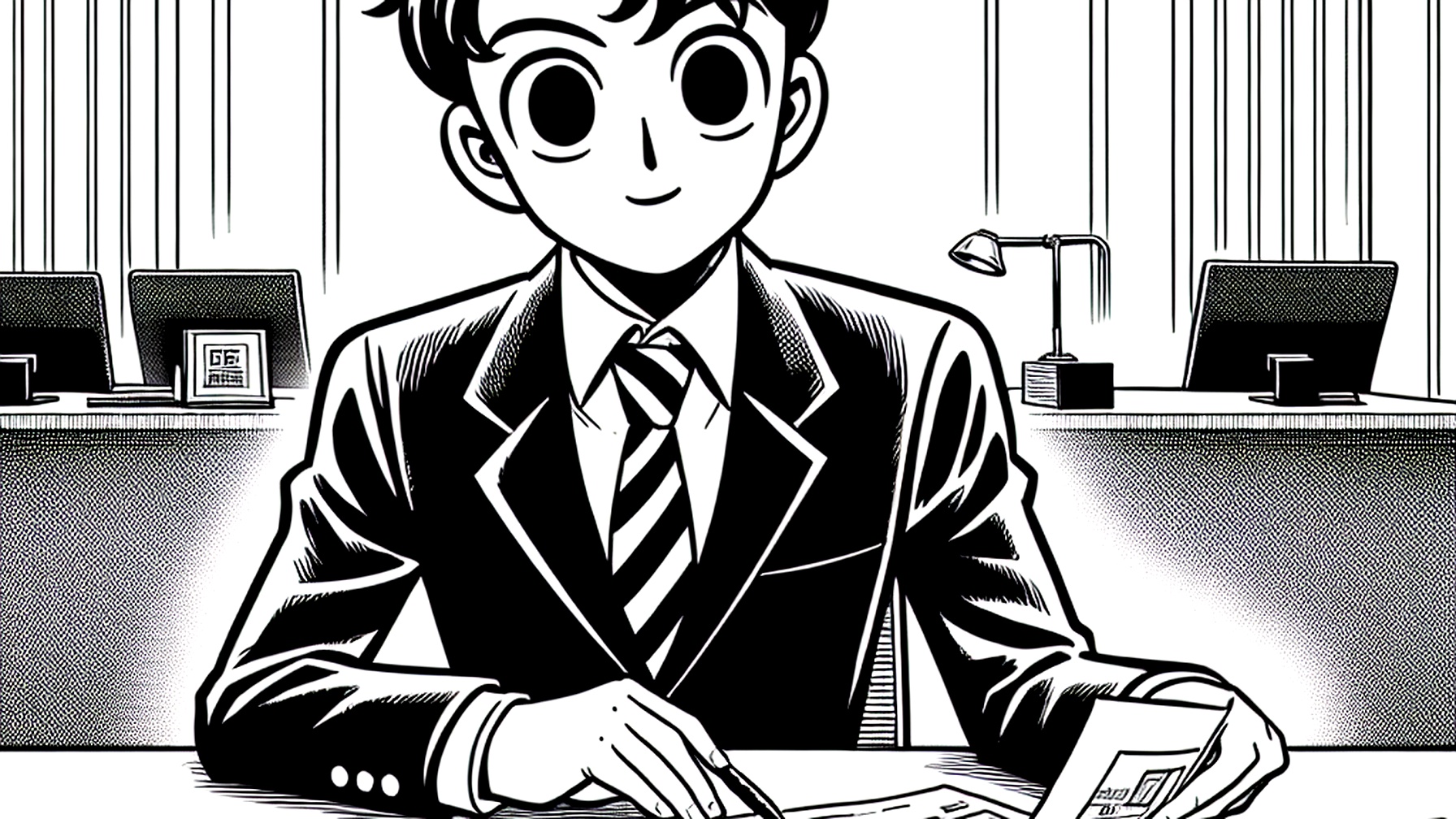
実は「区別人口は伸びているが、賃貸需要は頭打ち」というケースが増えています。理由は持ち家志向の高まりと、不動産価格の上昇による持ち分譲マンションへのシフトです。例えば中央区の人口は2025年3月時点で対前年比2.1%増でしたが、賃貸募集件数は同期間で6%増え、平均家賃は横ばいでした。供給増が吸収し切れない状況がうかがえます。
一方で台東区は観光回復に伴い短期賃貸の需要が戻り、ワンルームの成約速度が早まっています。都営浅草線や日比谷線沿線は、インバウンド需要が賃貸市場にも波及しているため、投資家にとっては安定した稼働率を期待できます。ポイントは、区の統計だけでなく「募集件数」「成約家賃」「平均空室期間」を併せて追うことです。
さらに、外国人労働力の受け入れ拡大で城北エリアの技能実習生向け物件が不足しています。北区や板橋区では月額6万円前後のシェアハウスが高稼働を維持しており、競合が少ないニッチ市場として検討する価値があります。多様な賃貸ニーズを区別に読み解くことで、価格が高い都心でも意外な“穴場”を発見できます。
駅徒歩と再開発計画が与える影響
重要なのは、駅徒歩だけでなく「将来の駅勢圏」を意識することです。再開発に伴い人の流れが大きく変わるからです。例えば品川区の「品川開発プロジェクト」は2026年の先行街区開業が目前に迫り、山手線・京浜東北線の乗降客増が予測されています。実際、2025年上期の品川駅徒歩15分圏内の中古ワンルーム成約単価は前年同期比8%上昇しました。
一方で、大規模再開発を控えたエリアは地価が先行して上がりすぎることもあります。虎ノ門ヒルズ駅周辺では2023〜2024年にかけて坪単価が25%上昇し、賃料上昇率を上回りました。このような過熱相場では、家賃が追いつくまでキャッシュフローが圧迫されやすい点に注意が必要です。
歩行者動線の変化も見逃せません。北千住駅西口はバスターミナル整備で商業施設が集積し、徒歩10分圏の物件でも実質徒歩7分圏並みの賃料で成約する事例が増えています。つまり、再開発情報を読むときは「駅徒歩の物理距離」より「生活導線の実感距離」をどう短縮するかがカギになるのです。
利回りと資産価値のバランスを取る方法
ポイントは、高利回り物件でも出口戦略を考えないと総合収益が下がることです。例えば葛飾区の築30年木造アパートは表面利回り8%前後で購入できますが、耐用年数超過による融資期間の短さがネックになります。融資期間が10年に制限されると、キャッシュフローが想定より縮むケースが多いです。
一方、港区の築浅区分マンションは表面利回り4%程度でも、資産価値の下落が緩やかで、売却益まで含めると実質利回りが高くなることがあります。出口を売却に設定するか、長期保有で家賃収入を得るかで、適切なエリアと築年数が変わるわけです。
そこで、キャッシュフロー重視派は「利回り6%以上」「築20年前後」「人口が微増」の城東・城北エリアを中心に探すと融資条件も得やすくなります。資産価値重視派は「再開発エリア近接」「築10年未満」「空室期間が短い」都心3区が候補となります。投資目的を明確にし、数字の裏側にあるリスクとリターンをセットで判断する姿勢が欠かせません。
2025年度制度を活用したエリア選び
まず知っておきたいのは、2025年度の「住宅エコリフォーム減税」が継続している点です。居住用部分が50%以上の賃貸併用住宅なら、一定の省エネ改修費用を所得税から控除できます。物件を購入後に適用できるため、築古マンションを安く仕入れ、改修後に付加価値を付けて貸し出す戦略と相性が良い制度です。
さらに、東京都の「空き家活用助成(2025年度)」は、耐震補強を伴うリノベーション費用の1/3(上限150万円)を補助します。城南・城北の木造戸建てをシェアハウスや賃貸住宅に転用する際、初期費用を圧縮できるため、表面利回りを一気に高める効果があります。ただし申請前に工事契約を結ぶと対象外になるため、物件取得から助成金交付までのスケジュール管理が重要です。
一方、国交省の「賃貸住宅管理業登録制度」は2021年から続き、2025年現在も有効です。登録事業者への委託で入居者トラブル対応の透明性が高まり、入居者満足度が向上しやすくなります。つまり制度を活用することで、物件力だけでなく管理品質を高め、長期的な稼働率を確保できるのです。
まとめ
東京で失敗しない立地選定のカギは、人口動態と供給量を重ね合わせて需要を読むこと、再開発で変わる導線を見極めること、目的に応じて利回りと資産価値のバランスを調整することです。さらに2025年度の減税や助成を活用すれば、築古物件でも収益性を引き上げられます。データと制度を味方に付け、自分の投資目的に合ったエリアを選び、次の一歩を踏み出しましょう。
参考文献・出典
- 東京都総務局統計部「東京都の人口推計(2025年3月)」- https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp
- 国土交通省「建築着工統計調査報告 2024年度」- https://www.mlit.go.jp
- 東京都都市整備局「住宅市場動向調査 2025年版」- https://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp
- 国土交通省「賃貸住宅管理業登録制度 公式サイト」- https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 東京都住宅政策本部「空き家活用助成事業 2025年度概要」- https://www.jutaku.metro.tokyo.jp

