不動産を所有していると、「建物の修繕費はいつ計上すればいいのか」「将来の相続税がどれくらいになるのか」という悩みがつきまといます。特に賃貸経営を始めたばかりの方にとって、修繕費と相続対策はまったく別の話題のように映るかもしれません。しかし、実はこの二つは密接に結びついており、計画的にリンクさせることで税負担を抑えながら収益性を高めることができます。本記事では、2025年9月時点で有効な制度や最新データを踏まえつつ、初心者でも理解しやすい形でポイントを解説します。読み終えるころには、修繕計画と相続対策を一体で考えるメリットと具体的な実践手順がつかめるはずです。
修繕費が相続税に影響する仕組み
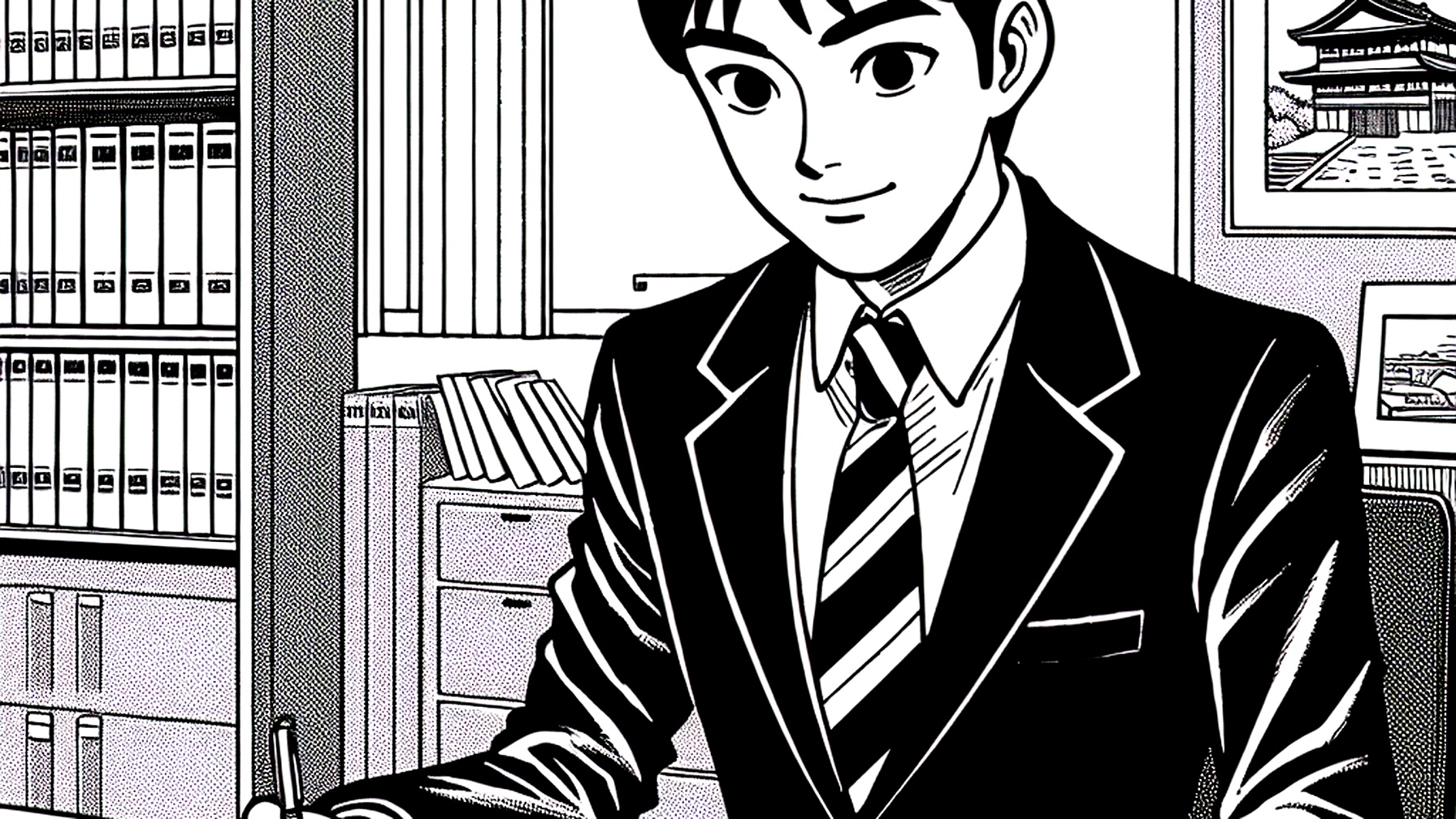
重要なのは、修繕費の計上タイミングが相続財産の評価額に影響する点です。国税庁の通達によると、賃貸用建物の固定資産税評価額は、直近の修繕状況と耐用年数で補正されます。つまり、大規模修繕を完了したばかりの物件は評価額が上がりやすく、逆に修繕直前の物件は評価が抑えられる傾向があります。
一方で、相続税は被相続人の死亡時点の評価額で計算されます。したがって、相続の直前に高額な修繕を行うと、評価額が上がり相続税負担が増える可能性があります。言い換えると、修繕の時期を数年ずらすだけで税額に差が生じるわけです。
加えて、修繕費は損金(必要経費)として所得税を圧縮する効果があります。所得税・住民税を抑えつつ、相続時の評価額にも配慮する二重の視点が欠かせません。相続が視野に入る年齢なら、損金効果と相続税評価のバランスを常に意識して修繕計画を立てるべきです。
修繕タイミングで変わる評価額の考え方
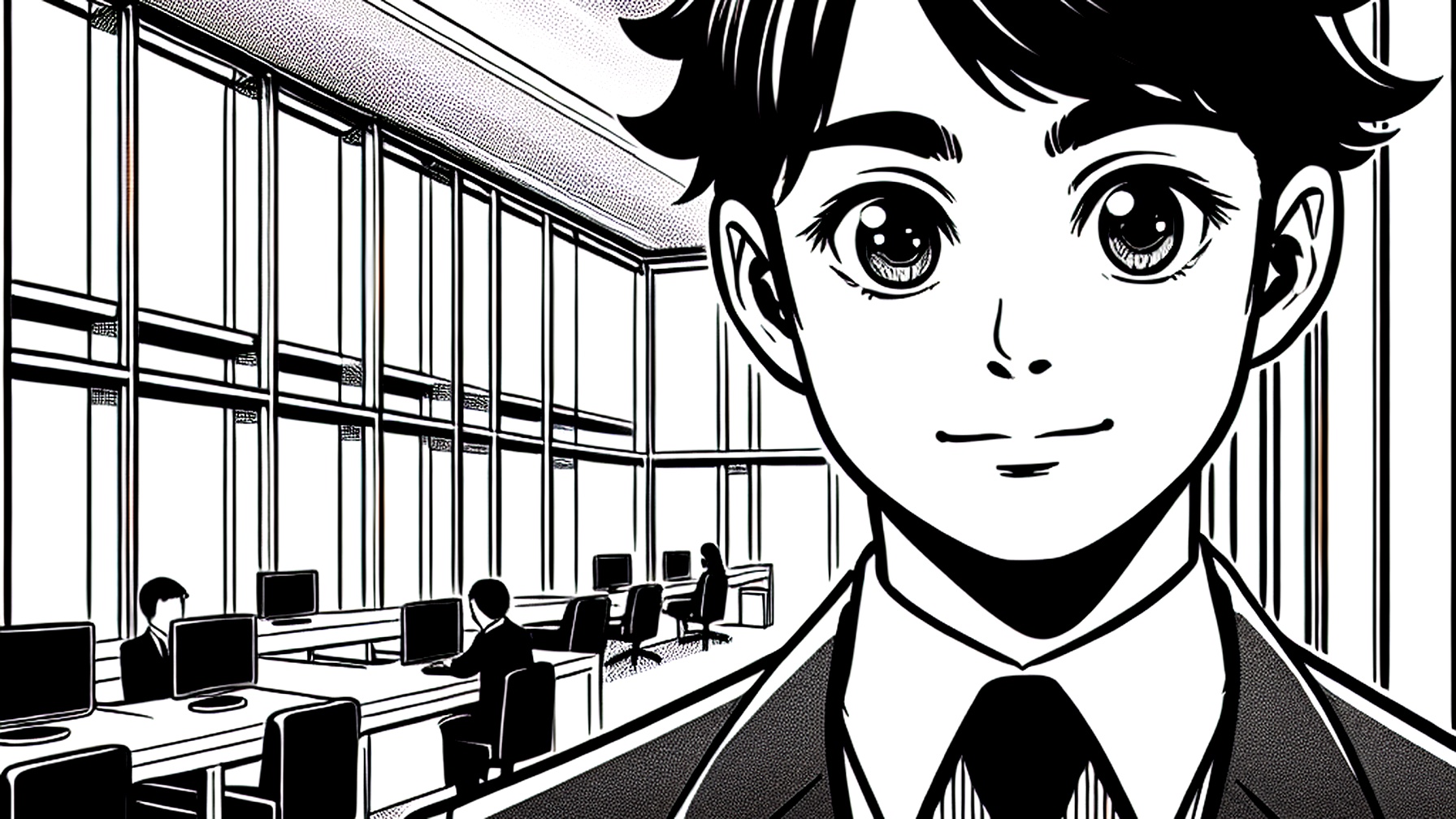
まず押さえておきたいのは、建物の評価額が「原価法」と呼ばれる方法で算定される点です。原価法では、再調達価格から経過年数に応じた減価を引くため、築年数が進むほど評価は下がります。しかし実務では、外壁や屋上防水をやり替えると「再調達価格」が見直され、評価額が一時的に上がるケースがあります。
例えば、鉄筋コンクリート造マンション(築25年)を想定しましょう。外壁改修に1,000万円を投入すると、固定資産税評価額が改修前より200万円程度上がることがあります。相続税評価は固定資産税評価額×1.0〜1.25で算定されるため、200万円の上昇は相続財産を最大250万円押し上げる計算です。資産規模が大きい方ほど影響は無視できません。
しかし、修繕を先送りにして相続時点で劣化が進んでいると、入居者からのクレーム増加や賃料下落を招くリスクが高まります。空室率が上がれば収支が悪化し、相続人が物件を引き継いでもキャッシュフローが回らない事態になりかねません。つまり、相続税と運営収支はトレードオフの関係にあります。
そこで、相続が5年以上先の場合は計画的に修繕を実施し、築年数に応じた賃料維持を図るのが現実的です。一方、相続が視野に入る3年以内なら、過度なバリューアップを避けつつ必要最低限のメンテナンスに留め、相続完了後に大規模修繕を行う選択肢も検討できます。
2025年度に使える主な節税制度
ポイントは、2025年度も継続している相続関連の特例を上手に組み合わせることです。まず「小規模宅地等の特例」は、自宅や賃貸用土地を相続する際、最大80%の評価減が適用される制度で、賃貸併用住宅にも利用できます。適用要件を満たすためには、相続人が賃貸事業を継続する意思を示し、申告期限までに届出を行う必要があります。
次に「相続時精算課税制度」を活用すると、生前に最大2,500万円まで非課税で資金移動でき、その資金を修繕費に充てることが可能です。贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上という年齢制限がありますが、修繕費を早めに確保したい場合に有効な選択肢となります。
また、令和6年度税制改正で創設された「賃貸住宅耐震改修税額控除」は2025年度も継続しています。一定の耐震基準を満たす改修工事を行うと、改修費の10%(上限250万円)が所得税から控除されます。ただし、控除額を相続税の圧縮に直接充てることはできないため、所得税負担の軽減によって捻出したキャッシュを修繕費の一部に回すという発想が必要です。
制度には申請期限や工事完了期限が定められています。計画から着工まで半年以上かかることも多いため、早めのスケジュール管理が欠かせません。
キャッシュフローと相続設計を両立させる方法
実は、多くのオーナーが「節税」に気を取られすぎて日々のキャッシュフロー管理をおろそかにしがちです。修繕費を一括で支払うと翌年度の損金効果は大きいものの、手元資金を圧迫して返済余力を削る恐れがあります。そこで、長期修繕計画に基づいて10年単位で現金流出を平準化することが重要です。
たとえば、屋上防水と共用部塗装を同時に実施すると2,000万円超の支出になることがありますが、屋上防水を2025年、塗装を2027年に分割するだけで資金繰りは大幅に改善します。分割しても減価償却の期間は変わらず、相続税評価への影響も緩やかです。
さらに、修繕積立金として月々のキャッシュフローから一定額をプールし、金融機関のリフォームローンと組み合わせる方法もあります。返済期間を5年以内に設定すれば金利は1.5〜2.0%程度に抑えられ、所得税の損金効果と相続税の圧縮メリットを享受しながら流動性を保てます。
空室対策を兼ねたリノベーションを行う場合は、将来の賃料アップによって相続人の収益性が向上します。結果として「争族(そうぞく)」リスクを減らし、円満な資産承継につながる点も見逃せません。
専門家の活用と長期戦略
まず、税理士・司法書士・一級建築士の三者連携が不可欠です。税理士は修繕費の損金算入や相続税試算を行い、司法書士は遺言書や家族信託の設計をサポートします。一級建築士は長期修繕計画を作成し、工事の妥当性とコストをチェックします。
また、金融機関とのコミュニケーションも早い段階で始めましょう。2025年9月現在、地銀や信金のリフォームローンは最大5,000万円・最長15年が主流ですが、賃貸事業用の場合は審査が厳しめです。事業計画書に相続シミュレーションを盛り込み、収益性と承継計画を同時に提示すると融資承認率が高まります。
家族会議も立派な専門家ツールです。資産状況と修繕計画を家族と共有し、誰が物件を引き継ぐか、相続税をどう納税するかを具体的に話し合っておけば、相続開始後のトラブルを防げます。
最後に、長期戦略を作るうえで大事なのは「10年後に出口をどうするか」を先に決めることです。売却益を狙うのか、安定収入を維持するのかで、修繕費の投下額や時期は大きく変わります。出口戦略を見据えた逆算思考が、修繕費 相続対策で失敗しない最大のポイントです。
まとめ
修繕費と相続対策は切り離せないテーマであり、計画的に連動させることで税金・キャッシュフロー・家族の安心を同時に守れます。修繕の時期が相続税評価額を左右するため、相続までの年数に応じて投資額を調整しましょう。2025年度に有効な特例や控除を活用しつつ、長期修繕計画と家族の承継方針をすり合わせることが成功への近道です。今日から専門家と協力して具体的なシミュレーションを作り、行動に移してみてください。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 総務省 統計局「住宅・土地統計調査」 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省「賃貸住宅市場実態調査 2024」 – https://www.mlit.go.jp
- 令和6年度税制改正 大綱 – https://www.mof.go.jp
- 日本政策金融公庫「小企業の経営動向 2025年版」 – https://www.jfc.go.jp

